
上海で台風の直撃に遭い、観光もままならなかった我々は、列車を使って一気に香港へと向かうことにした。
旅立ちから約3週間が過ぎ、にいやはしんたろーの態度にキレ、しんたろーはにいやのわがままにキレていたため、お互いが会話を拒否していた。
香港に着き、ラッキー・ゲストハウスという大部屋にベッドだけが並ぶドミトリータイプの宿を選択したのも、香港では自由行動にしたのも、当然の成り行きだった。ゲストハウスは日本人旅行者のたまり場になっており、ロビーには日本語で書かれたガイドブック、本、マンガが山のように積み重ねられていた。にいやはゴルゴ13を、しんたろーはドラえもんを手に取り、無言で読みふけっていた。
ほどなくして、1人の女性がくわえタバコで、にいやのゴルゴ13をのぞき込み、
「それ、この外人が黒幕やねん。会議中に殺されて終わんねんで」
と言って、紫煙を吐き出した。そしてかぶせるように、
「飯食いに行こうや。腹減ってんねん、うち」
とのたまった。それが遅越嬢(仮名)との出会いだった。
2日後、我々は香港入国で途切れてしまった中国ビザを再び取得し、広州行きのバスに乗っていた。目的地は遅越嬢が留学している大学だった。香港の路地裏の屋台でサンミゲルビールを吐くまで飲まされ、すっかり打ち解けられた我々に彼女は、
「お前ら楽しい奴やのう。もっと飲ませたるけん、うちの留学先に来い!」
という和田アキ子ばりの脅しに屈してのことだった。
広州に着くと、すぐに大学に案内された。そして、遅越嬢の友人、美由紀嬢(仮名)もいつの間にか我々の輪のなかに加えられ、4人で広州市内を観光することになり、タクシーに連れ込まれた。
連れて行かれたのは、中国随一のゲテモノ市場と言われる清平市場。あたりにはすさまじいアンモニア臭が広がっていた。しんたろーは吐き気をもよおし、涙目になりながら3人の後ろを着いて歩くのに精一杯だった。
檻に入れられた犬、猫、アルマジロ、オウム、クジャク…etc。それらはすべて食材として売られていた。市場では次々と呼び止められ、買わないか、試食しないか、としつこく言われた。一件の店先に何やら謎の木箱を発見したにいやはしんたろーに「このなかのものを試食せよ」と命令した。命令に従いゆっくりと木箱を覗くしんたろー。
ギャーッという断末魔を発して、しんたろーは転んだ。なかには箱から飛び出さんばかりのミミズが入っていたのだった。
「ほら、食べろよ。死にゃあしねえよ」
とにいやに蹴られても、しんたろーは涙と鼻水とほんのちょっぴりのゲロを顔面に溜めながら、
「でぎばじぇん(できません)」
と謝るだけだった。この件でミミズがトラウマになったしんたろーは、以来ミミズは口にしていないという。ちなみに強がっていたにいやは、そのオヤジから親指大のカブトムシの幼虫を渡され、一気に口のなかに入れ咀嚼した。「クリーミーな味がする」と言ってニカッと笑った前歯には、幼虫の内蔵が引っかかっていた。
4人が次に向かった先は、豪華海鮮レストラン。しかし出てきた料理は海鮮ではなく…、蛇と野菜のスープ、蛇肉の唐揚げ、蛇皮の湯引き、蛙の姿蒸し、ゴキブリのトウガラシ炒め…など、すべてゲテモノだった。我々は恐る恐る口に運んだ。予想に反してゲテモノたちは美味しかった。蛇は鶏のささみの味がした。蛙を食べたにいやは、涙を流しながら
「こんな美味いものは食べたことがない」と喜んでいた。
ゴキブリは羽根のパリッとした食感がビールのつまみに丁度よかった。市場で吐き気をもよおしていたしんたろーも、赤ら顔でゴキブリをつまみながら、どうして僕には彼女ができないと思いますか、と女性2人に詰め寄っていた。
旅も残りわずかとなり、最後を締めくくる意味でも、ゲテモノはふさわしかったと、泥酔の4人は大声で歌いながら、食べきれなかったゴキブリの折り詰めを片手に持ち、ネオン輝く広州の街に消えていった。
ゴキブリの羽根の部分は、きれいにむしってから食べるべきところで、広州ではゴキブリの羽根を食べると腹痛を起こすと言われていることを知るのは、帰国してからだった。
←前へ戻る


















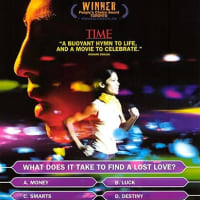

うげげげぇ。
Gを食べたなんて。
なみだ目になってきた。
ちなみにかつて映画のなかでゴジラのことも「G」と呼ばれていました。
G、案外いけたんです。ほんまに。
もちろん食用ですよ。そこらへんのとちゃいますよ。
はい、そこ、ひかないで(祈)。