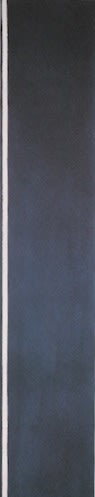
バーネット・ニューマン『夜の女王I』(1951年)
ところで今回、現代美術のことを書こうと思ったきっかけは、先日また国立国際美術館に出向き、全館を使った一大所蔵品展を観たからだ。
そのタイトルは「視覚芸術百態 19のテーマによる196の作品」というもので、規模からいうと途方もなく大きい。ただ、ぼくは現代美術作品の前ではあまり時間を費やすこともなく、サクサクと次に行ってしまうので、196点の作品といえども、予想よりはるかに早く観終わってしまった。
だいたい、ぼくは現代美術の前でいかに時間を過ごすべきか、よく分からないのである。通常の(というと語弊があるが)展覧会では、会場の混み具合にもよるけれど、一枚の絵を鑑賞するのに数分かかることも珍しくない。細部に眼を近づけたり、一歩下がって全体を眺めたり、それこそ舐めるように全体を味わっていると、時間の経つのも忘れて作品に没入してしまうことがあるのだ。
これをぼくなりのいい方で「作品との対話」と呼んでいる。対話といっても実際に言葉に出すわけではなく、作品とこちら側との間に、何らかの双方向的な、命の交流のようなものが現出するのである。これは文学を読むときにも、音楽を聴くときにも同じではないかと思うが、お仕着せのように芸術を受け取るだけではない、前向きな心の動きといったものを感じることができる。
***
しかしながら、作品に向かって何かを語りかけようとしても、冷たく跳ね返されてしまうことがないわけではない。ああ、歯が立たないな、と思うのはそんなときだ。特に、現代美術のある種の作品にはそういったケースが多いような気がする。
たとえば、バーネット・ニューマン。『夜の女王I』は観たところ、紺色に塗りつぶされたキャンバスに、白い線が一本入っているきりである。ここから、何を感じ取るか。ぼくなどは正直なところ、首を傾げてしまう。
バーネット・ニューマンというと、かつてDIC川村記念美術館に『アンナの光』という絵が所蔵されていたことがある。ぼくは実物を観たことがなく、テレビで少し拝見しただけだが、画面のほとんどが赤く塗られただけのシロモノだった。ただその作品は、数年前、100億円余りで売却されたという。
そういえば某テレビ局で、家の蔵などから出てきたお宝を鑑定してもらう番組があるが、それはプロの鑑定家が虫眼鏡などを使って詳細に観察し、本物か贋作かを見分けるというものである。ときには依頼者がびっくりするような高値がつくこともある。ただ、ニューマンのようなニセモノ作りの容易な(とぼくには思える)作品のどこから100億という価値が出てくるのか、よく理解できないというのが本当のところなのだ。
もしこの作品を「○○鑑定団」に出品したら、どれぐらいの値段がつくのだろう?
つづきを読む
この随想を最初から読む



















