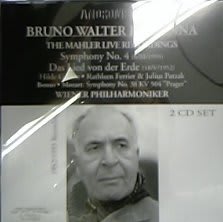ジャーヌ・ギア(sp) オデット・リキア(sp)コッポラ指揮パドルー管弦楽団、サン・ジェルヴェ女声合唱団(gramophone/victor/lys/andante他)1934/11パリ、ラモー・ホール・CD
ロセッティの詩文に材をとった初期の香りを残す明るい作品で、牧歌的な雰囲気からどんどんと素朴な耽美の世界に沈潜していくさまは、ワグナーというよりまるきりディーリアスであり、世紀末だなという感じ。しかしひたすら女性の言葉が支配する世界はコッポラの一連の録音にみられる「クッキリした輪郭」のためにさらに、幻想味より即物的な表現をもって伝わる。だが、この録音が比較的復刻され続けるのは声と楽団が非常に美しい響きを湛えているところにもあると思う。コッポラはSPという枠にキッチリ合わせた音楽を作る印象もあろうが、パドルー管弦楽団の木管陣、もちろんその他のパートもそうなんだが骨董録音には珍しい技巧的瑕疵の僅かな、時代を感じさせない如何にもフランスの一流オケらしい品良い清潔な音で綺麗なハーモニーを演じて見せ、沸き立つような雰囲気の上で歌を踊らせる。歌唱もじつに確かだ。名唱と言って良いだろう。ドビュッシー作品に過度な暗喩的イメージを持たず、初期作品の一部として、ダンディらと同じ時代のものとして聴けば、この昭和9年の録音でもまったく楽しめるだろう。リアルな音でしか収録できなかった時代(電気録音とはいえ実演とは格段の情報量の差を埋めるための、演奏の調整は、特に大規模作品ではされることがあった)にこれだけ雰囲気を作れるのは凄い。低音の刻みなど、影りもまた曲の陰影として的確に伝わり、そうとうに準備して録音しただろうことも伺える。
だがまあ、夢十夜の第一夜で思い立って聴いたら脳内の儚いイメージが、まだもってリアリズム表現においては明確な象徴主義絵画の、しかもちっとも暗示的でない美文体を伴うロセッティ路線を直截に推進する音楽の力に押しつぶされてしまった。ドビュッシーは漱石とほぼ同じ頃に生まれ同じ頃に死んでいる。イギリス人の絵に感化された日本人とフランス人の感覚差に面白みを感じる。日本は先んじていたのだろう。残念ながらこの録音は古いと言っても、共に亡くなったあとである。漱石が同曲初演の頃は、極東に戻って帝大をちょうど卒業した時期にあたる。程なく弦楽四重奏曲も初演されドビュッシーは長足の進歩を遂げるのだから、夢十夜の時期はすでに描写的表現からスッカリ離れ牧神はおろか、「映像」を仕上げた頃にあたる。いっぽうコッポラは指揮録音時代を過ぎると1971年まで作曲家として長生した。フランシスとの関係は無い。
ロセッティの詩文に材をとった初期の香りを残す明るい作品で、牧歌的な雰囲気からどんどんと素朴な耽美の世界に沈潜していくさまは、ワグナーというよりまるきりディーリアスであり、世紀末だなという感じ。しかしひたすら女性の言葉が支配する世界はコッポラの一連の録音にみられる「クッキリした輪郭」のためにさらに、幻想味より即物的な表現をもって伝わる。だが、この録音が比較的復刻され続けるのは声と楽団が非常に美しい響きを湛えているところにもあると思う。コッポラはSPという枠にキッチリ合わせた音楽を作る印象もあろうが、パドルー管弦楽団の木管陣、もちろんその他のパートもそうなんだが骨董録音には珍しい技巧的瑕疵の僅かな、時代を感じさせない如何にもフランスの一流オケらしい品良い清潔な音で綺麗なハーモニーを演じて見せ、沸き立つような雰囲気の上で歌を踊らせる。歌唱もじつに確かだ。名唱と言って良いだろう。ドビュッシー作品に過度な暗喩的イメージを持たず、初期作品の一部として、ダンディらと同じ時代のものとして聴けば、この昭和9年の録音でもまったく楽しめるだろう。リアルな音でしか収録できなかった時代(電気録音とはいえ実演とは格段の情報量の差を埋めるための、演奏の調整は、特に大規模作品ではされることがあった)にこれだけ雰囲気を作れるのは凄い。低音の刻みなど、影りもまた曲の陰影として的確に伝わり、そうとうに準備して録音しただろうことも伺える。
だがまあ、夢十夜の第一夜で思い立って聴いたら脳内の儚いイメージが、まだもってリアリズム表現においては明確な象徴主義絵画の、しかもちっとも暗示的でない美文体を伴うロセッティ路線を直截に推進する音楽の力に押しつぶされてしまった。ドビュッシーは漱石とほぼ同じ頃に生まれ同じ頃に死んでいる。イギリス人の絵に感化された日本人とフランス人の感覚差に面白みを感じる。日本は先んじていたのだろう。残念ながらこの録音は古いと言っても、共に亡くなったあとである。漱石が同曲初演の頃は、極東に戻って帝大をちょうど卒業した時期にあたる。程なく弦楽四重奏曲も初演されドビュッシーは長足の進歩を遂げるのだから、夢十夜の時期はすでに描写的表現からスッカリ離れ牧神はおろか、「映像」を仕上げた頃にあたる。いっぽうコッポラは指揮録音時代を過ぎると1971年まで作曲家として長生した。フランシスとの関係は無い。