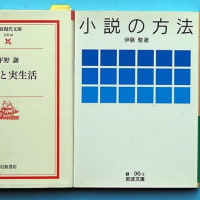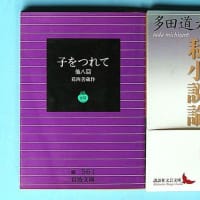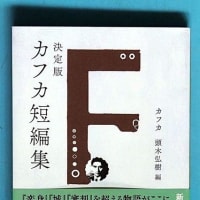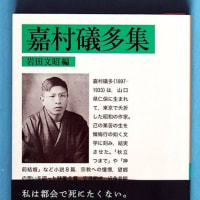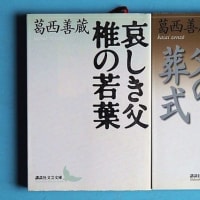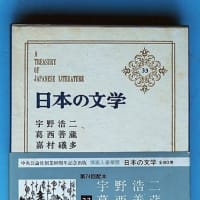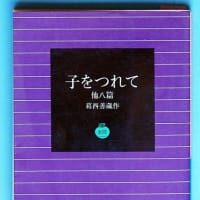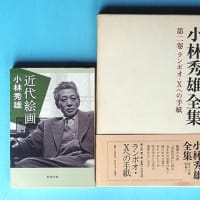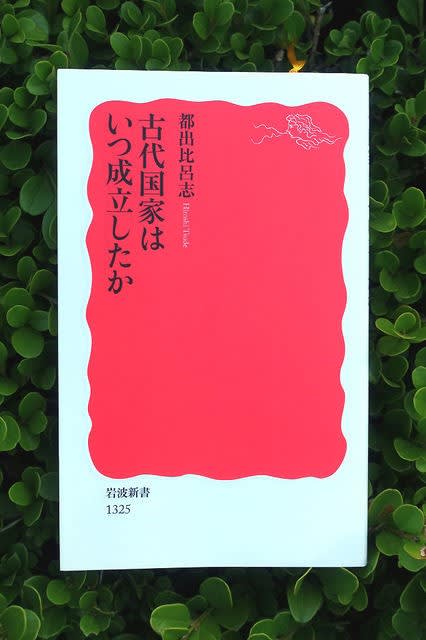
のっけから失礼ながら、amazonデータベースの内容紹介を引用させていただく。
《日本列島に「国家」はいつ成立したのか。それを解き明かす一つの鍵が考古学の成果にある。
集落の構造、住居間の格差、富を蓄えた倉庫の様子など、社会構造の変遷を追っていったとき、邪馬台国は国家なのか、倭の五王の頃はどうか、あるいは七世紀以降の律令体制を待つのか…。
諸外国の集落との比較も交え、わかりやすく語る。》
都出比呂志さんは、つでひろしさんとお読みするのだ。はじめて聞くめずらしい苗字だ。
本書「古代国家はいつ成立したか」のテーマは、わたしが現在、もっとも興味をもっている古代史の中心テーマである。期待が裏切られることないよう、祈るようなつもりで(大げさ!)読みはじめた。
ところがとんでもない、「はじめに」でその危惧は、見事に吹き飛ばされた。
《私は、日本の初期国家は古墳時代にあたると提唱しました。法律により国家体制を整えた成熟した古代律令制国家は七世紀から八世紀に成立しましたが、この古代律令制国家の形成過程を知るには、その直前の古墳時代の社会の動きを解明するしか方法はありません。
古墳時代の始まる三世紀前半から律令国家誕生までに、国家の制度がどのように構築されてきたのか、そして日本の古代国家形成に、古墳時代がどのような役割を担ったのかを考古学者は明らかにしたいと思っています。》
都出さんは1942年のお生まれだが、ういういしいばかりに単刀直入なことばではないか( ・・)
もくじを掲げてみよう。
第一章 弥生社会をどう見るか
第二章 卑弥呼とその時代
第三章 巨大古墳の時代へ
第四章 権力の高まりと古墳の終焉
第五章 律令国家の完成へ
第六章 日本列島に国家はいつ成立したか
「あとがきに代えて」までで202ページ、図版出典一覧、参考文献、遺跡名・古墳名索引・・・とつづいているが、どちらかといえば新書としても薄い部類に入る。このところ古代史の関連本をたてつづけに読んでいるため、すでに知っているトピックも出てくる。ではつまらないかといえば、まったくそんなことはない。都出さんは都出さんの文脈の中で語っているからだ。
日本の古代史といっても、どこに焦点を合わせるかによって見えてくる風景は変わる。
本書では“初期国家”ということばが重要なキーワード。国家の誕生は710年、平城京遷都を画期とするとかんがえるのが一般的な定説だという。では古墳時代はどうなのか?
この初期国家という概念について、いろいろな角度から考察している。
《国家の誕生に立ち会った人たちの驚きに思いを馳せながら》書いたそうである。
したがって、最も注目すべきなのは「第六章 日本列島に国家はいつ成立したか」の一章。エンゲルスとヴェーバーの国家論や文化人類学の概念まで駆使しながら思想史的な考察をおこなっている。そのあたりが、古代史の本としてはユニークといっていいだろう。
都出さんのご専門は文献史学ではなく、考古学・比較考古学。
また、188ページに掲載された「古墳時代の6地帯区分」は秀逸な着眼点(^ー゚)
細かい説明はしないが、わたしは「わが意を得たり」と、膝を叩きたくなった。
くも膜下出血に倒れ、現在闘病中とのこと。ご家族や周囲の人たちに支えられて、本書を刊行したのだ。
切れ味鋭い、明快な論旨につらぬかれた読み応え十分な一冊。“名著”というにはためらいがなくはないが、限りなく名著に近いと思える。
なお本書は、第1回古代歴史文化賞を受賞している。
わたしが買った刊本は2016年刊、第11刷。
よき本はよき読者にめぐまれる。そのことをキモに銘じておこう。
http://kodaibunkasho.jp/archive.html
評価:☆☆☆☆☆
《日本列島に「国家」はいつ成立したのか。それを解き明かす一つの鍵が考古学の成果にある。
集落の構造、住居間の格差、富を蓄えた倉庫の様子など、社会構造の変遷を追っていったとき、邪馬台国は国家なのか、倭の五王の頃はどうか、あるいは七世紀以降の律令体制を待つのか…。
諸外国の集落との比較も交え、わかりやすく語る。》
都出比呂志さんは、つでひろしさんとお読みするのだ。はじめて聞くめずらしい苗字だ。
本書「古代国家はいつ成立したか」のテーマは、わたしが現在、もっとも興味をもっている古代史の中心テーマである。期待が裏切られることないよう、祈るようなつもりで(大げさ!)読みはじめた。
ところがとんでもない、「はじめに」でその危惧は、見事に吹き飛ばされた。
《私は、日本の初期国家は古墳時代にあたると提唱しました。法律により国家体制を整えた成熟した古代律令制国家は七世紀から八世紀に成立しましたが、この古代律令制国家の形成過程を知るには、その直前の古墳時代の社会の動きを解明するしか方法はありません。
古墳時代の始まる三世紀前半から律令国家誕生までに、国家の制度がどのように構築されてきたのか、そして日本の古代国家形成に、古墳時代がどのような役割を担ったのかを考古学者は明らかにしたいと思っています。》
都出さんは1942年のお生まれだが、ういういしいばかりに単刀直入なことばではないか( ・・)
もくじを掲げてみよう。
第一章 弥生社会をどう見るか
第二章 卑弥呼とその時代
第三章 巨大古墳の時代へ
第四章 権力の高まりと古墳の終焉
第五章 律令国家の完成へ
第六章 日本列島に国家はいつ成立したか
「あとがきに代えて」までで202ページ、図版出典一覧、参考文献、遺跡名・古墳名索引・・・とつづいているが、どちらかといえば新書としても薄い部類に入る。このところ古代史の関連本をたてつづけに読んでいるため、すでに知っているトピックも出てくる。ではつまらないかといえば、まったくそんなことはない。都出さんは都出さんの文脈の中で語っているからだ。
日本の古代史といっても、どこに焦点を合わせるかによって見えてくる風景は変わる。
本書では“初期国家”ということばが重要なキーワード。国家の誕生は710年、平城京遷都を画期とするとかんがえるのが一般的な定説だという。では古墳時代はどうなのか?
この初期国家という概念について、いろいろな角度から考察している。
《国家の誕生に立ち会った人たちの驚きに思いを馳せながら》書いたそうである。
したがって、最も注目すべきなのは「第六章 日本列島に国家はいつ成立したか」の一章。エンゲルスとヴェーバーの国家論や文化人類学の概念まで駆使しながら思想史的な考察をおこなっている。そのあたりが、古代史の本としてはユニークといっていいだろう。
都出さんのご専門は文献史学ではなく、考古学・比較考古学。
また、188ページに掲載された「古墳時代の6地帯区分」は秀逸な着眼点(^ー゚)
細かい説明はしないが、わたしは「わが意を得たり」と、膝を叩きたくなった。
くも膜下出血に倒れ、現在闘病中とのこと。ご家族や周囲の人たちに支えられて、本書を刊行したのだ。
切れ味鋭い、明快な論旨につらぬかれた読み応え十分な一冊。“名著”というにはためらいがなくはないが、限りなく名著に近いと思える。
なお本書は、第1回古代歴史文化賞を受賞している。
わたしが買った刊本は2016年刊、第11刷。
よき本はよき読者にめぐまれる。そのことをキモに銘じておこう。
http://kodaibunkasho.jp/archive.html
評価:☆☆☆☆☆