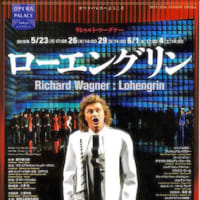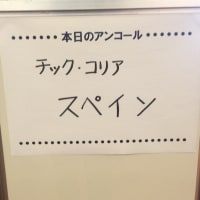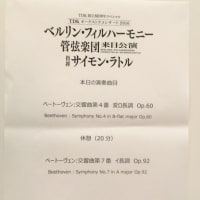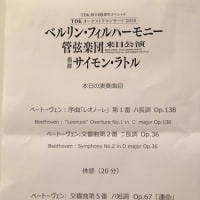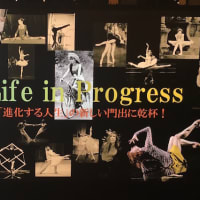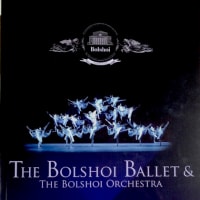一昨日(28日)新国立劇場・オペラ劇場で公演されている『さまよえるオランダ人』(4日目)を観てきた。演出はマティアス・フォン・シュテークマン。指揮は飯守泰次郎。管弦楽は東京交響楽団。主な出演者は下記の通り。
ダーラント:ラファウ・シヴェク
ゼンタ:リカルダ・メルベート
エリック:ダニエル・キルヒ
マリー:竹本節子
舵手:望月哲也
オランダ人:トーマス・ヨハネス・マイヤー
合唱:新国立劇場合唱団
評判があまりよろしくない公演である。理由はなんとなく察していた。というのも、今回の公演は全5回のうち4回がマチネなのである。いくら高齢化社会になったからとはいえ、ほとんどがマチネ公演というのは異常である。ましてや初日をマチネにするというのも大疑問だ。
私は基本的に芝居にしろ音楽にしろマチネ公演には行かないようにしている。というのも、終演後に劇場から外に出たときに明るいと、劇場で味わった非日常が一瞬にして興ざめてしまうからだ。芸術は非日常の世界である。だから、それにしっかりと浸りたいがために、マチネを避けてソアレに行くようにしている。
そして、もう1つ理由がある。これは演劇制作者としての経験から言わせてもらう。マチネは歌い手にしろ役者にしろ声が出にくい。身体のキレも良くない。同じことは演奏する側も同じだと思う。以前ある音楽家に聞いたことがあるが、マチネとソアレでは音色の感覚が違うそうだ。あと、芝居やオペラの場合は稽古を夜遅くまでやっている場合が多い。そのために通し稽古やゲネプロは大概夜に行っている。それなのに、公演のほとんどがマチネだったり、初日がマチネというのはどう考えてもおかしい。
ということで、私は唯一のソアレ公演を観に行った。
飯守泰次郎が指揮するオペラを観るのは初めてである。結論として、彼の指揮は目立ちすぎる。椅子に座って指揮をしているとき(間奏曲など音楽のみのとき)はまだしも、出演者が登場して舞台で歌いはじめると、彼は立って指揮を行う。しかし、彼の指揮ぶりは1階席で見ているにもかかわらず、上半身がほとんど見えて「まるで私が主役です」と言わんばかりである。オペラにおける指揮者は確かに出演者に対しても指示をすることは分かるが、あんなに観客に目立つ必要性はないと思う。もう少し配慮がほしい。
さて、舞台であるが第1幕。長い。とにかく長い。意味もなく長い。序曲も長いが話の中身はさほどないのに長い。オペラ全体のただの序章でしかないのに延々とやっている。音楽もまったく抑揚がなく欠伸がでるほど退屈である。これはひとえに作曲者のワーグナーもしくは創設時のプロデューサーに責任があるだろう。
休憩後の第2幕。ヒロインのゼンタに魅力を感じない。ゼンタ役のリカルダ・メルベートはバイロイトでも歌っているし、新国立劇場にも何度か出ているがまったく没個性的なのである。これはひとえに終始一貫陰湿で暗い演出をしているマティアス・フォン・シュテークマンに責任があるだろう。
第3幕。必要以上に人数が多い新国立劇場合唱団がでてくるが、合唱団があまりにも多すぎて声が割れている。新国立劇場はさほど大きくない舞台なのだから50人もの水夫などいらない。加えて、オランダ人を演じたトーマス・ヨハネス・マイヤーにも魅力を感じさせない。これらはひとえに演出の問題である。一方で、ダーラントを演じたラファウ・シヴェクは魅力的であった。なんとも皮肉だ。
最後に私のようなオペラ素人(ただし演劇は元玄人)が引導を渡すのもなんだが、新国立劇場は今回で3回目となるシュテークマン版『さまよえるオランダ人』はもう上演しない方がいい。日本人の有能な演出家に依頼してもっと斬新な新制作に生まれ変わることを切に願う。
ダーラント:ラファウ・シヴェク
ゼンタ:リカルダ・メルベート
エリック:ダニエル・キルヒ
マリー:竹本節子
舵手:望月哲也
オランダ人:トーマス・ヨハネス・マイヤー
合唱:新国立劇場合唱団
評判があまりよろしくない公演である。理由はなんとなく察していた。というのも、今回の公演は全5回のうち4回がマチネなのである。いくら高齢化社会になったからとはいえ、ほとんどがマチネ公演というのは異常である。ましてや初日をマチネにするというのも大疑問だ。
私は基本的に芝居にしろ音楽にしろマチネ公演には行かないようにしている。というのも、終演後に劇場から外に出たときに明るいと、劇場で味わった非日常が一瞬にして興ざめてしまうからだ。芸術は非日常の世界である。だから、それにしっかりと浸りたいがために、マチネを避けてソアレに行くようにしている。
そして、もう1つ理由がある。これは演劇制作者としての経験から言わせてもらう。マチネは歌い手にしろ役者にしろ声が出にくい。身体のキレも良くない。同じことは演奏する側も同じだと思う。以前ある音楽家に聞いたことがあるが、マチネとソアレでは音色の感覚が違うそうだ。あと、芝居やオペラの場合は稽古を夜遅くまでやっている場合が多い。そのために通し稽古やゲネプロは大概夜に行っている。それなのに、公演のほとんどがマチネだったり、初日がマチネというのはどう考えてもおかしい。
ということで、私は唯一のソアレ公演を観に行った。
飯守泰次郎が指揮するオペラを観るのは初めてである。結論として、彼の指揮は目立ちすぎる。椅子に座って指揮をしているとき(間奏曲など音楽のみのとき)はまだしも、出演者が登場して舞台で歌いはじめると、彼は立って指揮を行う。しかし、彼の指揮ぶりは1階席で見ているにもかかわらず、上半身がほとんど見えて「まるで私が主役です」と言わんばかりである。オペラにおける指揮者は確かに出演者に対しても指示をすることは分かるが、あんなに観客に目立つ必要性はないと思う。もう少し配慮がほしい。
さて、舞台であるが第1幕。長い。とにかく長い。意味もなく長い。序曲も長いが話の中身はさほどないのに長い。オペラ全体のただの序章でしかないのに延々とやっている。音楽もまったく抑揚がなく欠伸がでるほど退屈である。これはひとえに作曲者のワーグナーもしくは創設時のプロデューサーに責任があるだろう。
休憩後の第2幕。ヒロインのゼンタに魅力を感じない。ゼンタ役のリカルダ・メルベートはバイロイトでも歌っているし、新国立劇場にも何度か出ているがまったく没個性的なのである。これはひとえに終始一貫陰湿で暗い演出をしているマティアス・フォン・シュテークマンに責任があるだろう。
第3幕。必要以上に人数が多い新国立劇場合唱団がでてくるが、合唱団があまりにも多すぎて声が割れている。新国立劇場はさほど大きくない舞台なのだから50人もの水夫などいらない。加えて、オランダ人を演じたトーマス・ヨハネス・マイヤーにも魅力を感じさせない。これらはひとえに演出の問題である。一方で、ダーラントを演じたラファウ・シヴェクは魅力的であった。なんとも皮肉だ。
最後に私のようなオペラ素人(ただし演劇は元玄人)が引導を渡すのもなんだが、新国立劇場は今回で3回目となるシュテークマン版『さまよえるオランダ人』はもう上演しない方がいい。日本人の有能な演出家に依頼してもっと斬新な新制作に生まれ変わることを切に願う。