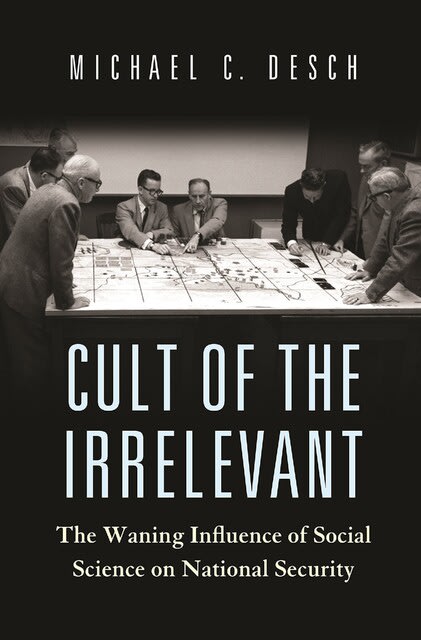日本に拡大抑止(核の傘)を提供するアメリカは、4年前に、「核態勢の見直し(NPR: Nuclear Posture Review)」を発表しました。このアメリカ政府の公式文書は、同国の核戦略の概要を示す重要なものです。NPRは、1994年に初めて公表されてから、2018年版で4回目の報告になります。アメリカの同盟国である日本は、外務省が、その概要と評価をウェッブ・ページで紹介しています。日本政府は、外務大臣談話として、2018年版のNPRを以下のように、肯定的に評価しています。
「今回のNPRは、前回のNPRが公表された2010年以降、北朝鮮による核・ミサイル開発の進展等、安全保障環境が急速に悪化していることを受け、米国による抑止力の実効性の確保と我が国を含む同盟国に対する拡大抑止へのコミットメントを明確にしています。我が国は、このような厳しい安全保障認識を共有するとともに、米国のこのような方針を示した今回のNPRを高く評価します」。
2018年版のNPRについては、国防省傘下にあるアメリカ国防大学の機関誌 Joint Force Quarterly が特集を組んで分析しています。この学術誌は、日本では、ほとんど知る人はいないでしょう。今回のブログ記事では、日本のことにも言及している同雑誌に掲載された、ある論文の内容を紹介したいと思います。Ryan W. Kort, Carlos R. Bersabe, Dalton H. Clarke, and Derek J. Di Bello, "Twenty-First Century Nuclear Deterrence: Operationalizing the 2018 Nuclear Posture Review," Joint Force Quarterly, Vol. 94, No. 3, July 2019 です。著者はアメリカ軍の佐官級の将校です。なお、本論文の掲載内容は、アメリカ政府や国防省、国防大学の見解を代表するものではないとのことです。
論文の冒頭では、著名な核戦略家だったトーマス・シェリング氏のちょっと物騒な言葉が引用されています。「痛めつける力、すなわち誰かが大切にしているものを破壊するという、まったくもって何かを欲するのでもなく生産するわけでもない力は、一種のバーゲニング・パワーであり、それは簡単には使えないが、しばしば使われるのだ」(Arms and Influence, Yale University Press, 1966, p. v) 。この一節は、核兵器が国家間のバーゲニングにおいて最大のパワーであることを示唆するために、引用されたのでしょう。
そして著者たちは、これまでのNPRを批判することから議論を始めています。「1994年からのNPRの調査は、(軍事)作戦を行う環境が変化したにもかかわらず、国家は、遺物のような核抑止概念に頼っていることを例証している…アメリカは核兵器の近代化が遅れる一方で、他のグローバルな競争相手は主導権を握ったのだ…アメリカは冷戦以降、ほとんど同じようなやり方で、核抑止を実行しようとしてきた…『第二の核時代は、アメリカが核兵器の作戦を抑制し続けたことが生み出した、核兵器の力の真空として広く説明できる…中国と北朝鮮はこの機会を利用して、核兵器の作戦概念と能力を向上したのだ」(74-76ページ)。このように著者たちは、アメリカの核戦力の低下と核戦略の停滞に危機感を募らせています。
その後で、中国と北朝鮮の核兵器が分析されます(ロシアの核戦力に対する言及は割愛します)。「中国の拡大する核抑止ドクトリンと能力は、アメリカの核抑止の遂行の仕方に深刻な戦略的挑戦となっている。2016年、習近平は中国の第二砲兵を独立した中国人民解放軍ロケット軍に格上げして、全ての核戦力に対する指揮・統制を固めた…『中国はいくつかの新型で多様な攻撃用ミサイルの開発・試射を行い、旧式のミサイルシステムを改良して、弾道ミサイル防衛を突破する方法を開発している』…北朝鮮は核兵器を保有し続ける限り、それが何発であれ非常に現実的で現存の危険であり続ける…もし抑制されなければ、北朝鮮は東アジア地域、そして、おそらく、いつかはアメリカ自体を脅かすだろう。北朝鮮のミサイル実験に対して、日本や韓国は『アメリカがこれらの国々を守ろうにも、そうすることは北朝鮮からのロサンジェルスやワシントンへのミサイル発射を引き起こしかねないので、躊躇するかもしれないとの懸念から、核武装の選択』を検討したと伝えられている」(77ページ)。このように中国と北朝鮮の強化される核兵器が、日本や韓国の核武装を促す懸念が示されています。
これらの戦略分析を踏まえて、著者たちは以下のような驚くべき政策を提言しています。
「アメリカは、敵国に対する質的、概念的優位を再び取り戻して、それを維持するのであれば、迅速に行動しなければならない…断固とした行動をとらず、必要な概念やこの戦略を可能にする関連能力を構築できなければ、アメリカの拡大抑止の傘は破れてしまい、同盟国は強制に対して脆弱になり、核戦争の可能性が高まるだろう。今、大胆な行動をとれば、政治的、軍事的リスクは低減できるだけでなく、アメリカは懸念すべきアクターに対して、強い立場から誤算やエスカレーションのリスクを軽減する機会も与えられるだろう...さらに、アメリカは危機に際して、選ばれたアジア太平洋のパートナー、とりわけ日本や韓国と非戦略核能力を管理された形で共有することを含む、物議をかもすであろう新しい概念を強く考慮すべきである…この態勢は政治や軍事の制約ゆえに、NATOの非戦略核の運用方式をまねることにならないだろう…東アジアにおける非戦略核能力の前方展開は、アメリカの地域的な同盟国に多大な安心を供与することにより、さらなる優位を提供することになる…一連の行動はアメリカの決意の新たな物理的証明となるだろう。これは統合地域演習を通じた軍事的パートナーの強化と協力への道も切り開くだろう。これらすべては、潜在的な敵国を抑止して、同盟国に安心を供与するために必要なことなのだ」(77-78ページ)。
この論文は、アメリカ政府や軍の意見を代表しないとはいえ、現役の将校が、これまでの核戦略を公に批判すると共に、日本や韓国との核兵器の共有まで提言していることには、正直、驚かされます。日本で現役の自衛官が、日本の既存の防衛政策を批判したり、アメリカとの核共有を提案したりするなど、とても考えられません(そんなことをしたら社会的な大騒動になるでしょう)。アメリカ国防大学において「アカデミック・フリーダム」が徹底されているからこそ、また、シビリアン・コントロールに自信があるからこそ、こうしたタブーなしの論考を将校に発表させることが許されるのでしょう。同時に、現役の軍人たちの指摘は、おそらくアメリカの軍事組織の改善や国防政策の見直しにフィードバックされるのでしょう。日本とアメリカは、民主主義の価値を共有する同盟国ですが、両国の軍事組織の文化は、これほどまでに違うものなのだと感じさせられました。
「今回のNPRは、前回のNPRが公表された2010年以降、北朝鮮による核・ミサイル開発の進展等、安全保障環境が急速に悪化していることを受け、米国による抑止力の実効性の確保と我が国を含む同盟国に対する拡大抑止へのコミットメントを明確にしています。我が国は、このような厳しい安全保障認識を共有するとともに、米国のこのような方針を示した今回のNPRを高く評価します」。
2018年版のNPRについては、国防省傘下にあるアメリカ国防大学の機関誌 Joint Force Quarterly が特集を組んで分析しています。この学術誌は、日本では、ほとんど知る人はいないでしょう。今回のブログ記事では、日本のことにも言及している同雑誌に掲載された、ある論文の内容を紹介したいと思います。Ryan W. Kort, Carlos R. Bersabe, Dalton H. Clarke, and Derek J. Di Bello, "Twenty-First Century Nuclear Deterrence: Operationalizing the 2018 Nuclear Posture Review," Joint Force Quarterly, Vol. 94, No. 3, July 2019 です。著者はアメリカ軍の佐官級の将校です。なお、本論文の掲載内容は、アメリカ政府や国防省、国防大学の見解を代表するものではないとのことです。
論文の冒頭では、著名な核戦略家だったトーマス・シェリング氏のちょっと物騒な言葉が引用されています。「痛めつける力、すなわち誰かが大切にしているものを破壊するという、まったくもって何かを欲するのでもなく生産するわけでもない力は、一種のバーゲニング・パワーであり、それは簡単には使えないが、しばしば使われるのだ」(Arms and Influence, Yale University Press, 1966, p. v) 。この一節は、核兵器が国家間のバーゲニングにおいて最大のパワーであることを示唆するために、引用されたのでしょう。
そして著者たちは、これまでのNPRを批判することから議論を始めています。「1994年からのNPRの調査は、(軍事)作戦を行う環境が変化したにもかかわらず、国家は、遺物のような核抑止概念に頼っていることを例証している…アメリカは核兵器の近代化が遅れる一方で、他のグローバルな競争相手は主導権を握ったのだ…アメリカは冷戦以降、ほとんど同じようなやり方で、核抑止を実行しようとしてきた…『第二の核時代は、アメリカが核兵器の作戦を抑制し続けたことが生み出した、核兵器の力の真空として広く説明できる…中国と北朝鮮はこの機会を利用して、核兵器の作戦概念と能力を向上したのだ」(74-76ページ)。このように著者たちは、アメリカの核戦力の低下と核戦略の停滞に危機感を募らせています。
その後で、中国と北朝鮮の核兵器が分析されます(ロシアの核戦力に対する言及は割愛します)。「中国の拡大する核抑止ドクトリンと能力は、アメリカの核抑止の遂行の仕方に深刻な戦略的挑戦となっている。2016年、習近平は中国の第二砲兵を独立した中国人民解放軍ロケット軍に格上げして、全ての核戦力に対する指揮・統制を固めた…『中国はいくつかの新型で多様な攻撃用ミサイルの開発・試射を行い、旧式のミサイルシステムを改良して、弾道ミサイル防衛を突破する方法を開発している』…北朝鮮は核兵器を保有し続ける限り、それが何発であれ非常に現実的で現存の危険であり続ける…もし抑制されなければ、北朝鮮は東アジア地域、そして、おそらく、いつかはアメリカ自体を脅かすだろう。北朝鮮のミサイル実験に対して、日本や韓国は『アメリカがこれらの国々を守ろうにも、そうすることは北朝鮮からのロサンジェルスやワシントンへのミサイル発射を引き起こしかねないので、躊躇するかもしれないとの懸念から、核武装の選択』を検討したと伝えられている」(77ページ)。このように中国と北朝鮮の強化される核兵器が、日本や韓国の核武装を促す懸念が示されています。
これらの戦略分析を踏まえて、著者たちは以下のような驚くべき政策を提言しています。
「アメリカは、敵国に対する質的、概念的優位を再び取り戻して、それを維持するのであれば、迅速に行動しなければならない…断固とした行動をとらず、必要な概念やこの戦略を可能にする関連能力を構築できなければ、アメリカの拡大抑止の傘は破れてしまい、同盟国は強制に対して脆弱になり、核戦争の可能性が高まるだろう。今、大胆な行動をとれば、政治的、軍事的リスクは低減できるだけでなく、アメリカは懸念すべきアクターに対して、強い立場から誤算やエスカレーションのリスクを軽減する機会も与えられるだろう...さらに、アメリカは危機に際して、選ばれたアジア太平洋のパートナー、とりわけ日本や韓国と非戦略核能力を管理された形で共有することを含む、物議をかもすであろう新しい概念を強く考慮すべきである…この態勢は政治や軍事の制約ゆえに、NATOの非戦略核の運用方式をまねることにならないだろう…東アジアにおける非戦略核能力の前方展開は、アメリカの地域的な同盟国に多大な安心を供与することにより、さらなる優位を提供することになる…一連の行動はアメリカの決意の新たな物理的証明となるだろう。これは統合地域演習を通じた軍事的パートナーの強化と協力への道も切り開くだろう。これらすべては、潜在的な敵国を抑止して、同盟国に安心を供与するために必要なことなのだ」(77-78ページ)。
この論文は、アメリカ政府や軍の意見を代表しないとはいえ、現役の将校が、これまでの核戦略を公に批判すると共に、日本や韓国との核兵器の共有まで提言していることには、正直、驚かされます。日本で現役の自衛官が、日本の既存の防衛政策を批判したり、アメリカとの核共有を提案したりするなど、とても考えられません(そんなことをしたら社会的な大騒動になるでしょう)。アメリカ国防大学において「アカデミック・フリーダム」が徹底されているからこそ、また、シビリアン・コントロールに自信があるからこそ、こうしたタブーなしの論考を将校に発表させることが許されるのでしょう。同時に、現役の軍人たちの指摘は、おそらくアメリカの軍事組織の改善や国防政策の見直しにフィードバックされるのでしょう。日本とアメリカは、民主主義の価値を共有する同盟国ですが、両国の軍事組織の文化は、これほどまでに違うものなのだと感じさせられました。