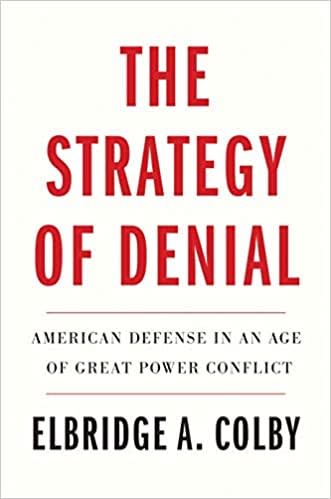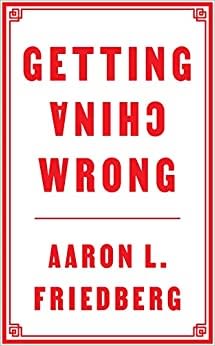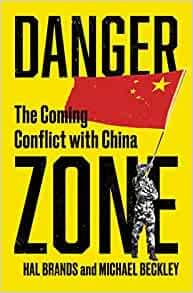政治学者のスティーヴン・ウォルト氏(ハーバード大学)が、興味深いエッセーをアメリカの外交専門誌『フォーリン・ポリシー』に寄稿している。タイトルは「リアリストの世界だったなら、どうなっていただろうか」である。リアリストとは、国際関係をパワーと利益から読み解く学派の人たちの総称だ。そのリアリストの1人であるウォルト氏は、「リアリズムの予測は冷戦後の米国外交政策を支配してきたリベラルやネオコンの主張より明らかにマシだ」というのである。
NATO拡大への後悔
第1に、ロシアのウクライナ侵攻は起こらなかった可能性がある。なぜなら、リアリストがワシントンの外交政策立案者であったならば、NATOを東方に拡大しないので、ロシアとアメリカや西欧諸国の関係、ひいてはロシアとウクライナの関係は異なっていただろうからだ。今では忘れられがちだが、冷戦後、ロシアとヨーロッパ諸国は「平和のためのパートナーシップ」により協調的に共存していた。
アメリカ外交の賢人とうたわれたジョージ・ケナン氏が、NATO拡大はロシアとの関係を決定的に悪化させるので反対であり、「致命的な間違いだ」と強く主張していたのは有名である。ジョン・ミアシャイマー氏(シカゴ大学)も、ウクライナ危機が悪化する以前から、NATO拡大とウクライナへの軍事支援の行き着く先は、ウクライナにとって「いばらの道」になると反対していた。
NATO拡大を進めたビル・クリントン元大統領は、雑誌『アトランティック』でのインタビューで、「我々がロシアを無視し、敬意を払わず、孤立させようとしたという考えは間違いだ。確かに、NATOはロシアの反対にもかかわらず拡大したのだが、拡大はアメリカとロシアの関係以上ものだった」とやや言い訳がましく述懐した。クリントン政権の国防長官だったウィリアム・ペリー氏は、最近、アメリカは過ちを素直に認めるべきだと言っている。クリントン政権時に職を辞す覚悟でNATO拡大に反対したペリー氏は、アメリカがロシアを追い詰めたことは失策であり、ロシアのウクライナ侵攻の遠因になったと自戒を込めて告白している。少し長くなるが、彼の悔恨を以下に引用したい。
「私たちは、平和のためのパートナーシップと呼ばれる NATO プログラムを通じて、すべての東ヨーロッパ諸国との共同プログラムを開始した。平和のためのパートナーシップにより、ロシアやその他の東ヨーロッパ諸国は、NATO のメンバーになることなく、NATO と協力することができた…しかし、多くの東ヨーロッパ諸国が実際の NATO 加盟を熱望していたため、クリントン政権は NATO の拡大に関する議論を開始した。ロシアは提案された境界の変更に反対を表明したが、その見解は無視された。その結果、ロシアはNATOとの協力的なプログラムから撤退し始めたのだ…NATO の拡大に対するロシアの強い見解を無視したことは、西側諸国がロシアの懸念を真剣に受け止めていないという一般的なロシアの信念を強化した。実際、西側諸国の多くは、ロシアを冷戦の敗者としてしか見ておらず、私たちの尊敬に値しないと考えていたのだ」。
にもかかわらず、クリントン政権でNATO東方拡大が決定されたのは、東欧にルーツを持つ「民主主義の擁護者」といわれたマドレーン・オルブライト国務長官の影響が強かったと言われている。リベラル派の彼女は、NATOによるユーゴ空爆を主導するとともに、この軍事同盟の拡大に尽力したのだ。当時、NATOの東方拡大はロシアを刺激するという一定の懸念がアメリカ議会に存在していた。こうした懸念に対して、彼女は、東ヨーロッパ諸国がNATOに加盟しなければ、これらの国家は軍事力を強化したりロシアに対抗する軍事的取り決めが結んだりして、かえってロシアとの緊張を高めることになると主張した。したがって、オルブライト氏の論理では、NATOを東方に拡大したほうが、ヨーロッパは安定するのみならず、ロシアを脅かさずに済むということになる。こうした彼女の主張はワシントンで勝利を収めた結果、NATOは東方に拡大したのである。しかしながら、そもそもロシアの前身であるソ連を仮想敵とするNATOがロシアに向かって拡大すれば、ロシアが必然的に脅威に感じるのは自明ではないだろうか。NATO研究者の金子譲氏は、オルブライト氏の「NATOは軍事同盟であって、社交クラブではない」という発言を引きながら、NATO東方拡大により「冷戦の終焉やCFE条約の調印によって減退した筈のNATOとの緊張が高まることも必至であった」と当時の論文で述べており、卓見といえるだろう。
NATO拡大とロシアのウクライナ侵攻の因果関係については、それを肯定するリアリストと否定するリベラルとの間で、今後も研究と論争が続くことだろう。ここではウクライナ危機が先鋭化した2014年の「マイダン革命」を取材した『ガーディアン』誌の当時の記事を紹介したい。
「ウクライナにおいて…レーガン時代以降初めて、アメリカは世界を戦争に巻き込むと脅している。東欧とバルカン半島がNATOの軍事拠点となり、ロシアと国境を接する最後の『緩衝国家』であるウクライナは、アメリカとEU(ヨーロッパ共同体)により放たれたファシストの力により引き裂かれようとしている」。
アメリカ政府が親露派のヤヌコビッチ大統領の失脚にどのように関与していたのか、詳細はいまだに明らかにされていないが、これがプーチン大統領を「クリミア併合」へと駆り立てた可能性は否定できないだろう。その後、紆余曲折を経て、ロシアはウクライナが西側に取り込まれることを「レッド・ライン(超えてはならない1線)」とみなし、NATO拡大を阻むためにウクライナに侵攻したとリアリストや一部のロシア研究者は主張している(下斗米伸夫『プーチン戦争の論理』集英社、2022年、55頁)。
不要だったイラク戦争とアフガニスタン戦争
第2に、リアリストはアメリカによるイラク侵攻に「不必要な戦争」であるとして反対であった。その主な理由は、サダム・フセインのイラクは湾岸地域で覇権を打ち立てるほどの力はないので封じ込められること、イラクへの軍事侵攻と強引な民主化はアメリカの国益ではないことだ。しかしながら、「軍事力を行使してでもアメリカのように世界を変える」と意気込む「ネオコン」が中枢を占めるブッシュ政権は、イラク戦争を始めた。その結果は、約200兆円の戦争関連の費用や約27-30万人の死者と今も続く政情不安だ。
第3に、アメリカはアフガニスタンに深入りすることはなかった。9.11同時多発テロのインパクトを考えると、アメリカはアルカイダを匿ったタリバン政権への何らの「報復措置」を発動しただろうが、死者約24万人、約231兆円を費やすアフガンの平定作戦を20年間も続けることには、間違いなくならなかっただろう。全てがアフガニスタン戦争に起因するわけではないが、アフガニスタンの状況は戦争前より悪化している。アフガニスタン人の苦境を戦前と戦後で比較すると、食糧不足は62%から92%、5歳以下の栄養不良は9%から50%、貧困率は80%から97%にいずれも増えている。
悪化したリビアの人道危機
第4に、リビア人道危機の悲劇も起きなかっただろう。オバマ政権が「人道的介入」の名のもとに軍事介入した結果の惨状は、アラン・クーパーマン氏(テキサス大学)が、このように批判している。
「NATOが軍事介入するまでには、リビア内戦はすでに終わりに近づいていた。しかし、軍事介入で流れは大きく変化した。カダフィ政権が倒れた後も紛争が続き、少なくとも1万人近くが犠牲になった。今から考えれば、オバマ政権のリビア介入は惨めな失敗だった。民主化が進展しなかっただけでなく、リビアは破綻国家と化してしまった。暴力による犠牲者数、人権侵害の件数は数倍に増えた。テロとの戦いを容易にするのではなく、いまやリビアは、アルカイダやイスラム国(ISISの)関連組織の聖域と化している」と。
こうした反実仮想から言えることは、冷戦後のアメリカの歴代政権の外交政策は、リベラル派の介入主義に立脚しており、リアリストの政策提言を受け入れていれば失うことのなかった人命を犠牲にして、世界をますます危険にしたということだ。
リアリストの和平提案
ロシア・ウクライナ戦争でも、ワシントンやキーウはリアリストの助言に耳を貸そうとしていない(時々、ベルリンやパリから、リアリストのような提案が聞かれるが、大きな発言力にはなっていない)。この戦争でリアリストは一貫して和平交渉による戦争の終結を主張している。元国務長官のヘンリー・キッシンジャー氏は、「時のムード」に流され、欧州におけるロシアのパワーの地位を忘れることは西側にとって「致命的」だ。ロシアは4世紀以上「欧州の本質的部分」であったし「長期的関係を見失ってはならない」と、スイスのダボス会議で警告した。
アンドリュー・ラーサム氏(マカレスター大学)は「取引をする時だ。プーチンに『退路』(孫子)を提供して、彼が(長期にわたり禍根を残すような)ロシアの屈辱感を増幅させることなく戦争を終わらせるよう導くのである」と主張している。
こうしたリアリストの処方箋は、よくウクライナを無視した大国重視の非道徳的な意見だと批判されるが、そうではない。ケネス・ウォルツ氏が指摘するように「大国に焦点をあてるということは、小国を見落とすことではない。小国の命運をについてしるためには、大国に注目することが必要なの」だ(『国際政治の理論』勁草書房、2010年〔原著1979年〕、95頁)。

こうした和平の提案は、ウクライナの土地を犠牲にして、ロシアに利益を与える非道徳的なものだと批判されがちだ。確かに、ウクライナにとっては、ロシアがクリミアを含む全占領地から撤退することが最良の結果だろう。ゼレンスキー大統領は11月18日、ロシアとの「停戦協定」案は事態を悪化させるだけであり、「ロシアは今、力を取り戻すための休息として停戦を求めている。このような休息は事態を悪化させるだけだ。真の永続的な平和は、ロシアの侵略を完全打破することによってのみ実現する」と訴えている。
しかしながら、ウクライナのロシアに対する完全勝利には疑問符がついている。アメリカの軍のトップである、マーク―・ミリー統合参謀本部議長は、11月16日、ロシア軍をクリミアなどを含むウクライナ全土から撤退させることを意味する「ウクライナの軍事的勝利が近く起きる確率は高くない」と述べている。同時に、彼は「ロシアが撤退するという政治的解決策が存在する可能性はある」とも示唆している。
多方面から批判されているミアシャイマー氏ほど、ウクライナの独立と主権の維持を気にしていた政治学者はいないだろう。「ウクライナはロシアが牙をむいてきたときの保険として核兵器を放棄すべきでない」との彼の助言は、その時は孤立無援の主張だったが、今ではウクライナ政府関係者から、これに同意する後悔の発言が聞かれている。
戦争長期化の無視できないコスト
戦争が長期化すれば、ウクライナのみならず支援国にも悪影響を及ぼす。第1に、戦争の予期せぬエスカレーションは、ウクライナや西側に甚大な損害を与えるだろう。前出のミリー氏は、ロシア軍とウクライナ軍の死傷者が、既に、それぞれ約10万人に達しているとの推計を示している。さらに、ウクライナ難民は1500-3000万人、民間人の死者は4万人とも言われている。ミリー氏は、第一次世界大戦では早い段階で交渉が拒否されたため人的被害が拡大し、死傷者がさらに増えたことを前提として、「交渉の機会が訪れ、和平の実現が可能なら機会をつかむべきだ」と主張している。
戦略や戦争の研究で必ずと言ってよいほど引用される、クラウゼヴィッツの「戦争の霧」にも注意が必要である。すなわち、「戦争は不確実性を本領とする。軍事的行動の基礎を成すところのものの四分の三は、多かれ少なかれ不確実性という煙霧に包まれている」のだ(『戦争論(上)』岩波書店、1968年〔原著1832年〕、91-92頁)。ロシア軍からのミサイルを迎撃するために発射されたウクライナ軍のミサイルが、誤ってポーランドに落下してしまい、複数の民間人の犠牲者がでた。この事故が示唆することは重大である。ラジャン・メノン氏(ニューヨーク市立大学)とダン・デペリス氏は、こう警鐘を鳴らしている。
「ポーランドで起きたことは、戦争とは本質的に予測不可能なものであり、戦争を起こす側が想定しているよりも、はるかに制御が困難であることを私たちに思い起こさせる。戦争はエスカレートし、銃が発射されたときには戦闘地域でなかった場所にも広がり、想像を絶する経済的影響をもたらすことがある。戦争が長引けば長引くほど、『予期せぬ結果』の法則が働く可能性が高くなる。ウクライナでの戦争は、これを完璧に物語っている」。
要するに、ロシアとNATO諸国が衝突を望んでいなくても、意図せざる結果として「第三次世界大戦」は起こり得るのだ。最悪の結果は、ウクライナでの戦争が核兵器の応酬に発展することである。これはウクライナだけでなく世界全体にとっても不幸である。
第2に、戦争の長期化はウクライナのロシアに対するバーゲニングの立場を悪化させる恐れがあるす。そうなると、ウクライナは今よりも不利な条件で停戦や終戦に応じざるを得なくなるかもしれない。こうした懸念は、『ワシントン・ポスト』誌のコラムニストであるカトリーナ・ヒュベル氏の主張に表れている。彼女は「外交にチャンスを与える時だろう…アメリカやNATOはウクライナ側に立っているが、支援の継続は無制限ではない。ロシアに対する制裁措置はヨーロッパに残酷な不況をもたらすことになった。生活費の高騰を理由にした怒りのデモが欧州各地で起きており、国民の反発が強まっている」と、西側のウクライナ支援の持続性に懸念を示している。
ウクライナへ最大のサポートをしているアメリカの支援総額は、既にとてつもないレベルに達している。アメリカのウクライナ支援の総額は1,055億ドル(約16兆円)に達する見込みであり、現在の支出率(月68億ドル≒1兆円)では、来年の5月頃までしか持たない。その時点で、戦争が終結するか、膠着状態で決着しない限り、米政権は追加資金を要求する必要があるだろうということだ。アメリカは世界第一位の経済大国であるが、これほど高額な援助をウクライナにどれほどの期間にわたり提供できるかは、350兆円もの財政赤字を抱え、今後インフレに悩まされるだろうことを考慮すれば、不透明なところがある。
手本とすべきヨーロッパ協調
多くのリアリストがモデルにする平和のメカニズムは、19世紀前半のヨーロッパ協調である。この時期は近代国際政治において、相対的に最も平和であった。これに尽力したカースルレーやメッテルニヒは、自分たちが絶対的な平和を求めると他国の平和を脅かしてしまうパラドックスをよく理解していた。かれらは、ヒトラーのナチス・ドイツと同等の平和の破壊者とされるナポレオンのフランスに対して、徹底的に罰して弱体化するのではなく、「寛大な」和平を結んで、大国協調システムに組み込むという外交的な離れ業を成し遂げたのだ。

近代国際システムにおいて、最も平和の時期を構築した「ヨーロッパ協調」は、キッシンジャー氏が強調する「正統性」のある国際秩序であった。彼の以下の警句は、ロシア・ウクライナ戦争の終わり方を考えるうえで、参考にすべき含意があるといえる。
「どんな国際問題の解決の場も、ある国が、自分自身に対して抱いている姿と、他の諸国が、その国に対して抱いている姿とを調整する過程を意味する…一国にとっての絶対的な安全は、他のすべての国にとっては、絶対的な不安を意味するがゆえに、そのような安全は”正統性”にもとづいた解決の一つとしては達成できない…すべての主要大国によって受け入れられている枠組みをもつ秩序というものは”正統性”があるのである。一国でもその枠組みを抑圧的と考えるような秩序は”革命的”秩序なのである…結局、フランスが、ヨーロッパ問題に参加することになったのである。なぜならば、ヨーロッパ問題はフランス抜きにしては解決できないからだった」『回復された世界平和』268ー274頁)。
ロシア・ウクライナ戦争は、いつか終了する。欧米やウクライナが絶対的な安全保障を追求すれば、ロシアを戦略的に不安にする。ロシアに屈辱的な講和を押しつければ、それは将来にプーチンより過激なポピュリスト政治指導者の台頭を促しかねない。そうなるとヨーロッパは長い将来にわたり、戦争の危険が常に付きまとう不安定な状態が続くことになる。その危険を最も深刻に受けるのがウクライナであることは、言うまでもないだろう。くわえて、ロシアという「大国」が消滅しない限り、ヨーロッパの安全保障がロシア抜きにしては解決できない現実は、どれほどロシアを嫌悪しようとも事実として残るのだ。
第一次世界大戦の和平でドイツに戦争責任を押し付けて、同国を徹底的に弱体化するとともに多額の賠償金を科すベルサイユ条約を受け入れさせたことは、ドイツ国民に屈辱感を与え、過激なヒトラー政権を誕生させる温床になったとよくいわれる。パリ講和会議の一員であった経済学者のジョン・メイナード・ケインズ氏は、こうした懲罰的講和はドイツの遺恨を招くと反対した。しかし、彼の警告は無視された。もちろん、ドイツにおけるヒトラーの台頭は単純にベルサイユ講和には結びつけられないとの反論もある。歴史学の大家であるマーガレット・マクミラン氏(オックスフォード大学)は、ケインズ氏の主張を批判して、「ヒトラーが権力を掌握すると、ドイツは公然と賠償金をキャンセルした…大恐慌がなかったら、(ドイツの)侵略そして戦争への地滑りは起こらなかったかもしれない。悪い歴史…が教える教訓は、あまりに単純であるか、単に間違っているかのどちらかである…私たちは、ヒトラーとナチスがヨーロッパの最も強力な国家の一つを掌握しなかったら、世界がどれほど違っていたかをということを自問するだけでいい」と注意を促している(『誘惑する歴史—誤用・濫用・利用の実例—』えにし書房、2014年〔原著2009年〕、39ー40頁)
このように第一次世界大戦の講和を唯一の歴史の教訓とするわけにはいかないが、ただ1つだけ確実にいえることは、ウクライナ戦争後のヨーロッパの平和は、ロシア抜きでは構築できないということである。それでは、リアリストが考えるロシア・ウクライナ戦争の「和平」とは、どのようなものであろうか。再度、ウォルト氏の主張を引用して、この記事を締めくくりたい。
「この戦争は、主人公たちが当初の目的をすべて達成することはできず、理想的とはいえない結果を受け入れなければならないことを理解するまで、コストがかさむ膠着状態に陥る可能性が高い。ロシアは、ウクライナを従順な衛星国にすることはできないし、モスクワを中心とした『ユーラシア帝国』も手に入れられないだろう。ウクライナはクリミアを取り戻すことも、NATOに完全加盟をすることもできないだろう。アメリカは、他の国家をNATOに加盟させることをいつかは諦めなければならないだろう。しかし、真の策略は、当事者が永続的に共存し、機会を見て覆そうとしないような解決を考案することだろう。これは非常に困難な課題であり、賢明な人々が、そのような合意がどのようなものであるかをより早く理解し始めれば、もっとよいだろう」。
※このブログ記事は、『毎日新聞』政治プレミアに掲載された「リベラルではなくリアリストならウクライナ戦争は防げた」に加筆したものである。
NATO拡大への後悔
第1に、ロシアのウクライナ侵攻は起こらなかった可能性がある。なぜなら、リアリストがワシントンの外交政策立案者であったならば、NATOを東方に拡大しないので、ロシアとアメリカや西欧諸国の関係、ひいてはロシアとウクライナの関係は異なっていただろうからだ。今では忘れられがちだが、冷戦後、ロシアとヨーロッパ諸国は「平和のためのパートナーシップ」により協調的に共存していた。
アメリカ外交の賢人とうたわれたジョージ・ケナン氏が、NATO拡大はロシアとの関係を決定的に悪化させるので反対であり、「致命的な間違いだ」と強く主張していたのは有名である。ジョン・ミアシャイマー氏(シカゴ大学)も、ウクライナ危機が悪化する以前から、NATO拡大とウクライナへの軍事支援の行き着く先は、ウクライナにとって「いばらの道」になると反対していた。
NATO拡大を進めたビル・クリントン元大統領は、雑誌『アトランティック』でのインタビューで、「我々がロシアを無視し、敬意を払わず、孤立させようとしたという考えは間違いだ。確かに、NATOはロシアの反対にもかかわらず拡大したのだが、拡大はアメリカとロシアの関係以上ものだった」とやや言い訳がましく述懐した。クリントン政権の国防長官だったウィリアム・ペリー氏は、最近、アメリカは過ちを素直に認めるべきだと言っている。クリントン政権時に職を辞す覚悟でNATO拡大に反対したペリー氏は、アメリカがロシアを追い詰めたことは失策であり、ロシアのウクライナ侵攻の遠因になったと自戒を込めて告白している。少し長くなるが、彼の悔恨を以下に引用したい。
「私たちは、平和のためのパートナーシップと呼ばれる NATO プログラムを通じて、すべての東ヨーロッパ諸国との共同プログラムを開始した。平和のためのパートナーシップにより、ロシアやその他の東ヨーロッパ諸国は、NATO のメンバーになることなく、NATO と協力することができた…しかし、多くの東ヨーロッパ諸国が実際の NATO 加盟を熱望していたため、クリントン政権は NATO の拡大に関する議論を開始した。ロシアは提案された境界の変更に反対を表明したが、その見解は無視された。その結果、ロシアはNATOとの協力的なプログラムから撤退し始めたのだ…NATO の拡大に対するロシアの強い見解を無視したことは、西側諸国がロシアの懸念を真剣に受け止めていないという一般的なロシアの信念を強化した。実際、西側諸国の多くは、ロシアを冷戦の敗者としてしか見ておらず、私たちの尊敬に値しないと考えていたのだ」。
にもかかわらず、クリントン政権でNATO東方拡大が決定されたのは、東欧にルーツを持つ「民主主義の擁護者」といわれたマドレーン・オルブライト国務長官の影響が強かったと言われている。リベラル派の彼女は、NATOによるユーゴ空爆を主導するとともに、この軍事同盟の拡大に尽力したのだ。当時、NATOの東方拡大はロシアを刺激するという一定の懸念がアメリカ議会に存在していた。こうした懸念に対して、彼女は、東ヨーロッパ諸国がNATOに加盟しなければ、これらの国家は軍事力を強化したりロシアに対抗する軍事的取り決めが結んだりして、かえってロシアとの緊張を高めることになると主張した。したがって、オルブライト氏の論理では、NATOを東方に拡大したほうが、ヨーロッパは安定するのみならず、ロシアを脅かさずに済むということになる。こうした彼女の主張はワシントンで勝利を収めた結果、NATOは東方に拡大したのである。しかしながら、そもそもロシアの前身であるソ連を仮想敵とするNATOがロシアに向かって拡大すれば、ロシアが必然的に脅威に感じるのは自明ではないだろうか。NATO研究者の金子譲氏は、オルブライト氏の「NATOは軍事同盟であって、社交クラブではない」という発言を引きながら、NATO東方拡大により「冷戦の終焉やCFE条約の調印によって減退した筈のNATOとの緊張が高まることも必至であった」と当時の論文で述べており、卓見といえるだろう。
NATO拡大とロシアのウクライナ侵攻の因果関係については、それを肯定するリアリストと否定するリベラルとの間で、今後も研究と論争が続くことだろう。ここではウクライナ危機が先鋭化した2014年の「マイダン革命」を取材した『ガーディアン』誌の当時の記事を紹介したい。
「ウクライナにおいて…レーガン時代以降初めて、アメリカは世界を戦争に巻き込むと脅している。東欧とバルカン半島がNATOの軍事拠点となり、ロシアと国境を接する最後の『緩衝国家』であるウクライナは、アメリカとEU(ヨーロッパ共同体)により放たれたファシストの力により引き裂かれようとしている」。
アメリカ政府が親露派のヤヌコビッチ大統領の失脚にどのように関与していたのか、詳細はいまだに明らかにされていないが、これがプーチン大統領を「クリミア併合」へと駆り立てた可能性は否定できないだろう。その後、紆余曲折を経て、ロシアはウクライナが西側に取り込まれることを「レッド・ライン(超えてはならない1線)」とみなし、NATO拡大を阻むためにウクライナに侵攻したとリアリストや一部のロシア研究者は主張している(下斗米伸夫『プーチン戦争の論理』集英社、2022年、55頁)。
不要だったイラク戦争とアフガニスタン戦争
第2に、リアリストはアメリカによるイラク侵攻に「不必要な戦争」であるとして反対であった。その主な理由は、サダム・フセインのイラクは湾岸地域で覇権を打ち立てるほどの力はないので封じ込められること、イラクへの軍事侵攻と強引な民主化はアメリカの国益ではないことだ。しかしながら、「軍事力を行使してでもアメリカのように世界を変える」と意気込む「ネオコン」が中枢を占めるブッシュ政権は、イラク戦争を始めた。その結果は、約200兆円の戦争関連の費用や約27-30万人の死者と今も続く政情不安だ。
第3に、アメリカはアフガニスタンに深入りすることはなかった。9.11同時多発テロのインパクトを考えると、アメリカはアルカイダを匿ったタリバン政権への何らの「報復措置」を発動しただろうが、死者約24万人、約231兆円を費やすアフガンの平定作戦を20年間も続けることには、間違いなくならなかっただろう。全てがアフガニスタン戦争に起因するわけではないが、アフガニスタンの状況は戦争前より悪化している。アフガニスタン人の苦境を戦前と戦後で比較すると、食糧不足は62%から92%、5歳以下の栄養不良は9%から50%、貧困率は80%から97%にいずれも増えている。
悪化したリビアの人道危機
第4に、リビア人道危機の悲劇も起きなかっただろう。オバマ政権が「人道的介入」の名のもとに軍事介入した結果の惨状は、アラン・クーパーマン氏(テキサス大学)が、このように批判している。
「NATOが軍事介入するまでには、リビア内戦はすでに終わりに近づいていた。しかし、軍事介入で流れは大きく変化した。カダフィ政権が倒れた後も紛争が続き、少なくとも1万人近くが犠牲になった。今から考えれば、オバマ政権のリビア介入は惨めな失敗だった。民主化が進展しなかっただけでなく、リビアは破綻国家と化してしまった。暴力による犠牲者数、人権侵害の件数は数倍に増えた。テロとの戦いを容易にするのではなく、いまやリビアは、アルカイダやイスラム国(ISISの)関連組織の聖域と化している」と。
こうした反実仮想から言えることは、冷戦後のアメリカの歴代政権の外交政策は、リベラル派の介入主義に立脚しており、リアリストの政策提言を受け入れていれば失うことのなかった人命を犠牲にして、世界をますます危険にしたということだ。
リアリストの和平提案
ロシア・ウクライナ戦争でも、ワシントンやキーウはリアリストの助言に耳を貸そうとしていない(時々、ベルリンやパリから、リアリストのような提案が聞かれるが、大きな発言力にはなっていない)。この戦争でリアリストは一貫して和平交渉による戦争の終結を主張している。元国務長官のヘンリー・キッシンジャー氏は、「時のムード」に流され、欧州におけるロシアのパワーの地位を忘れることは西側にとって「致命的」だ。ロシアは4世紀以上「欧州の本質的部分」であったし「長期的関係を見失ってはならない」と、スイスのダボス会議で警告した。
アンドリュー・ラーサム氏(マカレスター大学)は「取引をする時だ。プーチンに『退路』(孫子)を提供して、彼が(長期にわたり禍根を残すような)ロシアの屈辱感を増幅させることなく戦争を終わらせるよう導くのである」と主張している。
こうしたリアリストの処方箋は、よくウクライナを無視した大国重視の非道徳的な意見だと批判されるが、そうではない。ケネス・ウォルツ氏が指摘するように「大国に焦点をあてるということは、小国を見落とすことではない。小国の命運をについてしるためには、大国に注目することが必要なの」だ(『国際政治の理論』勁草書房、2010年〔原著1979年〕、95頁)。

こうした和平の提案は、ウクライナの土地を犠牲にして、ロシアに利益を与える非道徳的なものだと批判されがちだ。確かに、ウクライナにとっては、ロシアがクリミアを含む全占領地から撤退することが最良の結果だろう。ゼレンスキー大統領は11月18日、ロシアとの「停戦協定」案は事態を悪化させるだけであり、「ロシアは今、力を取り戻すための休息として停戦を求めている。このような休息は事態を悪化させるだけだ。真の永続的な平和は、ロシアの侵略を完全打破することによってのみ実現する」と訴えている。
しかしながら、ウクライナのロシアに対する完全勝利には疑問符がついている。アメリカの軍のトップである、マーク―・ミリー統合参謀本部議長は、11月16日、ロシア軍をクリミアなどを含むウクライナ全土から撤退させることを意味する「ウクライナの軍事的勝利が近く起きる確率は高くない」と述べている。同時に、彼は「ロシアが撤退するという政治的解決策が存在する可能性はある」とも示唆している。
多方面から批判されているミアシャイマー氏ほど、ウクライナの独立と主権の維持を気にしていた政治学者はいないだろう。「ウクライナはロシアが牙をむいてきたときの保険として核兵器を放棄すべきでない」との彼の助言は、その時は孤立無援の主張だったが、今ではウクライナ政府関係者から、これに同意する後悔の発言が聞かれている。
戦争長期化の無視できないコスト
戦争が長期化すれば、ウクライナのみならず支援国にも悪影響を及ぼす。第1に、戦争の予期せぬエスカレーションは、ウクライナや西側に甚大な損害を与えるだろう。前出のミリー氏は、ロシア軍とウクライナ軍の死傷者が、既に、それぞれ約10万人に達しているとの推計を示している。さらに、ウクライナ難民は1500-3000万人、民間人の死者は4万人とも言われている。ミリー氏は、第一次世界大戦では早い段階で交渉が拒否されたため人的被害が拡大し、死傷者がさらに増えたことを前提として、「交渉の機会が訪れ、和平の実現が可能なら機会をつかむべきだ」と主張している。
戦略や戦争の研究で必ずと言ってよいほど引用される、クラウゼヴィッツの「戦争の霧」にも注意が必要である。すなわち、「戦争は不確実性を本領とする。軍事的行動の基礎を成すところのものの四分の三は、多かれ少なかれ不確実性という煙霧に包まれている」のだ(『戦争論(上)』岩波書店、1968年〔原著1832年〕、91-92頁)。ロシア軍からのミサイルを迎撃するために発射されたウクライナ軍のミサイルが、誤ってポーランドに落下してしまい、複数の民間人の犠牲者がでた。この事故が示唆することは重大である。ラジャン・メノン氏(ニューヨーク市立大学)とダン・デペリス氏は、こう警鐘を鳴らしている。
「ポーランドで起きたことは、戦争とは本質的に予測不可能なものであり、戦争を起こす側が想定しているよりも、はるかに制御が困難であることを私たちに思い起こさせる。戦争はエスカレートし、銃が発射されたときには戦闘地域でなかった場所にも広がり、想像を絶する経済的影響をもたらすことがある。戦争が長引けば長引くほど、『予期せぬ結果』の法則が働く可能性が高くなる。ウクライナでの戦争は、これを完璧に物語っている」。
要するに、ロシアとNATO諸国が衝突を望んでいなくても、意図せざる結果として「第三次世界大戦」は起こり得るのだ。最悪の結果は、ウクライナでの戦争が核兵器の応酬に発展することである。これはウクライナだけでなく世界全体にとっても不幸である。
第2に、戦争の長期化はウクライナのロシアに対するバーゲニングの立場を悪化させる恐れがあるす。そうなると、ウクライナは今よりも不利な条件で停戦や終戦に応じざるを得なくなるかもしれない。こうした懸念は、『ワシントン・ポスト』誌のコラムニストであるカトリーナ・ヒュベル氏の主張に表れている。彼女は「外交にチャンスを与える時だろう…アメリカやNATOはウクライナ側に立っているが、支援の継続は無制限ではない。ロシアに対する制裁措置はヨーロッパに残酷な不況をもたらすことになった。生活費の高騰を理由にした怒りのデモが欧州各地で起きており、国民の反発が強まっている」と、西側のウクライナ支援の持続性に懸念を示している。
ウクライナへ最大のサポートをしているアメリカの支援総額は、既にとてつもないレベルに達している。アメリカのウクライナ支援の総額は1,055億ドル(約16兆円)に達する見込みであり、現在の支出率(月68億ドル≒1兆円)では、来年の5月頃までしか持たない。その時点で、戦争が終結するか、膠着状態で決着しない限り、米政権は追加資金を要求する必要があるだろうということだ。アメリカは世界第一位の経済大国であるが、これほど高額な援助をウクライナにどれほどの期間にわたり提供できるかは、350兆円もの財政赤字を抱え、今後インフレに悩まされるだろうことを考慮すれば、不透明なところがある。
手本とすべきヨーロッパ協調
多くのリアリストがモデルにする平和のメカニズムは、19世紀前半のヨーロッパ協調である。この時期は近代国際政治において、相対的に最も平和であった。これに尽力したカースルレーやメッテルニヒは、自分たちが絶対的な平和を求めると他国の平和を脅かしてしまうパラドックスをよく理解していた。かれらは、ヒトラーのナチス・ドイツと同等の平和の破壊者とされるナポレオンのフランスに対して、徹底的に罰して弱体化するのではなく、「寛大な」和平を結んで、大国協調システムに組み込むという外交的な離れ業を成し遂げたのだ。

近代国際システムにおいて、最も平和の時期を構築した「ヨーロッパ協調」は、キッシンジャー氏が強調する「正統性」のある国際秩序であった。彼の以下の警句は、ロシア・ウクライナ戦争の終わり方を考えるうえで、参考にすべき含意があるといえる。
「どんな国際問題の解決の場も、ある国が、自分自身に対して抱いている姿と、他の諸国が、その国に対して抱いている姿とを調整する過程を意味する…一国にとっての絶対的な安全は、他のすべての国にとっては、絶対的な不安を意味するがゆえに、そのような安全は”正統性”にもとづいた解決の一つとしては達成できない…すべての主要大国によって受け入れられている枠組みをもつ秩序というものは”正統性”があるのである。一国でもその枠組みを抑圧的と考えるような秩序は”革命的”秩序なのである…結局、フランスが、ヨーロッパ問題に参加することになったのである。なぜならば、ヨーロッパ問題はフランス抜きにしては解決できないからだった」『回復された世界平和』268ー274頁)。
ロシア・ウクライナ戦争は、いつか終了する。欧米やウクライナが絶対的な安全保障を追求すれば、ロシアを戦略的に不安にする。ロシアに屈辱的な講和を押しつければ、それは将来にプーチンより過激なポピュリスト政治指導者の台頭を促しかねない。そうなるとヨーロッパは長い将来にわたり、戦争の危険が常に付きまとう不安定な状態が続くことになる。その危険を最も深刻に受けるのがウクライナであることは、言うまでもないだろう。くわえて、ロシアという「大国」が消滅しない限り、ヨーロッパの安全保障がロシア抜きにしては解決できない現実は、どれほどロシアを嫌悪しようとも事実として残るのだ。
第一次世界大戦の和平でドイツに戦争責任を押し付けて、同国を徹底的に弱体化するとともに多額の賠償金を科すベルサイユ条約を受け入れさせたことは、ドイツ国民に屈辱感を与え、過激なヒトラー政権を誕生させる温床になったとよくいわれる。パリ講和会議の一員であった経済学者のジョン・メイナード・ケインズ氏は、こうした懲罰的講和はドイツの遺恨を招くと反対した。しかし、彼の警告は無視された。もちろん、ドイツにおけるヒトラーの台頭は単純にベルサイユ講和には結びつけられないとの反論もある。歴史学の大家であるマーガレット・マクミラン氏(オックスフォード大学)は、ケインズ氏の主張を批判して、「ヒトラーが権力を掌握すると、ドイツは公然と賠償金をキャンセルした…大恐慌がなかったら、(ドイツの)侵略そして戦争への地滑りは起こらなかったかもしれない。悪い歴史…が教える教訓は、あまりに単純であるか、単に間違っているかのどちらかである…私たちは、ヒトラーとナチスがヨーロッパの最も強力な国家の一つを掌握しなかったら、世界がどれほど違っていたかをということを自問するだけでいい」と注意を促している(『誘惑する歴史—誤用・濫用・利用の実例—』えにし書房、2014年〔原著2009年〕、39ー40頁)
このように第一次世界大戦の講和を唯一の歴史の教訓とするわけにはいかないが、ただ1つだけ確実にいえることは、ウクライナ戦争後のヨーロッパの平和は、ロシア抜きでは構築できないということである。それでは、リアリストが考えるロシア・ウクライナ戦争の「和平」とは、どのようなものであろうか。再度、ウォルト氏の主張を引用して、この記事を締めくくりたい。
「この戦争は、主人公たちが当初の目的をすべて達成することはできず、理想的とはいえない結果を受け入れなければならないことを理解するまで、コストがかさむ膠着状態に陥る可能性が高い。ロシアは、ウクライナを従順な衛星国にすることはできないし、モスクワを中心とした『ユーラシア帝国』も手に入れられないだろう。ウクライナはクリミアを取り戻すことも、NATOに完全加盟をすることもできないだろう。アメリカは、他の国家をNATOに加盟させることをいつかは諦めなければならないだろう。しかし、真の策略は、当事者が永続的に共存し、機会を見て覆そうとしないような解決を考案することだろう。これは非常に困難な課題であり、賢明な人々が、そのような合意がどのようなものであるかをより早く理解し始めれば、もっとよいだろう」。
※このブログ記事は、『毎日新聞』政治プレミアに掲載された「リベラルではなくリアリストならウクライナ戦争は防げた」に加筆したものである。