国際関係論・国際政治学の1つのメインテーマは、「戦争と平和」です。にもかかわらず、我が国のこの分野の研究者たちは、「世界では暴力が激減しており、平和への道を進んでいる」ことを論証する大作について、あまり大きな関心を払っていないように見えます。その大著とは、スティーブン・ピンカー(幾島幸子・塩原通緒訳)『暴力の人類史(上)(下)』青土社、2015年(Steven Pinker, The Better Angles of Our Nature: Why Violence Has Declined, NY: Penguin, 2011)です。
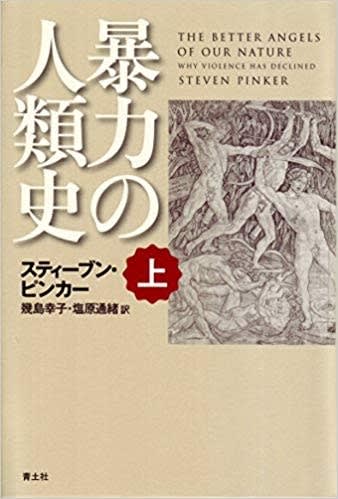
このピンカー氏(ハーバード大学)の著作は、この学問分野の代表的な国際政治学会の機関紙『国際政治』において、これまで書評の対象になっていません。それでは、日本平和学会は、どうなのでしょうか。この学会なら、その活動目的に「様々な暴力を科学的・批判的にとらえて、それらの克服をめざす研究活動」を趣旨として掲げているくらいですから、同会の機関紙『平和研究』が、本書に注目して取り上げてもよさそうでしょう。ですが、私が調べた限りでは、この学会誌も同書を書評していません(見落としていたら、訂正いたします)。ビックリしたのは、私だけでしょうか。
ピンカー著『暴力の人類史』は、文字通りの「大作」です。訳書は、2巻合計で約1200ページ、英語の原書でも、約800ページのボリュームです。もちろん、本書の価値は、その分厚さもさることながら、むしろ内容にあります。ピンカー氏は、認知科学者・進化心理学者ですが、この図書の内容は、これらの学問分野を超えて、文字通り、学際的アプローチから、世界における「暴力の激減」のナゾに迫っています。ここで使われている学問は、著者の専門分野はもちろんのこと、国際関係論・国際政治学のみならず社会思想史、文化人類学、統計学、歴史学、進化生物学など、文理の枠を超えて、「暴力衰退」論を構築しようとしています。さらに、国家間戦争や内戦を含めて、現在に近づくにしたがい、「暴力」があらゆる側面で低下していることを豊富な実証データを使って裏づけています。
では、どのような理由で、国家は戦争をしなくなってきたのでしょうか。人類が暴力に訴えにくくなってきたのは、どうしてなのでしょうか。ピンカー氏の答えは、意外なほどシンプルで簡潔です。つまり、人類は暴力に訴える原動力となる「内なる悪魔(The Inner Demons)」を克服しつつあり、人間本性において、「善なる天使(The Better Angels)」が優位になりつつあるからだというものです。もちろん、彼は人間が前者を撲滅したと主張しているわけではありません。同情や自制心、道義心、理性などが、貪欲や支配、復讐、サディズムなどに打ち勝ちつつある結果、、世界が「平和」になってきたと主張しているのです。
では、なぜ人間本性において「善なる天使」が「内なる悪魔」より、優位になってきたのでしょうか。それをピンカー氏は、進化生物学の視点から解明しようとします。すなわち、暴力のコストが利得を上回るようになってきたため、人間は自然選択の結果として暴力に頼らない適応を遂げてきたと、次のように説明しています。
「暴力の減少(は)…生存と繁栄の成立条件が変わったことに対するダーウィン的な反応だろう…(中略)…暴力は、加害者側に生じさせる幸福よりも多大な不幸を被害者側に生じさせるので、そのすべての幸と不幸を公平無私な観察者が合算すれば、世界の幸福の総量は暴力によって下げられている」(㊦430、550ページ)。
そして、こうした人間の「適応」をうながす外的要因が、「リバイヤサン(国家=政府)」「通商」「女性化」「コスモポリタニズム」「理性のエスカレータ」などです。
ピンカー氏の大胆で物議をかもしそうな「暴力衰退論」や「平和化論」には、もちろん、反論があります。詳しくは、ISA(International Studies Association) の "The Forum: The Decline of War," International Studies Review, No. 15, 2013 をお読みください。ここでは、はじめに、戦争原因研究の大御所であるジャック・リーヴィ氏(ラトガース大学)・ウィリアム・トンプソン氏(インディアナ大学)の反論をざっと紹介します。彼らは、ピンカー氏が戦争衰退の原因として、物質的要因をあまりに軽視している一方、理念的・文化的要因に偏っていると批判しています。ただし、ピンカーの経験的データや「楽観論」には、ほとんど意義を唱えていません。また、直観的にはピンカー氏が説明するように、上記の心理的変数は暴力を減らしているようだが、戦争データのジグザクの軌跡をよく見ると、この理論と合致しない時期も少なくないので、怪しいとのことです。くわえて、リーヴィ氏とトンプソン氏によれば、ピンカー氏の理論は「因果ロジック」に問題があり、「善なる天使」→「暴力の減少」とは限らないと言います。代わりに、彼らは、競合的で危険な国際環境が国家を強くした結果、戦争のコストが上昇して、国家は暴力に訴えにくくなったとの仮説を提示しています。
同じように物質的要因からピンカー氏の「楽観論」は、予測に向かないことを主張したのが、ブラッドリー・セイヤー氏(ユタ州立大学)です。彼は、バランス・オブ・パワーが変われば、人間の特性にも影響するだろうから、「内なる悪魔」を引き戻すことになりかねないと主張します。そこでセイヤ―氏が注目するのは、中国の台頭です。彼によれば、中国はいまだ善なる天使に支配されてないのは明らかです。「中国国民のリバイヤサン(中国共産党による政治支配、引用者)はピンカーの好みではなさそうなのだが、それとも逆に好みなのだろうか」と皮肉っています。そして「中国の相対的パワーの向上が、紛争の重大なリスクと強烈な安全保障上の競争を内包しているのは疑いない」と断じています。南シナ海などで強欲的に現状を打破するリスク受容の中国政府は、近い将来、「善なる天使」に取り込まれるのでしょうか。
国際関係研究の視点からまとめると、ピンカー氏の「暴力衰退論」は、これまで同分野の研究者が、戦争原因の研究において、ややもすれば置き去りにしがちだった「個人レベル」の要因に正面から焦点を当てて、進化生物学などの知見を取り入れながら、その因果関係を明らかにしようとした、画期的で論争的な研究だと思います。それにしても、「戦争」や「暴力」を研究対象に含める日本の主要な2つの学会が、この研究にあまり注目しないのは、ISAとは対照的です。ピンカー氏が、あまりに多くの学術アプローチを総合的に使っているので、少なからぬ日本の研究者たちは、安易に扱うと「やけど」すると判断したのでしょうか。それとも、書評するには値しない研究内容だと判断したのでしょうか...。
追記:ロバート・ジャーヴィス氏が、上記書に関するエッセーを『ナショナル・インタレスト』誌に寄稿していることを知りました。ピンカー氏の主張はよいニュースにもかかわらず、素直に、そう認識できな理由などが論じられています。Robert Jervis, "Pinker the Prophet," National Interest, October 25, 2011. リンクを貼りましたので、ご関心がある方は読んでみてはいかがでしょうか。
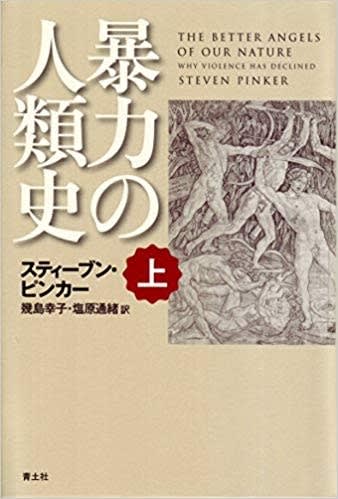
このピンカー氏(ハーバード大学)の著作は、この学問分野の代表的な国際政治学会の機関紙『国際政治』において、これまで書評の対象になっていません。それでは、日本平和学会は、どうなのでしょうか。この学会なら、その活動目的に「様々な暴力を科学的・批判的にとらえて、それらの克服をめざす研究活動」を趣旨として掲げているくらいですから、同会の機関紙『平和研究』が、本書に注目して取り上げてもよさそうでしょう。ですが、私が調べた限りでは、この学会誌も同書を書評していません(見落としていたら、訂正いたします)。ビックリしたのは、私だけでしょうか。
ピンカー著『暴力の人類史』は、文字通りの「大作」です。訳書は、2巻合計で約1200ページ、英語の原書でも、約800ページのボリュームです。もちろん、本書の価値は、その分厚さもさることながら、むしろ内容にあります。ピンカー氏は、認知科学者・進化心理学者ですが、この図書の内容は、これらの学問分野を超えて、文字通り、学際的アプローチから、世界における「暴力の激減」のナゾに迫っています。ここで使われている学問は、著者の専門分野はもちろんのこと、国際関係論・国際政治学のみならず社会思想史、文化人類学、統計学、歴史学、進化生物学など、文理の枠を超えて、「暴力衰退」論を構築しようとしています。さらに、国家間戦争や内戦を含めて、現在に近づくにしたがい、「暴力」があらゆる側面で低下していることを豊富な実証データを使って裏づけています。
では、どのような理由で、国家は戦争をしなくなってきたのでしょうか。人類が暴力に訴えにくくなってきたのは、どうしてなのでしょうか。ピンカー氏の答えは、意外なほどシンプルで簡潔です。つまり、人類は暴力に訴える原動力となる「内なる悪魔(The Inner Demons)」を克服しつつあり、人間本性において、「善なる天使(The Better Angels)」が優位になりつつあるからだというものです。もちろん、彼は人間が前者を撲滅したと主張しているわけではありません。同情や自制心、道義心、理性などが、貪欲や支配、復讐、サディズムなどに打ち勝ちつつある結果、、世界が「平和」になってきたと主張しているのです。
では、なぜ人間本性において「善なる天使」が「内なる悪魔」より、優位になってきたのでしょうか。それをピンカー氏は、進化生物学の視点から解明しようとします。すなわち、暴力のコストが利得を上回るようになってきたため、人間は自然選択の結果として暴力に頼らない適応を遂げてきたと、次のように説明しています。
「暴力の減少(は)…生存と繁栄の成立条件が変わったことに対するダーウィン的な反応だろう…(中略)…暴力は、加害者側に生じさせる幸福よりも多大な不幸を被害者側に生じさせるので、そのすべての幸と不幸を公平無私な観察者が合算すれば、世界の幸福の総量は暴力によって下げられている」(㊦430、550ページ)。
そして、こうした人間の「適応」をうながす外的要因が、「リバイヤサン(国家=政府)」「通商」「女性化」「コスモポリタニズム」「理性のエスカレータ」などです。
ピンカー氏の大胆で物議をかもしそうな「暴力衰退論」や「平和化論」には、もちろん、反論があります。詳しくは、ISA(International Studies Association) の "The Forum: The Decline of War," International Studies Review, No. 15, 2013 をお読みください。ここでは、はじめに、戦争原因研究の大御所であるジャック・リーヴィ氏(ラトガース大学)・ウィリアム・トンプソン氏(インディアナ大学)の反論をざっと紹介します。彼らは、ピンカー氏が戦争衰退の原因として、物質的要因をあまりに軽視している一方、理念的・文化的要因に偏っていると批判しています。ただし、ピンカーの経験的データや「楽観論」には、ほとんど意義を唱えていません。また、直観的にはピンカー氏が説明するように、上記の心理的変数は暴力を減らしているようだが、戦争データのジグザクの軌跡をよく見ると、この理論と合致しない時期も少なくないので、怪しいとのことです。くわえて、リーヴィ氏とトンプソン氏によれば、ピンカー氏の理論は「因果ロジック」に問題があり、「善なる天使」→「暴力の減少」とは限らないと言います。代わりに、彼らは、競合的で危険な国際環境が国家を強くした結果、戦争のコストが上昇して、国家は暴力に訴えにくくなったとの仮説を提示しています。
同じように物質的要因からピンカー氏の「楽観論」は、予測に向かないことを主張したのが、ブラッドリー・セイヤー氏(ユタ州立大学)です。彼は、バランス・オブ・パワーが変われば、人間の特性にも影響するだろうから、「内なる悪魔」を引き戻すことになりかねないと主張します。そこでセイヤ―氏が注目するのは、中国の台頭です。彼によれば、中国はいまだ善なる天使に支配されてないのは明らかです。「中国国民のリバイヤサン(中国共産党による政治支配、引用者)はピンカーの好みではなさそうなのだが、それとも逆に好みなのだろうか」と皮肉っています。そして「中国の相対的パワーの向上が、紛争の重大なリスクと強烈な安全保障上の競争を内包しているのは疑いない」と断じています。南シナ海などで強欲的に現状を打破するリスク受容の中国政府は、近い将来、「善なる天使」に取り込まれるのでしょうか。
国際関係研究の視点からまとめると、ピンカー氏の「暴力衰退論」は、これまで同分野の研究者が、戦争原因の研究において、ややもすれば置き去りにしがちだった「個人レベル」の要因に正面から焦点を当てて、進化生物学などの知見を取り入れながら、その因果関係を明らかにしようとした、画期的で論争的な研究だと思います。それにしても、「戦争」や「暴力」を研究対象に含める日本の主要な2つの学会が、この研究にあまり注目しないのは、ISAとは対照的です。ピンカー氏が、あまりに多くの学術アプローチを総合的に使っているので、少なからぬ日本の研究者たちは、安易に扱うと「やけど」すると判断したのでしょうか。それとも、書評するには値しない研究内容だと判断したのでしょうか...。
追記:ロバート・ジャーヴィス氏が、上記書に関するエッセーを『ナショナル・インタレスト』誌に寄稿していることを知りました。ピンカー氏の主張はよいニュースにもかかわらず、素直に、そう認識できな理由などが論じられています。Robert Jervis, "Pinker the Prophet," National Interest, October 25, 2011. リンクを貼りましたので、ご関心がある方は読んでみてはいかがでしょうか。
















