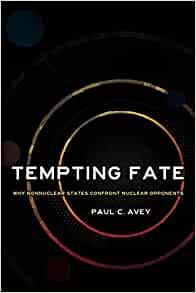ロシアのプーチン大統領による核兵器の威嚇は、多くの人に核戦争の恐怖を思い出させました。桁違いの破壊力を持つ核兵器は、人類に想像を絶する災厄をもたらす「絶対兵器」です。こうした核兵器は、政治学者や国際関係研究者の高い関心の的であり続けました。とりわけアメリカの社会科学者は核兵器の恐怖に縛られても、思考停止することなく、核政治(nuclear politics)の実証研究を積み重ねてきました。
冷戦終焉後、この分野の研究は一時的に停滞しましたが、その後、多くの若い研究者の参入もあり、次々と画期的な理論が構築され、新しい発見がなされています。他方、我が国では「際限もない軍拡競争が起こる」とか、「同盟の信頼性こそが拡大抑止を確実にする」とか、既に用済みとなった半世紀以上前の「お蔵入り」した議論が、「専門家」と言われる人たちの口から、今でも発せられるお寒い状態です。そこで、この記事では、核兵器が戦争や平和、危機、国家の安全保障や戦略、対外政策等に与える影響を明らかにした重要な基礎文献を紹介します。核政治の文献はあまりにも多いので、古典的なもの以外は、今世紀に入ってから発表された、代表的なものに限りました。
核革命論
全ての核政治の土台は、Robert Jervis, The Meaning of Nuclear Revolution, Cornell University Press, 1989の核革命理論です。ここでロバート・ジャーヴィス氏は、戦略家のバーナード・ブローディ氏の「核兵器は軍隊の役割を戦争に勝つことから、戦争を防ぐことに変えた」という主張を発展させました。すなわち、核兵器は国家に究極的な安全保障を提供する(核武装国の生存を脅かす戦争行為は危険すぎてできなくなった)だけでなく、核保有国間では戦争や危機でさえも起こりにくくなり、敵国に耐え難い損害を確実に与えられる核報復力(第二撃能力)を超えた核戦力は政治的に無意味であることを強力な理論として提示しました。

スコット・セーガン、ケネス・ウォルツ、齋藤剛訳『核兵器の拡散』勁草書房、2017年(原著2013年)。
日本語で読める数少ない核政治の書籍です。ここでケネス・ウォルツ氏は、国家が抑止されるのは、核攻撃から受けるコストが利得を上回ると認識するからではなく、核戦争の恐怖であると力説しています。抑止は、コスト>利得という合理性の観点からよく議論されますが、彼は、こうした「合理性」の議論を否定しています。くわえて、ウォルツ氏は核抑止が戦争を防ぐので、核保有国が増えるほど世界は平和になるだろうと考えています。他方、スコット・セーガン氏は、組織論が教えるところは、偶発的核戦争などのリスクを無視できないことであり、核兵器を保有する国家が増えると、世界は危険になると反論しています。
Keir A. Lieber and Daryl G. Press, The Myth of the Nuclear Revolution: Power Politics in the Atomic Age, Cornell University Press, 2020.
ケイル・リーバ氏とダリル・プレス氏による核革命論への反論です。彼らによれば、国家は第二撃能力を持っても、より確実な安全保障を求めて競争を続けることになります。
David C. Logan, "The Nuclear Balance Is What States Make of It," International Security, Vol. 46, No. 4, (Spring 2022), pp. 172–215.
核戦力バランスの最近の定量的研究では、核弾頭数を用いて、核優位性が戦争や危機の力学にどのような影響を与え得るかを検証しています。これらの分析では、国家の核戦力を構成する他の要素は考慮されていません。デーヴィッド・ロガン氏は、この論文において、相対的な核バランスは、技術的・軍事的要素だけでなく、国家の認識や信条にも依存することを明らかにしています。
核兵器による抑止と強制
トーマス・シェリング、齋藤剛訳『軍備と影響力—核兵器と駆け引きの論理—』勁草書房、2018年(原著1966年)。
国家間のバーゲニングにおける暴力とりわけ核兵器の影響力について、その論理を明らかにしています。読者は、ノーベル経済学賞受賞者のトーマス・シェリング氏の冷徹な分析に驚くかもしれませんが、彼の議論が核政治の研究に与えた影響は計り知れません。抑止と強要のメカニズムの違いなどを理解上では必読の学術書です。我が国でシェリング氏が「誤読」されていることについては、こちらの拙文、この研究の「輸入」を怠った学問的代償については、こちらをお読みください。
Todd S. Sechser and Matthew Fuhrmann, Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy, Cambridge University Press, 2017.
本書において、トッド・セクサー氏とマシュー・ファーマン氏は、核兵器が抑止に有効である反面、相手に政治的意思を強要することには、概して向かないことを明らかにしています。
核軍拡
Charles L. Glaser, "When Are Arms Races Dangerous? Rational versus Suboptimal Arming," International Security, Vol. 28, No. 4 (Spring 2004), pp. 44–84.
我が国では、信じがたいことに、軍備増強は際限のない軍拡競争を引き起こし、国家の安全保障を損なうとの「神話」が、今でもしばしば擁護されています。そんなことはありません。チャールズ・グレーザー氏によるこの論文は、軍備増強が国家の安全保障にとって合理的であるケースと最適解以下のケースがあることを明らかにしています。
Robert Jervis, "Why Nuclear Superiority Doesn't Matter," Political Science Quarterly, Vol. 94, No. 4 (Winter, 1979-1980), pp. 617-633.
ここでジャーヴィス氏は、第二撃能力を超えた核武装は政治力として使えないので、核軍拡を無効にすると主張しています。この論文はリンク先に邦訳があります。
Matthew Kroenig, The Logic of American Nuclear Strategy: Why Strategic Superiority Matters, Oxford University Press, 2018.
マシュー・クローニグ氏は、ジャーヴィス氏に反論して、核の優位が危機における政治的意思の競争で勝利をもたらすと主張しています。
拡大抑止
Paul K. Huth, Extended Deterrence and the Prevention of War, Yale University Press, 1988.
拡大抑止論の古典的文献でしょう。ここでポール・ハース氏は、拡大抑止の成否を左右する変数として軍事バランスや同盟国の価値を重視しています。
野口和彦「拡大抑止理論の再構築―信用性と利害関係の視点から―」『東海大学教養学部紀要』第36輯、2005年、167ー181頁。
拙稿では、拡大抑止の効果は信ぴょう性ではなく、抑止提供国と受容国の利害関係に影響されると主張しました。
相互確証破壊(MAD: Mutual Assured Destruction)
ケイル・リーバー、ダリル・プレス「21世紀の核抑止力を考える―抑止力への信頼性を再確立するには—」『フォーリン・アフェアーズ・リポート』2009年11月。
Keir A. Lieber, Daryl G. Press, "The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence," International Security, Vol. 41, No. 4, 2017, pp. 9–49.
相手に耐え難い損害を与える非脆弱な核戦力を持つ国家間には、これまで「相互確証破壊」が成立していました。このために、先制核攻撃の誘因を持たない戦略的安定性が保れていましたが、軍事関連技術の進歩等により、アメリカは第一撃(先制攻撃により相手の核戦力を無力化する)能力を持つようになり、相互抑止が脆くなっていると著者たちは警告しています。
核拡散
Alexander Debs and Nuno P. Monteiro, Nuclear Politics: The Strategic Causes of Proliferation, Cambridge University Press, 2017.
核兵器の拡散は、国家が核爆弾を作る意思と機会の両方がある時にのみ起こることを理論と膨大な事例研究により明らかにした労作です。著者たちの理論は、核兵器を開発した国が、これほどまでに少ない理由を説明するものです。
マシュー・ファーマン、藤井留美訳『原子力支援—「原子力の平和利用」がなぜ世界に核兵器を拡散させたか—』太田出版、2015年(原著2012年)。
本書は、より高いレベルの平和的原子力支援を受けたが、特に支援を受けた後に国際的な危機を経験した場合、核兵器を追求し取得する傾向が強いことを明らかにしています。
核保有国と非核国の対立
Paul C. Avey, Tempting Fate: Why Nonnuclear States Confront Nuclear Opponents, Cornell University Press, 2019.
核時代におけるパラドックスは、核兵器を保有しない通常戦力で劣る国家が、戦力に優る核保有国と戦うことです。詳しくは、こちらの記事をお読みください。
核保有国の行動パターン
Mark S. Bell, Nuclear Reactions: How Nuclear-Armed States Behave, Cornell University Press, 2021.
核革命論は第二撃能力が国家の対外行動を現状維持志向にすると予測しますが、マーク・ベル氏が構築した「核の機会主義理論」は、国家が核武装により、さまざまな政治目的(領土紛争での侵攻、断固とした姿勢、国益の拡大、同盟強化、独立した対外政策など)を追求するようになることを明らかにしています。
我が国の大学・大学院では、核政治や核戦略に特化した授業や講座は、ほとんどないでしょう。したがって、国際政治に対する核兵器の影響については、自分で勉強しないと、論理的に筋が通らない「俗説」を信じてしまったり、根拠のない主張に拘泥されたりしてしまいます。核兵器や核エスカレーションを正しく恐れると同時に、その特性を的確に理解して、平和や安全保障に役立つ政策を立案することは、国家の指導者に課せられた責任でしょう。同時に、核兵器に関する問題は、政治家や軍人のみにまかせるには、あまりにも重大すぎます。民主社会における市民は、核兵器を曇りのない視点で理解するべきです。核政治や核抑止、核戦略に関する研究は膨大ですが、ここに挙げた図書や論文を読めば、その概要は把握できるでしょう。核問題にアプローチするには、残念ながら日本語で書かれた文献は少ないために、英語で書かれたものを読まなくてはなりません。
このブログの文献解題が、核政治に対する皆様のより深い知識の獲得と思考の向上に貢献できれば幸いです。
冷戦終焉後、この分野の研究は一時的に停滞しましたが、その後、多くの若い研究者の参入もあり、次々と画期的な理論が構築され、新しい発見がなされています。他方、我が国では「際限もない軍拡競争が起こる」とか、「同盟の信頼性こそが拡大抑止を確実にする」とか、既に用済みとなった半世紀以上前の「お蔵入り」した議論が、「専門家」と言われる人たちの口から、今でも発せられるお寒い状態です。そこで、この記事では、核兵器が戦争や平和、危機、国家の安全保障や戦略、対外政策等に与える影響を明らかにした重要な基礎文献を紹介します。核政治の文献はあまりにも多いので、古典的なもの以外は、今世紀に入ってから発表された、代表的なものに限りました。
核革命論
全ての核政治の土台は、Robert Jervis, The Meaning of Nuclear Revolution, Cornell University Press, 1989の核革命理論です。ここでロバート・ジャーヴィス氏は、戦略家のバーナード・ブローディ氏の「核兵器は軍隊の役割を戦争に勝つことから、戦争を防ぐことに変えた」という主張を発展させました。すなわち、核兵器は国家に究極的な安全保障を提供する(核武装国の生存を脅かす戦争行為は危険すぎてできなくなった)だけでなく、核保有国間では戦争や危機でさえも起こりにくくなり、敵国に耐え難い損害を確実に与えられる核報復力(第二撃能力)を超えた核戦力は政治的に無意味であることを強力な理論として提示しました。

スコット・セーガン、ケネス・ウォルツ、齋藤剛訳『核兵器の拡散』勁草書房、2017年(原著2013年)。
日本語で読める数少ない核政治の書籍です。ここでケネス・ウォルツ氏は、国家が抑止されるのは、核攻撃から受けるコストが利得を上回ると認識するからではなく、核戦争の恐怖であると力説しています。抑止は、コスト>利得という合理性の観点からよく議論されますが、彼は、こうした「合理性」の議論を否定しています。くわえて、ウォルツ氏は核抑止が戦争を防ぐので、核保有国が増えるほど世界は平和になるだろうと考えています。他方、スコット・セーガン氏は、組織論が教えるところは、偶発的核戦争などのリスクを無視できないことであり、核兵器を保有する国家が増えると、世界は危険になると反論しています。
Keir A. Lieber and Daryl G. Press, The Myth of the Nuclear Revolution: Power Politics in the Atomic Age, Cornell University Press, 2020.
ケイル・リーバ氏とダリル・プレス氏による核革命論への反論です。彼らによれば、国家は第二撃能力を持っても、より確実な安全保障を求めて競争を続けることになります。
David C. Logan, "The Nuclear Balance Is What States Make of It," International Security, Vol. 46, No. 4, (Spring 2022), pp. 172–215.
核戦力バランスの最近の定量的研究では、核弾頭数を用いて、核優位性が戦争や危機の力学にどのような影響を与え得るかを検証しています。これらの分析では、国家の核戦力を構成する他の要素は考慮されていません。デーヴィッド・ロガン氏は、この論文において、相対的な核バランスは、技術的・軍事的要素だけでなく、国家の認識や信条にも依存することを明らかにしています。
核兵器による抑止と強制
トーマス・シェリング、齋藤剛訳『軍備と影響力—核兵器と駆け引きの論理—』勁草書房、2018年(原著1966年)。
国家間のバーゲニングにおける暴力とりわけ核兵器の影響力について、その論理を明らかにしています。読者は、ノーベル経済学賞受賞者のトーマス・シェリング氏の冷徹な分析に驚くかもしれませんが、彼の議論が核政治の研究に与えた影響は計り知れません。抑止と強要のメカニズムの違いなどを理解上では必読の学術書です。我が国でシェリング氏が「誤読」されていることについては、こちらの拙文、この研究の「輸入」を怠った学問的代償については、こちらをお読みください。
Todd S. Sechser and Matthew Fuhrmann, Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy, Cambridge University Press, 2017.
本書において、トッド・セクサー氏とマシュー・ファーマン氏は、核兵器が抑止に有効である反面、相手に政治的意思を強要することには、概して向かないことを明らかにしています。
核軍拡
Charles L. Glaser, "When Are Arms Races Dangerous? Rational versus Suboptimal Arming," International Security, Vol. 28, No. 4 (Spring 2004), pp. 44–84.
我が国では、信じがたいことに、軍備増強は際限のない軍拡競争を引き起こし、国家の安全保障を損なうとの「神話」が、今でもしばしば擁護されています。そんなことはありません。チャールズ・グレーザー氏によるこの論文は、軍備増強が国家の安全保障にとって合理的であるケースと最適解以下のケースがあることを明らかにしています。
Robert Jervis, "Why Nuclear Superiority Doesn't Matter," Political Science Quarterly, Vol. 94, No. 4 (Winter, 1979-1980), pp. 617-633.
ここでジャーヴィス氏は、第二撃能力を超えた核武装は政治力として使えないので、核軍拡を無効にすると主張しています。この論文はリンク先に邦訳があります。
Matthew Kroenig, The Logic of American Nuclear Strategy: Why Strategic Superiority Matters, Oxford University Press, 2018.
マシュー・クローニグ氏は、ジャーヴィス氏に反論して、核の優位が危機における政治的意思の競争で勝利をもたらすと主張しています。
拡大抑止
Paul K. Huth, Extended Deterrence and the Prevention of War, Yale University Press, 1988.
拡大抑止論の古典的文献でしょう。ここでポール・ハース氏は、拡大抑止の成否を左右する変数として軍事バランスや同盟国の価値を重視しています。
野口和彦「拡大抑止理論の再構築―信用性と利害関係の視点から―」『東海大学教養学部紀要』第36輯、2005年、167ー181頁。
拙稿では、拡大抑止の効果は信ぴょう性ではなく、抑止提供国と受容国の利害関係に影響されると主張しました。
相互確証破壊(MAD: Mutual Assured Destruction)
ケイル・リーバー、ダリル・プレス「21世紀の核抑止力を考える―抑止力への信頼性を再確立するには—」『フォーリン・アフェアーズ・リポート』2009年11月。
Keir A. Lieber, Daryl G. Press, "The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence," International Security, Vol. 41, No. 4, 2017, pp. 9–49.
相手に耐え難い損害を与える非脆弱な核戦力を持つ国家間には、これまで「相互確証破壊」が成立していました。このために、先制核攻撃の誘因を持たない戦略的安定性が保れていましたが、軍事関連技術の進歩等により、アメリカは第一撃(先制攻撃により相手の核戦力を無力化する)能力を持つようになり、相互抑止が脆くなっていると著者たちは警告しています。
核拡散
Alexander Debs and Nuno P. Monteiro, Nuclear Politics: The Strategic Causes of Proliferation, Cambridge University Press, 2017.
核兵器の拡散は、国家が核爆弾を作る意思と機会の両方がある時にのみ起こることを理論と膨大な事例研究により明らかにした労作です。著者たちの理論は、核兵器を開発した国が、これほどまでに少ない理由を説明するものです。
マシュー・ファーマン、藤井留美訳『原子力支援—「原子力の平和利用」がなぜ世界に核兵器を拡散させたか—』太田出版、2015年(原著2012年)。
本書は、より高いレベルの平和的原子力支援を受けたが、特に支援を受けた後に国際的な危機を経験した場合、核兵器を追求し取得する傾向が強いことを明らかにしています。
核保有国と非核国の対立
Paul C. Avey, Tempting Fate: Why Nonnuclear States Confront Nuclear Opponents, Cornell University Press, 2019.
核時代におけるパラドックスは、核兵器を保有しない通常戦力で劣る国家が、戦力に優る核保有国と戦うことです。詳しくは、こちらの記事をお読みください。
核保有国の行動パターン
Mark S. Bell, Nuclear Reactions: How Nuclear-Armed States Behave, Cornell University Press, 2021.
核革命論は第二撃能力が国家の対外行動を現状維持志向にすると予測しますが、マーク・ベル氏が構築した「核の機会主義理論」は、国家が核武装により、さまざまな政治目的(領土紛争での侵攻、断固とした姿勢、国益の拡大、同盟強化、独立した対外政策など)を追求するようになることを明らかにしています。
我が国の大学・大学院では、核政治や核戦略に特化した授業や講座は、ほとんどないでしょう。したがって、国際政治に対する核兵器の影響については、自分で勉強しないと、論理的に筋が通らない「俗説」を信じてしまったり、根拠のない主張に拘泥されたりしてしまいます。核兵器や核エスカレーションを正しく恐れると同時に、その特性を的確に理解して、平和や安全保障に役立つ政策を立案することは、国家の指導者に課せられた責任でしょう。同時に、核兵器に関する問題は、政治家や軍人のみにまかせるには、あまりにも重大すぎます。民主社会における市民は、核兵器を曇りのない視点で理解するべきです。核政治や核抑止、核戦略に関する研究は膨大ですが、ここに挙げた図書や論文を読めば、その概要は把握できるでしょう。核問題にアプローチするには、残念ながら日本語で書かれた文献は少ないために、英語で書かれたものを読まなくてはなりません。
このブログの文献解題が、核政治に対する皆様のより深い知識の獲得と思考の向上に貢献できれば幸いです。