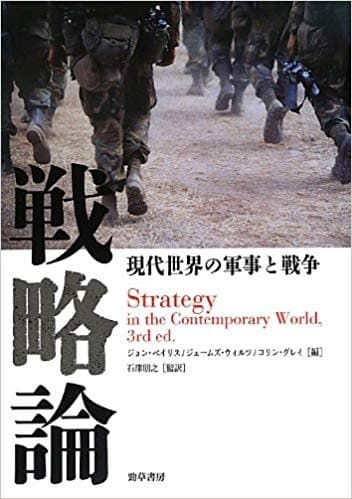中国の急激な台頭は、米中の覇権交代をもたらし、その過程で大きな混乱やトラブルを引き起こすのではないかと懸念されています。中国はGDPで既に日本を追い抜き、アメリカに追いつくのも時間の問題と予測されています。国力にとって重要な高等教育や研究をつかさどる大学ランキングにおいても、中国の勢いはとまりません。最新のTimes Higher Education発表の世界大学ランキングにおいて、中国の精華大学はアジアトップに躍り出ました(世界22位)。さらに北京大学(31位)、香港大学(36位)、香港科技大学(46位)といったように、中国の大学はもはや世界トップの常連です。アメリカの大学も依然として強いですが、日本は…。東京大学が42位にポツンといる寂しい状況です。
多くの人たちが中国の総合的な国力の急上昇を懸念する中、「中国はたいしたことない」と大胆に主張する研究が発表されました。著者は、新進気鋭の政治学者、マイケル・ベックレイ氏(タフツ大学)です。彼は、『フォーリン・アフェアーズ』誌に発表した論文「中国に強迫観念を持つのはやめよう―中国がアメリカの覇権を脅かすことのない理由―」において、「アメリカは経済と軍事において中国を大きくリードしている。中国には、アメリカの世界的優位に挑戦できる余地などない」と結論づけています。どういうことでしょうか。
ベックレイ氏は、国力をGDPや軍事支出で測ることが、そもそも間違っていると言います。なぜなら、人口が多い国家は、それらの数値が大きくなり、その結果、パワーを過大評価するミスにつながりやすいからです。パワーというものは、国家が持つ資源のストックだけでなく、それをどう効率よく使えるかにもかかわります。つまり、経済・軍事資源の保有量だけで国力をみるのは誤りだということです。彼は経済力の計算には、「資源の純ストック」(生産資本・人的資本・自然資本)といった指標を使用すべきだと主張しています。こうした指標を使って米中の経済力を測ると、アメリカは中国の数倍の規模になり、そのリードは縮まるどころか、年々拡大しているそうです。軍事力も米国の対中優位は変わりません。火力、精度、射程距離において、中国の武器はアメリカの半分程度の能力しかありません。また、兵士の練度や軍事力の展開能力においても、アメリカは中国を圧倒しています。これれらの証拠は、中国が次の来るべき覇権国ではないことを示唆しているのです。
他方、日本の安全保障にとって気になるのは、海洋における日米中のパワーバランスです。このことについて、ベックレイ氏は別稿「東アジアにおける軍事バランス―どのように中国の周辺国は中国の海洋拡張行動を阻止できるのか― 」(『国際安全保障』42:2、2017年秋)において、「中国は戦力投射能力に余裕がなく、周辺国の拒否力を凌駕できないため、台湾を征服することはできないのみならず、東シナ海および南シナ海で自らの主張を各国に強要でいる見込みもほとんどない」と結論づけています。東シナ海における日中の軍事バランスについて、彼は日本に分があると見ています。第1に、西南諸島に展開する日本の移動式地対空ミサイルや対艦ミサイルは、中国の攻勢を拒否できるだけの能力を備えています。第2に、東シナ海域では、日米が張り巡らせた優れた監視システムにより、中国艦船の動向はつぶさに捉えられています。第3に、日本は高い対潜戦能力とりわけ機雷封鎖戦に強く、中国は掃海能力に欠けることです。最後に、日本は第5世代の航空機(F-35)を導入し始めていることもあり、今後も航空優勢を維持できるだろうということです。したがって、中国は総トン数において日本に優りますが、東シナ海において、日本は中国の航空優勢や制海権の確立を阻止できるだろうと、彼は分析しています。
ベックレイ氏によれば、アメリカ(そして日本も?)にとっての脅威は、中国そのものではなく、ありもしない中国の影におびえて中国に対抗する結果、敵意のスパイラルが上昇することです。このような政策提言には賛否両論あるでしょうが、中国の台頭の実態や外交政策上の含意を再検討することには、大きな意義があることでしょう。
多くの人たちが中国の総合的な国力の急上昇を懸念する中、「中国はたいしたことない」と大胆に主張する研究が発表されました。著者は、新進気鋭の政治学者、マイケル・ベックレイ氏(タフツ大学)です。彼は、『フォーリン・アフェアーズ』誌に発表した論文「中国に強迫観念を持つのはやめよう―中国がアメリカの覇権を脅かすことのない理由―」において、「アメリカは経済と軍事において中国を大きくリードしている。中国には、アメリカの世界的優位に挑戦できる余地などない」と結論づけています。どういうことでしょうか。
ベックレイ氏は、国力をGDPや軍事支出で測ることが、そもそも間違っていると言います。なぜなら、人口が多い国家は、それらの数値が大きくなり、その結果、パワーを過大評価するミスにつながりやすいからです。パワーというものは、国家が持つ資源のストックだけでなく、それをどう効率よく使えるかにもかかわります。つまり、経済・軍事資源の保有量だけで国力をみるのは誤りだということです。彼は経済力の計算には、「資源の純ストック」(生産資本・人的資本・自然資本)といった指標を使用すべきだと主張しています。こうした指標を使って米中の経済力を測ると、アメリカは中国の数倍の規模になり、そのリードは縮まるどころか、年々拡大しているそうです。軍事力も米国の対中優位は変わりません。火力、精度、射程距離において、中国の武器はアメリカの半分程度の能力しかありません。また、兵士の練度や軍事力の展開能力においても、アメリカは中国を圧倒しています。これれらの証拠は、中国が次の来るべき覇権国ではないことを示唆しているのです。
他方、日本の安全保障にとって気になるのは、海洋における日米中のパワーバランスです。このことについて、ベックレイ氏は別稿「東アジアにおける軍事バランス―どのように中国の周辺国は中国の海洋拡張行動を阻止できるのか― 」(『国際安全保障』42:2、2017年秋)において、「中国は戦力投射能力に余裕がなく、周辺国の拒否力を凌駕できないため、台湾を征服することはできないのみならず、東シナ海および南シナ海で自らの主張を各国に強要でいる見込みもほとんどない」と結論づけています。東シナ海における日中の軍事バランスについて、彼は日本に分があると見ています。第1に、西南諸島に展開する日本の移動式地対空ミサイルや対艦ミサイルは、中国の攻勢を拒否できるだけの能力を備えています。第2に、東シナ海域では、日米が張り巡らせた優れた監視システムにより、中国艦船の動向はつぶさに捉えられています。第3に、日本は高い対潜戦能力とりわけ機雷封鎖戦に強く、中国は掃海能力に欠けることです。最後に、日本は第5世代の航空機(F-35)を導入し始めていることもあり、今後も航空優勢を維持できるだろうということです。したがって、中国は総トン数において日本に優りますが、東シナ海において、日本は中国の航空優勢や制海権の確立を阻止できるだろうと、彼は分析しています。
ベックレイ氏によれば、アメリカ(そして日本も?)にとっての脅威は、中国そのものではなく、ありもしない中国の影におびえて中国に対抗する結果、敵意のスパイラルが上昇することです。このような政策提言には賛否両論あるでしょうが、中国の台頭の実態や外交政策上の含意を再検討することには、大きな意義があることでしょう。