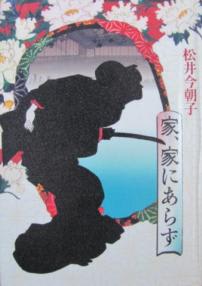
今年2月に『吉原手引草』と『仲蔵狂乱』を立て続けに読んで以来、この作家の小説を興味にまかせた順番で読み進めてきた。これが15冊目になる。(当ブログを開設してからは、この本が最初に読了したもの。)
登場人物の筋からすると、歌舞伎物の系譜だがちょっと脇道にそれた謎解き小説といえる。
「家、家にあらず」というタイトルは、世阿弥の『風姿花伝』(『花伝書』)の第七「別紙口伝」中、最後から二つ目の条に記された文言が引用されている。世阿弥は能の伝承の観点で述べているが、作者はそれを武家大名の「家」というものに重ね合わせ、さらに大名屋敷の奥御殿に住む女たちの世界における「人」に重ねて合わせていったのだろう。「家、家にあらず・・・・・人、人にあらず・・・・」この言葉の意味するものがこの本の主題であり、読者への問いかけなのだ。
中心人物が複数いる。それぞれの生き様という点でも興味深い。
瑞江 :笹岡伊織の娘で、おば様(浦尾)の声がかりで大名屋敷の奥勤めに出る。
浦尾 :志摩二十余万石の大名、砥部家の奥御殿御年寄。
笹岡伊織 :北町奉行所同心。定町廻り。芝居検分も職務のうち。
荻野沢之丞:中村座立女形。
真幸 :砥部家の奥御殿表使。
貞徳院 :砥部家藩主生母
大名屋敷の奥勤めに出た瑞江が、奥女中の世界に当初一種のカルチャーショックを感じながら、いじめを経験し、長局全体の人間関係も分かり始め、少しずつ奥勤めに慣れていく。ところが、長局において、立て続けに、中老・玉木の死、当藩主の元乳母で今は茶の湯の師匠を務める五百崎の死に巻き込まれる。玉木は自室での自害として扱われる事件、一方、五百崎の死は、先代藩主時代の中老で何十年も前から心の箍がはずれている「おゆら様」に刺し殺された態の事件である。玉木の自害に不審を抱き、五百崎の刺殺された現場に駆けつけて見聞した瑞江は、二人の死について疑惑を深め、その奥に隠された謎を推理しようとする。二人の死の事件それぞれに御年寄・浦尾が様々に表の重臣との間で話し合いを繰り返し、行動している様子を瑞江は見聞する。三之間勤めという下層奥女中の視点から大名家の実態に触れていく。奥女中の口の端から様々な情報を集め、自らの推理を働かせ、謎を解こうとする。そこは、同心の娘として育った性なのか、究明心を突き動かされるのだった。
一方、父・笹岡伊織は、男女一対の屍体が大川の百本杭に引っかかったという相対死(心中)事件を扱う立場になる。男は人気歌舞伎役者・小佐川十次郎で、女は水茶屋の主人の妹だが、砥部家下屋敷の奥勤めをしていたことがやがて判明する。二人の屍体を検分したことで、伊織は心中という点に不審を抱き、探索を始める。役者仲間の荻野沢之丞は、番所に呼び出されて、伊織から小佐川のことについて事情聴取を幾度も受ける。その過程で大名屋敷内の舞台での歌舞伎披露の宴のことに話が及んでいく。
娘・瑞江が奥勤めをする砥部家に関わるきな臭い筋書きが伊織には読めてくる。そして、その大名屋敷で娘が奥勤めしていることへの気懸かりが強くなる。娘は娘で、自分の推理と疑問を父に伝えてみようと、然るべきルートを通じて文を託す行動に出る。
二十年前の苦い思い出に再び関わりたくはないと思いつつも、沢之丞は結局関わりを深めざるを得なくなり、伊織の手助けをする役回りを担っていく。
大名・砥部家のお家騒動、八丁堀同心・笹岡家の秘め事、歌舞伎役者・荻野沢之丞の家と言う形で、「家、家にあらず」というフレーズが幾重にも色合いを変えながら関わっていくのだ。
さてこの謎解き、攻め口は二つ。父・伊織の扱う事件からのアプローチと、長局での見聞情報を土台に瑞江が行う推理のアプローチ。その二つがいつしか収斂していくという構成上の面白さがこの本の特徴だろう。瑞江の推理が主で、父の事件が添えになり、事の広がりを読者に示唆していく。
本文中に、書体を変えた記述がいくつか出てくる。これがストーリー展開の中で重要な伏線を果たしている。(読後にそれが一層明瞭になった。)そして、個々の事件を集約した大本の問題の解明が進展する。それと同時に、やはりそうだったのか・・・別次元の事実が解き明かされるという二重構造のしかけに驚嘆する。本文中の言葉の各所に作者のしかけが潜んでいたのだ。
大名屋敷内の長局という特異空間での殺人事件。密室殺人趣向の謎解きを瑞江と一緒に楽しんでいただくとよい。そして、奥勤めでの瑞江自身の心の動きを味わってもらうと、一層興味深いものになろう。
この小説の副産物が併せておもしろい。大名屋敷の長局における奥女中の日常生活を垣間見させてくれるところが一つの興味深い点だ。奥女中の位・格式、生活様式、愛欲の確執、生活の保障、外部世界との関わり方・・・・など。さらに、当時の歌舞伎役者の有り様の一端が窺えるという点、定町廻り同心の実態という点、も挙げることができる。
作者の引用した言葉に触れておこう。(この本の標題ページの裏に引用文が記載されている。)
『花伝書(風姿花伝)』(世阿弥編 川瀬一馬校注、現代語訳 講談社文庫)から引用する。
原文
一、この別紙の口伝・当芸において、家の大事、一代一人相伝なり。たとへ一子たりといふとも、不器量の者には伝ふべからず。「家家にあらず、続くをもて家とす。人人にあらず、知るをもて人とす。」といへり。これ万徳了達の妙花をきはむるところなるべし。
現代語訳
一、この別紙の口伝は、この申楽芸において、観世の家の大事なことで、一代には一人だけ受け伝えるというものである。たとい、一人っ子であろうとも、才能の無い者には伝えてはならなぬ。古人も「芸の家というものは血統が続くのが家ではない、芸の真髄が続くのが家である。人間は人間の形をしているのが人間ではない、人の道を知っているのが人間である。」と言っている。そういうのが、あらゆる徳をすっかり修めつくした芸の上の妙花を究めた境地というのであろう。
そこで、作者の引用文だが「家、家にあらず。継ぐをもて家とす。」となっている。『風姿花伝』にも表記の異本があるということなのだろうか。
末尾にネット検索でサンプリングしたように、「続く」とする出版物の方は見つけることができたのだが・・・・。
「知るをもて人とす」に値する人が、「続くをもて家とす」ということに意味が存在する。「人人にあらず」レベルの輩が画策して、「続くをもて家とす」と思うとしたら、それは間違いだということなのだろう。
砥部家の奥御殿は後者の現状になることを浦尾は恐れたということなのだろう。笹岡伊織の家は「続くをもて家とす」そのものであり、荻野沢之丞の家は、いずれ『風姿花伝』どおりに歩むということなのだろうか。この小説を読み、引用文を確認して、そんな思い抱いた。
作者は本文の中で、笹岡伊織に、その父に臨終のきわでこう言わせた。
「伝えておきたいことがある」「我が家は、家にあらず、と心せよ」と。
伊織はこう解釈していると記す。
「お前は立派な家に生まれたわけではない。黙っていても代々受け継いでいけるような家をもたない身分なのだから、業を懸命に磨くことでしか世を渡れないぞ、と父は諭すつもりだったのだろう。たしかにこの役目は当人の年季と腕だけがものをいう。」
伊織の父の臨終の言葉には、伊織のこの思い以外にも意味が込められていたのではなかろうか。「風姿花伝」の言の如くに。
この小説に出てくる言葉について、より深く楽しむために、ビジュアル情報その他をネット検索してみた。そして、そこからのワード連想も。
裲襠(うちかけ)
笄(こうがい)
片外し :御殿女中の髪型の一つ
銀杏髷 :ウィキペディアから
築地塀
長屋門
荻野沢之丞
歌舞伎の鬘
烏枢沙摩明王 :ウィキペディアから
烏枢沙摩明王 画像集
江戸時代に実在した藩の一覧 :ウィキペディアから
江戸三百藩HTML便覧
秋海棠、鳳仙花、曼珠沙華、桔梗、小車、藤袴、
「植物園へようこそ!」の「名前による索引」から、これらの花々をお楽しみください
羅漢槇 この庭木も上記の植物園サイトで見られます。
『花伝書』の該当条について :岩波文庫(昭和10年9刷)
44/56のページをご確認ください。
『花伝書・能作書 校註』中の該当条について :新日本図書(昭和22)
55/76のページをご確認ください。
ご一読ありがとうございます。



















