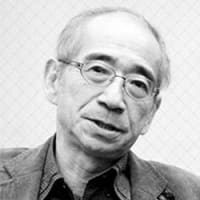▲ 今週のみけちゃん
▼ 新しい街でもぶどう記録;第455週

■ 武相境斜面



■ 今週の草木花実



■ 今週の連合国 Uuited nations、いわゆる国連
国連ビジネスと人権の作業部会が4日、東京・内幸町の日本記者クラブで会見した。同部会は初めて日本を公式訪問。7月24日から8月4日にわたり、ジャニーズ事務所のジャニー喜多川前社長による性加害疑惑についても聞き取り調査をしており、「深く憂慮すべき疑惑が明らかになった」などと指摘した。(ソース)

ジャニー喜多川が子供たちに性的虐待を行っていたのは、米軍住宅であるワシントン・ハイツであった。ジャニー喜多川の国籍ははっきりしないのだが、彼は朝鮮戦争に従軍している。その後、ワシントン・ハイツに住んでいるのだから米軍の軍属であり、米軍属なのだから米国人なのだろう。ところで、朝鮮戦争で米軍は国連軍となった。したがって、今さらであるが、「国連ビジネスと人権の作業部会」はおのれの組織の軍事組織の一員が「犯した」蛮行の調査をしたこととなる。

YouTube 70年前の"ジャニー氏性加害"を告白【報道特集】
ジャニー喜多川が、さんざん噂されながら、逃れられてきたのは、米軍特権に守られていたのだろう。もちろん、ジャニーズ事務所経営時は米軍の軍属ではないが、何か庇護者がいるとみるのが当然ではないか?
一方、日本の警察・検察のペドロフィア・マニアのためにジャニー喜多川が「生贄」をだしていたのではないか?というホリ〇モンの主張は、いささか、かなりspeculation( 〔不確かな情報に基づく〕推論、臆測 、投機の意味もある)ではある。
■ 今週借りていて、読んだ本

『江藤淳と少女フェミニズム的戦後』1998-1999年の文章、『村上春樹論ーサブカルチャーと倫理』1994-2002年の文章、『物語論で読む村上春樹と宮崎駿』2009年。
▼ 江藤淳
江藤淳はかつて村上龍をサブカルチャーだと云って批判し、その文学性、表現を評価しなかった。江藤のいうサブカルチャーとは何か?という問題について、大塚英志は考えている。なので、おいらは大塚英志に興味があり、見てみた。江藤淳は現代日本の文学状況をサブカルチャー化に堪えかねて、毎日新聞の文藝時評を1970年代末に、ちょうど村上龍がデビューし村上春樹がデビューする前に、辞めた。しかし、江藤淳はその後も新人文学賞の審査委員を続け、サブカルチャー化した日本現代文学につきあいつづけたのだという。その詳細が書かれている。
▼ 村上春樹
<サブカルチャーを利用したガジェット集積作品>
大塚英志の村上春樹作品の認識は、物語は過去からの定型をなぞったものであり、構成要素・プロットは過去のサブカルチャーから採取したガジェットが多いとの指摘。このガジェットの寄せ集めで物語をつくりあげるのはオウム真理教と類似したものであると主張。だから、村上春樹はオウム真理教を見たときに正視に堪えなかったのだという。
<戦争と憲法>
大塚英志による湾岸戦争後の村上春樹の言動についての言及。湾岸戦争の3年後の話(1994年)。この頃から、自由主義史観グループなどによる歴史認識問題/新規歴史教科書刊行運動が生じていた。前世紀末。大塚英志は湾岸戦争を受けての日本の安全保障政策転換、憲法見直運動に危機感をもったらしい。その後、戦後民主主義擁護運動(?)、憲法「選び直し」運動を行う。こういう状況で、湾岸戦争を受けて、村上春樹の「動揺」について『村上春樹論ーサブカルチャーと倫理』において論じている。その中で村上春樹のインタビューが引かれている。現在、どの単行本のこのインタビューが入っているのかわからないので、村上春樹の発言を孫引きとして引用する。
当時、多くのアメリカ人に「お前は日本人として湾岸戦争についてどう思うか?」と面と向かって尋ねられたんです。もちろん僕は僕なりに考えてたんだけれど、答えながら自分で何かひとつしっくりしないところがある。「俺は今本当の言葉で喋ってないな」というのが自分でなんとなくわかるんです。そういうのって、言葉を職業とする小説家としてはけっこう辛いんです。僕らは冷戦時代の育ちだから、極端にいえば右か左か前か後かというものの捉え方が自然に身についてしまっている。でもそういう従来の政治的な観点からはポスト冷戦の枠組みの中での湾岸戦争とは何か、自分がそれに対してどのように対処していかなくてはならないかというヴィジョンがなかなか見えてこないわけです。
僕は平和憲法で育った世代です。僕の子供の頃の日本は決して今のように豊かな国ではなかったけれど、僕は子供心に自分の国に対して誇りのようなものを持つことができたと思う。中略 でも文章をなりわいとする人間として今この九条の条文をあらためて文章的に読み直してみると、哀しいことだけど、僕はそこからもはや美しさや気概というものをかつてほど強く感じることができない。それを長い年月にわたって損なってきたのは、僕ら自身の中の誤魔化しであり偽善性ではなかったかと思うんです
これらの発言内容について、大塚英志は、「いたって凡庸な戦後民主主義批判である」という。なお、自由主義史観グループの中心人物のひとりである(元日本共産党員)藤岡信勝は「1991年に米国に渡る。湾岸戦争を契機に、「一国平和主義」を脱し、司馬遼太郎の著作や渡米体験を通じて冷戦終結後の新しい日本近代史観確立の必要性を感じたという」(wiki)。つまり、村上春樹と同じ時期、すなわち湾岸戦争勃発時、滞米していた。大塚英志は村上春樹が、自由主義史観グループ的動きをしないか危惧したのだろう。
一方、以下、おいらの意見。村上春樹が日本の憲法ー安保体制の欺瞞性をイラクのクウエート侵略:湾岸戦争で初めて悟ったかのような発言にびっくした。村上春樹は大学生であったときの「1968年運動」は、戦後民主主義の欺瞞、日米安保体制、憲法による日本の武装解除と日米地位協定による米軍天国、沖縄の米軍要塞化による日本の「平和」を暴いたのでは?と思っていた。この1994年の村上春樹のインタビューを読むと、1991年で初めて気づいたかのようだ。村上春樹は「1968年」の人ではなかったのか?
■ 今週の購書

「Stories of a Paratrooper in Occupied Japan: A Clerk and Paratrooper in the 11th Airborne Division in Sendai, Japan in 1946-47 after WW II. 」 (Amazon)
米軍の第11空挺師団所属の軍人の自伝の存在をネットで知り、贖う。米軍の第11空挺師団とは敗戦後、マッカーサー来日のため、「厚木」に到来した最初の日本本土への進駐軍。この部隊の話はこれまで、たくさんしてきた。例えば、「子猿の話」。同師団はこの後、仙台、札幌に進駐。こういう中で、第11空挺師団所属の軍人の自伝「Stories of a Paratrooper in Occupied Japan」を知る。贖う。この本、日本で印刷された本であった。みてみると、著者 Norman R. Hansen は1928年生まれ。18歳で入隊し、来日する。この時点で戦争は終わっていた。したがって、「厚木」に来た第11空挺師団兵士ではないのだ。その点、残念。著者 Norman R. Hansen は、2016年、88歳で死去。この本は最晩年に書かれた。N.R. Hansenは1946年に来日し、仙台に駐留、1947年に帰国。仙台での従軍勤務は1年。その1年の話が書いてある。つまり、戦場体験がない兵士の日本滞在記。
シアトルから船で横浜に到着。その後、第11空挺師団が駐屯している仙台へ。基地は、キャンプ・シンメルフェニヒ(現在、苦竹の仙台駐屯地)。一方、訓練は、Carelus operation field in Yamato (現在、王城寺原演習場 [wiki])。なお、Carelus operation field in Yamatoは、ググってもヒットしない。まず、王城寺原演習場の一部は大和(たいわ)町である。おそらく、当時、米軍は大和=Yamatoと呼称していたのだろう。さらに、Carelusがわからなかった。これは固有名詞で、人名。日本到来前のフィリピン戦で事故死したCharles Carelus大尉にちなみつけられた戦域(演習所)名(ソース)。なお、王城寺原演習場の前は、矢野目(現在の仙台空港付近)を演習場にしていた。そこでの体験が書いてある。仙台(苦竹)と大和の往復は列車。車内の写真が載せてある。日頃は、フットボールやスキーなどで余暇を過ごしていた。市内の様子も写真が載せてある。

Stories of a Paratrooper in Occupied Japan:

八木山橋と龍ノ口渓谷 Stories of a Paratrooper in Occupied Japan:
▼ 札幌に行く
第11空挺師団は仙台から札幌に移駐したことは愚ブログで書いたことがある。この移駐はすべての第11空挺師団が札幌に移ったのではないと知る。司令部は札幌に移ったが仙台に残った部隊もあるのだ。N.R. Hansenは仙台「残留」組。そして、札幌に出張業務があったと書いてある。「りんご箱」に「組織と設備の表( TOE または TO&E) [wiki]」を詰めて、札幌に運んだ。1947年1月。進駐軍も「りんご箱」(apple boxとある)も使っていたのだ。段ボール箱なぞない時代だ。札幌の基地は月寒のキャンプ・シーデンバーグに行ったはずだ。なぜなら、当時日本最大級といわれ第八軍最高司令官アイケルバーガーが贅沢すぎるといったキャンプ・クロフォードは1947年秋の開設であったからだ。仙台からの列車の旅は青函連絡船の乗り場の写真などがある。ただし、札幌の写真はなく、さらに、著者は残念なことにほとんど忘れてしまい、街の積雪のこと以外、記憶がないと報告している。
7月には、仙台港から小樽港まで駆逐艦 USS hollister に乗り、青森方面に行っている。小樽まで行って、列車で仙台に帰ってきたとある。
1947年9月には横浜港からサンフランシスコへ帰国。このあと、GI奨学金をうけて、大学に行く。3人の子供、9人の孫、10人のひ孫に恵まれる。2016年、88歳で死去。
▼ 米軍・第11空挺師団の概略史
■