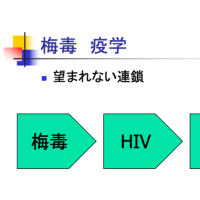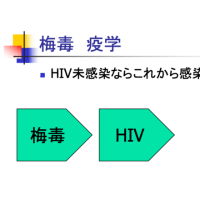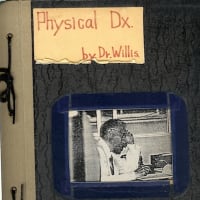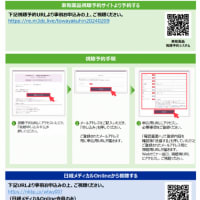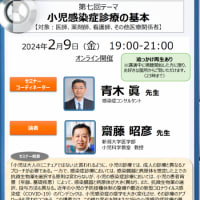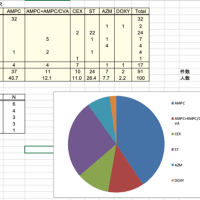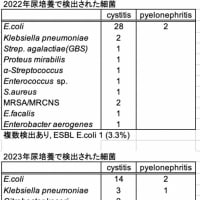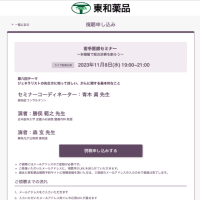感染症は人権とセットに語られることが多いのですが、よく考えないで中途半端な議論をすると誤解を広げるリスクがある場面にしばしば出会います。
偏見・差別とセットにしてしまう人が多いのですが、偏見と差別には大きな違いがありますので、実際にその問題がおきているのかどうか、それはどう不適切なのかを検討する必要があります。
インターネット辞書をみますと、偏見は「かたよった見方。ゆがめられた考え方・知識にもとづき、客観的根拠がないのに、特定の個人・集団などに対して抱く非好意的な意見や判断、またそれにともなう感情。」とあります。
えーい!偏見をもってやれ!と思ってもつのではなく、ある人の価値観や基準ベースでおきるものですので、ゼロにはできませんし、いけないことかといわれたら、偏見はヨクナイと思想統一されるほうが怖いようにおもいます。
問題は対人・社会コミュニケーションにおいて相手や周囲を不快にさせない表現(出さない)工夫、というのが実際のところです。
差別はどうでしょうか。
(1)ある基準に基づいて、差をつけて区別すること。扱いに違いをつけること。また、その違い。
とあります。思い込みではなく(個人レベルではなく)何か必要があって基準があり、その「扱いがかわる」こと。その基準は妥当ですか?ということが問われます。
(2)偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。また、その扱い。
ということが問題になります。実際に何か不利益・不平等が生じているか?が重要なポイントです。
偏見と差別には違いがあります。
多くの人は「これって偏見かなー」とチラリおもいつつ、何らかの価値観や基準をもっていますが、誰かを差別してやれ!というコミュニケーションを悪意をもっていることは稀だと考えると、よく検討もしないで「それは差別ですっ!」と言い切るのはとても危険だとおもいます。
北海道新聞に医学生が関わるシンポジウムの記事がありました。
B型肝炎訴訟に関連したもののようです。
『食器の共用では感染しないにもかかわらず、入院した病院で食器に赤い印をつけられた原告の差別体験・・・』
とあります。
ぎょ! いつの時代の話だ?とか、そのときの状態は?といった情報がないのでそのことじたいはさておきますが、食器にマーキングなんてみためbeautifulではないので、色や柄などで不快な感情につながらない工夫があるんじゃないの?とか、そもそも分けないといけないんだろうか(家庭で?病院で?)、わける必要があるとしたらどんなとき?等。
マネジメントに必要なディスカッション事項があります。学部1年生あたりに考えてもらいたい切り口です。
学会のQ&Aコーナー
B型肝炎患者の食器をどうしたらよいですか?
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/2006_10_pdf/13.pdf
血液感染と血液の付着した食器をどうしたらよいですか?
http://www.jarmam.gr.jp/situmon3/ketsueki-kansen.html
病棟や施設で指示を出す立場になったり、マネジメントに関わるようになると、スタッフが安心して働くこともよいケアにつながる必要条件だと知ります。
ヒューマンエラーをおこさず、根拠無く不愉快な思いをしないように配慮する、そのために意見や質問をいいやすくする(看護師長や院長への手紙BOXをつくる)ことも工夫のひとつ。
医療者の行動や態度が社会にリスクメッセージとして伝わることも忘れないように。
偏見・差別とセットにしてしまう人が多いのですが、偏見と差別には大きな違いがありますので、実際にその問題がおきているのかどうか、それはどう不適切なのかを検討する必要があります。
インターネット辞書をみますと、偏見は「かたよった見方。ゆがめられた考え方・知識にもとづき、客観的根拠がないのに、特定の個人・集団などに対して抱く非好意的な意見や判断、またそれにともなう感情。」とあります。
えーい!偏見をもってやれ!と思ってもつのではなく、ある人の価値観や基準ベースでおきるものですので、ゼロにはできませんし、いけないことかといわれたら、偏見はヨクナイと思想統一されるほうが怖いようにおもいます。
問題は対人・社会コミュニケーションにおいて相手や周囲を不快にさせない表現(出さない)工夫、というのが実際のところです。
差別はどうでしょうか。
(1)ある基準に基づいて、差をつけて区別すること。扱いに違いをつけること。また、その違い。
とあります。思い込みではなく(個人レベルではなく)何か必要があって基準があり、その「扱いがかわる」こと。その基準は妥当ですか?ということが問われます。
(2)偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。また、その扱い。
ということが問題になります。実際に何か不利益・不平等が生じているか?が重要なポイントです。
偏見と差別には違いがあります。
多くの人は「これって偏見かなー」とチラリおもいつつ、何らかの価値観や基準をもっていますが、誰かを差別してやれ!というコミュニケーションを悪意をもっていることは稀だと考えると、よく検討もしないで「それは差別ですっ!」と言い切るのはとても危険だとおもいます。
北海道新聞に医学生が関わるシンポジウムの記事がありました。
B型肝炎訴訟に関連したもののようです。
『食器の共用では感染しないにもかかわらず、入院した病院で食器に赤い印をつけられた原告の差別体験・・・』
とあります。
ぎょ! いつの時代の話だ?とか、そのときの状態は?といった情報がないのでそのことじたいはさておきますが、食器にマーキングなんてみためbeautifulではないので、色や柄などで不快な感情につながらない工夫があるんじゃないの?とか、そもそも分けないといけないんだろうか(家庭で?病院で?)、わける必要があるとしたらどんなとき?等。
マネジメントに必要なディスカッション事項があります。学部1年生あたりに考えてもらいたい切り口です。
学会のQ&Aコーナー
B型肝炎患者の食器をどうしたらよいですか?
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/2006_10_pdf/13.pdf
血液感染と血液の付着した食器をどうしたらよいですか?
http://www.jarmam.gr.jp/situmon3/ketsueki-kansen.html
病棟や施設で指示を出す立場になったり、マネジメントに関わるようになると、スタッフが安心して働くこともよいケアにつながる必要条件だと知ります。
ヒューマンエラーをおこさず、根拠無く不愉快な思いをしないように配慮する、そのために意見や質問をいいやすくする(看護師長や院長への手紙BOXをつくる)ことも工夫のひとつ。
医療者の行動や態度が社会にリスクメッセージとして伝わることも忘れないように。