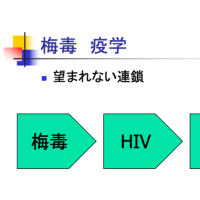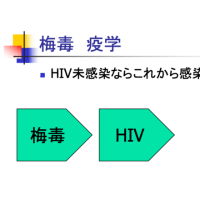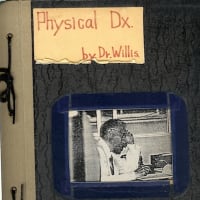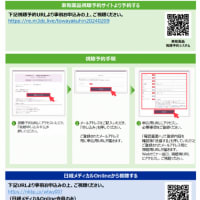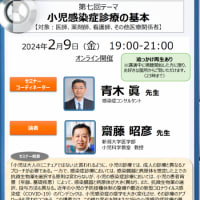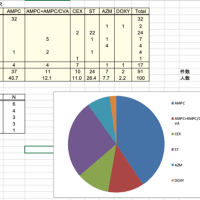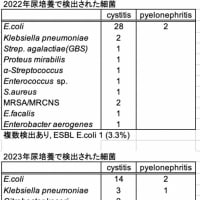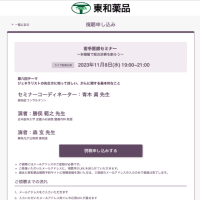病原性微生物が問題となった(なる)食材がわかれば(知っていれば)、回収したり、調理法を注意したり、別の産地からとりよせたりと工夫ができますし、対策をすれば改善するものもあります。
体調が悪くなったとしても、治療があったり、身体が勝って、たいていの場合、どこかの時点でその原因も消えます。
しかし放射性物質は事情が大きくことなります。
放射性物質は、煮ても焼いても消えません。自ら「半減期」で減っていくのを待つだけです。
洗い流せば水系が汚染され、現在は処理場の汚泥が高度に汚染されており、現在その処理でもめています。
埋め立てると雨水などで地下水を汚染します。
燃やせば大気中に拡散してより広く環境を汚染します。
コンクリートにまぜて流通させる、肥料用の土にまぜてもよい、というアイデアが採用されていますが、その先のリスクのアセスメントは不十分といわれています。
目に見えないので、思考停止にならないようにしよう!と思わなければ自分のリスクと考えるのはとても難しい状況にあります。

現在、このことに一番関心をもっているのは、小さなお子さん~思春期のお子さんがいるご家庭、そして妊婦さん。

柚木ミサトさんのイラストはこちらTwitter @pelukiss。
(「1日1絵」のページ)
「検出限界以下ですから安心です」は、もし基準値が1の場合、0.9ならOKなわけですが、食事をするときはそれだけではないですし、「積算」で考えていきます。
ですので、(ちょっと単純すぎる式ですみませんが)0.9+0.9+0.9+0.9をどう考えるのか?という問題がお母さんたちを不安にしています。
現在、自分の住んでいる地域で流通している食品の安全がどのように考えられ、担保されているかは、自分で考えて調べないとわからない状況にあります。考えるのメンドクセという場合は、思考停止に何でも受け入れる(気にしない)、あるいは大事をとって自分で決めた条件以外のものはやめておくということになります。
神楽坂にあるオーガニックのお店が閉店の理由として、工夫の中でも安全性の確保ができない、ということを上げています。
「震災にともなう原発事故の影響で東京の空気や土、水もあっさりと汚染されてしまいました。この間、契約農家の野菜も出荷停止となったり、本来健全であった魚や肉類にも放射能の影響が出てくるようになりました。私はそのような状況下で、レストランにとって最低限の必要条件=『安全な食事』をみなさんに提供するのを不可能と考え、また、今後短期間に事態の収束が見込めないため、閉店の決断をいたしました。」
TVのニュースでも、「安全ですよ」「ただちに問題はありません」というコメントが流れています。
リテラシーとかリスコミの話にもつながっていきますが、判断の基準が「公的な見解」にあれば、そこで納得する人もいるのだとおもいます。
しかし、ずっと複数の情報源を見ている人たちは(リスクテイクの基本)、そもそも安全性の基準の値がかなりいきあたりばったりに変更されていることを知っています。
なので、その数字(基準)が納得いかない、と引っかかる人もいれば、「数字はよくわかんないけど、動きが怪しすぎて信用ならない」と思う人たちもいます。
他の国はどうしているんだろう?世界的なスタンダードってあるのかな?と感染症対策でも思うわけです。


(以上2つの資料は金吾さんのHPにあります。 金吾さんTwitter @kingo999 )
新聞やTVの報道のもとになっているのは「記者会見」(と、そのあとのぶらさがり取材)ですが、これをみると、検査を外注しているのに「まだ検査に出していません」と回答したり、時期を大きくずらして測定する、測定した値が高いのに地名を公表しないというやりとりがあり、「そもそも発表されている情報はどこまでがホントなのか」がよくわからなくなります。
(記者会見はインターネット「ニコニコ生放送」でどなたでも見ることができます。アーカイブもあります)
見ていると、何が真実はわかりませんが、「誠意に基づいたせいいっぱいの事実」と信用できないところ(そういったやりとりがくりひろげられている風景)が悲しいところです。
環境省、農水省、厚生労働省、文部科学省の代表が東電+経産省の保安院会見+政府の会見にでてきていろいろ説明をしてくれてはいるのですが。
特に、高度に汚染された水が海洋に放出された件については、世界から非難をされているのですが、国内のメディアはそのことをほとんど伝えていません。
(可能な人は英語メディアを併用して考える)
日本人の食卓に欠かせない海産物については、勝川俊夫先生の公式サイトが参考になります。「長いものには 巻かれません」の先生です。
「食品の放射性物質の暫定基準値はどうやって決まったか」
放射性物質の広がりを考えれば、牛から検出されたという話は「いまさら」感があります。
全頭検査という展開も、この国が今までやってきた危機管理のストーリーからして想定内。
「ヒステリックになったら食べるものがなくなるじゃないか」・・は現実です。
もう、こどもをもつ年齢ではない人や、50歳以上は、気にせず食べましょう、と厳しい話をする専門家でさえいっています。
「そのかわり、子どもたちには安全なものを提供しましょう」です。
その努力や工夫はしなくてはいけません。おおざっぱすぎる許容論や、ヒステリックな反応は、この直面している課題の思考を遠ざけます。
「うちにはもう小さい子はいないからいいや」ではなく、皆で守ろうという話につなげていかないと、です。(その先の話はまた別記事で)
社会における「子どもを守る」という精神や空気(の有無)は、ワクチンの話などともリンクしています。
お子さんのいる家庭がしている工夫
宅配野菜
■Oisix 放射性物質に関する取り組みについて
■らでぃっしゅぼーや 「西日本の野菜をオーダーできる」
■大地を守る会 「子どもたちへの安心野菜セット」
教育関係の動き
学校の給食 たとえば
■世田谷区 「学校給食の食材の安全性(牛乳の放射性物質測定など)」7月11日
ずっと水をためていたプール(緑色になっちゃった状態)の清掃は、これまでは子供たちがやっていたところが多いのですが、こどもではなく大人がやろうと保護者が申し出ている学校も多数あります。
修学旅行や林間学校の訪問先を変更したり、原発事故が子どもたちの生活含め、社会や経済に与えている影響は多岐にわたっています。
体調が悪くなったとしても、治療があったり、身体が勝って、たいていの場合、どこかの時点でその原因も消えます。
しかし放射性物質は事情が大きくことなります。
放射性物質は、煮ても焼いても消えません。自ら「半減期」で減っていくのを待つだけです。
洗い流せば水系が汚染され、現在は処理場の汚泥が高度に汚染されており、現在その処理でもめています。
埋め立てると雨水などで地下水を汚染します。
燃やせば大気中に拡散してより広く環境を汚染します。
コンクリートにまぜて流通させる、肥料用の土にまぜてもよい、というアイデアが採用されていますが、その先のリスクのアセスメントは不十分といわれています。
目に見えないので、思考停止にならないようにしよう!と思わなければ自分のリスクと考えるのはとても難しい状況にあります。

現在、このことに一番関心をもっているのは、小さなお子さん~思春期のお子さんがいるご家庭、そして妊婦さん。

柚木ミサトさんのイラストはこちらTwitter @pelukiss。
(「1日1絵」のページ)
「検出限界以下ですから安心です」は、もし基準値が1の場合、0.9ならOKなわけですが、食事をするときはそれだけではないですし、「積算」で考えていきます。
ですので、(ちょっと単純すぎる式ですみませんが)0.9+0.9+0.9+0.9をどう考えるのか?という問題がお母さんたちを不安にしています。
現在、自分の住んでいる地域で流通している食品の安全がどのように考えられ、担保されているかは、自分で考えて調べないとわからない状況にあります。考えるのメンドクセという場合は、思考停止に何でも受け入れる(気にしない)、あるいは大事をとって自分で決めた条件以外のものはやめておくということになります。
神楽坂にあるオーガニックのお店が閉店の理由として、工夫の中でも安全性の確保ができない、ということを上げています。
「震災にともなう原発事故の影響で東京の空気や土、水もあっさりと汚染されてしまいました。この間、契約農家の野菜も出荷停止となったり、本来健全であった魚や肉類にも放射能の影響が出てくるようになりました。私はそのような状況下で、レストランにとって最低限の必要条件=『安全な食事』をみなさんに提供するのを不可能と考え、また、今後短期間に事態の収束が見込めないため、閉店の決断をいたしました。」
TVのニュースでも、「安全ですよ」「ただちに問題はありません」というコメントが流れています。
リテラシーとかリスコミの話にもつながっていきますが、判断の基準が「公的な見解」にあれば、そこで納得する人もいるのだとおもいます。
しかし、ずっと複数の情報源を見ている人たちは(リスクテイクの基本)、そもそも安全性の基準の値がかなりいきあたりばったりに変更されていることを知っています。
なので、その数字(基準)が納得いかない、と引っかかる人もいれば、「数字はよくわかんないけど、動きが怪しすぎて信用ならない」と思う人たちもいます。
他の国はどうしているんだろう?世界的なスタンダードってあるのかな?と感染症対策でも思うわけです。


(以上2つの資料は金吾さんのHPにあります。 金吾さんTwitter @kingo999 )
新聞やTVの報道のもとになっているのは「記者会見」(と、そのあとのぶらさがり取材)ですが、これをみると、検査を外注しているのに「まだ検査に出していません」と回答したり、時期を大きくずらして測定する、測定した値が高いのに地名を公表しないというやりとりがあり、「そもそも発表されている情報はどこまでがホントなのか」がよくわからなくなります。
(記者会見はインターネット「ニコニコ生放送」でどなたでも見ることができます。アーカイブもあります)
見ていると、何が真実はわかりませんが、「誠意に基づいたせいいっぱいの事実」と信用できないところ(そういったやりとりがくりひろげられている風景)が悲しいところです。
環境省、農水省、厚生労働省、文部科学省の代表が東電+経産省の保安院会見+政府の会見にでてきていろいろ説明をしてくれてはいるのですが。
特に、高度に汚染された水が海洋に放出された件については、世界から非難をされているのですが、国内のメディアはそのことをほとんど伝えていません。
(可能な人は英語メディアを併用して考える)
日本人の食卓に欠かせない海産物については、勝川俊夫先生の公式サイトが参考になります。「長いものには 巻かれません」の先生です。
「食品の放射性物質の暫定基準値はどうやって決まったか」
放射性物質の広がりを考えれば、牛から検出されたという話は「いまさら」感があります。
全頭検査という展開も、この国が今までやってきた危機管理のストーリーからして想定内。
「ヒステリックになったら食べるものがなくなるじゃないか」・・は現実です。
もう、こどもをもつ年齢ではない人や、50歳以上は、気にせず食べましょう、と厳しい話をする専門家でさえいっています。
「そのかわり、子どもたちには安全なものを提供しましょう」です。
その努力や工夫はしなくてはいけません。おおざっぱすぎる許容論や、ヒステリックな反応は、この直面している課題の思考を遠ざけます。
「うちにはもう小さい子はいないからいいや」ではなく、皆で守ろうという話につなげていかないと、です。(その先の話はまた別記事で)
社会における「子どもを守る」という精神や空気(の有無)は、ワクチンの話などともリンクしています。
お子さんのいる家庭がしている工夫
宅配野菜
■Oisix 放射性物質に関する取り組みについて
■らでぃっしゅぼーや 「西日本の野菜をオーダーできる」
■大地を守る会 「子どもたちへの安心野菜セット」
教育関係の動き
学校の給食 たとえば
■世田谷区 「学校給食の食材の安全性(牛乳の放射性物質測定など)」7月11日
ずっと水をためていたプール(緑色になっちゃった状態)の清掃は、これまでは子供たちがやっていたところが多いのですが、こどもではなく大人がやろうと保護者が申し出ている学校も多数あります。
修学旅行や林間学校の訪問先を変更したり、原発事故が子どもたちの生活含め、社会や経済に与えている影響は多岐にわたっています。