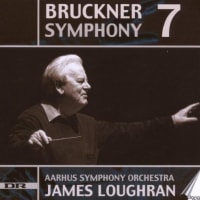ベルリンに戻ってプ―ランクのオペラ「カルメル会修道女の対話」をみた。2009年の新国立劇場オペラ研修所の公演が記憶に新しいが、あれはまだプロの公演ではなかったと、ベルリンのこの公演をみて思った。ドラマの掘り下げが、プロはちがう。
演出はギュンター・クレーマー。あちこちでみているが、決定的だったのは、ドレスデンでみたオトマール・シェックのオペラ「ペンテジレーア」だ。原作のハインリヒ・フォン・クライストの戯曲もすごいが、シェックの音楽も圧倒的だ。クレーマーの演出は原作・音楽と同じレベルで共鳴していた。人間の狂気の果ての魂の崇高さといったらよいか。精神的なものをここまで表現できる演出家は、ほかにいないのではないかと思った。
「カルメル会修道女の対話」も、ひたすら作品の本質に迫ろうとする演出だった。無駄なものをそぎ落とし、骨太にドラマを描こうとする気迫。舞台にたち現れる人間のドラマの崇高さ。
ところどころに細かいカットがあった。一例をあげるなら、ブランシュの兄が修道院を訪れる場面では、慌てるリドワーヌ修道院長とマリー修道女の部分はカットされ、いきなりブランシュとその兄の重苦しい対話になった。このように、説明的な部分はカットし、本筋のみを語り続ける演出だ。
舞台装置はなにもない。背景の巨大な黒い壁だけ。機械設備もむき出しだ。そんなことにはお構いなし。修道女たちは黒い修道服。舞台は黒のモノトーンだ。ブランシュだけが白い服。頭には白と緑の花冠を巻いている。それがイエスの茨の冠のようにみえてきた。ブランシュは世の贖罪の子羊か。
ブランシュと同じようにマリー修道女にも焦点があてられていた。その描き方は、ひたすら殉教を主張するドグマティックな人物ではなく、苦悩する人間として。これには共感した。そもそもこの物語は、フランス革命のさなかに起きた事件を、唯一人生き残ったマリー修道女が手記に残したものだ。その手記をナチスの猛威におびえるゲルトルート・フォン・ル・フォールが小説にした。それをジョルジュ・ベルナノスが、亡くなる前に、戯曲にした。プーランクは作曲中に精神的な危機に陥り、入院騒ぎになった。このオペラにはこれらの人々の危機が多層的に重なり合っている。本作が特別なオペラたる所以だ。
ミヒャエラ・カウネがリドワーヌ修道院長を歌っていた。昨年、新国立劇場の「アラベッラ」であでやかな姿をみせてくれたが、今回は一転して老け役。指揮はイヴ・アベル。本年6月には新国立劇場で「蝶々夫人」を振る指揮者だ。
(2011.2.12.ベルリン・ドイツ・オペラ)
演出はギュンター・クレーマー。あちこちでみているが、決定的だったのは、ドレスデンでみたオトマール・シェックのオペラ「ペンテジレーア」だ。原作のハインリヒ・フォン・クライストの戯曲もすごいが、シェックの音楽も圧倒的だ。クレーマーの演出は原作・音楽と同じレベルで共鳴していた。人間の狂気の果ての魂の崇高さといったらよいか。精神的なものをここまで表現できる演出家は、ほかにいないのではないかと思った。
「カルメル会修道女の対話」も、ひたすら作品の本質に迫ろうとする演出だった。無駄なものをそぎ落とし、骨太にドラマを描こうとする気迫。舞台にたち現れる人間のドラマの崇高さ。
ところどころに細かいカットがあった。一例をあげるなら、ブランシュの兄が修道院を訪れる場面では、慌てるリドワーヌ修道院長とマリー修道女の部分はカットされ、いきなりブランシュとその兄の重苦しい対話になった。このように、説明的な部分はカットし、本筋のみを語り続ける演出だ。
舞台装置はなにもない。背景の巨大な黒い壁だけ。機械設備もむき出しだ。そんなことにはお構いなし。修道女たちは黒い修道服。舞台は黒のモノトーンだ。ブランシュだけが白い服。頭には白と緑の花冠を巻いている。それがイエスの茨の冠のようにみえてきた。ブランシュは世の贖罪の子羊か。
ブランシュと同じようにマリー修道女にも焦点があてられていた。その描き方は、ひたすら殉教を主張するドグマティックな人物ではなく、苦悩する人間として。これには共感した。そもそもこの物語は、フランス革命のさなかに起きた事件を、唯一人生き残ったマリー修道女が手記に残したものだ。その手記をナチスの猛威におびえるゲルトルート・フォン・ル・フォールが小説にした。それをジョルジュ・ベルナノスが、亡くなる前に、戯曲にした。プーランクは作曲中に精神的な危機に陥り、入院騒ぎになった。このオペラにはこれらの人々の危機が多層的に重なり合っている。本作が特別なオペラたる所以だ。
ミヒャエラ・カウネがリドワーヌ修道院長を歌っていた。昨年、新国立劇場の「アラベッラ」であでやかな姿をみせてくれたが、今回は一転して老け役。指揮はイヴ・アベル。本年6月には新国立劇場で「蝶々夫人」を振る指揮者だ。
(2011.2.12.ベルリン・ドイツ・オペラ)