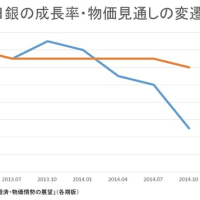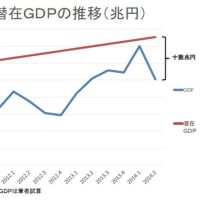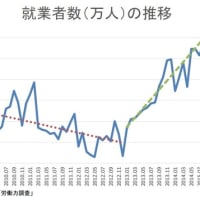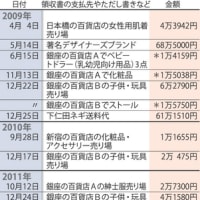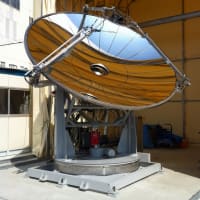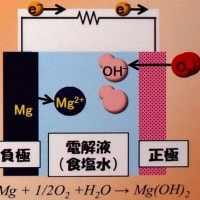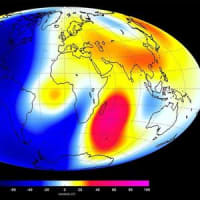発・送・配電は大規模統合し、小売りサービス競争を促進
2011年12月27日、枝野経済産業大臣が「電力システム改革タスクフォース論点整理」を公表した。この論点整理をもとに、これから電力システム改革の議論が本格化する。
本稿では、そうした議論に一石を投じるために、筆者の考え方に基づいて具体的な電力システム改革の方向性と電力産業再編案を提示したい。発送電分離論や自由化問題に対して一定の回答を示しつつ、論点整理に含まれていない原子力発電の取り扱いも加えて、具体的な構想を述べる。
電力会社は大規模化する方が合理的
日本の電力システムは、(1)安定供給に必要十分な一定のゆとり(冗長性)を持った設備の確保、(2)国際エネルギー市場で伍していける購買力の形成、(3)電源の多様化によるリスク分散、の3つの条件を満たす必要がある。
(1)の安定供給のための予備力については、市場の価格シグナルに委ねるだけでは、必ずしも必要な設備投資がなされない。そもそも安定供給のために必要な予備的設備は、厳しい競争下では「余剰」設備になるからだ。米国や欧州のような自由化先行国でも、発送電の設備形成不足が解消せず、市場メカニズムを補完するさまざまな方策が検討されている。
(2)の燃料輸入についての問題は深刻だ。化石燃料については、基本的には独占企業体や資源国政府との交渉で利権を確保してく必要がある。国内の発電市場での競争だけを考えれば、プレイヤーが多いほど良いということになるが、その分対外的には小さな購買主体が独占体を相手に調達交渉を挑むことになる。双方独占的な交渉ができなければ、結局大きな国富が流出してしまうだろう。
(3)についても、国内市場の競争が厳しければ、どの事業者も、燃料の多様化が重要と頭では理解していても、短期的に有利な電源(英国のケースではガス火力)の建設に走ってしまうだろう。国全体としてのエネルギー安全保障の確保・リスク分散は果たせなくなる。また、民営による原子力発電や核燃料サイクル事業を維持するのであれば、運営主体である民間電力会社は財務的に盤石な体制を確保し、安全対策費用や保険料はもちろんのこと、賠償リスクも民間分担分を負える体力を持たなければならない。
以上のような理由から、筆者は、日本の電力会社は発送電分離を進めて小さな主体に分割するよりも、むしろ大規模化を目指す方が合理的だと考えている。これは、発電分野の新規参入を促して電気料金低減を目指す競争政策とは逆の方向である。しかし、現状のような供給力が不足している状況の下で自由化を進めれば、料金はむしろ上昇するのは自明の理である。政治的に料金を上げないように抑制している現在の政府の対応は、「自由化を進める」という自らの政策そのものに矛盾している。
家庭ユーザーが求めるは料金メニューの多様化
今後の電力システムにおいてどんな競争が期待されているのか。確かに、既に自由化されている大口ユーザーの間では、電気の価格と質が重要な要素となるため、発送電分離も一つの回答かもしれない。しかし、原発事故を契機に電力システムについて関心を持ち始めたユーザーは、家庭を中心とする小口ユーザーだ。彼らは、単なる安さだけではなく、むしろ料金メニューや購入する電源について「多様な選択肢が提供されること」を望んでいるというのが筆者の実感だ。一言でいえば、今後は発電分野の競争に重点を置くよりも、ユーザーへのサービスを巡る競争を促進する政策に焦点を当てていくべきなのである。
発電分野は、(例えば電気通信分野に比べて)技術革新は活発とは言えず、需要も成熟化に向かう見込みの下で、自由化を進めても新規参入はそれほど見込めない。対照的に、太陽光発電や燃料電池、蓄電池といった新たな電力供給設備や、需要情報を細かくやりとりできるスマートメーターの設置が需要側で進む。それゆえ近い将来、ユーザーに対して提供されるサービスについては、新たな付加価値を生む商品開発や技術革新の進展が期待されている。
そうだとすると、必要なのは「小売りサービス多様化モデル」による自由化である。発電から送電・配電に至るシステムとこれを通じて供給される電力、つまり電力卸分野を共通インフラと位置付け、燃料調達交渉力や余剰設備を維持できる財務力を有する事業規模を確保する。他方で、そこから共通の条件で卸電力供給を受ける多数の小売事業者が、需要側のサービスの分野で工夫をこらして競争するという新たな自由化モデルだ。送電線開放モデルでは発送電分離が求められるが、このモデルでは発電から送電、配電は一体を維持する一方で、小売りサービス部門を分離することになる。
「小売りサービス」を分離して自由化する
この自由化モデルのイメージをもう少し膨らませてみよう。
現在の比較的狭い供給エリアをまたいで大規模化した電力会社が、共通インフラとしての卸電力を供給する主体となる。系統の最適な規模や周波数の差異問題なども勘案すると、全国に3~4社程度になるだろうか。この発送配電網を管理する大規模卸電力会社は、受け持ちエリアの電力需要を想定し、安定供給に必要十分な一定のゆとりを持った設備を確保する。また、まとまった需要を強みに、燃料調達で購買パワーを発揮し、電源種の多様化によるリスク分散を推進する。
一方、これまでの既存の電力会社の小売り部門は、発送配電網管理会社と組織的に分離する(法人または資本分離)。小売り部門には多様な小売りサービス・パッケージを販売する企業が参入し、上記の既存電力会社系小売りサービス会社と競争する。これまでの供給者の論理に立ちがちであったと言われる電力会社の硬直的なサービス内容も多様化を迫られよう。
小売り部門に対して付与されるライセンスを電気事業法で新たに規定すれば、将来さまざまな業態の電力関連サービス会社がそのライセンスを取得して新規参入してくると期待される。それとともに、より先端的・創造的なサービスを提供するビジネスモデルを目指して、各社間で戦略的な資本提携や業務提携が進むとこともあるだろう。鉄道や航空事業を行うインフラサービス提供会社とそれらを組み合わせてユーザーに魅力的なパッケージ商品を提供する旅行会社とが存在する旅行業分野をイメージすれば分かりやすいだろう。なお、既存のPPS(特定規模電気事業者)も小売りサービス会社となり、確保している電源は、IPP(卸電力事業)化して大規模卸電力会社にコストベースで卸売りする。
再編した大規模会社はやはり地域独占となるので、効率的な事業運営を確保するための規律づけが大きな課題となる。電源の建設については、自社の建設計画とIPPとの競争入札を活用することが考えられる。競争入札でIPPが落札した場合は、事業主体の実力にもよるが、交渉力確保のため、燃料調達は卸電力会社が代行し、購入実費+手数料で売り渡すことも考えられよう。
日々の需給運用においては、手持ちの全電源の発電コストを把握した上で、コストが最小になるように発電所を運転する。デマンドレスポンスもオープンかつ積極的に活用する。また、他の大規模卸電力会社との間では、燃料費の安い余剰電源がある場合は、お互いに融通し合うなど経済ベースの相対卸取引を積極的に実施するものとする。
卸電力会社が電力を安定供給
卸電力システムは共通インフラであるので、自社系列の小売りサービス会社だけでなく、すべての小売りサービス会社に対して同じ条件で電力を卸す。具体的には、時間帯別(例えば30分毎)の電力の需給を反映して合理的な卸電力価格を算定し、その価格ですべてのサービス会社に電力を卸す。価格の決め方は、あらかじめ供給曲線を公表し、各時間帯の需要に対応して決まるようにする。設備の定期点検などで電源構成は時期によって変わるので、3カ月に1度程度のペースで供給曲線を見直すこととする。価格は基本的にコストベースであり、かかったコストは固定費を含めて回収できるように制度設計する。
それとは別に、送配電ネットワークの利用料金は、ユーザーの受電電圧によりあらかじめ定められた料率で課金する。こうした料金は、設備投資の十全性と効率的経営の徹底を前提とし、すべての小売りサービス会社に対して公平・透明な規制価格となる。
物理的な電気の供給は大規模卸電力会社の仕事である。つまり、停電などが起こった場合の対応は卸電力会社がすべての需要家・小売りサービス会社に対して公平に行う。日本の電力会社が有する「現場力」もこの形態であれば維持されよう。
再生可能エネルギーによる電気は、固定価格買取制度にしたがって卸電力会社が一括して買い上げ、その費用を卸電力価格に反映する。再生可能エネルギーの大量連系を可能とするような系統対策も積極的に進める。ただし、そのための費用負担はユーザーに転嫁されることになる。
大規模卸電力会社は、わが国の電力産業全体が国際競争力をもつための産業政策としても重要な意味を持ち得る。大規模卸電力会社は、アジアを中心に成長するインフラ事業を、わが国の新たな成長産業として取り込んでいくために、エネルギー分野のフラッグシップ企業として大きな役割を果たす。国内では、新たな発電技術、例えば、1700℃級ガスタービンのGTCC(ガスタービンコンバインドサイクル発電)やIGCC(石炭ガス化複合発電)の実用化に向けての取り組みなど、国策に沿った電源開発・電力技術開発を進める主体を担う。海外では、国内で培った建設監理や運転・保守のノウハウを駆使し、日本の電力技術をパッケージ化して売り込んでいく主体を担う。さらにはパッケージ化した技術を、温暖化対策で新たに排出枠を獲得するための二国間オフセット・クレジットシステム事業の有力なプロジェクトとしてつくり込むことができる。これは発電技術に限らず送配電技術でも同様だ。
大規模卸電力会社は、共通インフラを供給する独占事業体となるため、公的規制が必要になる。とはいえ、従来のような所管行政庁による規制では、癒着構造の維持との批判は避けられず、一般社会からの信頼を得るのは難しい。また、今のように電気料金の値上げが政治問題化して、消費税引き上げなどの別のイシューと関連付けられるような状況は、電力の安定供給の観点から見て問題が大きい。自由化を進めるためには、政治や所管行政庁からの独立を極力高め、かつ十分な専門知識を備えたスタッフをもつ「公益事業委員会」による規制とすべきである。
電源の種類もユーザーが選ぶ
一方、小売りサービス会社にとって、時間帯別の卸電力価格は「料理の素材」である。金融的リスクヘッジなどを行って多様な小売メニューに加工するとともに、デマンドレスポンスなどのサービスも提供する。デマンドレスポンスによって確保した調整力は、需給の安定のために、大規模卸電力会社に適切な対価で提供する。もちろんすべてのユーザーにスマートメーターを設置する。ユーザーは、自分に電力使用パターンに最も合った料金メニューやサービスを提供してくれるサービス会社を選択する。
電源種をユーザーが選択できる仕組みを整備することも重要である。値段が高くても構わないから再生可能エネルギーの比率が高い電気を買いたいとか、原子力発電が含まれていない電気を買いたいといったニーズにも応えられる仕組みが必要だ。あまり難しく考えず、グリーン電力証書のような証券を用いてバーチャルに選択できるようにすれば十分だろう。
まずは、再生可能エネルギーについて、希望するユーザーにはサーチャージをより多く負担してもらえるように、全量固定価格買い取り制度を改正する必要がある。例えば、固定価格買い取りに必要な追加コストが1kWhあたり10円だとすれば、自分の消費電力量×10円をサーチャージとして支払ったユーザーは、再生可能エネルギー100%の電気を使ったと見なすことが可能である。こうすれば、シンプルな形でユーザーの電源種選択が実現する。
東京電力の将来像
今まで論じてきたようなモデルは、トップダウン的に制度改革を行っても、各電力会社が民間事業者であり株主の意向を踏まえる必要があることから、一朝一夕に実現することは難しい。原発事故賠償を契機とした東京電力改革が待ったなしの課題であることから、東京電力の将来像を描くことを通じて、上記の電力システム改革をステップバイステップで実現していくのが現実的である。そこで、これまで論じたことを踏まえて、東京電力の将来像を構想してみた(下の図)。
この構想のポイントは以下のとおりである。
(1)東京電力の3原子力発電所(福島第一、福島第二、柏崎刈羽)は事業分離し、原子力損害賠償支援機構との共同出資で設立する「東京電力原子力発電・事故処理機構」(仮称)に引き継ぐ。上記機構は、被災者への賠償と廃炉事業を担う。
国が東京電力に注入する資本は、東日本卸電力(仮称)に残す部分は近い将来に上場することを予定し、上記機構に移す分は原子力発電事業及び廃炉事業が軌道に乗るまでの間、国が保有する。この形態をとることで、国策民営で進めてきたと受け止められている原子力発電事業の事故による賠償についても、国と民間の連帯責任において完遂するという意思を明示することができる。また、東北電力の女川・東通原子力発電所や北海道電力の泊原子力発電所も当該機構に集中するかどうかも検討課題となる。
また、この機構に、原子力発電プラントの輸出事業や国内での新設原子力発電所の設置主体としての位置づけも与えることによって、原子力関連技術や人材を継承をしていく役割を持たせることも重要だ。
(2)新機構は、保有する原子力発電所が発電する電力を、東日本卸電力に全量卸売する。これによって得た利益は、賠償および廃炉事業の原資とする。ただし、原子力発電が生む利益で、賠償と廃炉事業の資金が賄えない場合は、東日本卸電力は引き続き、機構に時限や上限額を設定した上で特別負担金を支払う仕組みにすることも検討する。
(3)北海道電力、東北電力、東京電力は、それぞれ小売り部門を分離分社化した上で、発電・送電・配電部門は東日本卸電力として合併する。合併交渉に時間がかかるようであれば、持ち株会社を設立して実質的に統合する方法も一案だろう。東日本卸電力は、東日本エリアにあるすべての電源の発電コストを把握した上で、コストが最小になるように需給運用し、安定供給を確保する。
そして、新規参入者を含むすべての小売りサービス会社に共通の条件で卸電力を供給する。東日本卸電力が増資する際には、電力の大口ユーザーたる各企業が出資し、独占企業のガバナンスをユーザーの立場から監視することがより望ましい。金融機関から見ても、原子力への国のリスク分担が明確化されるとともに、賠償・廃炉債務が切り離された大規模卸電力会社は財務力が増強されるため、ファイナンスリスクも低下する結果、社債・融資条件の改善(電気料金への低下圧力)が期待される。
西日本における電力再編は、原子力発電所についての状況が東日本と異なることや各電力会社の資金繰りがひっ迫している状況にないことから、当面は東日本を先行させることが現実的だ。しかし、ユーザーの電力自由化に対する要望は、東西で差異があるわけではなく、将来の原子力損害賠償リスクについては同じ問題を抱えるため、遠からずこうした構想を踏まえたシステム改革や産業再編への動きが始まるものと予想される。
最後に、こうした具体的構想にはさまざまな異論があると思う。これまでの原子力民営、9電力地域独占、発送電一体という立場の電力関係者からは、原子力の分離・国の介入、9電力から大規模統合への変革、小売り部門の分離などについて、反論が出てくるだろう。
また、現在の政権の検討の方向性からすれば、原子力の取り扱い(国がそこまでリスクを分担するのか)、送電線開放モデル=発電事業参入促進ではなく重点が小売りに偏っていること、電力会社の分割ではなく統合の方向であることなどを問題視するだろう。
筆者の案は、そういう意味ではすべての関係者が合意できる案ではなく、政治的にも実現可能かどうか微妙だ。しかし、そうであるがゆえに提示する価値があると考えている。
 日本経済団体連合会 21世紀政策研究所 研究主幹
日本経済団体連合会 21世紀政策研究所 研究主幹
大阪府生まれ。1981年一橋大学経済学部卒業後、同年通商産業省(現在の経済産業省)入省。1987年プリンストン大学にてMPA(行政学修士)取得。通産省工業技術院人事課長、経産省産業技術環境局環境政策課長、資源エネルギー庁資源燃料部政策課長などを経て2004年8月から2008年7月まで東京大学先端科学技術研究センター教授。2007年5月より現職。編著書に「エコ亡国論」「地球温暖化問題の再検証-ポスト京都議定書の交渉にどう臨むか」「大学改革 課題と争点」「競争に勝つ大学-科学技術システムの再構築に向けて」「民意民力-公を担う主体としてのNPO/NGO」「無名戦士たちの行政改革」。また、21世紀政策研究所で地球温暖化政策についての提言(セクター別アプローチ、排出量取引制度など)多数。
澤昭裕の「不都合な環境政策」
国際間でさまざまな駆け引きが繰り返される温暖化交渉。「ポスト京都」の目標設定や新たな枠組みづくりをめぐって、今、まさに熾烈な攻防が繰り広げられている。経済産業省で環境政策を描き、東京大学で教鞭をとった筆者が、温暖化政策の最前線を分析する。