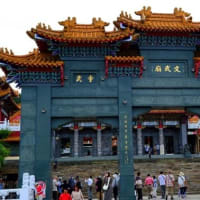自然教育園日記 その267 虫のハイスピード撮影・中間総括その1
2023-11-9
今日はFuifilm X-H2S にZeissレンズを付けてみる。まずは
Fuifilm X-H2S+Zeiss touit 50mm macro F2.8
このレンズはAFなのだが、AFがとろいからMFに近い、偶然ピントの合った絵を載せているようなもの。











ピントさえ合えば、このちっちゃいTouit 50mm macroは結構迫力ある絵を作る。さすが当方の信奉するZeiss様です。
ここからCarl Zeiss Planar 50mm macroF2に切り替える。ということは完全にMF撮影になる。
Fujifilm X-H2S + Carl Zeiss Planar 50mm macro (Makro-Planar) F2

MFですから連写して、偶然ピントが合ったものを載せています。ピントが合ったとはいえないかもしれないですが。






Carl Zeiss Planar 50mm macro F2 のボケはほれぼれするほど魅力的。こういうのを写真というのだろう。何のことは無いMFオールドレンズが一番いい写真が撮れた。
同じような被写体に4種のレンズを使いました。ほぼ偶然に撮れた絵ではありますが、中判カメラの味、Zeiss touit, Zeiss Planarの味はそれぞれに味わい深いものです。一方Fujifilm XF80mm macroF4は機能的にはハイスピード・マクロ撮影に対応するこの4種の中で唯一のレンズです。
以下は長くて込み合っていますから、カメラのメカに興味ない人は飛ばしてください。
さて、偶然に頼らずに、味わい深いハイスピード・マクロ撮影を行うにはどういう機材が適切なのかと考えてみました。
1, 連写:高速連写は必要だが、時間に余裕のある人しかうれしくない。高速連写といえるのは8コマ/秒が最低限界、 10コマ/秒は欲しい。問題はいらない絵を消す操作というか、いる絵をピックアップする操作というかこれがうんざりである。30コマ/秒で限界に近い。最近ニコンやソニーが120コマ/秒の連写カメラを出してきた。お手上げである。ニコンZ9/Z8の120コマ/秒連写では1/4にクロップされるが、最新のソニーα9 IIIはフルサイズで120コマ/秒をやるらしい。世の中がざわつくわけだ。プロがオリンピックの撮影をするならともかく、素人の虫ハイスピード・マクロ撮影には120コマ/秒は相当なコリ性か暇人しか使う気にならないだろう。但し後述のシステムが開発されればこの問題は簡単に解決するのだが。
2, プリ撮影は必要か? 当方は当然必要と思っている。最新のソニーα9IIIでやっとソニーはプリ撮影を導入した。オリンパス、フジフィルム、ニコン、キャノン、パナソニックはすでにプリ撮影を付けている。ソニーがなぜ今頃プリ撮影を導入したのだろう? 当方はソニーが今度のパリオリンピックで是が非でも撮影隊のカメラ列の中でトップをとりたいからだと推測している。つまりプリ撮影が必要であることをやっとこ認めたということだ。
3, 追尾能力:AFの良し悪しは今や瞳AFと追尾性能の議論になっている。どちらも同じことで、画像認識AIの能力をうんぬんしていることだ。プリ撮影も追尾能力がなければ意義が大幅に減ずる。しかし当方はこの現在の画像認識AIを信じていない、というか嫌いである。
いくら人の瞳の画像認識AIが発達しても、ピントを合わせる対象が左の目が右の目か決めるのは撮影者でありカメラではない。ようするに簡単だ、撮影者が何をとりたいかを察知して、カメラはそこに自動的にピントを合わせればいいだけだ。タッチフォーカスと同じである。撮影者が何をとりたいかを察知したらカメラは対象の画像認識をして、その画像を追尾すればいいのである。これで虫の目と擬態の目を見誤ることもない。人や鳥や虫の目の情報をいっぱい集めて、カメラに認識させそこにピントを合わせることは先にカメラの認識があり、撮影者は二の次なのだ。撮影者がどこに興味があるかが先にあるべきで、その後に画像を認識して覚えるように順序を逆にすべきなのだ。今のところカメラの目より人の目というか脳ミソの方が判断能力は優秀に決まっている(目の悪い人とか何を撮るか考えるのがめんどうな人はべつだが)から、人の目の判断を優先するのが当然と思うのだが、なぜかカメラの目を優先している。これは当方には<人を馬鹿扱いしている>と思うのである。
4, ピックアップ:虫のマクロ高速撮影で必要な写真を選び出す為には、虫の目を拡大する必要がある。いちいち拡大して判断して拾うか捨てるか決めるのがたいへん面倒なのだ。3番で述べたように撮影者が必要とする画像をカメラが認識していれば、その部分にピントが合っているかを自動的に判断して拾いあげてから、その拡大図をスピーディーに流せば簡単に撮影者がピックアップできるのである。120コマ/秒でも簡単にピックアップできる。
5, 必要な画素数:最新のソニーα9IIIはなぜ約2520万画素という低い値にしたのか?パリオリンピックでトップをとるのが目的なら、デカ望遠レンズで人を狙えばいいのだからトリミング拡大は必要ない、よって2520万画素で十分なのだ。むしろフルサイズでグローバルシャッターと120コマ/秒をうたいたかった。もう一つの理由は、来年にソニーα9IIIのハイスピードに高画素を組み合わせて<てんこ盛り>のα1IIを出す為だ。
虫の高速マクロ撮影も望遠レンズを使えばトリミング拡大はいらないというが、現在はAFのきく望遠マクロで機動性も兼ね備えている(794g)レンズはソニー70-200mmF4のハーフマクロ(0.26~0.42m)しかない。 虫は小さいから、高速マクロ撮影はトリミング拡大が必須なのである。小鳥もトリミング拡大は必須である。しかるにどうしても5000万画素は必要なのだ。
結局これ等の条件をそなえたシステムは現在無いのだ。よって虫の高速マクロ撮影は楽しく、楽ちんに、満足ゆく方法はないのである。方法が無いから人気が集まらない、集まらないから機材の開発も進まない、悪循環である。それに比べて望遠レンズ一本でうろうろする鳥撮り屋さんがごまんと増えた。機材次第でこれまで撮れなかった鳥が撮れるから人が集まる。集まるから機材が進歩する好循環に入っている。
当方みたいなひねくれ者は、人が集まるところから追い出されてといいうか、追い出てというか、苦労が絶えないというか、苦労が好きというか?
当面の虫のハイスピード・マクロ撮影機材は
近々ソニーα1にプリ撮影がつくらしいので、これにソニー70-200mmF4ハーフマクロの組み合わせがベストに近いかな? やっとソニーがプレ撮影に目覚めてくれたのでソニーに戻ることになる気がしてきた。
次回は虫のハイスピード・マクロ撮影機材の徹底比較として、虫のハイスピード撮影・中間総括その2を書きます。
2023-11-9
今日はFuifilm X-H2S にZeissレンズを付けてみる。まずは
Fuifilm X-H2S+Zeiss touit 50mm macro F2.8
このレンズはAFなのだが、AFがとろいからMFに近い、偶然ピントの合った絵を載せているようなもの。











ピントさえ合えば、このちっちゃいTouit 50mm macroは結構迫力ある絵を作る。さすが当方の信奉するZeiss様です。
ここからCarl Zeiss Planar 50mm macroF2に切り替える。ということは完全にMF撮影になる。
Fujifilm X-H2S + Carl Zeiss Planar 50mm macro (Makro-Planar) F2

MFですから連写して、偶然ピントが合ったものを載せています。ピントが合ったとはいえないかもしれないですが。






Carl Zeiss Planar 50mm macro F2 のボケはほれぼれするほど魅力的。こういうのを写真というのだろう。何のことは無いMFオールドレンズが一番いい写真が撮れた。
同じような被写体に4種のレンズを使いました。ほぼ偶然に撮れた絵ではありますが、中判カメラの味、Zeiss touit, Zeiss Planarの味はそれぞれに味わい深いものです。一方Fujifilm XF80mm macroF4は機能的にはハイスピード・マクロ撮影に対応するこの4種の中で唯一のレンズです。
以下は長くて込み合っていますから、カメラのメカに興味ない人は飛ばしてください。
さて、偶然に頼らずに、味わい深いハイスピード・マクロ撮影を行うにはどういう機材が適切なのかと考えてみました。
1, 連写:高速連写は必要だが、時間に余裕のある人しかうれしくない。高速連写といえるのは8コマ/秒が最低限界、 10コマ/秒は欲しい。問題はいらない絵を消す操作というか、いる絵をピックアップする操作というかこれがうんざりである。30コマ/秒で限界に近い。最近ニコンやソニーが120コマ/秒の連写カメラを出してきた。お手上げである。ニコンZ9/Z8の120コマ/秒連写では1/4にクロップされるが、最新のソニーα9 IIIはフルサイズで120コマ/秒をやるらしい。世の中がざわつくわけだ。プロがオリンピックの撮影をするならともかく、素人の虫ハイスピード・マクロ撮影には120コマ/秒は相当なコリ性か暇人しか使う気にならないだろう。但し後述のシステムが開発されればこの問題は簡単に解決するのだが。
2, プリ撮影は必要か? 当方は当然必要と思っている。最新のソニーα9IIIでやっとソニーはプリ撮影を導入した。オリンパス、フジフィルム、ニコン、キャノン、パナソニックはすでにプリ撮影を付けている。ソニーがなぜ今頃プリ撮影を導入したのだろう? 当方はソニーが今度のパリオリンピックで是が非でも撮影隊のカメラ列の中でトップをとりたいからだと推測している。つまりプリ撮影が必要であることをやっとこ認めたということだ。
3, 追尾能力:AFの良し悪しは今や瞳AFと追尾性能の議論になっている。どちらも同じことで、画像認識AIの能力をうんぬんしていることだ。プリ撮影も追尾能力がなければ意義が大幅に減ずる。しかし当方はこの現在の画像認識AIを信じていない、というか嫌いである。
いくら人の瞳の画像認識AIが発達しても、ピントを合わせる対象が左の目が右の目か決めるのは撮影者でありカメラではない。ようするに簡単だ、撮影者が何をとりたいかを察知して、カメラはそこに自動的にピントを合わせればいいだけだ。タッチフォーカスと同じである。撮影者が何をとりたいかを察知したらカメラは対象の画像認識をして、その画像を追尾すればいいのである。これで虫の目と擬態の目を見誤ることもない。人や鳥や虫の目の情報をいっぱい集めて、カメラに認識させそこにピントを合わせることは先にカメラの認識があり、撮影者は二の次なのだ。撮影者がどこに興味があるかが先にあるべきで、その後に画像を認識して覚えるように順序を逆にすべきなのだ。今のところカメラの目より人の目というか脳ミソの方が判断能力は優秀に決まっている(目の悪い人とか何を撮るか考えるのがめんどうな人はべつだが)から、人の目の判断を優先するのが当然と思うのだが、なぜかカメラの目を優先している。これは当方には<人を馬鹿扱いしている>と思うのである。
4, ピックアップ:虫のマクロ高速撮影で必要な写真を選び出す為には、虫の目を拡大する必要がある。いちいち拡大して判断して拾うか捨てるか決めるのがたいへん面倒なのだ。3番で述べたように撮影者が必要とする画像をカメラが認識していれば、その部分にピントが合っているかを自動的に判断して拾いあげてから、その拡大図をスピーディーに流せば簡単に撮影者がピックアップできるのである。120コマ/秒でも簡単にピックアップできる。
5, 必要な画素数:最新のソニーα9IIIはなぜ約2520万画素という低い値にしたのか?パリオリンピックでトップをとるのが目的なら、デカ望遠レンズで人を狙えばいいのだからトリミング拡大は必要ない、よって2520万画素で十分なのだ。むしろフルサイズでグローバルシャッターと120コマ/秒をうたいたかった。もう一つの理由は、来年にソニーα9IIIのハイスピードに高画素を組み合わせて<てんこ盛り>のα1IIを出す為だ。
虫の高速マクロ撮影も望遠レンズを使えばトリミング拡大はいらないというが、現在はAFのきく望遠マクロで機動性も兼ね備えている(794g)レンズはソニー70-200mmF4のハーフマクロ(0.26~0.42m)しかない。 虫は小さいから、高速マクロ撮影はトリミング拡大が必須なのである。小鳥もトリミング拡大は必須である。しかるにどうしても5000万画素は必要なのだ。
結局これ等の条件をそなえたシステムは現在無いのだ。よって虫の高速マクロ撮影は楽しく、楽ちんに、満足ゆく方法はないのである。方法が無いから人気が集まらない、集まらないから機材の開発も進まない、悪循環である。それに比べて望遠レンズ一本でうろうろする鳥撮り屋さんがごまんと増えた。機材次第でこれまで撮れなかった鳥が撮れるから人が集まる。集まるから機材が進歩する好循環に入っている。
当方みたいなひねくれ者は、人が集まるところから追い出されてといいうか、追い出てというか、苦労が絶えないというか、苦労が好きというか?
当面の虫のハイスピード・マクロ撮影機材は
近々ソニーα1にプリ撮影がつくらしいので、これにソニー70-200mmF4ハーフマクロの組み合わせがベストに近いかな? やっとソニーがプレ撮影に目覚めてくれたのでソニーに戻ることになる気がしてきた。
次回は虫のハイスピード・マクロ撮影機材の徹底比較として、虫のハイスピード撮影・中間総括その2を書きます。