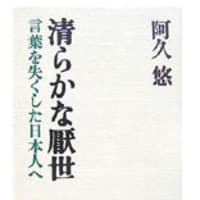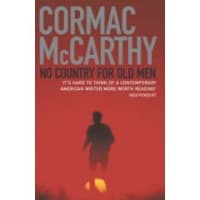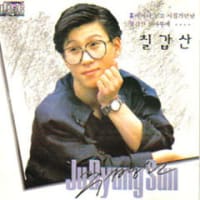冬至に食べるものといえば南瓜だろうか。魚屋の御用聞きに押し売りされた「南瓜の煮物」を昼食に戴く。柔らかいのはいいが、これが結構甘い。南瓜自体の甘さだけではなく、砂糖を加えているらしい。甘いものが好きな年寄の常連たちが多いのだろう。
冬至に南瓜を食べるのは「中風除け」とか「風邪除け」といった健康対策のほかに「金運祈願」という身勝手な意味もあるという。現代的に解釈すれば、緑黄色野菜の少ない冬に、カロチンやビタミンの多く含まれた南瓜を食べて、寒さへの抵抗力をつけようという先人の知恵だといえるとウイキにあった。
ツイッターのタイムラインには外国からのこんなツイートも読める。
冬至には餅団子入りのパッチュ(小豆粥)を作って食べるという韓国。冬至に小豆粥というのは、小豆の赤には厄除けの効果があると信じられてきたためで、昔は、小豆粥を玄関の柱に掛けたり、部屋に撒いたりしていたが、後片づけを嫌う主婦連の圧力でこの風習は廃れたという。セアルシムと呼ばれるもち米の団子は齢の数だけ食べると先一年を無事に過ごせるというから、節分の豆とおなじだ。もっとも日本の場合は大豆だが。
台湾からのツイートには、冬至には湯円(タンユェン)がつきものとある。もち米粉をこねて団子にし黑砂糖の水で煮たり、野菜や肉といっしょに煮た鹹湯円を、冬至の朝、先祖に供え、その後一家全員で朝食として食べるとある。具入りの餅団子というのなら日本の雑煮と同じだ。湯円は台湾だけでなく、中国本土でも食べられている伝統食だともあるから、彼らのソールフードと言え「吃了湯圓好団圓」という韻を踏んだ言い方をするように「湯円食べれば家族円満」という冬場の縁起ものであるようだ。
Wishing You a Happy Winter Solstice
祝大家冬至快楽