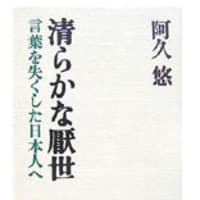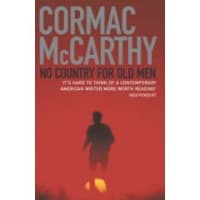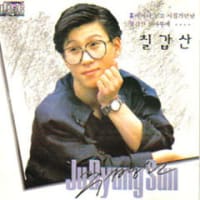県図書館に行ったついでに名古屋城の周りを廻って帰ろうと歩いた。前に来たのはもう3年ほど前になるから、様子が変わったろうと思ったのだが、案外変化がない。堀川の西側に新しいビルが数件立っているのが目につく程度。昔からの住宅地だから世代が変わっても住み続けている住民たちが多いのだろうか。
この辺りを樋ノ口町というのは、城の堀の水量を調整する施設があったことに由来するというとウイキにはある。江戸時代には今の幅下橋の袂あたりから運河としての堀川が始まっていたようで、内堀から樋を伸ばして堀川に繋ぎ、堀水と川水との調整をしていたらしい。樋とは排水門のことでもあって、今でも西堀の南西角にはその石組が残っている。
市長悲願の木造天守閣の再建は石垣の耐震性に疑問ありという物言いで延期となっているが、問題の石垣はそれでも修復の工事には着手できたようだ。冬の堀端は薄汚れて見る影もない。いっそ雪が積もった光景なら石垣も枯れ木もきれいに装えただろうに。
天守閣の石垣といえば、岐阜城の石垣は信長が威勢を張ろうと複数段を築いたのかもしれないというNHK岐阜局の今日のニュースを読みながら、名古屋市長の顔をちょっと思い浮かべた。
ニュースによれば、岐阜市の教育委員会は、去年の発掘調査で岐阜城天守閣の土台部分で信長が築いたと見られる石垣を発見したのに続いて、年明け早々に追加の調査を行い、その結果、去年見つかった石垣の下に、もう一段、石垣の裏に詰める小石の層があるのを見つけたのだという。
上の段の石垣がこの層に食い込むように載っていることから、2つの石垣が同じ時期に造られた可能性があり、石垣を複数段積み重ねる城づくりの手法は、岐阜の前に信長が居城にしていた小牧山城でも採られている。
だから「信長は、麓から石垣を一気に高く積み上げたように見えるようにして、権威や技術力の高さを示そうとした」のではないかというのが教育委員会の見解だ。
「信長は、城造りを通して斎藤道三を超える力を示したかったのではないか」という仮説をたてて今後も調査をつづけ、その可能性を裏付けたいというのが教育委員会の担当課長の意気込みだ。
京に向かって覇をとなえる若き信長ならば、精一杯の背伸びもしたかったことだろう。石垣に下駄を履かせることくらいは簡単にやってのけたかもしれない。
名古屋城の石垣も調査をしながらの再構築なのだろうから、岐阜城とおなじじような証拠でも見つかったら面白かろうが。家康は大阪の秀吉に対抗する意味でいったいどんな下駄を新しい名古屋城に履かせようとしたのか。石垣の謎は深まるばかりである。