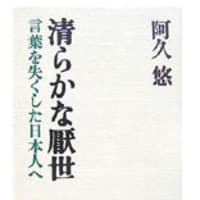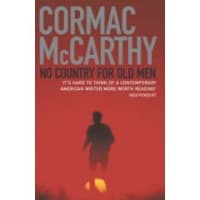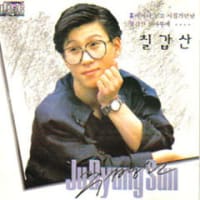朝飯用の梅干しがなくなった。買わねばと思ったせいか、梅のポスターやニュースが目についた。
乗り換え待ちの名鉄のホーム。明るい陽光の中でポスターボードを眺めていた。沿線案内には知多半島の「佐布里池梅まつり」が大きくPRスペースを取っている。
知多市のほぼ真ん中にある佐布里池の周辺がその会場。25種類5000本以上の梅の木が植えられた愛知県下第一の梅林だとは市のPR。梅まつりには毎年15万人がおとずれるとあるが、自分は未だ行ったことがない。お仲間のSさんは巽が丘の在住だから、毎年歩きで出かけるのだと聞いた。佐布里の小梅を使った梅干しはスーパーの売り場にも置かれたこの地域のブランドだ。
昼のNHKでは「熊野 梅林で最後の梅祭り」というローカルニュースを取り上げていた。熊野紀和町にある小船の梅林。南高梅や小梅など800本の梅木が植えられて、梅まつりも30年以上になるのだという。だが、住民の高齢化もあって祭りを担当する人手が確保できなくなったことで、今年限りで梅まつりはお終いという淋しいことになったらしい。
放送が終われば視聴者のほとんどが忘れてしまうような小さなニュースだが、地方の田舎の過疎高齢化ははっきりしたものになっているのだと確認せざるを得ない。梅まつりは終わるが、梅の収穫は今後も続けるもののようだ。
最後に残った梅干しをなめながら入れ物の裏を見てみたら、なんと製造者は熊野市紀和町だとある。ひょっとすると小船で採れた梅だったのかなと、偶然にちょっと驚いた。
梅花雪を帯びて琴上に飛ぶ
柳色煙に和して酒中に入る
唐の詩人、章考標の詩だ。和漢朗詠集に入っているものだといい、大岡新が「折々の歌」で取り上げている。平安貴族に好かれた中国詩人だろうという。
白梅の花が雪さながら、弾奏する琴の上を舞い、萌え出でた柳の薄緑は、けぶる霞と融け合って酒盃にただよう
梅花・柳色、雪・煙、帯びて・和して、琴上・酒中、飛ぶ・入る。対句の各語がすべて対になっている巧みな修辞が軽やかだとある。
中川運河の橋の袂に梅花と柳が植わった場所を知っている。来週は万歩のコースにしてみよう。章考標の詩の雰囲気が望めるかもしれない。
最新の画像[もっと見る]