いつも専務のブログをご覧くださっている皆さんに、お詫びと訂正しなければならない可能性があります。
先日のブログで、令和の新元号の由来について盛り上がっていた専務。
万葉集の時代から蘭が愛されていた!!と盛り上がっていた専務。
盛り上がってビールが進み、二日酔いだった専務。
この二日酔いの原因が、なんと間違いかもしれない?説がある事がわかりました。
専務の信じるのは、日本に古来より自生している春蘭や寒蘭、エビネなどの東洋蘭説。
諸説ある中で、九州大学の先生の見解です。
問題となっている万葉集の
「初春令月 氣淑風和 梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之」
という一節。
蘭 という文字に興奮してしまっていた専務。
大学時代から、「蘭」の言葉に反応する所は変わりません。
しかしながら、実は
「蘭」の漢字= ラン科植物 となったのは中国が宋の時代 10世紀〜13世紀の頃。
万葉集の8世紀の頃は
「蘭」 = 香りのある植物の総称。
もちろん日本に自生にている春蘭などは、この蘭に含まれるが、この一節に出てくる蘭は「フジバカマ」の事ではないか。
との事。
日本名,藤袴 フジバカマ
学名,Eupatorium japonicum
中国名,蘭草
ユーパトリウムは、草花として花屋さんにも並ぶ事があります。
生ではあまり香りがなく、切った後で乾燥させると香りがあるそうです。
諸説あり。
本当の所は、、、
730年の春、梅の花の会に出席していた人達のみぞ知る。
いずれにせよ、1300年前の歌であれこれと思いを巡らせる事が出来るのを、とっても幸せに思います。
花。
いいですね!
先日のブログで、令和の新元号の由来について盛り上がっていた専務。
万葉集の時代から蘭が愛されていた!!と盛り上がっていた専務。
盛り上がってビールが進み、二日酔いだった専務。
この二日酔いの原因が、なんと間違いかもしれない?説がある事がわかりました。
専務の信じるのは、日本に古来より自生している春蘭や寒蘭、エビネなどの東洋蘭説。
諸説ある中で、九州大学の先生の見解です。
問題となっている万葉集の
「初春令月 氣淑風和 梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之」
という一節。
蘭 という文字に興奮してしまっていた専務。
大学時代から、「蘭」の言葉に反応する所は変わりません。
しかしながら、実は
「蘭」の漢字= ラン科植物 となったのは中国が宋の時代 10世紀〜13世紀の頃。
万葉集の8世紀の頃は
「蘭」 = 香りのある植物の総称。
もちろん日本に自生にている春蘭などは、この蘭に含まれるが、この一節に出てくる蘭は「フジバカマ」の事ではないか。
との事。
日本名,藤袴 フジバカマ
学名,Eupatorium japonicum
中国名,蘭草
ユーパトリウムは、草花として花屋さんにも並ぶ事があります。
生ではあまり香りがなく、切った後で乾燥させると香りがあるそうです。
諸説あり。
本当の所は、、、
730年の春、梅の花の会に出席していた人達のみぞ知る。
いずれにせよ、1300年前の歌であれこれと思いを巡らせる事が出来るのを、とっても幸せに思います。
花。
いいですね!














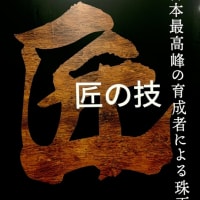





問題は珮で、これは香を焚き込めて衣類に香りをうつすことを意味します。(本来は見に帯びる意で、英語でも香水はwear)。
この時代にはフジバカマの類を乾燥保存して、炊きこめることが多かったようです。逆に蘭では、ほとんど聞きません。
よって今ではフジバカマ説をとっています。
各方面からの検証報告を見る限り、フジバカマ説が最有力のようですね。
新元号発表後の、蘭業界の盛り上がりを見ていると、反動からくる精神的な凹みが、とても心配です。