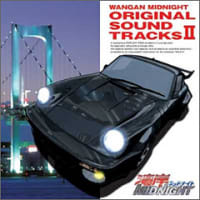雨に煙るで眠っていたS30型フェアレディZに、「地獄のチューナー」北見淳の手によって、当時国内では入手不可能だったL2.8型エンジンが搭載され、とてつもないパワーを与えられた、湾岸ミッドナイトの主役マシン・『悪魔のZ』。そのボディを手がけたのが高木だった。前楽章に記述したとおり、600馬力のパワーと時速300kmのスピードに耐えられる補強を施したのだから、当時としてはおそらくレーシングカーかそれ以上の強度としなやかさを兼ね備えていたであろう。
だが、Zは北見をも受け入れず、サーキットの帰りに東名高速道路でクラッシュを起こしてしまう。その後、アキオと同姓同名の「朝倉昌夫」の命を奪い、続く3人のオーナーを事故に見舞わせたマシンとなってしまった。
その後、朝倉アキオの手に渡った悪魔のZは、湾岸でのバトル中大クラッシュを起こして炎上し、Zが死に絶えたかに見えたが、アキオは「もう一度お前と走り出したい」と願い、北見の手によって高木のガレージに運びこまれていた。
北見は高木に言った。
「一ヶ月以内に仕上げろ 今度は時速330kmに耐えられるボディだ」「何よりもカタく 何よりもしなやかなボディに仕上げてくれ この悪魔はお前にしか直せない」と。
Zの所へ行ったアキオは、「まっすぐ走れなくてもいいから元の姿に戻す」といい、高木のショップに通い修理を始めた。「純正パーツをそろえていっても もとの姿にはならないぜ」と言う高木だが、Zの復活を信じるアキオは、
【あのとき僕はこのZを助けてやれなかった・・
オレだけはお前をみすてない オレだけは最後までついてゆく そう言ったのに・・
Zは走り続けようとした
僕は一生かかっても もう一度Zを走らす】
と力強い言葉と目で高木に訴える。
アキオと出会った頃の高木は、車に対する情熱は薄れ、見積もり上乗せに注力していた商売人に徹することで地位を築いていた。長いブランクが高木から自信を失わせており、「どうして・・そんな目をしている・・?」「どうしてそんなにZを信じられる目をしている・・」と不思議がっていた高木は、アキオの言葉と修理を続ける姿に心を揺さぶられ、ツナギを身にまとい、アキオと一緒に作業を進めていく。作業の節々でボディ補強のノウハウをアキオに伝授し、作業を通して人生そのものの哲学までをも語る。そして語ることでますますアキオに心を許し、自分の気持ちを、心を、高ぶらせていったのだろう。他人をほとんど信用せず、金儲けに走っていた高木は、アキオと出会うことで、変わっていった。
いや、「かつての自分を取り戻した」と言ったほうがいいかもしれない。
高木の胸中のこのセリフは、自分より年下だろうが、経験の浅い若造だろうが、魅力を湛えた者の存在は、人の気持ちを大きく昂ぶらせる何かがあることを証明しているかのようだ。
【・・アキオ ・・アキオ 選ばれし者よ 与えてくれ オレに勇気を
最高の そして最速の悪魔に選ばれし者よ オレは今でもやれる・・と 勇気を与えてくれ】
しかし、期限の一ヶ月まであと少しとなったある日、高木はプレッシャーと過労で倒れ、入院してしまった。雨が降る日、入院先に北見が現れ、「たまたまお前の工場に電話したら入院したっていうからさ 今日はゆっくり寝て 明日からまた頼むぜ」という。しかし高木は「オレには出来ませんよ オレはもうダメなんだ ムリだよ・・ 直せないい・・」と泣き出してしまう(このシーンもかなり泣ける!)。
天才チューナーと称された北見は現在では小さな自転車屋のオッチャンであり、北見の後輩である高木は立派なボディショップの社長サン。しかし、北見はそんなことは一切気にせず、若かった当時のままのスタイルで高木に接し、高木も北見の前では泣き虫小僧に戻ってしまう。これは、裏を返せば二人の信頼関係の厚さを表している。
泣き言を言い、涙を流して泣く高木に北見がこう切り出す。
【相変わらずすぐ泣くヤツだなおメェは
覚えてるか Green Autoの2台目のポルシェターボ 280km/hで事故ったぐしゃぐしゃの
お前んトコの親方でさえ『アレは無理』といった・・ でもおメェは
『やらせてください!直らないボディなんてありませんヨ!』
泣きみその小僧と思ってたら生意気にいっちょまえの口ききやがってヨ
あれは本当にいい仕事だった―】
(アニメーション版湾岸ミッドナイト ACT.9 「甦る悪魔」より)《「昔からポルシェって車は板金屋泣かせだったよな スポットもやたらと多いしめんどくせえ車だ それがあそこまでイっちまった 誰もやりたがらねーよな・・」「本当にいい仕事だった あれはもう新車だ おまけにあのケツの重いRRがウソのようにまっすぐ走る あんなポルシェはどこにもねえ」←コミック版よりセリフを補足》
「自信を失いかけている人間にかける言葉」の一つに、過去の行いそのものや、成功例や功績を語ることで、そのときの喜び、感動を思い出させ、心に潤いを戻してやる―というこの行為は、部下の言う事を傾聴できない傾向の強い上司が多い会社組織なども含め、しっかり出来る人間が少ないと思う。
ダイヤモンド社のビジネス情報サイト内「若手社員を辞めさせず成長させる適度なかまい方マニュアル」の記事内にこのような興味深い文章がある(http://diamond.jp/series/masugi/10008/)。
熟達化理論を研究する松尾睦・小樽商科大学教授の研究によれば、営業担当者が、業績に繋がる優れた知識やスキルを獲得するためには10年以上かかっていることが示されたそうです。営業という仕事に限らず、スポーツやアートの領域でも「熟達化の10年ルール」は定説になっています。ただし注意が必要なのは、「10年経てば自動的に熟達する」わけではなく、「熟達するには最低10年かかる」ということです。さらに、10年という期間において「よく考えられた練習を積むことが大切になります」と松尾教授は指摘しています。
「よく考えられた練習というのは、課題が適度に難しく、明確である。すなわちストレッチされていること。また、実行した結果についてフィードバックがあること、何度も繰り返すことができ、誤りを修正する機会があるような練習の仕方です。つまり、ストレッチ&フィードバックが熟達化の条件となります」(松尾教授)やりっぱなし、やらせっぱなしでは、いつまでたっても実力はつかない、というのは普通に理解できますね。若手社員がひとつの業務を終えた後は、その仕事をあなたの経験に照らし合わせて評価し、先輩としての意見を伝えましょう。フィードバックするときには、
1)若手社員の人格についてではなく、行動を評価すること。
2)挑戦して失敗したことを責めない。
この2つが肝心なポイントです。
北見が実践したのはその1つ目のポイントだ。福祉の世界に生きる私は、社会人になって「後輩」という人間に出会ったことはあっても、直接育てることはしていない。せいぜい若い学生の現場実習を一日受け持ったことがあるくらいだ。そういう機会に恵まれたとき、あるいはこれからそうなった場合に心がけていることがある。それは、「アメと鞭」の「鞭」は最初から手に持たないことだ。忠告、叱責、その他もろもろ―そーゆうコトは、直接でも人づてでも言わない。その代わりに褒めるときは匙加減を大事にして、人のいないところで心を込めていう、ということだ。できるかできないかという単純な物差しで人を判断することをしないように、個々人への愛情を持つのが大事だ、ということだ。「いいから黙ってやりなさい」的なモノの言い方では通じない。そう思っている。
「門前の小僧習わぬ経を読む」という諺があり、そういう世界(職場)も中にはあるのだろう。しかし、私は先輩の背中を見て(観察して)、技を盗んで自分で成長するのが全てではないと思っている。植物も動物もそうであるように、自分で育つ責任もあれば育てる責任もあるのだ。
福祉を含めた医療の世界は、現場に入れば患者さん・利用者さんありきだ。その人たちの安全を守る、その人の立場になるのが大前提。しかし、それを成す人間の心が折れてしまっては満足な医療行為など出来るはずがない。自己責任もあると思うが、仕事を為そうとする者の行為や今後の成長をサポートするのは、その人間のパワー・やる気を刺激するコト、心をくすぐるコトであり、それはまぎれもなく上司の仕事である。それはどこの世界でも同じ。それがしっかり出来ている上司がいるならば、若者が入社早々に辞めていくハズがない。
話を物語の方に戻そう。北見はその後、こう語りかける。
【ほら ゆっくりとイメージしろ ミッドナイトブルーの悪魔のボディだ
今1速でゆっくりと動き出した
9000まで回して2速 車速はあがる
3速 4速―
タイヤは確実に路面を捉えているか 轍に進路を乱されてはいないか
そして5速 250 260― さぁ 空気の壁が大きく立ちはだかってきた―
270 280―L2.8改ツインターボ オレが新しく組んだ悪魔の心臓はまだ加速をやめない
もっとだ エンジンはもっと回ろうとしている あとはお前しだいだ
信じろ お前こそが天才だ―】
(湾岸ミッドナイト ACT.9 「甦る悪魔」より)
この場面は、私の上記の文をそのまま読んだり、コミックを見たりするよりも、アニメのシーンでじっくりとご覧いただきたい。北見は、叱咤の言葉でありながら、今まさに高木が着手している仕事が上手くいった暁にはこんな素晴らしい結果が待っている、と暗示をかけることで、高木に最後の勇気をふりしぼる力を与えたのだ。そうして仕上がったボディ―高木の仕事は、北見の手によって新たなエンジンが載せられ、悪魔のZ復活という大きな成果となって表れる。
【よくやった 高木・・】
(アニメーション版湾岸ミッドナイト ACT.10 「ドッグファイト」より)
その時もホロリと涙を流す高木。「北見に褒められることは、高木にとって何よりの賞賛なのだ」と言える。 「ボディ補強は魔法じゃない」と高木は言うが、他の人間には絶対出来ない仕事をしている・できる男だ。その高木の心の動きやそこから溢れた言葉についてはまた別の楽章で綴ってみることにしよう。
だが、Zは北見をも受け入れず、サーキットの帰りに東名高速道路でクラッシュを起こしてしまう。その後、アキオと同姓同名の「朝倉昌夫」の命を奪い、続く3人のオーナーを事故に見舞わせたマシンとなってしまった。
その後、朝倉アキオの手に渡った悪魔のZは、湾岸でのバトル中大クラッシュを起こして炎上し、Zが死に絶えたかに見えたが、アキオは「もう一度お前と走り出したい」と願い、北見の手によって高木のガレージに運びこまれていた。
北見は高木に言った。
「一ヶ月以内に仕上げろ 今度は時速330kmに耐えられるボディだ」「何よりもカタく 何よりもしなやかなボディに仕上げてくれ この悪魔はお前にしか直せない」と。
Zの所へ行ったアキオは、「まっすぐ走れなくてもいいから元の姿に戻す」といい、高木のショップに通い修理を始めた。「純正パーツをそろえていっても もとの姿にはならないぜ」と言う高木だが、Zの復活を信じるアキオは、
【あのとき僕はこのZを助けてやれなかった・・
オレだけはお前をみすてない オレだけは最後までついてゆく そう言ったのに・・
Zは走り続けようとした
僕は一生かかっても もう一度Zを走らす】
と力強い言葉と目で高木に訴える。
アキオと出会った頃の高木は、車に対する情熱は薄れ、見積もり上乗せに注力していた商売人に徹することで地位を築いていた。長いブランクが高木から自信を失わせており、「どうして・・そんな目をしている・・?」「どうしてそんなにZを信じられる目をしている・・」と不思議がっていた高木は、アキオの言葉と修理を続ける姿に心を揺さぶられ、ツナギを身にまとい、アキオと一緒に作業を進めていく。作業の節々でボディ補強のノウハウをアキオに伝授し、作業を通して人生そのものの哲学までをも語る。そして語ることでますますアキオに心を許し、自分の気持ちを、心を、高ぶらせていったのだろう。他人をほとんど信用せず、金儲けに走っていた高木は、アキオと出会うことで、変わっていった。
いや、「かつての自分を取り戻した」と言ったほうがいいかもしれない。
高木の胸中のこのセリフは、自分より年下だろうが、経験の浅い若造だろうが、魅力を湛えた者の存在は、人の気持ちを大きく昂ぶらせる何かがあることを証明しているかのようだ。
【・・アキオ ・・アキオ 選ばれし者よ 与えてくれ オレに勇気を
最高の そして最速の悪魔に選ばれし者よ オレは今でもやれる・・と 勇気を与えてくれ】
しかし、期限の一ヶ月まであと少しとなったある日、高木はプレッシャーと過労で倒れ、入院してしまった。雨が降る日、入院先に北見が現れ、「たまたまお前の工場に電話したら入院したっていうからさ 今日はゆっくり寝て 明日からまた頼むぜ」という。しかし高木は「オレには出来ませんよ オレはもうダメなんだ ムリだよ・・ 直せないい・・」と泣き出してしまう(このシーンもかなり泣ける!)。
天才チューナーと称された北見は現在では小さな自転車屋のオッチャンであり、北見の後輩である高木は立派なボディショップの社長サン。しかし、北見はそんなことは一切気にせず、若かった当時のままのスタイルで高木に接し、高木も北見の前では泣き虫小僧に戻ってしまう。これは、裏を返せば二人の信頼関係の厚さを表している。
泣き言を言い、涙を流して泣く高木に北見がこう切り出す。
【相変わらずすぐ泣くヤツだなおメェは
覚えてるか Green Autoの2台目のポルシェターボ 280km/hで事故ったぐしゃぐしゃの
お前んトコの親方でさえ『アレは無理』といった・・ でもおメェは
『やらせてください!直らないボディなんてありませんヨ!』
泣きみその小僧と思ってたら生意気にいっちょまえの口ききやがってヨ
あれは本当にいい仕事だった―】
(アニメーション版湾岸ミッドナイト ACT.9 「甦る悪魔」より)《「昔からポルシェって車は板金屋泣かせだったよな スポットもやたらと多いしめんどくせえ車だ それがあそこまでイっちまった 誰もやりたがらねーよな・・」「本当にいい仕事だった あれはもう新車だ おまけにあのケツの重いRRがウソのようにまっすぐ走る あんなポルシェはどこにもねえ」←コミック版よりセリフを補足》
「自信を失いかけている人間にかける言葉」の一つに、過去の行いそのものや、成功例や功績を語ることで、そのときの喜び、感動を思い出させ、心に潤いを戻してやる―というこの行為は、部下の言う事を傾聴できない傾向の強い上司が多い会社組織なども含め、しっかり出来る人間が少ないと思う。
ダイヤモンド社のビジネス情報サイト内「若手社員を辞めさせず成長させる適度なかまい方マニュアル」の記事内にこのような興味深い文章がある(http://diamond.jp/series/masugi/10008/)。
熟達化理論を研究する松尾睦・小樽商科大学教授の研究によれば、営業担当者が、業績に繋がる優れた知識やスキルを獲得するためには10年以上かかっていることが示されたそうです。営業という仕事に限らず、スポーツやアートの領域でも「熟達化の10年ルール」は定説になっています。ただし注意が必要なのは、「10年経てば自動的に熟達する」わけではなく、「熟達するには最低10年かかる」ということです。さらに、10年という期間において「よく考えられた練習を積むことが大切になります」と松尾教授は指摘しています。
「よく考えられた練習というのは、課題が適度に難しく、明確である。すなわちストレッチされていること。また、実行した結果についてフィードバックがあること、何度も繰り返すことができ、誤りを修正する機会があるような練習の仕方です。つまり、ストレッチ&フィードバックが熟達化の条件となります」(松尾教授)やりっぱなし、やらせっぱなしでは、いつまでたっても実力はつかない、というのは普通に理解できますね。若手社員がひとつの業務を終えた後は、その仕事をあなたの経験に照らし合わせて評価し、先輩としての意見を伝えましょう。フィードバックするときには、
1)若手社員の人格についてではなく、行動を評価すること。
2)挑戦して失敗したことを責めない。
この2つが肝心なポイントです。
北見が実践したのはその1つ目のポイントだ。福祉の世界に生きる私は、社会人になって「後輩」という人間に出会ったことはあっても、直接育てることはしていない。せいぜい若い学生の現場実習を一日受け持ったことがあるくらいだ。そういう機会に恵まれたとき、あるいはこれからそうなった場合に心がけていることがある。それは、「アメと鞭」の「鞭」は最初から手に持たないことだ。忠告、叱責、その他もろもろ―そーゆうコトは、直接でも人づてでも言わない。その代わりに褒めるときは匙加減を大事にして、人のいないところで心を込めていう、ということだ。できるかできないかという単純な物差しで人を判断することをしないように、個々人への愛情を持つのが大事だ、ということだ。「いいから黙ってやりなさい」的なモノの言い方では通じない。そう思っている。
「門前の小僧習わぬ経を読む」という諺があり、そういう世界(職場)も中にはあるのだろう。しかし、私は先輩の背中を見て(観察して)、技を盗んで自分で成長するのが全てではないと思っている。植物も動物もそうであるように、自分で育つ責任もあれば育てる責任もあるのだ。
福祉を含めた医療の世界は、現場に入れば患者さん・利用者さんありきだ。その人たちの安全を守る、その人の立場になるのが大前提。しかし、それを成す人間の心が折れてしまっては満足な医療行為など出来るはずがない。自己責任もあると思うが、仕事を為そうとする者の行為や今後の成長をサポートするのは、その人間のパワー・やる気を刺激するコト、心をくすぐるコトであり、それはまぎれもなく上司の仕事である。それはどこの世界でも同じ。それがしっかり出来ている上司がいるならば、若者が入社早々に辞めていくハズがない。
話を物語の方に戻そう。北見はその後、こう語りかける。
【ほら ゆっくりとイメージしろ ミッドナイトブルーの悪魔のボディだ
今1速でゆっくりと動き出した
9000まで回して2速 車速はあがる
3速 4速―
タイヤは確実に路面を捉えているか 轍に進路を乱されてはいないか
そして5速 250 260― さぁ 空気の壁が大きく立ちはだかってきた―
270 280―L2.8改ツインターボ オレが新しく組んだ悪魔の心臓はまだ加速をやめない
もっとだ エンジンはもっと回ろうとしている あとはお前しだいだ
信じろ お前こそが天才だ―】
(湾岸ミッドナイト ACT.9 「甦る悪魔」より)
この場面は、私の上記の文をそのまま読んだり、コミックを見たりするよりも、アニメのシーンでじっくりとご覧いただきたい。北見は、叱咤の言葉でありながら、今まさに高木が着手している仕事が上手くいった暁にはこんな素晴らしい結果が待っている、と暗示をかけることで、高木に最後の勇気をふりしぼる力を与えたのだ。そうして仕上がったボディ―高木の仕事は、北見の手によって新たなエンジンが載せられ、悪魔のZ復活という大きな成果となって表れる。
【よくやった 高木・・】
(アニメーション版湾岸ミッドナイト ACT.10 「ドッグファイト」より)
その時もホロリと涙を流す高木。「北見に褒められることは、高木にとって何よりの賞賛なのだ」と言える。 「ボディ補強は魔法じゃない」と高木は言うが、他の人間には絶対出来ない仕事をしている・できる男だ。その高木の心の動きやそこから溢れた言葉についてはまた別の楽章で綴ってみることにしよう。