「アメ」とは「アはある。メは目・芽」というイミ。
従って「メがある。メが出る」というのが語源。
「あめ」というイミは
①あめ(雨))②あめ(飴)③あめ(天)④あめ(豆汁)⑤あめ(芽を出す)⑥・・・
として日本人の生活の中で使っていますが、本来の「アメ」という日本語(やまとことば)の語源を探求すれば、次のような解釈が得られます。
日本語では「アメ」とは(芽を出す)イミですから、
①の(雨)は、同じ水滴でも人が撒いたのでは、雨が降ったとは言わない。
すれば日本語で何を「アメ」というか。アメという日本語は「芽を出す」という語源から、天から降る水滴で、地上の草木が芽を出し大きく成長するので、之を「アメ」という。
夏の水枯れ時には「アメは慈雨」とか一アメ百万石といわれる「アメ・雨」という日本語である。
万物が芽を出す、正気をとりもどすから、これを先人は「アメ」と教えてくれた。
するとアメという日本語は
①物名の雨
⑤の芽を出すイミを抱かえた「複数のイミ」
中国の漢字は雨(う)という単一のイミしかない。
日本語の「アメ」と漢字の「雨」を同一と考えることはオカシイ。
確かに、くも、はしなど・・・子どものころから、同じ仮名でも意味が違うのを、私たちは知っています。
そこで、発する言葉が先にあった(歴史的に古い)と考えると、あとで漢字を当てはめていったということは理解できます。
従って「メがある。メが出る」というのが語源。
「あめ」というイミは
①あめ(雨))②あめ(飴)③あめ(天)④あめ(豆汁)⑤あめ(芽を出す)⑥・・・
として日本人の生活の中で使っていますが、本来の「アメ」という日本語(やまとことば)の語源を探求すれば、次のような解釈が得られます。
日本語では「アメ」とは(芽を出す)イミですから、
①の(雨)は、同じ水滴でも人が撒いたのでは、雨が降ったとは言わない。
すれば日本語で何を「アメ」というか。アメという日本語は「芽を出す」という語源から、天から降る水滴で、地上の草木が芽を出し大きく成長するので、之を「アメ」という。
夏の水枯れ時には「アメは慈雨」とか一アメ百万石といわれる「アメ・雨」という日本語である。
万物が芽を出す、正気をとりもどすから、これを先人は「アメ」と教えてくれた。
するとアメという日本語は
①物名の雨
⑤の芽を出すイミを抱かえた「複数のイミ」
中国の漢字は雨(う)という単一のイミしかない。
日本語の「アメ」と漢字の「雨」を同一と考えることはオカシイ。
確かに、くも、はしなど・・・子どものころから、同じ仮名でも意味が違うのを、私たちは知っています。
そこで、発する言葉が先にあった(歴史的に古い)と考えると、あとで漢字を当てはめていったということは理解できます。










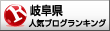




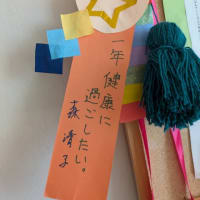

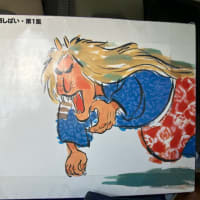









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます