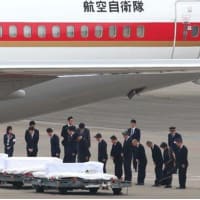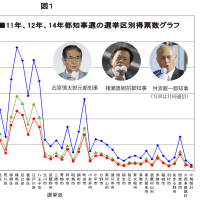■ 裁判員・参加せずとも罰則なし 大久保太郎(元東京高裁部総括判事)
2009年5月19日 Voice
http://news.goo.ne.jp/article/php/life/php-20090516-10.html
本当に「国民の義務」か
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(通称「裁判員法」)が本年5月21日から施行され、裁判員制度が実施されようとしている。
政府(法務省)と最高裁は、「裁判参加」は国民の義務であると強調し、裁判員候補者とされている人々が、具体的な事件についての裁判員等選任手続期日への呼出状を受け取ったときは、呼び出しに応じて裁判所に出頭するように呼び掛けている。
しかし、裁判員法を憲法との関係において検討すれば、国民には「裁判参加の義務」などはなく、むしろ国民には裁判に参加する資格がなく、裁判参加は、法的に違法(違憲)であるとともに、倫理的に参加者自身および被告人に対する二重の冒涜であり、また、裁判所に出頭しなかったからといって過料の制裁を受けることはないと考えられる。
裁判員法には、国民に対し作為または不作為を命じる多くの規定があるが、裁判参加との関係で根本的なものは、国民に裁判所への出頭を命じる規定である。すなわち、同法23条1項は、呼び出しを受けた裁判員候補者は裁判員等選任手続期日に出頭しなければならないと定め、また52条は、裁判員および補充裁判員は公判期日に出頭しなければならないと定めており、これらの規定違反の罰則として、112条は、正当な理由がなく出頭しないときは、10万円以下の過料に処すると定めている。
このような規定の体裁を見るかぎり、裁判所への出頭は「義務」といわざるをえないであろう。政府(法務省)と最高裁が裁判参加は国民の義務だと強調するのは、この裁判員法の規定を根拠とするものであろう。
しかし、この「義務づけ」は、(1)裁判員法の立法が憲法13条に違反すること、(2)「裁判員」自体が合憲であるとの説明はなく、むしろ違憲の疑いが非常に強いことから、憲法上許されるものではないと考えられる。
権利侵害には抵抗権がある
日本国憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しており、憲法の基本的人権保障の要ともいうべき重要な規定である。
ところが裁判員法は、憲法上の根拠もないのに、国民に対し、重大刑事事件の裁判に裁判官と同等の評決権を持って参加するという重い責務を課すものであり、明らかに国民の自由および幸福追求に対する権利を制約するものである。
それゆえ国は、少なくとも立法前に全国民に対し、つくろうとする制度の目的と内容、その必要性、憲法上それが許される理由等を十分に説明したうえ、国民の意見を十分に聴取しなければならなかったと考えられる。
しかし国は、全国民に対する説明や意見聴取を行なうことなく、ただただ立法を急いだのであった。これは、裁判員制度の内容を国民に説明すれば、国民から制度に反対する声が湧き上がって、制度ができなくなることが十分に予想されたからであろう。
つまり、裁判員制度は、国が国民多数の意向とかかわりなく制度をつくって、「さあ協力して参加せよ」と押しつけているのである。
このことのもっとも明白な証拠は、裁判員制度が始まろうとするいまでも多くの国民が「こんな制度を誰が言い出し、どうしてつくったのか」との強い疑問を抱いている事実である。平成20年12月6日に放映された「NHKスペシャル 検証・裁判員制度」のなかでも、討論に参加した人々のなかから「裁判員制度はどうして国民によく説明もされず、国民の意見も聴かずにつくられたのか」との趣旨の声が強く上がっていた。
また、いままでの累次の世論調査でも、圧倒的に多数の人々が「絶対に参加したくない」「本心は参加したくない」との意向を示している。前記NHK番組中のリアルタイムの視聴者に対する調査でも、「参加したくない」が「参加したい」の2倍以上の数字を示していた。このことも、裁判員制度が国民の意向とかかわりなくつくられたことを物語っている。
裁判員制度のこのような“押しつけ性”について、元最高裁判事の東京大学名誉教授團藤重光氏も、「この制度は、あくまで『官製』のものでしょ。司法の民主化、公開性、透明性を本当に言うのであれば、それは国民の中から、民衆の中から湧きあがってくる力でなければならない。それなら僕は尊敬しますけどね。要するに法務省あたりで考えて、誰かが裁判員って名前を考えついて、そうしただけのことでしょう。だから僕は、この裁判員ってのは、くだらないの一言に尽きるんです」と批判している(朝日新書『反骨のコツ』134頁)。
すなわち、以上のような裁判員法の立法状況は、国民の自由および幸福追求に対する権利について、立法という国政のうえで「最大の尊重」がされなかったことを明白に示している。国の当局者は、裁判員制度をつくることは「公共の福祉」だというのかもしれないが、それが当局の独善であることは上記のような国民の声からも明らかである。裁判員法は、この点で憲法13条に明白に違反するものであり、国民に対する前記裁判所への出頭の義務づけは無効だ(憲法の最高法規性を宣言する憲法98条1項参照)といわなければならない。
しかも、この「出頭義務」に従うことは、直ちにその国民の自由および幸福追求に対する権利が侵害されることを意味し、その国民にとって被害は切実(重大)である。このような場合、憲法の人権保障が空文であってはならない以上、その国民には抵抗権があり、出頭しなくても、「正当な理由」の有無にかかわらず、過料の制裁を受けることはないといわなければならない。
不出頭者が増えたら……
このようにいっても、あるいは「それは理論上のことであって、実際上は過料の制裁があるのではないか」との疑問が提出されるかもしれない。しかし、そうではないのだ。
「過料」とは一種の金銭罰だが、罰金ではなく(受けても前科にはならない)、交通違反に対する反則金のようなものである。
これを課す手続きも、呼び出しを受けた裁判員候補者が選任手続期日に出頭しないと、追いかけるように過料の制裁がくるのではなく、あらためて、非訟事件手続法という法律の規定(161条以下)に従って、「過料についての裁判の手続」として、検察官の意見および当事者の陳述を聴き、証拠により「不出頭につき正当な理由のないこと」を確認したうえで、裁判で課されることになっているのだ。
全国で何千人も生じるであろう不出頭者1人ひとりについて、公平にこのような手間のかかる手続きを行ないうるほど裁判所はひまではない。
しかも、裁判員制度には数々の違憲問題がありながら、これについて何の説明もないまま、嫌がる国民に三拝九拝しておいでを願っているのが、いまの司法の実情である。過料の制裁を発動することなど、この制度の強権性をいっそう露わにし、ますます国民の反発を買うことになるだろう。
たまたまある不出頭者に対してだけ過料を課すような、軽はずみの裁判官は1人もいないはずだ。
以上の理由から、実際に過料が課されることはないと考えられる。過料の罰則は、出頭を促すための“おどし”なのである。
むしろ心ある不出頭者が増えれば増えるだけ、この制度の本質的な無理が白日の下に晒されることになるだろう。
最高裁の変節
裁判員制度は、裁判官でない国民に裁判官と同等の評決権を与えて裁判官とともに裁判を行なわせるもので、いわゆる参審制の一種である。
ところが憲法には、裁判員制度はもとより、参審制について何の規定もないから、国は裁判員制度をつくって国民に参加を呼び掛ける以上、当然この制度が憲法上許容される理由を説明しなければならないはずだ。
しかし、法務省も最高裁も、一言半句も説明しない。じつは、まともな説明ができないのである。
元最高裁判事の東京大学名誉教授伊藤正己著『憲法入門』(第4版補訂版230頁)には、「素人を裁判官として参与させる参審制は、憲法にそれについての規定がなく、しかも裁判官の任期や身分保障について専門の裁判官のみを予想しているところから、違憲の疑いが強い」とあり、これが従来の通説である。
さればこそ、ほかならぬ最高裁自身が、過般の司法制度改革審議会において、平成12年9月12日、「陪審制、参審制を採用する国では、憲法上これを保障又は許容する旨の規定が置かれている国が少なくない。しかし、わが国の憲法では、司法権の担い手としての裁判官について身分保障等の詳細な規定が置かれている一方、陪審制、参審制を想定した規定はなく、果たしてこれが憲法上許容されるかどうか問題である。(中略)陪審制について憲法問題を回避するためには、旧陪審のように陪審員の事実認定に裁判官に対する拘束力を認めない形態のものが考えられるであろう。また、参審制について憲法上の疑義を生じさせないためには、評決権を持たない参審制という独自の制度が考えられよう」と述べたのであった。
ところが、この提案が審議会の反対に遭うや、最高裁は沈黙し、やがて参加者に評決権を与える裁判員制度が提案されると、何の説明もなく賛同し、その後は懸命に推進役を演じているのである。この最高裁の変節には、法律家一同、呆気にとられているのが現実だ。
もっとも、大日本帝国憲法24条には「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」と規定されていたのに対し、現憲法32条が「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定している点を主な理由として(傍点引用者)、現憲法上参審制、裁判員制度は許容されるとする異説があり、法務省も最高裁も内心この説を頼りにしてきたようである。しかし、この説の根拠のないことは、近時、新潟大学大学院教授・西野喜一氏の労作『裁判員制度批判』(平成20年、西神田編集室発行。223頁以下)により明らかにされており、いまや筋道の立った合憲論は存在しないのが実情である。
当局は合憲性を説明しようにも説明できないのだ。
のみならず、裁判員法が憲法との関係を慎重厳密に検討することなく拙速に立法された結果、裁判員制度にはこのほか、公平な裁判所の保障(憲法37条 1項)違反、裁判官の独立の規定(同76条3項)違反、国民の基本的人権の保障違反等の少なからぬ憲法違反が指摘され、前記西野喜一氏により「違憲のデパート」と酷評されている有り様である(同氏著、講談社現代新書『裁判員制度の正体』90頁)。
ところで、裁判官は等しく憲法を尊重し、擁護する義務を負うから(憲法99条)、以上のような状況下で裁判員法が施行されると、同法が適用される事件を担当する裁判官はすべて、被告人、弁護人からの申し立ての有無にかかわらず、同法がはたして合憲であるかどうかを審査し、判断する必要に迫られる。
しかしこの場合、裁判員法を合憲と解しようとする努力は、裁判員制度ができたあとからその合憲性を何とか理屈づけようとするものにほかならず、その理屈づけは黒を白と言いくるめるようなもので、当然に牽強付会、曲学阿世のものたらざるをえないが、このような無理を冒して「合憲」を理屈づけた法律を適用して裁判をし、有罪の場合被告人に死刑もありうる科刑をすることなど、裁判官の良心に照らすまでもなく、とうてい許されることではないであろう。
日本国憲法は「司法」に高い地位を与え、立派な規定を設けている。裁判員制度を合憲と理屈づけることは、この司法に与えられた立派な規定を歪曲し、司法の地位を低くすることにほかならない。憲法に根拠がなく、憲法改正に匹敵するような国民的合意を得たものでもない(むしろ大半の国民が反対している)、一時的熱病のような裁判員制度によって憲法を歪めることなど、絶対にあってはならないであろう。
拙速杜撰立法の当然の帰結
国民は当然に裁判参加の資格があるように思わされているが、実情は右のとおりである。裁判員が裁判に参加しうる資格(根拠)が憲法との関係で何も説明されておらず、むしろ説明できない疑いが非常に強いのである。
このような状況下で国民に裁判参加を義務づけ、裁判上の権力行使に参与させることなど、憲法上許されるものではない。
国民がうっかり宣伝に乗って裁判に参加することは、倫理的には背徳行為であり、自己自身および被告人に対する二重の冒涜である。参加すべきではないのだ。
すなわち、このような意味でも、国民には裁判参加の義務などなく、呼び出しに応じないで裁判所に出頭しなくても、過料の制裁を受けることはないといわなければならない。この点は、憲法13条違反との関係ですでに述べたとおりである。
裁判員制度にはこのほかに、事案が複雑で判断の難しい事件や大規模な事件で、審理が長期に及ばざるをえないものについて、審理が円滑に行なわれ、適正な判決が得られるとの見通しが存在しないという重要問題がある。
東京大学教授・井上正仁氏は、司法制度改革審議会委員で、裁判員制度の提案者の1人であるが、その当の井上氏が制度発足直前の今日、「起訴事実が多数などで審理に何カ月もかかるような事件は、裁判員制度の対象からはずせ。そうでもしておかないと大変な問題になる」旨の発言をしているくらいだ(『ジュリスト』平成21年1月1日・15日合併号205頁)。
憲法問題といい、この問題といい、「国民参加制度は司法改革の目玉だ」といった、つくられた時流に流され、慎重厳密な検討を欠いた拙速杜撰立法の当然の帰結である。法務省も最高裁も、いったん立法に賛成した以上、いまさら右のような根本問題があるとはいえないのか、何もないような振りをして制度を推進しているのだ。
マスコミも表面的なことは伝えても、掘り下げて真実を報道することはないから、国民は何も知らない。
こんな状況のなかで裁判員制度は実施されようとしているのだ。
正直であり、誠実であることが何よりも大切な「司法」がこんなことでよいのか! 筆者は声を大にして叫ばずにはいられない。
(終わり)
2009年5月19日 Voice
http://news.goo.ne.jp/article/php/life/php-20090516-10.html
本当に「国民の義務」か
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(通称「裁判員法」)が本年5月21日から施行され、裁判員制度が実施されようとしている。
政府(法務省)と最高裁は、「裁判参加」は国民の義務であると強調し、裁判員候補者とされている人々が、具体的な事件についての裁判員等選任手続期日への呼出状を受け取ったときは、呼び出しに応じて裁判所に出頭するように呼び掛けている。
しかし、裁判員法を憲法との関係において検討すれば、国民には「裁判参加の義務」などはなく、むしろ国民には裁判に参加する資格がなく、裁判参加は、法的に違法(違憲)であるとともに、倫理的に参加者自身および被告人に対する二重の冒涜であり、また、裁判所に出頭しなかったからといって過料の制裁を受けることはないと考えられる。
裁判員法には、国民に対し作為または不作為を命じる多くの規定があるが、裁判参加との関係で根本的なものは、国民に裁判所への出頭を命じる規定である。すなわち、同法23条1項は、呼び出しを受けた裁判員候補者は裁判員等選任手続期日に出頭しなければならないと定め、また52条は、裁判員および補充裁判員は公判期日に出頭しなければならないと定めており、これらの規定違反の罰則として、112条は、正当な理由がなく出頭しないときは、10万円以下の過料に処すると定めている。
このような規定の体裁を見るかぎり、裁判所への出頭は「義務」といわざるをえないであろう。政府(法務省)と最高裁が裁判参加は国民の義務だと強調するのは、この裁判員法の規定を根拠とするものであろう。
しかし、この「義務づけ」は、(1)裁判員法の立法が憲法13条に違反すること、(2)「裁判員」自体が合憲であるとの説明はなく、むしろ違憲の疑いが非常に強いことから、憲法上許されるものではないと考えられる。
権利侵害には抵抗権がある
日本国憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しており、憲法の基本的人権保障の要ともいうべき重要な規定である。
ところが裁判員法は、憲法上の根拠もないのに、国民に対し、重大刑事事件の裁判に裁判官と同等の評決権を持って参加するという重い責務を課すものであり、明らかに国民の自由および幸福追求に対する権利を制約するものである。
それゆえ国は、少なくとも立法前に全国民に対し、つくろうとする制度の目的と内容、その必要性、憲法上それが許される理由等を十分に説明したうえ、国民の意見を十分に聴取しなければならなかったと考えられる。
しかし国は、全国民に対する説明や意見聴取を行なうことなく、ただただ立法を急いだのであった。これは、裁判員制度の内容を国民に説明すれば、国民から制度に反対する声が湧き上がって、制度ができなくなることが十分に予想されたからであろう。
つまり、裁判員制度は、国が国民多数の意向とかかわりなく制度をつくって、「さあ協力して参加せよ」と押しつけているのである。
このことのもっとも明白な証拠は、裁判員制度が始まろうとするいまでも多くの国民が「こんな制度を誰が言い出し、どうしてつくったのか」との強い疑問を抱いている事実である。平成20年12月6日に放映された「NHKスペシャル 検証・裁判員制度」のなかでも、討論に参加した人々のなかから「裁判員制度はどうして国民によく説明もされず、国民の意見も聴かずにつくられたのか」との趣旨の声が強く上がっていた。
また、いままでの累次の世論調査でも、圧倒的に多数の人々が「絶対に参加したくない」「本心は参加したくない」との意向を示している。前記NHK番組中のリアルタイムの視聴者に対する調査でも、「参加したくない」が「参加したい」の2倍以上の数字を示していた。このことも、裁判員制度が国民の意向とかかわりなくつくられたことを物語っている。
裁判員制度のこのような“押しつけ性”について、元最高裁判事の東京大学名誉教授團藤重光氏も、「この制度は、あくまで『官製』のものでしょ。司法の民主化、公開性、透明性を本当に言うのであれば、それは国民の中から、民衆の中から湧きあがってくる力でなければならない。それなら僕は尊敬しますけどね。要するに法務省あたりで考えて、誰かが裁判員って名前を考えついて、そうしただけのことでしょう。だから僕は、この裁判員ってのは、くだらないの一言に尽きるんです」と批判している(朝日新書『反骨のコツ』134頁)。
すなわち、以上のような裁判員法の立法状況は、国民の自由および幸福追求に対する権利について、立法という国政のうえで「最大の尊重」がされなかったことを明白に示している。国の当局者は、裁判員制度をつくることは「公共の福祉」だというのかもしれないが、それが当局の独善であることは上記のような国民の声からも明らかである。裁判員法は、この点で憲法13条に明白に違反するものであり、国民に対する前記裁判所への出頭の義務づけは無効だ(憲法の最高法規性を宣言する憲法98条1項参照)といわなければならない。
しかも、この「出頭義務」に従うことは、直ちにその国民の自由および幸福追求に対する権利が侵害されることを意味し、その国民にとって被害は切実(重大)である。このような場合、憲法の人権保障が空文であってはならない以上、その国民には抵抗権があり、出頭しなくても、「正当な理由」の有無にかかわらず、過料の制裁を受けることはないといわなければならない。
不出頭者が増えたら……
このようにいっても、あるいは「それは理論上のことであって、実際上は過料の制裁があるのではないか」との疑問が提出されるかもしれない。しかし、そうではないのだ。
「過料」とは一種の金銭罰だが、罰金ではなく(受けても前科にはならない)、交通違反に対する反則金のようなものである。
これを課す手続きも、呼び出しを受けた裁判員候補者が選任手続期日に出頭しないと、追いかけるように過料の制裁がくるのではなく、あらためて、非訟事件手続法という法律の規定(161条以下)に従って、「過料についての裁判の手続」として、検察官の意見および当事者の陳述を聴き、証拠により「不出頭につき正当な理由のないこと」を確認したうえで、裁判で課されることになっているのだ。
全国で何千人も生じるであろう不出頭者1人ひとりについて、公平にこのような手間のかかる手続きを行ないうるほど裁判所はひまではない。
しかも、裁判員制度には数々の違憲問題がありながら、これについて何の説明もないまま、嫌がる国民に三拝九拝しておいでを願っているのが、いまの司法の実情である。過料の制裁を発動することなど、この制度の強権性をいっそう露わにし、ますます国民の反発を買うことになるだろう。
たまたまある不出頭者に対してだけ過料を課すような、軽はずみの裁判官は1人もいないはずだ。
以上の理由から、実際に過料が課されることはないと考えられる。過料の罰則は、出頭を促すための“おどし”なのである。
むしろ心ある不出頭者が増えれば増えるだけ、この制度の本質的な無理が白日の下に晒されることになるだろう。
最高裁の変節
裁判員制度は、裁判官でない国民に裁判官と同等の評決権を与えて裁判官とともに裁判を行なわせるもので、いわゆる参審制の一種である。
ところが憲法には、裁判員制度はもとより、参審制について何の規定もないから、国は裁判員制度をつくって国民に参加を呼び掛ける以上、当然この制度が憲法上許容される理由を説明しなければならないはずだ。
しかし、法務省も最高裁も、一言半句も説明しない。じつは、まともな説明ができないのである。
元最高裁判事の東京大学名誉教授伊藤正己著『憲法入門』(第4版補訂版230頁)には、「素人を裁判官として参与させる参審制は、憲法にそれについての規定がなく、しかも裁判官の任期や身分保障について専門の裁判官のみを予想しているところから、違憲の疑いが強い」とあり、これが従来の通説である。
さればこそ、ほかならぬ最高裁自身が、過般の司法制度改革審議会において、平成12年9月12日、「陪審制、参審制を採用する国では、憲法上これを保障又は許容する旨の規定が置かれている国が少なくない。しかし、わが国の憲法では、司法権の担い手としての裁判官について身分保障等の詳細な規定が置かれている一方、陪審制、参審制を想定した規定はなく、果たしてこれが憲法上許容されるかどうか問題である。(中略)陪審制について憲法問題を回避するためには、旧陪審のように陪審員の事実認定に裁判官に対する拘束力を認めない形態のものが考えられるであろう。また、参審制について憲法上の疑義を生じさせないためには、評決権を持たない参審制という独自の制度が考えられよう」と述べたのであった。
ところが、この提案が審議会の反対に遭うや、最高裁は沈黙し、やがて参加者に評決権を与える裁判員制度が提案されると、何の説明もなく賛同し、その後は懸命に推進役を演じているのである。この最高裁の変節には、法律家一同、呆気にとられているのが現実だ。
もっとも、大日本帝国憲法24条には「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」と規定されていたのに対し、現憲法32条が「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定している点を主な理由として(傍点引用者)、現憲法上参審制、裁判員制度は許容されるとする異説があり、法務省も最高裁も内心この説を頼りにしてきたようである。しかし、この説の根拠のないことは、近時、新潟大学大学院教授・西野喜一氏の労作『裁判員制度批判』(平成20年、西神田編集室発行。223頁以下)により明らかにされており、いまや筋道の立った合憲論は存在しないのが実情である。
当局は合憲性を説明しようにも説明できないのだ。
のみならず、裁判員法が憲法との関係を慎重厳密に検討することなく拙速に立法された結果、裁判員制度にはこのほか、公平な裁判所の保障(憲法37条 1項)違反、裁判官の独立の規定(同76条3項)違反、国民の基本的人権の保障違反等の少なからぬ憲法違反が指摘され、前記西野喜一氏により「違憲のデパート」と酷評されている有り様である(同氏著、講談社現代新書『裁判員制度の正体』90頁)。
ところで、裁判官は等しく憲法を尊重し、擁護する義務を負うから(憲法99条)、以上のような状況下で裁判員法が施行されると、同法が適用される事件を担当する裁判官はすべて、被告人、弁護人からの申し立ての有無にかかわらず、同法がはたして合憲であるかどうかを審査し、判断する必要に迫られる。
しかしこの場合、裁判員法を合憲と解しようとする努力は、裁判員制度ができたあとからその合憲性を何とか理屈づけようとするものにほかならず、その理屈づけは黒を白と言いくるめるようなもので、当然に牽強付会、曲学阿世のものたらざるをえないが、このような無理を冒して「合憲」を理屈づけた法律を適用して裁判をし、有罪の場合被告人に死刑もありうる科刑をすることなど、裁判官の良心に照らすまでもなく、とうてい許されることではないであろう。
日本国憲法は「司法」に高い地位を与え、立派な規定を設けている。裁判員制度を合憲と理屈づけることは、この司法に与えられた立派な規定を歪曲し、司法の地位を低くすることにほかならない。憲法に根拠がなく、憲法改正に匹敵するような国民的合意を得たものでもない(むしろ大半の国民が反対している)、一時的熱病のような裁判員制度によって憲法を歪めることなど、絶対にあってはならないであろう。
拙速杜撰立法の当然の帰結
国民は当然に裁判参加の資格があるように思わされているが、実情は右のとおりである。裁判員が裁判に参加しうる資格(根拠)が憲法との関係で何も説明されておらず、むしろ説明できない疑いが非常に強いのである。
このような状況下で国民に裁判参加を義務づけ、裁判上の権力行使に参与させることなど、憲法上許されるものではない。
国民がうっかり宣伝に乗って裁判に参加することは、倫理的には背徳行為であり、自己自身および被告人に対する二重の冒涜である。参加すべきではないのだ。
すなわち、このような意味でも、国民には裁判参加の義務などなく、呼び出しに応じないで裁判所に出頭しなくても、過料の制裁を受けることはないといわなければならない。この点は、憲法13条違反との関係ですでに述べたとおりである。
裁判員制度にはこのほかに、事案が複雑で判断の難しい事件や大規模な事件で、審理が長期に及ばざるをえないものについて、審理が円滑に行なわれ、適正な判決が得られるとの見通しが存在しないという重要問題がある。
東京大学教授・井上正仁氏は、司法制度改革審議会委員で、裁判員制度の提案者の1人であるが、その当の井上氏が制度発足直前の今日、「起訴事実が多数などで審理に何カ月もかかるような事件は、裁判員制度の対象からはずせ。そうでもしておかないと大変な問題になる」旨の発言をしているくらいだ(『ジュリスト』平成21年1月1日・15日合併号205頁)。
憲法問題といい、この問題といい、「国民参加制度は司法改革の目玉だ」といった、つくられた時流に流され、慎重厳密な検討を欠いた拙速杜撰立法の当然の帰結である。法務省も最高裁も、いったん立法に賛成した以上、いまさら右のような根本問題があるとはいえないのか、何もないような振りをして制度を推進しているのだ。
マスコミも表面的なことは伝えても、掘り下げて真実を報道することはないから、国民は何も知らない。
こんな状況のなかで裁判員制度は実施されようとしているのだ。
正直であり、誠実であることが何よりも大切な「司法」がこんなことでよいのか! 筆者は声を大にして叫ばずにはいられない。
(終わり)