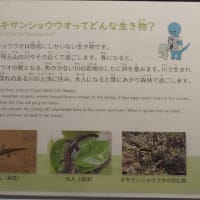【 2011年9月26日 】 京都シネマ
精神病院を全廃したイタリアでの話し。実際の話をベースにした映画で、期待していた以上にいい映画だった。
普通、この手の映画は希望的観測が先行してしまい、現実世界では通用しない、実際ありえないドタバタ喜劇風の成功話に終わってしまいがちだが、そうではなかった。

労働組合の仕事を取り上げられたネッロの新しい仕事は、病院から出された精神病患者の協働組合の管理者だった。
イタリアでは、1978年に制定されたバザーリア法により、順次精神病院は縮小され、2000年には全廃されたという。
先進的な医師バザーリアによって、トリエステで始まったこの精神医療改革は、人権を無視した強制入院や脅迫的な《治療》から精神病患者を解放したという点で画期的だし、精神病患者も社会の一員であるという位置づけも、日本ではちょっと考えられない先進的なものだ。
しかし一方では、精神病患者を強制隔離された病棟から解き放して大丈夫なのかという《心配》は当然ある。一般社会の中に放り出された患者は、日常生活をどうすごしていくのだろうか。仕事はどうなるのか。生活の基盤を誰がどう支えていくのか。

こうしたことを解決していくためにイタリアでは精神病院に代わって、各地に『精神保健センター』が作られ、患者のケアをして、その他さまざまな地域の組織が協力し合い、役割を果たしていくことになる。
映画の中のネッロが新たに派遣された『生産協同組合』もそうした患者らを支える組織の1つである。

その結果、この映画にあるように患者が社会に積極的に関わっていけるようになり、《病院が患者を作る》という事態も改善されることになる。
それでも《緊急事態で入院》ということも有り得る現実だが、患者の平均入院日数も日本の10分の1以下になっているという。
映画の中のネッロが新たに派遣された『生産協同組合』もそうした患者らを支える組織の1つである。

それでも《現実世界》とのギャップは大きい。それまで『協働組合』の仕事といえば、封筒の切手貼りとかの単純作業で、市役所から入る報酬はわずか。社会にもっとかかわるためにも自立のためにも、ネッロはそれを個々人の能力を引き出しより《高度》な仕事をしてよりましな報酬を得ようと考える。そのためには市場に参入し認めてもらう必要がある。

ここからネッロを始めとする9人の《患者》の悪戦苦闘が始まる。
難しい問題を扱っているにもかかわらず、小気味よいテンポとリアルで個性を持った配役。必死にそして人生を楽しく前向きに生きようとする人たち。意見を誇張して主張するわけでもなく、嬉しい出来事、悲しい事件、ありうる日常を、自然に描いていく。

映画の中で、何気なく懐かしい名前が一瞬だけ出てきた。《友人のベルリンゲルが亡くなった》というシーンだ。その葬儀に出席するため職場を離れなければならないという、《よっぽど重大な事件が起こった》と想像させるシーンだが、ほとんどの人は誰のことか分らないだろう。

【エンリコ・ベルリンゲル】
懐かしい名前に触れ、ふと、あつく燃えていた昔を思い出した。
○ ○ ○

【 トリエステにある実際の『生産協同組合』の様子 】
 『人生、ここにあり』-公式サイト
『人生、ここにあり』-公式サイト