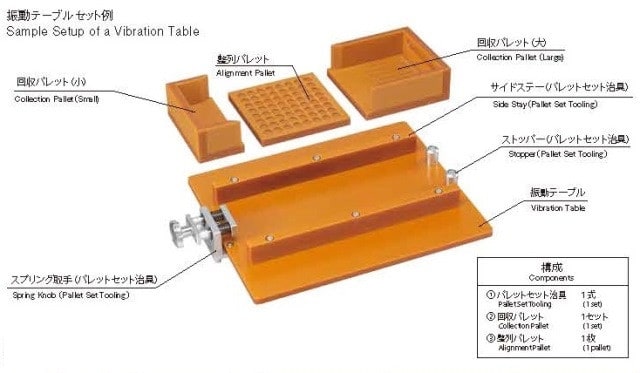コーヒータイム(与太話)
先週は北品川の寒桜の写真を投稿しましたが、
今週は白梅と紅梅が綺麗に並んで咲いている
写真を一つ。

春が近付いているなあ、と写真だけだと
そう感じますが、実際にその場にいると、
やはり寒いです。今年の冬は本当に寒いです。
ちなみに、これは江戸川公園の中です。
江戸川公園は、普通の公園とは違い、
川に沿った細長い公園です。
幅は10mあるかないか程度ですが、
長さは1kmくらいあります。
今の時期だと梅ですが、江戸川公園は桜並木が
有名です。満開の時は見事で、ライトアップも
されます。
ところで、当の川自体は、東京の都心にありがちな
用水路っぽい川で、綺麗な川とは程遠いものです。
排水路のような色です。
しかし、昔は、神田上水の堰が有った所らしいです。
私のような地方出身者は、江戸の水道の歴史を
知らない人が多いです。
江戸に幕府が出来ると、江戸は急速に発展し、
人口も急増しました。街中は海が近いので、
普通に井戸水をくみ上げると、
塩分が混じっています。
そこで、生活用水・飲用水として、
川の上流の方から、江戸の街に
水道を通したのです。
時代劇に出て来る、江戸の街に有る井戸、
あれは湧き水ではなく、地下に作られた
上水道の水をくみ上げていたのです。
ご存知の方も多いかと思いますが、
有名なのが神田上水と玉川上水です。
神田上水は井の頭公園から引いた上水道で、
玉川上水は、今の羽村市から引いた上水道でした。
江戸川公園は、その神田上水の堰が有った跡、
というわけです。
非常に長い距離の上水道で、川のように水面が
見えている場所もありましたが、江戸の街中では、
瓦(焼き物)や石、木や竹などで水道管を造り、
それを地中に埋め込んでいました。
江戸時代の初頭、もちろんポンプなどは有りませんから、
重力、即ち自然落下を利用して作られた水道でした。
しかし、玉川上水の場合、上水道の起点である羽村と、
終点である四谷は、高低差が100mほどしかありません。
一方で、距離は43kmもあります。
つまり、平均の傾斜角度は、僅か0.133°という
事になります。これだけの僅かな傾斜の水道を、
43kmにも渡って作り上げたというのは、
驚異的な技術です。
しかし、作ったのも大変でしたが、運営・管理も
大変だったようです。今とは違って、浄水設備が
ありませんから、上水道が汚れないように
監視・管理が必要でした。
しかも、水道管が石や瓦ならまだしも、
木や竹の部分もありました。耐久性にかなり
問題がありそうです。水圧こそ掛かりませんが、
補修などで、水道工事は結構頻繁に行われていたと
思われます。
実際には、部分的にかなりの水漏れを起こしながら、
流れ着いていたんだろうなあと想像されます。
今のように化学的な殺菌とかもされませんから、
一見綺麗に見えても、衛生的にはかなり
不純物が混じっていた水だったろうなあ
という事は想像に難くありません。
実際、明治期に入って、江戸幕府による上水の
管理が止まってしまうと、水道管の補修工事も滞り、
疫病が発生しやすくなったそうです。
こりゃいかん、という事で、今の水道管に近い技術で、
急いで水道を作り直したとの事です。
さて、神田上水の終点近くに、東京都水道歴史館
というのが今は有ります。神田上水や玉川上水の
詳しい資料や遺物が展示されています。
しかも、隣接している公園には、ちょっとした
バラ園が有ります。少し小高い位置にあり、
近所からは死角になっているため、
人が少ないですが、春には結構見応えのある
バラが咲きます。
公園が有る事自体、あまり知られていないためか、
都会の真ん中なのに、非常に落ち着ける穴場と
なっています。
先週は北品川の寒桜の写真を投稿しましたが、
今週は白梅と紅梅が綺麗に並んで咲いている
写真を一つ。

春が近付いているなあ、と写真だけだと
そう感じますが、実際にその場にいると、
やはり寒いです。今年の冬は本当に寒いです。
ちなみに、これは江戸川公園の中です。
江戸川公園は、普通の公園とは違い、
川に沿った細長い公園です。
幅は10mあるかないか程度ですが、
長さは1kmくらいあります。
今の時期だと梅ですが、江戸川公園は桜並木が
有名です。満開の時は見事で、ライトアップも
されます。
ところで、当の川自体は、東京の都心にありがちな
用水路っぽい川で、綺麗な川とは程遠いものです。
排水路のような色です。
しかし、昔は、神田上水の堰が有った所らしいです。
私のような地方出身者は、江戸の水道の歴史を
知らない人が多いです。
江戸に幕府が出来ると、江戸は急速に発展し、
人口も急増しました。街中は海が近いので、
普通に井戸水をくみ上げると、
塩分が混じっています。
そこで、生活用水・飲用水として、
川の上流の方から、江戸の街に
水道を通したのです。
時代劇に出て来る、江戸の街に有る井戸、
あれは湧き水ではなく、地下に作られた
上水道の水をくみ上げていたのです。
ご存知の方も多いかと思いますが、
有名なのが神田上水と玉川上水です。
神田上水は井の頭公園から引いた上水道で、
玉川上水は、今の羽村市から引いた上水道でした。
江戸川公園は、その神田上水の堰が有った跡、
というわけです。
非常に長い距離の上水道で、川のように水面が
見えている場所もありましたが、江戸の街中では、
瓦(焼き物)や石、木や竹などで水道管を造り、
それを地中に埋め込んでいました。
江戸時代の初頭、もちろんポンプなどは有りませんから、
重力、即ち自然落下を利用して作られた水道でした。
しかし、玉川上水の場合、上水道の起点である羽村と、
終点である四谷は、高低差が100mほどしかありません。
一方で、距離は43kmもあります。
つまり、平均の傾斜角度は、僅か0.133°という
事になります。これだけの僅かな傾斜の水道を、
43kmにも渡って作り上げたというのは、
驚異的な技術です。
しかし、作ったのも大変でしたが、運営・管理も
大変だったようです。今とは違って、浄水設備が
ありませんから、上水道が汚れないように
監視・管理が必要でした。
しかも、水道管が石や瓦ならまだしも、
木や竹の部分もありました。耐久性にかなり
問題がありそうです。水圧こそ掛かりませんが、
補修などで、水道工事は結構頻繁に行われていたと
思われます。
実際には、部分的にかなりの水漏れを起こしながら、
流れ着いていたんだろうなあと想像されます。
今のように化学的な殺菌とかもされませんから、
一見綺麗に見えても、衛生的にはかなり
不純物が混じっていた水だったろうなあ
という事は想像に難くありません。
実際、明治期に入って、江戸幕府による上水の
管理が止まってしまうと、水道管の補修工事も滞り、
疫病が発生しやすくなったそうです。
こりゃいかん、という事で、今の水道管に近い技術で、
急いで水道を作り直したとの事です。
さて、神田上水の終点近くに、東京都水道歴史館
というのが今は有ります。神田上水や玉川上水の
詳しい資料や遺物が展示されています。
しかも、隣接している公園には、ちょっとした
バラ園が有ります。少し小高い位置にあり、
近所からは死角になっているため、
人が少ないですが、春には結構見応えのある
バラが咲きます。
公園が有る事自体、あまり知られていないためか、
都会の真ん中なのに、非常に落ち着ける穴場と
なっています。