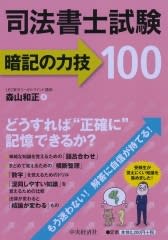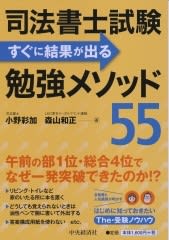最高裁平成27年11月20日第2小法廷判決
【裁判要旨】遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
赤のボールペンで、遺言書に大きく斜線を入れた行為が遺言書の破棄に該当するということです。
テキストには、遺言書を火に投げ入れるなどという事例が載っていると思いますが、
それと同じ扱いになるということですね。
その理由として、
最高裁は、
「本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である」
と述べています。
Yahoo!ニュース
最高裁平成27年11月19日第1小法廷判決
【裁判要旨】保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない
最高裁は、
「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,主たる債務者の資力が不十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される。」
と述べています。
【裁判要旨】遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
赤のボールペンで、遺言書に大きく斜線を入れた行為が遺言書の破棄に該当するということです。
テキストには、遺言書を火に投げ入れるなどという事例が載っていると思いますが、
それと同じ扱いになるということですね。
その理由として、
最高裁は、
「本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である」
と述べています。
Yahoo!ニュース
最高裁平成27年11月19日第1小法廷判決
【裁判要旨】保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない
最高裁は、
「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,主たる債務者の資力が不十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される。」
と述べています。