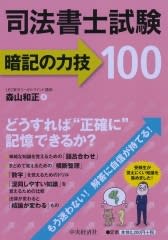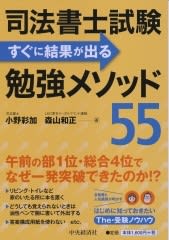刑法改正の情報です。
過去問の解答も変わります。
まず,次の過去問を答えてみてください。
日本人が日本国外において,日本国の公務員に対する,その職務に関しての賄賂の供与をした場合に,わが国の刑法が適用されない。(S56-25-3)
答えは○ですね。
外国で日本の公務員が収賄を受けたら,日本の刑法が適用されます(刑法4条)。
これに対して,
外国で日本人が日本の公務員に贈賄をしたら,日本の刑法は適用されない。
ということですね。
刑法3条の国外犯規定に贈賄が含まれていないのです。
基本知識ですね。
ケータイ司法書士にも書いてあります。
しかし,刑法が改正されて,刑法3条に贈賄が追加されました(刑法3条6号)。
組織的犯罪処罰法改正の関係です。
すでに施行されております。
改正後は,
「日本国外で,日本人が贈賄罪を犯した場合,日本の刑法が適用される」
となります。
ということで,先述の過去問,×に解答変更となります。
合格ゾーンの最新版も解答が○となっていますので,×に直しておいてください。
そして,
ケータイ司法書士を使っている方も,
ケータイ司法書士4
P214
[2]刑法の適用範囲
(4)の矢印を削っておいてください。
P215
下から2つめの問題の答えを×から○に直しておいてください。
すでに刑法の講義が終わってしまったクラスにおいては,
これらの情報の指摘ができませんでした。
情報提供が間に合わず本当に申し訳ありませんでした。
まだ,講座継続中のクラスの方は,講座の中でまたお話しします。
ケータイ司法書士や僕の講義を利用している方以外の方も,
各自のテキスト,過去問集を最新の情報に直しておいてください。
また,これ以外の改正点についても,ケータイ司法書士の情報アップデート動画とブログ記事の準備をしています。
読者の方に安心して使っていただけるように,情報を提供していきたいと思っています。
近いうちに更新します。
もうしばらくお待ちください。
過去問の解答も変わります。
まず,次の過去問を答えてみてください。
日本人が日本国外において,日本国の公務員に対する,その職務に関しての賄賂の供与をした場合に,わが国の刑法が適用されない。(S56-25-3)
答えは○ですね。
外国で日本の公務員が収賄を受けたら,日本の刑法が適用されます(刑法4条)。
これに対して,
外国で日本人が日本の公務員に贈賄をしたら,日本の刑法は適用されない。
ということですね。
刑法3条の国外犯規定に贈賄が含まれていないのです。
基本知識ですね。
ケータイ司法書士にも書いてあります。
しかし,刑法が改正されて,刑法3条に贈賄が追加されました(刑法3条6号)。
組織的犯罪処罰法改正の関係です。
すでに施行されております。
改正後は,
「日本国外で,日本人が贈賄罪を犯した場合,日本の刑法が適用される」
となります。
ということで,先述の過去問,×に解答変更となります。
合格ゾーンの最新版も解答が○となっていますので,×に直しておいてください。
そして,
ケータイ司法書士を使っている方も,
ケータイ司法書士4
P214
[2]刑法の適用範囲
(4)の矢印を削っておいてください。
P215
下から2つめの問題の答えを×から○に直しておいてください。
すでに刑法の講義が終わってしまったクラスにおいては,
これらの情報の指摘ができませんでした。
情報提供が間に合わず本当に申し訳ありませんでした。
まだ,講座継続中のクラスの方は,講座の中でまたお話しします。
ケータイ司法書士や僕の講義を利用している方以外の方も,
各自のテキスト,過去問集を最新の情報に直しておいてください。
また,これ以外の改正点についても,ケータイ司法書士の情報アップデート動画とブログ記事の準備をしています。
読者の方に安心して使っていただけるように,情報を提供していきたいと思っています。
近いうちに更新します。
もうしばらくお待ちください。