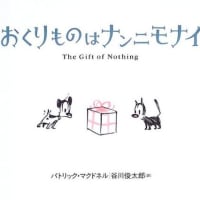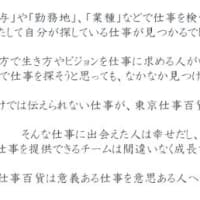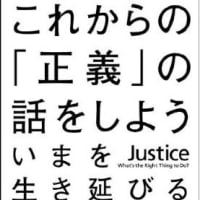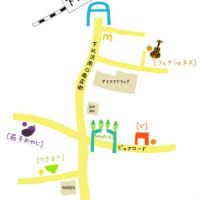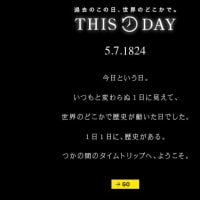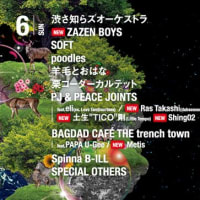まあ、気を取り直し、今回も一つ僕の好きな短編の一節を紹介してみる。
僕は懲りない性分なのです。
順子はいつものようにジャック・ロンドンの『たき火』のことを思った。
アラスカの奥地の雪の中で、一人で旅をする男が火をおこそうとする話だ。火がつかなければ、彼は確実に凍死してしまう。日は暮れようとしている。
彼女は小説なんてほとんど読んだことがない。でも高校一年生の夏休みに、読書感想文の課題として与えられたその短編小説だけは、何度も何度も読んだ。
物語の情景はとても自然にいきいきと彼女の頭に浮かんできた。死の瀬戸際にいる男の心臓の鼓動や、恐怖や希望や絶望を、自分自身のことのように切実に感じることができた。
でもその物語の中で、何よりも重要だったのは、―基本的には―その男が死を求めているという事実だった。彼女にはそれがわかった。うまく理由を説明することはできない。ただ最初から理解できたのだ。
この旅人はほんとうは死を求めている。
それが自分にふさわしい結末だと―知っている―。
それにもかかわらず、彼は全力を尽くして闘わなくてはならない。
生き残ることを目的として、圧倒的なるものを相手に闘わなくてはならないのだ。
順子を深いところで揺さぶったのは、物語の中心にあるそのような根源的ともいえる矛盾だった。
教師は彼女の意見を笑い飛ばした。
この主人公は実は死を求めている?教師はあきれたように言った。そんな不思議な感想を聞いたのは初めてだな。それはずいぶん独創的な意見みたいに聞こえるねえ。
彼が順子の感想文の一部を読み上げると、クラスのみんなも笑った。
『アイロンのある風景』村上春樹
これは茨城県のとある海岸で、たき火を囲む男と女の話です。
男は何らかの事情で家庭を捨て、茨城に住みつき変な絵を書いて暮らしている。
この男に親しみを覚えた主人公順子が、男のたき火に付き合い、冬の寒い夜、たき火を見ながら会話をするというそれだけの短編です。
読書感想文の課題にジャック・ロンドンが出されること自体ありえない話ではありますが、そんなことはどうでもいいのです。
この短編の主題は、―基本的に―死を求める人間が、全力で生きようとする矛盾にあります。
このことを感じ取った順子が、深い傷を負った男とたき火を見ながら語りあうのです。
時として僕達は、若い人々が死を望んでいることを軽薄に捉えてしまいがちです。
君にはまだ知らない未来がある、とか、そんなことで絶望するのは甘いよ、だとかね。
でも、そんな教科書通りのお説教なんてたいした意味をもたないんであって、あなたにとっては何でもないことかもしれないけれど、私にとっては生きるか死ぬかの問題なんですって言われてしまうのがオチです。
死にたいやつは勝手に死ねばいいんだ、とかいう怖い声もあがりそうですけど、それも間違いです。
なぜなら、そんなことを言っている人に限って「死」とろくに向き合ったこともないと思えてしまうからです。
これを読んでいるあなたは少なくとも生きているはずです。
ということは「死」を知りません。
間接的事実以外の「死」を、あなたや私は「経験する」ことができないのです。それだけは間違いありません。
そんな人類にとって永遠の「未経験」である「死」について、
僕やあなたが偉そうに言うことはできないのですよ。
なんてね。そんなことを僕が言うことがイチバン間違ってますよね、出過ぎました。
まあなんにせよ、この短編。
実に味わい深いお話です。
追記:
ジャック・ロンドンの『たき火』ですが、柴田元幸氏によって『火を熾す』というタイトルで訳されたものを読みました。
もちろん、期待を裏切らない素晴らしい作品でしたが、この日記に書いたような「本質的には死を求めている」という主題は、あくまで村上さんが設定している順子の持論です。
それが絶対に正しいという明確なところは何一つありません。
でもでも、ジャック・ロンドンという人間をよくよく知った上で、そういう主題が含まれているのかもしれない、という考えを否定したり、ましてや笑い飛ばす理由もまたありません。
死に抗う人間の本性を、そして死にあっけなく屈してしまう人間の脆さを、息もつかさぬスピードで刻んでゆくリズム、そのステップを、是非とも読んで体感してみて下さい。
僕は懲りない性分なのです。
順子はいつものようにジャック・ロンドンの『たき火』のことを思った。
アラスカの奥地の雪の中で、一人で旅をする男が火をおこそうとする話だ。火がつかなければ、彼は確実に凍死してしまう。日は暮れようとしている。
彼女は小説なんてほとんど読んだことがない。でも高校一年生の夏休みに、読書感想文の課題として与えられたその短編小説だけは、何度も何度も読んだ。
物語の情景はとても自然にいきいきと彼女の頭に浮かんできた。死の瀬戸際にいる男の心臓の鼓動や、恐怖や希望や絶望を、自分自身のことのように切実に感じることができた。
でもその物語の中で、何よりも重要だったのは、―基本的には―その男が死を求めているという事実だった。彼女にはそれがわかった。うまく理由を説明することはできない。ただ最初から理解できたのだ。
この旅人はほんとうは死を求めている。
それが自分にふさわしい結末だと―知っている―。
それにもかかわらず、彼は全力を尽くして闘わなくてはならない。
生き残ることを目的として、圧倒的なるものを相手に闘わなくてはならないのだ。
順子を深いところで揺さぶったのは、物語の中心にあるそのような根源的ともいえる矛盾だった。
教師は彼女の意見を笑い飛ばした。
この主人公は実は死を求めている?教師はあきれたように言った。そんな不思議な感想を聞いたのは初めてだな。それはずいぶん独創的な意見みたいに聞こえるねえ。
彼が順子の感想文の一部を読み上げると、クラスのみんなも笑った。
『アイロンのある風景』村上春樹
 | 神の子どもたちはみな踊る (新潮文庫)村上 春樹新潮社このアイテムの詳細を見る |
これは茨城県のとある海岸で、たき火を囲む男と女の話です。
男は何らかの事情で家庭を捨て、茨城に住みつき変な絵を書いて暮らしている。
この男に親しみを覚えた主人公順子が、男のたき火に付き合い、冬の寒い夜、たき火を見ながら会話をするというそれだけの短編です。
読書感想文の課題にジャック・ロンドンが出されること自体ありえない話ではありますが、そんなことはどうでもいいのです。
この短編の主題は、―基本的に―死を求める人間が、全力で生きようとする矛盾にあります。
このことを感じ取った順子が、深い傷を負った男とたき火を見ながら語りあうのです。
時として僕達は、若い人々が死を望んでいることを軽薄に捉えてしまいがちです。
君にはまだ知らない未来がある、とか、そんなことで絶望するのは甘いよ、だとかね。
でも、そんな教科書通りのお説教なんてたいした意味をもたないんであって、あなたにとっては何でもないことかもしれないけれど、私にとっては生きるか死ぬかの問題なんですって言われてしまうのがオチです。
死にたいやつは勝手に死ねばいいんだ、とかいう怖い声もあがりそうですけど、それも間違いです。
なぜなら、そんなことを言っている人に限って「死」とろくに向き合ったこともないと思えてしまうからです。
これを読んでいるあなたは少なくとも生きているはずです。
ということは「死」を知りません。
間接的事実以外の「死」を、あなたや私は「経験する」ことができないのです。それだけは間違いありません。
そんな人類にとって永遠の「未経験」である「死」について、
僕やあなたが偉そうに言うことはできないのですよ。
なんてね。そんなことを僕が言うことがイチバン間違ってますよね、出過ぎました。
まあなんにせよ、この短編。
実に味わい深いお話です。
追記:
ジャック・ロンドンの『たき火』ですが、柴田元幸氏によって『火を熾す』というタイトルで訳されたものを読みました。
もちろん、期待を裏切らない素晴らしい作品でしたが、この日記に書いたような「本質的には死を求めている」という主題は、あくまで村上さんが設定している順子の持論です。
それが絶対に正しいという明確なところは何一つありません。
でもでも、ジャック・ロンドンという人間をよくよく知った上で、そういう主題が含まれているのかもしれない、という考えを否定したり、ましてや笑い飛ばす理由もまたありません。
死に抗う人間の本性を、そして死にあっけなく屈してしまう人間の脆さを、息もつかさぬスピードで刻んでゆくリズム、そのステップを、是非とも読んで体感してみて下さい。