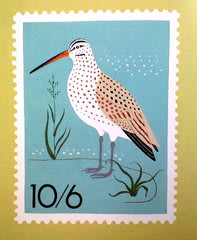さよならシナプス。さようなら。
先日、奥歯の神経を抜きました。
麻酔の技術が発達したせいか、痛みはまったくありませんが、、自分の一部が失われていく感覚は物悲しい。
一度、自分の歯の神経を医者に見せられたことがあります。
新鮮な薄桃色の細く小さな神経細胞がピンセットでつままれ、目の前でぷるぷると震えている様子を僕は鮮明に覚えています。
かつて僕の一部であった神経細胞よ、さようなら。
僕に痛みを教えてくれた細胞。
僕を支えてくれた細胞よ。
僕はできることなら君とともに生きたかった。我慢もした。
でも、結局はその痛みに耐え切れなかったのだ。
医者は言う。もう少し我慢できないのか、神経を抜くのは簡単だけど、もう二度と戻らないんだよ。
看護師の女の人は言った。こんな状態で我慢している人はなかなかいないよ。そりゃそうさ。僕だってできることなら失いたくはない。
しばらくの思考の後、僕はやはり神経を抜く決心を彼女に告げる。
人には本当に無数の決断するタイミングがある。
そして、その多くを、考えてみれば他人任せにして生きていることが驚くほど多い。その結果、決定的な判断すら他人任せにしてしまいたくなるのが人情である。そう感ずることが多い。
だからこそ、いざ、重要な判断。それが自分の人生に関わる大きな事柄であればあるほど人は困惑するのだ。私が私自身が判断をせねばならない。その事実に人は困惑する。
私は困惑し、そして決断を下す。
それは正しい判断であったか、わからない。
無数のありえたかもしれない結果は、所詮、無数の夢想に過ぎず、人は自らの通った道しか覗き見ることはできない。
そして、判断など、時の過ぎ行くままに変質を続ける。
不毛だ。
けだし、人は選び、生きなければならない。
さよならシナプス。
さようなら、僕の片隅。
先日、奥歯の神経を抜きました。
麻酔の技術が発達したせいか、痛みはまったくありませんが、、自分の一部が失われていく感覚は物悲しい。
一度、自分の歯の神経を医者に見せられたことがあります。
新鮮な薄桃色の細く小さな神経細胞がピンセットでつままれ、目の前でぷるぷると震えている様子を僕は鮮明に覚えています。
かつて僕の一部であった神経細胞よ、さようなら。
僕に痛みを教えてくれた細胞。
僕を支えてくれた細胞よ。
僕はできることなら君とともに生きたかった。我慢もした。
でも、結局はその痛みに耐え切れなかったのだ。
医者は言う。もう少し我慢できないのか、神経を抜くのは簡単だけど、もう二度と戻らないんだよ。
看護師の女の人は言った。こんな状態で我慢している人はなかなかいないよ。そりゃそうさ。僕だってできることなら失いたくはない。
しばらくの思考の後、僕はやはり神経を抜く決心を彼女に告げる。
人には本当に無数の決断するタイミングがある。
そして、その多くを、考えてみれば他人任せにして生きていることが驚くほど多い。その結果、決定的な判断すら他人任せにしてしまいたくなるのが人情である。そう感ずることが多い。
だからこそ、いざ、重要な判断。それが自分の人生に関わる大きな事柄であればあるほど人は困惑するのだ。私が私自身が判断をせねばならない。その事実に人は困惑する。
私は困惑し、そして決断を下す。
それは正しい判断であったか、わからない。
無数のありえたかもしれない結果は、所詮、無数の夢想に過ぎず、人は自らの通った道しか覗き見ることはできない。
そして、判断など、時の過ぎ行くままに変質を続ける。
不毛だ。
けだし、人は選び、生きなければならない。
さよならシナプス。
さようなら、僕の片隅。