東大寺大仏
聖武天皇が関東へ行幸したのは740年広嗣の乱直後である。吉野宮を出発した一向400名は伊賀・名張→伊勢・鈴鹿→桑名→野上(関ヶ原・不破)→近江→恭仁京(くにきょう)に着いた。
安積親王が急死したという恭仁宮(くにのみやこ)
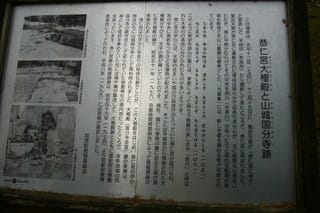

これは大海人皇子が大友皇子と戦い壬申の乱で勝利したときの軍行に非情に似ている。壬申の乱の後を辿り、自分の心の逃避を勝利宣言に塗り替えるための行動とも読み取れる。 僧・玄坊により母・宮子の幽閉が解け、37年ぶりに再会したときには、聖武天皇の藤原氏による呪縛も解けて、藤原氏に対する反発が、この流浪へと駆り立てたようにも思える。 恭仁京は平城京の真北すぐに位置し、橘諸兄とゆかりの深い地であったと同時に背後には天然の要塞があり、平城京という藤原一族への挑戦のようにも思える。 因みに藤原不比等の所有する5000戸を朝廷に返上したのは、聖武天皇一向が恭仁京に着いたすぐ後である。400名の軍行の先頭には藤原仲麻呂が任命され、漢氏・秦氏を指名した。藤原仲麻呂は背中に槍を付き立てられ、身動きができない状態で先導さされたのを考えると思いつきの流浪でもなさそうである。そう考えたとき、藤原氏の象徴である興福寺を圧倒するかのように建てられた東大寺の意味もわかるような気がするのである。
741年、諸国国分寺に与えられた藤原家の諸領は仏像造りに当てられた。聖武天皇は国分寺建立の詔を発し広嗣の乱の連座者を処刑にするとともに平城京にあった兵器・官位等の諸機能を恭仁京に移した。当時藤原の最高権威であった藤原豊成が平城京の留守役を命じられたのは屈辱であっただろう。742年に恭仁京内の大安殿にて踏歌の節会の宴が開かれ五節田舞(天武天皇の血統重視の舞)が行われ、翌月には皇后宮に行幸し、聖武天皇の絶頂の様子が記録されている。 藤原氏が敗北すると橘諸兄は左大臣となり、743年紫香楽宮に逗留したあと大仏発願の詔を発した。
大養徳国金光明寺で大仏の基壇が造り始められたのは745年8月頃である。聖武天皇が崩御する756年にはほとんど出来上がり、翌757年に完成する。大仏は民衆の協力によって完成させることを理想とするものであり、それを託されたのは行基とその集団であった。紫香楽で詔が出された直後には行基は弟子を率いて大仏造立の知識勧誘に乗り出していた。行基とともに東大寺の経営を支えたのは後の東大寺初代別当の良弁である。 良弁は689年生まれで聖武天皇の基皇太子供養のために金鐘山房に住まわされた僧の一人とされ、金鷲菩薩ともいわれた。 大仏建立により金光明寺は東大寺へと発展し、造東大寺司という組織が誕生する。 この最初の長官は施基皇子の曾孫・市原王で佐伯今毛人が支えたとされる。大仏の設計・鋳造を担ったのは国中公麻呂で、761年には造東大寺司次官になっている。
大仏は1180年南都焼き討ちによって灰燼に帰し、白河法皇の開眼供養により復活するが1567年に三好・松永の争いにより再び崩れ落ちた。1692年の再建後は1708年に大仏殿も再建され現在に至る。















































































































































































