2006年初頭にαはコニカミノルタからソニーに移管されました。
ソニーはそれまでもサイバーショットシリーズを展開してデジカメは販売していましたが、これにより、一眼レフを製造、販売するメーカーになりました。
デジタルが主流になり、元々カメラメーカーではなかったメーカーもデジカメの製造、販売に加わってきましたが(ソニー以外にもパナソニック、カシオ、サンヨーなどが思い浮かびます。)、一眼レフの分野に参入するには、クイックリターンミラーの構造など、フィルム時代から引き継がれた技術が必要であったため、新たな参入は敷居が高ったのです(後年パナソニックもレンズ交換式一眼で参入してきますが、これはミラーレスを採用した(クイックリターンミラーを使う必要がなくなりました。)から可能になったことです。)。ソニーはαのノウハウをすべて継承したので、一眼レフの分野に参入ができました。
さて、ソニーαは発足後、コニカミノルタ時代の導入機(αSweet DIGITAL)を改良したα100を2006年9月に登場させ(外観はソニーらしさが出され、それまでのイメージとは一線を画すものとなりました。)、2007年11月についに、α7デジタルの後継機であるソニーα700(APS-Cサイズ、1224万画素)が登場しました。
これは、α7デジタルまでのαの基本的な操作性は維持しつつ、性能はブラッシュアップされ、最新の機能も付加されました。
α700はデモ機を借りて何回か撮影しましたが、完成度が高く、α7デジタルから大きく進化したことを実感しました。使うと欲しくなってしまいますが、α7デジタルを購入してからまだ2年強しか経っておらず、買い替えも厳しい状況だったので、静観することになりました。
そうこうするうちに、αもフルサイズ(35mmのフィルムサイズ)の登場の期待が高まってきました。ディックもそうですが、フィルム時代から写真をやっている者にとってフルサイズに慣れていることも大きな理由ですが、フィルム時代のαのレンズをそのままの焦点距離で使えることがフルサイズを期待する別の大きな要素でした。
話が少し横道にそれますが、今一眼デジタルのセンサーは①フルサイズ(36mm×24mm)、②APS-Cサイズ(23.6mm×15.8mm)、③フォーサーズサイズ(17.3mm×13.8mm)の3つが主力です(さらに大きなセンサーを採用しているカメラ(いわゆる中版一眼)を出しているメーカー(ペンタックス、富士フィルム)もあります。)。
ニコン、キャノン、ソニー、ペンタックスは①と②を、富士フィルムは②を、パナソニックとオリンパスは③をラインナップしています。センサーの大きさだけをみると随分違います(ちなみに①を基準にすると、②は43%、③は26%の面積となります。)。センサーは、大きいほど高画質にしやすいという利点はありますが、私たちが通常に使う分には、どれも遜色ない範囲といえるのではないでしょうか。センサーが大きくなるとボディやレンズは大きくなる傾向にあるし、デジタルは画像処理も大きな要素となるので、どのセンサーのカメラ(メーカー)を選ぶかはトータルで決めることになるでしょう(特に、①と②を併売しているメーカーはどちらを選ぶか悩ましいことになります。)。
話を戻します。2008年10月についに、フルサイズ一眼レフα900が登場しました。このカメラの特徴はペンタ部(中央のファインダーに画像を導くプリズムが入っている部分)の三角形です。ニコンFの再来かと言われました。全体的に大柄なカメラですが、いかにも一眼レフという伝統的な匂いも感じられるスタイリングに、ディックもやられてしまいました。
ただ、値段もそれなりだったので、こなれるのを待って、2009年11月にお迎えしました。9がつくαはシリーズ頂点のカメラですが、ディックにはこれまで縁はありませんでした。ついに9のつくカメラとお付き合いすることになりました。
フルサイズのセンサーはやはりしっくりときました。少し重いですが、持ち運びに支障になる程ではありません。主役として活躍してくれました。
ただ、少々不満だったのは、AFの測距点がファインダーの中央寄りに集まっていること(ニコンやキャノンのフルサイズのカメラと比べるとその傾向にありました。)、動体へのAFの追随が弱いことで、AFだとうまく被写体をとらえてくれないシーンもありました。あと、高感度だとノイズが出やすく、ISO800が限界(できれば400くらいにとどめておきたい)といったところでしょうか。あとこれに関連して、Dレンジオプティマイザー(明暗さが激しい被写体で、白とび、黒つぶれを防いでくれる機能。とても優れものです。)の許容度が狭い(感度を低くしないと暗いところの画像にノイズが発生する。)というのもありました(過渡期だったのでしょう。今の一眼αでは解消されています。)。
全般的にはとても満足度が高いカメラで、しかも持つ喜びも感じるものでした。
2011年2月にはα700も中古で購入し、ソニーα2台体制となりました。これにより、α7デジタルはほぼ引退状態となりました
2014年4月に一眼ミラーレスのα7を導入するまでは、この体制が続きました。
α900はカメラ自体は魅力的なカメラですが、最近ほどんど出番がありません。
ディックの一眼での主力機はミラーレスのα7Ⅱ、α7s、α6500に移行しています。
α900はまだ使えるので、使ってもらえる人への売却を考えています(その方がカメラも喜ぶと思います。)。

α900 これぞ一眼レフといった形です
レンズはミノルタ85mm f1.4G 名玉です!

背面

ミノルタ85mm f1.4G このレンズを見ていると引き込まれる感じがします
ソニーはそれまでもサイバーショットシリーズを展開してデジカメは販売していましたが、これにより、一眼レフを製造、販売するメーカーになりました。
デジタルが主流になり、元々カメラメーカーではなかったメーカーもデジカメの製造、販売に加わってきましたが(ソニー以外にもパナソニック、カシオ、サンヨーなどが思い浮かびます。)、一眼レフの分野に参入するには、クイックリターンミラーの構造など、フィルム時代から引き継がれた技術が必要であったため、新たな参入は敷居が高ったのです(後年パナソニックもレンズ交換式一眼で参入してきますが、これはミラーレスを採用した(クイックリターンミラーを使う必要がなくなりました。)から可能になったことです。)。ソニーはαのノウハウをすべて継承したので、一眼レフの分野に参入ができました。
さて、ソニーαは発足後、コニカミノルタ時代の導入機(αSweet DIGITAL)を改良したα100を2006年9月に登場させ(外観はソニーらしさが出され、それまでのイメージとは一線を画すものとなりました。)、2007年11月についに、α7デジタルの後継機であるソニーα700(APS-Cサイズ、1224万画素)が登場しました。
これは、α7デジタルまでのαの基本的な操作性は維持しつつ、性能はブラッシュアップされ、最新の機能も付加されました。
α700はデモ機を借りて何回か撮影しましたが、完成度が高く、α7デジタルから大きく進化したことを実感しました。使うと欲しくなってしまいますが、α7デジタルを購入してからまだ2年強しか経っておらず、買い替えも厳しい状況だったので、静観することになりました。
そうこうするうちに、αもフルサイズ(35mmのフィルムサイズ)の登場の期待が高まってきました。ディックもそうですが、フィルム時代から写真をやっている者にとってフルサイズに慣れていることも大きな理由ですが、フィルム時代のαのレンズをそのままの焦点距離で使えることがフルサイズを期待する別の大きな要素でした。
話が少し横道にそれますが、今一眼デジタルのセンサーは①フルサイズ(36mm×24mm)、②APS-Cサイズ(23.6mm×15.8mm)、③フォーサーズサイズ(17.3mm×13.8mm)の3つが主力です(さらに大きなセンサーを採用しているカメラ(いわゆる中版一眼)を出しているメーカー(ペンタックス、富士フィルム)もあります。)。
ニコン、キャノン、ソニー、ペンタックスは①と②を、富士フィルムは②を、パナソニックとオリンパスは③をラインナップしています。センサーの大きさだけをみると随分違います(ちなみに①を基準にすると、②は43%、③は26%の面積となります。)。センサーは、大きいほど高画質にしやすいという利点はありますが、私たちが通常に使う分には、どれも遜色ない範囲といえるのではないでしょうか。センサーが大きくなるとボディやレンズは大きくなる傾向にあるし、デジタルは画像処理も大きな要素となるので、どのセンサーのカメラ(メーカー)を選ぶかはトータルで決めることになるでしょう(特に、①と②を併売しているメーカーはどちらを選ぶか悩ましいことになります。)。
話を戻します。2008年10月についに、フルサイズ一眼レフα900が登場しました。このカメラの特徴はペンタ部(中央のファインダーに画像を導くプリズムが入っている部分)の三角形です。ニコンFの再来かと言われました。全体的に大柄なカメラですが、いかにも一眼レフという伝統的な匂いも感じられるスタイリングに、ディックもやられてしまいました。
ただ、値段もそれなりだったので、こなれるのを待って、2009年11月にお迎えしました。9がつくαはシリーズ頂点のカメラですが、ディックにはこれまで縁はありませんでした。ついに9のつくカメラとお付き合いすることになりました。
フルサイズのセンサーはやはりしっくりときました。少し重いですが、持ち運びに支障になる程ではありません。主役として活躍してくれました。
ただ、少々不満だったのは、AFの測距点がファインダーの中央寄りに集まっていること(ニコンやキャノンのフルサイズのカメラと比べるとその傾向にありました。)、動体へのAFの追随が弱いことで、AFだとうまく被写体をとらえてくれないシーンもありました。あと、高感度だとノイズが出やすく、ISO800が限界(できれば400くらいにとどめておきたい)といったところでしょうか。あとこれに関連して、Dレンジオプティマイザー(明暗さが激しい被写体で、白とび、黒つぶれを防いでくれる機能。とても優れものです。)の許容度が狭い(感度を低くしないと暗いところの画像にノイズが発生する。)というのもありました(過渡期だったのでしょう。今の一眼αでは解消されています。)。
全般的にはとても満足度が高いカメラで、しかも持つ喜びも感じるものでした。
2011年2月にはα700も中古で購入し、ソニーα2台体制となりました。これにより、α7デジタルはほぼ引退状態となりました
2014年4月に一眼ミラーレスのα7を導入するまでは、この体制が続きました。
α900はカメラ自体は魅力的なカメラですが、最近ほどんど出番がありません。
ディックの一眼での主力機はミラーレスのα7Ⅱ、α7s、α6500に移行しています。
α900はまだ使えるので、使ってもらえる人への売却を考えています(その方がカメラも喜ぶと思います。)。

α900 これぞ一眼レフといった形です
レンズはミノルタ85mm f1.4G 名玉です!

背面

ミノルタ85mm f1.4G このレンズを見ていると引き込まれる感じがします













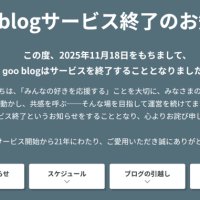












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます