A社商品の正規価格を100%とする。
B社がA社の商品を購入する。その際A社商品を無料化する。つまり上記の正規価格を0%で売る(というより“あげる”)ことになる。
このままではA社が丸損なので、A社はB社からA社商品価格100%分のB社商品をもらう。B社商品をもらうだけだと単なる物々交換になる。
A社がB社の商品を欲しければこれで問題はないのだけど、今回はC社がB社の商品を欲しがっていると考える。ついでにB社はC社の商品を欲しがっていることにしちゃう。
A社はB社の商品を、B社に売り込んだA社の商品価格分所持している。A社がC社にB社の商品を渡して、C社の商品をA社がもらい、それをB社に売ったらどうなるだろう。
なんとなくイメージが掴みにくいので簡潔に書いてみる。
AがBにA'(A社商品-以下同)を売る BはAにB'で払う(物々交換)
AはB'をCに売る CはAにC'で払う(物々交換)
AはC'をBに売る(貨幣交換)
つまりAはA'を売ってB'→C'と手に入れ、C'をBに売りお金を得たことになる。まぁもっと簡単に書くとわらしべ長者リアル版かな?(笑)
わらしべ長者は最終的に巨万の富を手にするのだけど、今回のモデルでは得た利益をどんどん回すイメージを持って欲しい。AはC'を更にDやEやF…に売りD'E'F'…を手に入れる、という考えだ。基本的に等価交換になる形で回していく。
しかし回し続けるだけではAの利益は一向に出てこない。それでは困る。C'をBに貨幣で売って初めて利益が出るのだ。現状の売掛買掛みたいなもんだよね。
ではこうしたらどうだろうか。AはA'を売るのだけど、決済はB'の割引券という形でBから受け取ることにする。割引率を簡単に10%としてみる。
【A'の値段が10万円だとする B'の値段は5万円だとする】
A'をBに売るのだから、等価交換のケースならB'を2個と交換することになる
それを、B'の10%割引券(5000円割引相当)20枚で交換する
AはA'を売ってB'の5000円割引券20枚を手に入れた。ここでAはCにもDにもA'を売る。その際に価格10万円ではなく、(10万円-B'の10%割引券)で売ったらどうだろう。ようするにCとDは、A'と更にB'の5000円割引券を10万円で買えたことになる。CとDにしてみれば本来はA'だけで10万円するところを、B'の割引券までもらえることになる。
CとDがB'の権利を行使したらどうなるだろうか。BはB'を2個それぞれ45000円で、CとDに売ることになる。つまりBはA'を無料で手に入れ、更にB'を正規価格の9割価格で20個売る機会を手にしたことになる。
もう少し読みやすく書いてみる。
ともきさんは自作チョコレートを100円で、たかしさんに売りました。
たかしさんは100円玉ではなく、たかしさんが販売している50円のパンの10%割引券20枚で支払いました。
ともきさんはたかしさんから受け取ったパンの割引券とチョコレートをセットにして100円でりえさんに売りました。
りえさんは目的のチョコレートを手にして、かつたかしさんの作ったパンを10%割り引いて買える機会を得ました。
同様にともきさんは残りの割引券を使って20個のチョコレートを販売しました。
割引券を得た、ともきさんのチョコレートを買ったお客さんのうち半数10人(適当な数字)がたかしさんのパンを買いに行きました。
たかしさんはともきさんのチョコレートを買うことで自分の目的を達成した上に、さらに自社のパンを10%割引とはいえ10個、普段より多く売ることが出来ました。次回もチョコレートを買う時はともきさんのところで買おうと思いました。
実際にもっとマクロな展開がなされれば、ほぼ無限の繋がりを作ることも出来る。自社の商品を売るにあたって、売り込む相手の商品の割引券で決済し、相手の商品の割引券を何らかの形で自社の商品を売る特典として位置づけ、自社のプレミアムと取引先会社の宣伝・売上貢献に繋げる、という構想だ。
単純な話コラボレートだね。でも共同開発ではなく、既存製品の、悪い書き方をするなら抱き合わせ販売になる(笑)でも誰も損はしていないよね。ともきさんは自社商品にプレミアム感を出せるし、たかしさんは自社の宣伝をしてもらった上にチョコレートを無料で手に入れられた。お客さんはチョコレートもパンも割安で買えるのだ。
問題はいろいろあると思う。例えばチョコレートを買いに来たお客さんがパンを欲しがっていない場合、パンの割引券はチョコレートのプレミアムではない。プレミアム感はあるかもしれないけど。客がパンの割引券を得ても、実際にパンを買ってくれなければチョコレートとパンのコラボレーションは失敗と言える。
でも客は選択肢を絞り易くなるのではないかと思うんだよね。もしパンを買うならたかし印のパンにしようかな?と考えると思う。もちろん味がとんでもなく悪ければ選択肢から除外されるだろうけど(笑)さらに割引券が行使されなくても、たかしさんは直接的には損していない。ともきさんがちょっと損かもしれないけど。まぁ損も得もみんなで分けあいましょうってことになるかな?
もうちょっと進化するなら、こうした割引券同士を交換できる場を作るともっと良い。
このやり方は商店街で活かせるはずだ。
商店街は個人商店の集合体だ。各商品は各商店・個人で仕入れる。しかし個人で仕入れるにも、同じ商品を仕入れるなら大手が大量に仕入れたほうが安くなるのが現状だ。個人商店はそうした部分で大手と戦いようもなく、また戦ってはいけない。これは鉄則だ。資本力で戦ったら負けるのは当たり前なのだ。個人商店が戦うには何らかの、大手が手を出しにくい戦術を取ることが大事だろう。
ところが大手が手を出しにくい戦術は、イコール大手のマーケティングから漏れる戦術で、実際のところそんなに多いものではない。大手という指標を頼らず、独自のマーケティングを展開し、さらにある程度の人に認知してもらう、そんな手段は少ない(思い浮かばない)。個人商店が、大手の目に止まらない、それでいて利益を出す程度売れ、更に宣伝をしなくてもそれなりに広まるような状況になるのは、かなり天文学的低確率じゃなかろうか。そうした状況になっても大手にマーケティングされれば、結局どれも資本力で負けちゃうし。最初は良くてもすぐに大手に負けるというのは良くある話だ。
消費者もこれだけ選択肢を増やされてしまった市場で、選択はもはや消極的選択だ。積極的選択もあるに違いないが、それは大手のマーケティングに引っかかるだろう。資本力で負ける。
消費者はどうやったら損をしない買い物が出来るか考える。大手ブランドを選ぶのが無難なのだ。実際は、大手ブランドが特別安全や安心に気を配ったり、消費者を考えたラインナップやコンテンツを用意しているわけではないのは、放射能対応を見ても分かる。しかし消費者は騙される。ある種の安心感・手頃感からだろう。
安全と安心は別物だ、と放射能を回避したい消費者は言う。実際に、コメから放射性物質が検出されなくても買わない、とする消費者は殊の外多い。それは不検出に対する疑念であり、ゼロと言われても東北で採れたのだから安全かどうか分からない、というものだろう。
これは正しい。なぜなら安全とは100%を保証しうる概念ではないからだ。他人が100%安全だと言ったものを信じるかどうかは、安心感の問題、つまり主観の問題だ。他人の提示する安全が客観だとすれば、主観と客観がずれるのは当然なのだ。ずれなければ、つまりカップリングに成功していれば、商品は売れるのだ。東北の商品であっても売れるだろう。
話を戻して、では個人商店がどうやってカップリングに成功するか、が問題になってくる。
大手が売るものは大量仕入れで仕入単価を安くするのが基本。個人商店はそれが出来ない。大手が見落としたもので、かつ消費者が好み、かつ売上になるくらい人が買う、それはかなりのラッキーパンチ・ミラクルだ。持続可能な商売に繋がらなければコンテンツ開発力では絶対に疲弊する。
安全と安心のカップリング(言い換えれば需要と供給のマッチング)をしようにも、カップリングしやすい商品は大手に値段で負け、カップリングしにくい商品を探すにも限界がある。
ここは一つ商店街単位で結託するべきではないだろうか?というのが、最初に書いた内容なのだ。資本力で戦ったら負け戦であるという鉄則にあえて挑む。挑み方次第で戦えるのではないか?という提案だ。安全と安心のカップリングでさえ、例えば放射能検査などでは大手に勝てるわけがないし、結局大手と個人が対等に戦うには限度があるだろうという視点だ。
噛み砕くと、仕入れ価格で割安にするのが大手であるなら、利益の一部を他店商品の割引に充てて、そこで発生した利益の一部を更に他店商品の割引に充てて、その連続性で大手の仕入れ価格を打破しようではないか、という発想なのだ。カップリングに費やした経費も商店街全体で受け止めれば良い。
そこにこっそりボクの会社が入ったらいいんではないかな?と思っているんです(笑)
まだ構想段階だけど、これを少しずつ営業のみんなと話し合っていき、どこかの商店街でモデリングしていけないかな、と思っているのであります。
ついでに書くと、これは実は地域通貨を模擬的に表したものなんです。その商店街でしか使えない通貨を売上の一部で発行することにより、その商店街でしか使えない通貨だからこそ、そこの商店街のリピーターになる、ということの前段階なんだよね。
最終的に商店街の中だけでやり取りが可能な通貨になってしまえば、小さな政府も作れるかもしれない。地方と都市部の金銭的価値の違いも地域通貨を介して埋められるかもしれない。これを道州制などと併せていけば、今後の日本にかなり見合ったスタイルが作れるかもしれない。そう思うのです。
大きな社会において、別々の地域の貨幣価値が同じだと不都合だ。どうしても大都市で稼いだほうが稼げることになる。為替ギャップが出来てはじめて経済はコントロールされる。ユーロが失敗したのはそういうことだろう。
これは逆から見ても真だと思う。つまり円も地域ごとで価値が変わって良いと思うんだよね。地方で稼いだ貨幣を都市で使うと、都市で稼いだ貨幣を地方で使うより得になってはじめて、地方の弱さ(不便さとか)がカバー出来るんだと思う。そのためには地域通貨を導入して、介在した場所に円を置くことで地域の活性化に繋がるんじゃなかろうかと妄想するんです。
ようするに大手の資本と個人商店の資本の貨幣価値差分を埋めることが目的なんだよね。大手は是非国外で稼いで欲しいのです。それが大手の特権だし、縮小する国内への社会貢献でもあると思うのです。
こうした動きに期待!まじ期待!自分で出来るかしら。頑張る!まずはうちの営業さんがたを口説かねば(笑)
拍手ボタン
B社がA社の商品を購入する。その際A社商品を無料化する。つまり上記の正規価格を0%で売る(というより“あげる”)ことになる。
このままではA社が丸損なので、A社はB社からA社商品価格100%分のB社商品をもらう。B社商品をもらうだけだと単なる物々交換になる。
A社がB社の商品を欲しければこれで問題はないのだけど、今回はC社がB社の商品を欲しがっていると考える。ついでにB社はC社の商品を欲しがっていることにしちゃう。
A社はB社の商品を、B社に売り込んだA社の商品価格分所持している。A社がC社にB社の商品を渡して、C社の商品をA社がもらい、それをB社に売ったらどうなるだろう。
なんとなくイメージが掴みにくいので簡潔に書いてみる。
AがBにA'(A社商品-以下同)を売る BはAにB'で払う(物々交換)
AはB'をCに売る CはAにC'で払う(物々交換)
AはC'をBに売る(貨幣交換)
つまりAはA'を売ってB'→C'と手に入れ、C'をBに売りお金を得たことになる。まぁもっと簡単に書くとわらしべ長者リアル版かな?(笑)
わらしべ長者は最終的に巨万の富を手にするのだけど、今回のモデルでは得た利益をどんどん回すイメージを持って欲しい。AはC'を更にDやEやF…に売りD'E'F'…を手に入れる、という考えだ。基本的に等価交換になる形で回していく。
しかし回し続けるだけではAの利益は一向に出てこない。それでは困る。C'をBに貨幣で売って初めて利益が出るのだ。現状の売掛買掛みたいなもんだよね。
ではこうしたらどうだろうか。AはA'を売るのだけど、決済はB'の割引券という形でBから受け取ることにする。割引率を簡単に10%としてみる。
【A'の値段が10万円だとする B'の値段は5万円だとする】
A'をBに売るのだから、等価交換のケースならB'を2個と交換することになる
それを、B'の10%割引券(5000円割引相当)20枚で交換する
AはA'を売ってB'の5000円割引券20枚を手に入れた。ここでAはCにもDにもA'を売る。その際に価格10万円ではなく、(10万円-B'の10%割引券)で売ったらどうだろう。ようするにCとDは、A'と更にB'の5000円割引券を10万円で買えたことになる。CとDにしてみれば本来はA'だけで10万円するところを、B'の割引券までもらえることになる。
CとDがB'の権利を行使したらどうなるだろうか。BはB'を2個それぞれ45000円で、CとDに売ることになる。つまりBはA'を無料で手に入れ、更にB'を正規価格の9割価格で20個売る機会を手にしたことになる。
もう少し読みやすく書いてみる。
ともきさんは自作チョコレートを100円で、たかしさんに売りました。
たかしさんは100円玉ではなく、たかしさんが販売している50円のパンの10%割引券20枚で支払いました。
ともきさんはたかしさんから受け取ったパンの割引券とチョコレートをセットにして100円でりえさんに売りました。
りえさんは目的のチョコレートを手にして、かつたかしさんの作ったパンを10%割り引いて買える機会を得ました。
同様にともきさんは残りの割引券を使って20個のチョコレートを販売しました。
割引券を得た、ともきさんのチョコレートを買ったお客さんのうち半数10人(適当な数字)がたかしさんのパンを買いに行きました。
たかしさんはともきさんのチョコレートを買うことで自分の目的を達成した上に、さらに自社のパンを10%割引とはいえ10個、普段より多く売ることが出来ました。次回もチョコレートを買う時はともきさんのところで買おうと思いました。
実際にもっとマクロな展開がなされれば、ほぼ無限の繋がりを作ることも出来る。自社の商品を売るにあたって、売り込む相手の商品の割引券で決済し、相手の商品の割引券を何らかの形で自社の商品を売る特典として位置づけ、自社のプレミアムと取引先会社の宣伝・売上貢献に繋げる、という構想だ。
単純な話コラボレートだね。でも共同開発ではなく、既存製品の、悪い書き方をするなら抱き合わせ販売になる(笑)でも誰も損はしていないよね。ともきさんは自社商品にプレミアム感を出せるし、たかしさんは自社の宣伝をしてもらった上にチョコレートを無料で手に入れられた。お客さんはチョコレートもパンも割安で買えるのだ。
問題はいろいろあると思う。例えばチョコレートを買いに来たお客さんがパンを欲しがっていない場合、パンの割引券はチョコレートのプレミアムではない。プレミアム感はあるかもしれないけど。客がパンの割引券を得ても、実際にパンを買ってくれなければチョコレートとパンのコラボレーションは失敗と言える。
でも客は選択肢を絞り易くなるのではないかと思うんだよね。もしパンを買うならたかし印のパンにしようかな?と考えると思う。もちろん味がとんでもなく悪ければ選択肢から除外されるだろうけど(笑)さらに割引券が行使されなくても、たかしさんは直接的には損していない。ともきさんがちょっと損かもしれないけど。まぁ損も得もみんなで分けあいましょうってことになるかな?
もうちょっと進化するなら、こうした割引券同士を交換できる場を作るともっと良い。
このやり方は商店街で活かせるはずだ。
商店街は個人商店の集合体だ。各商品は各商店・個人で仕入れる。しかし個人で仕入れるにも、同じ商品を仕入れるなら大手が大量に仕入れたほうが安くなるのが現状だ。個人商店はそうした部分で大手と戦いようもなく、また戦ってはいけない。これは鉄則だ。資本力で戦ったら負けるのは当たり前なのだ。個人商店が戦うには何らかの、大手が手を出しにくい戦術を取ることが大事だろう。
ところが大手が手を出しにくい戦術は、イコール大手のマーケティングから漏れる戦術で、実際のところそんなに多いものではない。大手という指標を頼らず、独自のマーケティングを展開し、さらにある程度の人に認知してもらう、そんな手段は少ない(思い浮かばない)。個人商店が、大手の目に止まらない、それでいて利益を出す程度売れ、更に宣伝をしなくてもそれなりに広まるような状況になるのは、かなり天文学的低確率じゃなかろうか。そうした状況になっても大手にマーケティングされれば、結局どれも資本力で負けちゃうし。最初は良くてもすぐに大手に負けるというのは良くある話だ。
消費者もこれだけ選択肢を増やされてしまった市場で、選択はもはや消極的選択だ。積極的選択もあるに違いないが、それは大手のマーケティングに引っかかるだろう。資本力で負ける。
消費者はどうやったら損をしない買い物が出来るか考える。大手ブランドを選ぶのが無難なのだ。実際は、大手ブランドが特別安全や安心に気を配ったり、消費者を考えたラインナップやコンテンツを用意しているわけではないのは、放射能対応を見ても分かる。しかし消費者は騙される。ある種の安心感・手頃感からだろう。
安全と安心は別物だ、と放射能を回避したい消費者は言う。実際に、コメから放射性物質が検出されなくても買わない、とする消費者は殊の外多い。それは不検出に対する疑念であり、ゼロと言われても東北で採れたのだから安全かどうか分からない、というものだろう。
これは正しい。なぜなら安全とは100%を保証しうる概念ではないからだ。他人が100%安全だと言ったものを信じるかどうかは、安心感の問題、つまり主観の問題だ。他人の提示する安全が客観だとすれば、主観と客観がずれるのは当然なのだ。ずれなければ、つまりカップリングに成功していれば、商品は売れるのだ。東北の商品であっても売れるだろう。
話を戻して、では個人商店がどうやってカップリングに成功するか、が問題になってくる。
大手が売るものは大量仕入れで仕入単価を安くするのが基本。個人商店はそれが出来ない。大手が見落としたもので、かつ消費者が好み、かつ売上になるくらい人が買う、それはかなりのラッキーパンチ・ミラクルだ。持続可能な商売に繋がらなければコンテンツ開発力では絶対に疲弊する。
安全と安心のカップリング(言い換えれば需要と供給のマッチング)をしようにも、カップリングしやすい商品は大手に値段で負け、カップリングしにくい商品を探すにも限界がある。
ここは一つ商店街単位で結託するべきではないだろうか?というのが、最初に書いた内容なのだ。資本力で戦ったら負け戦であるという鉄則にあえて挑む。挑み方次第で戦えるのではないか?という提案だ。安全と安心のカップリングでさえ、例えば放射能検査などでは大手に勝てるわけがないし、結局大手と個人が対等に戦うには限度があるだろうという視点だ。
噛み砕くと、仕入れ価格で割安にするのが大手であるなら、利益の一部を他店商品の割引に充てて、そこで発生した利益の一部を更に他店商品の割引に充てて、その連続性で大手の仕入れ価格を打破しようではないか、という発想なのだ。カップリングに費やした経費も商店街全体で受け止めれば良い。
そこにこっそりボクの会社が入ったらいいんではないかな?と思っているんです(笑)
まだ構想段階だけど、これを少しずつ営業のみんなと話し合っていき、どこかの商店街でモデリングしていけないかな、と思っているのであります。
ついでに書くと、これは実は地域通貨を模擬的に表したものなんです。その商店街でしか使えない通貨を売上の一部で発行することにより、その商店街でしか使えない通貨だからこそ、そこの商店街のリピーターになる、ということの前段階なんだよね。
最終的に商店街の中だけでやり取りが可能な通貨になってしまえば、小さな政府も作れるかもしれない。地方と都市部の金銭的価値の違いも地域通貨を介して埋められるかもしれない。これを道州制などと併せていけば、今後の日本にかなり見合ったスタイルが作れるかもしれない。そう思うのです。
大きな社会において、別々の地域の貨幣価値が同じだと不都合だ。どうしても大都市で稼いだほうが稼げることになる。為替ギャップが出来てはじめて経済はコントロールされる。ユーロが失敗したのはそういうことだろう。
これは逆から見ても真だと思う。つまり円も地域ごとで価値が変わって良いと思うんだよね。地方で稼いだ貨幣を都市で使うと、都市で稼いだ貨幣を地方で使うより得になってはじめて、地方の弱さ(不便さとか)がカバー出来るんだと思う。そのためには地域通貨を導入して、介在した場所に円を置くことで地域の活性化に繋がるんじゃなかろうかと妄想するんです。
ようするに大手の資本と個人商店の資本の貨幣価値差分を埋めることが目的なんだよね。大手は是非国外で稼いで欲しいのです。それが大手の特権だし、縮小する国内への社会貢献でもあると思うのです。
こうした動きに期待!まじ期待!自分で出来るかしら。頑張る!まずはうちの営業さんがたを口説かねば(笑)
拍手ボタン










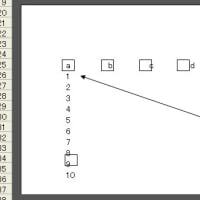
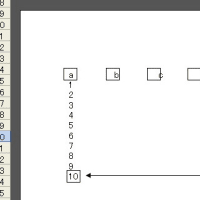
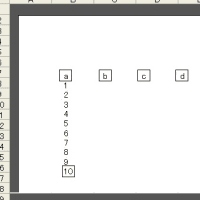





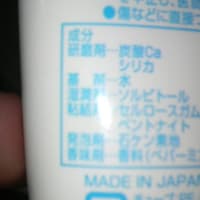
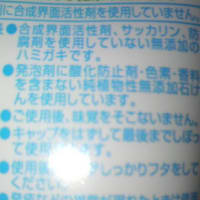
解りやすい例えですね~
釣り行きてぇ。