Esther & Abi Ofarim - Gone Home
アルティッチョの夜 小山田壮平
【#NOWAR0305 #NoWarInUkraine】2022.3.5 04反戦声明と演奏 坂口恭平さん
赤い花 白い花
Rufus Wainwright - Dinner At Eight (solo acoustic)
(ちんちくりんNo,77)
裕子に「結論」を伝えるその日まで、あと何日もなかった。僕はろくに眠ることができない日々を送っていて、次第に思考力が落ちてきていた。頭の中は靄にかかったようなはっきりしない状態で、自分が何処にどういう目的で進んでいるのかもはや分からなかった。そういう状況下、いつしか僕の思考は小さな悲鳴をあげるようになり、僕はたまらずベッドに倒れ込むようにして横たわったのだった。目を静かに瞑った。意識が途絶えた。
夢の中の僕は小説を書いていた。書いて書いて書きまくっていた。一心不乱に。一体どのような物語を書いているのだろうと見ていたら、突然引き寄せられるような感覚が走って、僕は「夢の中の僕」と一体になった。気づいたら机の前に座している僕。机の上には原稿が置かれ、息もつかずにペンを走らせ、文字を書き込んでいた。かほる?そうか……かほると僕……あの、あの頃の、物語……。そこまで「僕」の脳は認識した。が、その後は言葉の洪水が頭の中を巡り、僕はその中で適切な言葉を選び取り、器用に組み上げて、それを殆ど同時かと思われる程に頭から吐き出し現実の文章として目の前の原稿に書き込んだ。恐るべき速度で書いた。疲れない。それどころか楽しかった。こんな単純な作業。「ただ、目の前に原稿があるから書くんだよ」。何処かでそんな声を聴いた気がした。僕の心は徐々に軽くなっていった。
僕はまる一日眠っていたのだと思う。目を覚ますやいなや目の前に原稿がないことに気が付いた僕はすかさず起き上がり、仕事場の机に向かった。そして原稿を纏めて引き出しから取り出すと机の上に置き、椅子に座ってペンをとって「続きを書かねば」と思いつくがままに物語を紡いでいった。しばらくしてあれが夢であったことに気づいた僕は、一瞬馬鹿な自分を責めようとしたが、その馬鹿な自分がどうしょうもなく愛しくなり、思わず笑ってしまった。笑いながら「書けばいいんだよ、書けば」、僕はやっとトンネルを抜けたことを知り、異様に晴れ晴れした気分になっている自分を確認したのだった。
「多分、俺はかほるの影を消し去ることは出来ないと思う。君と一緒になったらなおさらのこと」
僕が裕子を彼女の自宅近くの公園に呼び出したのは、最初のプロポーズからひと月も経ってなかったのではないかと思う。夜のことだった。特段何があるというわけでもない、広いとも狭いとも言えないただ芝生が目の前に広がっているだけの公園。僕らは公園の端っこ、入り口近くにあったベンチに腰掛けて夜空を見上げていた。街灯のあかりはあったが、それほどの明るさはなかった。
「どういうこと」
一緒に夜空を見上げていた裕子は先に目線を降ろして右隣の僕の方に顔を向けた。僕はおもむろに夜空から目を離し、一度目を瞑ってから目を開いて左隣の裕子を見た。
「どんなに頑張ってもかほるの影を消すことが出来ないことが分かった。だからいっそのこと背負おうと決心した。背負いながら君ととも、歩んでいきたい。それと……」
「それと?」
「俺とかほるの物語を小説として書きたいと思う。彼女は消えない。消えないと思うけれど、そうして言葉として目に見えるようにすることによって、彼女とのことはただ単なる懐かしい過去の思い出になっていくと思うんだ。だから、そんなことしか出来ない俺だけど、結婚してくれないだろうか。君と、未来へ一緒に歩んでゆきたい」
裕子は目を伏せた。しばらく沈黙の時が流れた。どのくらいの時間が流れたのかよく憶えてはいないが、突然口を開いた彼女が言った言葉は僕に喜びと大いなる驚きを与えてくれた。
「ばかねえ、そんなの初めからイエスに決まってるじゃない。それに、ごめんなさい。私、怖くて言えなかったんだけど、子供ができたようなの。勿論あなたの子」
裕子は涙を流し、僕は慌てふためいてジーンズのポケットからハンカチを出そうとしたが上手く出せなくて、結局右手の親指の腹で彼女の流れる涙を必死に拭い、それから涙の跡が残る彼女の左の頬にキスをした。
―君は母親、俺は父親。君は俺の妻になってくれる。喜びが倍だ。ありがとう。
アルティッチョの夜 小山田壮平
【#NOWAR0305 #NoWarInUkraine】2022.3.5 04反戦声明と演奏 坂口恭平さん
赤い花 白い花
Rufus Wainwright - Dinner At Eight (solo acoustic)
(ちんちくりんNo,77)
裕子に「結論」を伝えるその日まで、あと何日もなかった。僕はろくに眠ることができない日々を送っていて、次第に思考力が落ちてきていた。頭の中は靄にかかったようなはっきりしない状態で、自分が何処にどういう目的で進んでいるのかもはや分からなかった。そういう状況下、いつしか僕の思考は小さな悲鳴をあげるようになり、僕はたまらずベッドに倒れ込むようにして横たわったのだった。目を静かに瞑った。意識が途絶えた。
夢の中の僕は小説を書いていた。書いて書いて書きまくっていた。一心不乱に。一体どのような物語を書いているのだろうと見ていたら、突然引き寄せられるような感覚が走って、僕は「夢の中の僕」と一体になった。気づいたら机の前に座している僕。机の上には原稿が置かれ、息もつかずにペンを走らせ、文字を書き込んでいた。かほる?そうか……かほると僕……あの、あの頃の、物語……。そこまで「僕」の脳は認識した。が、その後は言葉の洪水が頭の中を巡り、僕はその中で適切な言葉を選び取り、器用に組み上げて、それを殆ど同時かと思われる程に頭から吐き出し現実の文章として目の前の原稿に書き込んだ。恐るべき速度で書いた。疲れない。それどころか楽しかった。こんな単純な作業。「ただ、目の前に原稿があるから書くんだよ」。何処かでそんな声を聴いた気がした。僕の心は徐々に軽くなっていった。
僕はまる一日眠っていたのだと思う。目を覚ますやいなや目の前に原稿がないことに気が付いた僕はすかさず起き上がり、仕事場の机に向かった。そして原稿を纏めて引き出しから取り出すと机の上に置き、椅子に座ってペンをとって「続きを書かねば」と思いつくがままに物語を紡いでいった。しばらくしてあれが夢であったことに気づいた僕は、一瞬馬鹿な自分を責めようとしたが、その馬鹿な自分がどうしょうもなく愛しくなり、思わず笑ってしまった。笑いながら「書けばいいんだよ、書けば」、僕はやっとトンネルを抜けたことを知り、異様に晴れ晴れした気分になっている自分を確認したのだった。
「多分、俺はかほるの影を消し去ることは出来ないと思う。君と一緒になったらなおさらのこと」
僕が裕子を彼女の自宅近くの公園に呼び出したのは、最初のプロポーズからひと月も経ってなかったのではないかと思う。夜のことだった。特段何があるというわけでもない、広いとも狭いとも言えないただ芝生が目の前に広がっているだけの公園。僕らは公園の端っこ、入り口近くにあったベンチに腰掛けて夜空を見上げていた。街灯のあかりはあったが、それほどの明るさはなかった。
「どういうこと」
一緒に夜空を見上げていた裕子は先に目線を降ろして右隣の僕の方に顔を向けた。僕はおもむろに夜空から目を離し、一度目を瞑ってから目を開いて左隣の裕子を見た。
「どんなに頑張ってもかほるの影を消すことが出来ないことが分かった。だからいっそのこと背負おうと決心した。背負いながら君ととも、歩んでいきたい。それと……」
「それと?」
「俺とかほるの物語を小説として書きたいと思う。彼女は消えない。消えないと思うけれど、そうして言葉として目に見えるようにすることによって、彼女とのことはただ単なる懐かしい過去の思い出になっていくと思うんだ。だから、そんなことしか出来ない俺だけど、結婚してくれないだろうか。君と、未来へ一緒に歩んでゆきたい」
裕子は目を伏せた。しばらく沈黙の時が流れた。どのくらいの時間が流れたのかよく憶えてはいないが、突然口を開いた彼女が言った言葉は僕に喜びと大いなる驚きを与えてくれた。
「ばかねえ、そんなの初めからイエスに決まってるじゃない。それに、ごめんなさい。私、怖くて言えなかったんだけど、子供ができたようなの。勿論あなたの子」
裕子は涙を流し、僕は慌てふためいてジーンズのポケットからハンカチを出そうとしたが上手く出せなくて、結局右手の親指の腹で彼女の流れる涙を必死に拭い、それから涙の跡が残る彼女の左の頬にキスをした。
―君は母親、俺は父親。君は俺の妻になってくれる。喜びが倍だ。ありがとう。

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


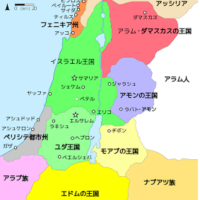






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます