先日、『「いじめ」と闘う親と子を応援する本』という本を紹介しました。2010年2月17日の記事
じゃあ、いじめって何? 何をもって「いじめ」と言うの?
という疑問が出てくるかもしれませんので、「いじめの定義」を紹介しておきます
この本の最初のほう(P9)に載っていまして、本では、この定義を前提として対応方法が書かれています。
-------引用ここから
●文部科学省によるいじめの定義
当該児童生徒が、一定の人間関係にある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を受けているものとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
●警察庁によるいじめの定義
いじめとは単独又は複数の特定人に対し、身体に物理的攻撃又は言動による脅かし、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えることをいう。
-------引用ここまで
人間関係のちょっとしたトラブルなのか、「いじめ」なのかということですが、私は、警視庁が定義している「反復継続」がポイントなのではないかと思っています。
なお、ネットで「いじめの定義」と検索しますと、例えば「伊丹市ウェブサイト」がヒットするのですが、ここには文科省が平成17年まで言っていた「いじめの定義」が紹介されています。(文科省のHPで直接確認しようとしたのですが、見つかりませんでした。。。)それによれば
-----引用ここから
<平成17年度調査分までのいじめの定義>
1.自分より弱いものに対して一方的に、
2.身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
3.相手が深刻な苦痛を感じているもの。
なお、起こった場所は学校の内外を問わないとする。
-----引用ここまで
だそうです。ここでも「継続的に加え」という言葉が出てきます。
ただ、現在は「継続的」ということが定義から外れているところを見ると、攻撃が継続しているかが問題なのではないのかもしれません。
例えば、表面的なトラブルは1回や2回だけだったとしても、被害を受けた側の精神的苦痛が「続いている」場合もあるからでは、と思います。つまり文科省の定義は「苦痛を感じたことを言う」ではなく、「苦痛を感じている(ing)ものとする」となっている点から、そう思われるのです。
*
先生や周囲の大人や友達は、「あれはいじめでは?」と疑いを持ったとしても、慎重に事実確認をする必要があるかもしれませんが、
けれど、
親としたら、何も「ゆっくり事実確認をする」必要などないのではと思います。自分の子の苦痛が些細なトラブルなのか「いじめ」によるものなのか、そんなことはさておき、先ずは苦痛を取り除くために相談にのってやるのが自然なわけで。
その上で、攻撃が継続して行われている、もしくは、本人の精神的苦痛が継続しているということが判明したら、学校や然るべき人・組織に相談すべきだと思います。迷わず
で
にほんブログ村
<script</script><noscript></noscript>
じゃあ、いじめって何? 何をもって「いじめ」と言うの?
という疑問が出てくるかもしれませんので、「いじめの定義」を紹介しておきます

この本の最初のほう(P9)に載っていまして、本では、この定義を前提として対応方法が書かれています。
-------引用ここから
●文部科学省によるいじめの定義
当該児童生徒が、一定の人間関係にある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を受けているものとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
●警察庁によるいじめの定義
いじめとは単独又は複数の特定人に対し、身体に物理的攻撃又は言動による脅かし、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えることをいう。
-------引用ここまで
人間関係のちょっとしたトラブルなのか、「いじめ」なのかということですが、私は、警視庁が定義している「反復継続」がポイントなのではないかと思っています。
なお、ネットで「いじめの定義」と検索しますと、例えば「伊丹市ウェブサイト」がヒットするのですが、ここには文科省が平成17年まで言っていた「いじめの定義」が紹介されています。(文科省のHPで直接確認しようとしたのですが、見つかりませんでした。。。)それによれば
-----引用ここから
<平成17年度調査分までのいじめの定義>
1.自分より弱いものに対して一方的に、
2.身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
3.相手が深刻な苦痛を感じているもの。
なお、起こった場所は学校の内外を問わないとする。
-----引用ここまで
だそうです。ここでも「継続的に加え」という言葉が出てきます。
ただ、現在は「継続的」ということが定義から外れているところを見ると、攻撃が継続しているかが問題なのではないのかもしれません。
例えば、表面的なトラブルは1回や2回だけだったとしても、被害を受けた側の精神的苦痛が「続いている」場合もあるからでは、と思います。つまり文科省の定義は「苦痛を感じたことを言う」ではなく、「苦痛を感じている(ing)ものとする」となっている点から、そう思われるのです。
*
先生や周囲の大人や友達は、「あれはいじめでは?」と疑いを持ったとしても、慎重に事実確認をする必要があるかもしれませんが、
けれど、
親としたら、何も「ゆっくり事実確認をする」必要などないのではと思います。自分の子の苦痛が些細なトラブルなのか「いじめ」によるものなのか、そんなことはさておき、先ずは苦痛を取り除くために相談にのってやるのが自然なわけで。
その上で、攻撃が継続して行われている、もしくは、本人の精神的苦痛が継続しているということが判明したら、学校や然るべき人・組織に相談すべきだと思います。迷わず

で
にほんブログ村
<script











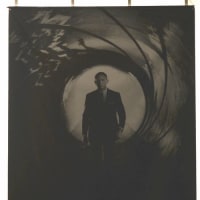








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます