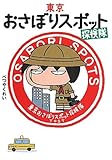この本を読んで、一番思ったこと。それは
「友情」や「親しさ」や「善意」などが、「社会の成熟」の邪魔になってやしないか?
ということです。よーく考えてみたい!
西洋哲学者の名前がいっぱい出てきますが、あまり素養の無い私には、少々難しい本でした。が、いろいろと目からウロコっていう話が出てきました。
例えば、「友人=親しい他人」という図式は、今では一般的だろうと思いますが、哲学者たちは、必ずしも「友情」に「親密さ」が必要だと考えていたわけではないということ。また、古代ギリシア語には現代日本の「友情」に正確に一致する言葉がなく、単に「好ましいもの」という意味の「フィリア」と遣っていたこと。
紀元前1世紀のローマ人「キケロ」という哲学者によれば、友人や友情は犯罪の温床だということです^^;; 親しい仲間が望むから、という理由で悪事に手を染めてしまう人間がいる=親しさは悪であると、そういう論を展開した人だそうです。
キケロの論を引きつつ、著者の清水さんは
「友情の命じる行動は、反社会的な性格を帯びる危険がある。これは、決して偶然ではない。友情には、もともとそのような性格が具わっているのであり、(中略) 仲間や同士としての連帯感や一体感は、友情の本質的な要素ではなく、友人との付き合いの副産物にすぎないのであり、しかも、連帯感や一体感のせいで、友人との付き合いが正常な軌道から逸脱してしまうことがあるのである」
と書かれています。最初は大胆な説だとは思いましたが、冷静になってみると「親しい人」が絡んでいるがために道を誤ってしまうということは、よくありそうな話です。
また、この本では、ジャン=ジャック・ルソーの友情論について長々と否定しているのですが、それは、清水さんによれば、
「自分と他人のあいだの境界をすべて取り払うような、いわば「裸の」付き合いを、(中略) 不特定多数の人間に対し理想として強要し、社会を「透明」なものに作り変えようとする試みが生れると、他人と異なる発言や行動を一切認めない全体主義の社会が誕生する。ルソーの友情論は、全体主義に結びつく要素を含んでいるのである。」
ということで、そうかそうかと。「腹を割って話せ!」みたいなのが一般化される社会は確かに息苦しいと思います。
そこから、フランス革命における「友愛」の意味に話がつながっていったり、カントの考える「引力と斥力(せきりょく)の均衡状態=友情」という考え方が紹介されたり、、、
まあ、いろいろ「友情論」が所狭しと記述されている本でした。
最後は現代における警告という感じですが、清水さんはこんなふうに書かれています。
↓
「友情は消滅するどころか、却って日々その役割を増大させている。(中略)見ず知らずの他人にたちしては礼儀正しく接するのではなく、むしろ、相手の生活の中に入り込んで積極的に親切にすべきであるという主張に出会うことが増えたからであるに違いない」
そして、災害地へのボランティア活動が肯定的に受け取られている最近の状況について
「困っている人を助けること、これはごく自然な行動のように見える。しかし、(中略)大量のボランティアの手を借りなければ災害からの復旧が進まないとすれば、それは、行政の不作為や制度の欠陥を示す事実に他ならない。」
とも書かれています。
「そもそも、人類の歴史の中で、構成員の善意や自発的な活動をあてにする社会というものが存在したことはない。構成員の善意をあてにし始めると、その社会は必ず滅亡するはずである。善意にもとづく行動は、公平への配慮を欠いているために、公共の空間を支配している社会的な正義(厚生)の原則を動揺させ腐食させるからである」
↑ちょっと文章が固いので、私なりに理解したことを書きますと、つまり、
人々の「善意」に頼る社会っていうのは、公平性や継続性などに不安がありますよと。本来、政治や行政がきちんとやらなきゃいけないところを、一般市民の「善意」や「良識」に頼るようになってしまうと、その社会っていうのは滅亡しますと。
政治や行政の不作為の多くを人々の「善意」で埋めるようになると、他人の善意に頼らなければ生きていけない社会になり、それは「親しさ」に捕らわれてしまう=つまり牢獄でしょう・・・
というような警告だと思います。
*
ここから先は、清水さんの本を読んで、私が勝手に考えたことなのですが。
身近に感じる例では、やはり子どもの学校のことなのですが、本来ならば自治体側がやることなんじゃないの?ということが、PTAや保護者に降りかかってくるので、
「人の善意に頼ってばかりいると、その社会は滅亡する」
などというのが、なるほどなーと思います。
本来、行政がやるべきことを放置して、「お母さんたち、善意あるよね? 自分の子どものことだもんね? よろしくね?」って感じで押し付けてきた結果、公平性や継続性の不安定さから無理が生じてきて、だんだんと母親側も「善意をあてにされても困ります!」という態度を取り始めている、そういうことなんじゃないかと思いました。
↓参加しています。
 にほんブログ村
<script</script><noscript></noscript>
にほんブログ村
<script</script><noscript></noscript>