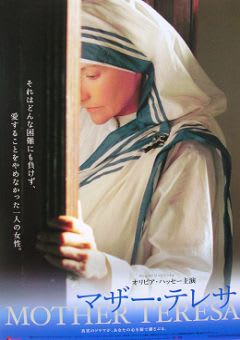独特の空気が銀幕に流れている。というより、澱んで留まっている。こういうタイプの映画は珍しいわけではなく、私が大学の3年あたりから徐々に出て、しかも流行った。1980年代後半である。プロも撮ったし、自主映画を制作する連中も撮った。その空気を漂わせる作品の制作は、5年は続いたろう。だから、私にとっては懐かしいタイプの作品であった。こういう空気を残しつつ焦点を明確にしたのが、犬童一心監督の「二人が喋っている」だと、当時、私は思った。そういう記憶がある。
大して疲れているわけでもないのに、途中から眠気が襲った。二本のハシゴだが、私はハシゴをする時は、上映時間より、作品の順番を決める。「重圧感のありそうな映画」→「日本映画」→「何も考えないで観ることのできる映画」・・・一例だが、要するに3作品観ても疲れない順番である。 昔は洋画は二本立て、邦画は三本立てが当たり前で、二本観ようが三本観ようが、そんなことは考えなかった。しかし、一本が当たり前になった今、移動して(映画館を変えて)観るという状態になった。人間は移動すると疲れる。同じ劇場内で、どんな作品であろうが、三本立てでも疲労感はない。しかし、劇場を変えて三本観ると、ひどく疲れる。私が歳をとったせいではなく、これは十代、二十代の時から思い続けてきた。 オールナイトの特集で五本連続上映でも疲労感はさほど無い。しかし、オールナイトで映画館を3館で三本観ると、かなり疲労感を覚える。人間の身体というものはそういうふうにできているのだろう。なぜかは、よくわからない。
二本なので、順番は考えなかった。しかし、「トランスアメリカ」の次の本作はきつかった。私は基本的に予備知識ゼロで映画を観るので、15分経ったあたりから「このタイプの映画はきついなぁ。」と思った。順番をテレコにすればいいのだが、本作は、レイトショーのみの上映である。静かな空気の中で、ばらばらだった3人が交差していく。主人公が台湾人で殺し屋という設定は安っぽく、インチキくさいが、彼、彼女らの心情をとらえた良いタイトルだと思いながら観ていた。が、最後の30分は眠気と戦った。どんどん空気が澱んでくるからだ。 眠気と戦いながら観た映画を評する資格は私にはないのだろうが、変幻自在に自分を操れるようになった鈴木京香という女優に感心した。モデル出身で、水着姿でグラビアに出ていた頃とは別人になっていて、テレビドラマより、映画に重きをおいている。ここのところ「キリッとした役」が多かったが、生きているのか死んでいるのか、掴みようのない過去を引きずった女を見事に演じていた。 <55点>