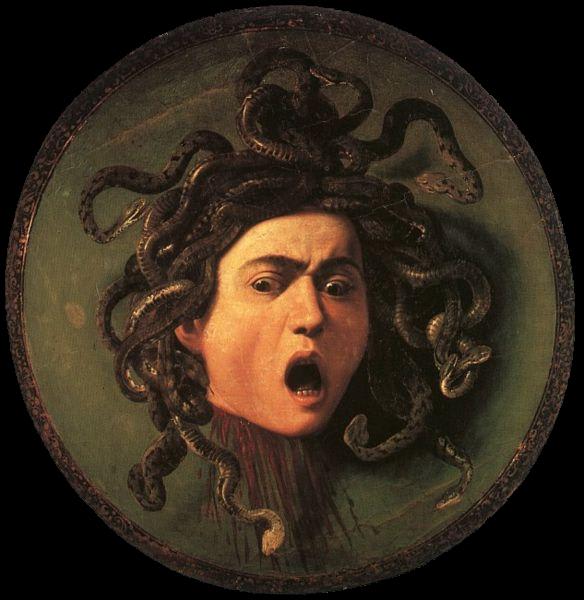2010年11月11日、私は風邪を引いてしまい頭が朦朧としていたのですが、来日中のダイ・シージエと彼のフランス語の作品を今のところ全て紹介している翻訳者の新島進氏とのトークショーを聴くため、タクシーで日仏学院へ向かいました。私にとっては単に耳で二人の対談を聴くだけではなく、ダイ・シージエという作家であり映画監督の在仏中国人がいったいどのような人物なのか、ユーモア溢れる作品を通して空想してきたイメージと合致しているのか、目で視定めることが大きな目的なのでした。
日仏学院には部屋ごとに同型のドアがあり、ドアの向こうがどのようになっているのか、内部で何が行われているのかは、外からは伺い知ることはできず、私はトイレの場所が分からず、間違って授業中の部屋のドアを開けてしまいました。こういう建物の構造は、昨年初に美術展で訪れた旧フランス大使館とも似ています。そんなところにも文化の香りを感じてしまうのはフランスならでは、です。
作家は時間に少し遅れて案内者に連れられて登壇しました。見るからに東洋人の特徴を備え、日仏学院の雰囲気とは似合わないおじさんで、小柄でどこかおどおどしているようにも見えました。ただ眼鏡の向こうの二つの目が(近眼のせいなのかもしれませんが)輝いていて、この男性の好奇心の分量は一般人に比べて過剰に多いのだろうと思えるのでした。そして彼こそがいかにも、あのような特別な、お互いに似ても似つかない個性的な作品群を産み出した人物に違いないのだと話を聴く前から納得したのでした。
新島氏の上手なリードに応えて、彼が次々と披露する体験談はどれも常人では想像しえない特異なものでした。聴いていると、それら自体が一篇の小説のようなのですが、彼のいくつかの作品と同様にユーモアで包まれているため、本来そこにあるはずの悲愴さは後退してしまっているのでした。例えば文化大革命期に下放政策で再教育を受けた体験は苛酷極まりないはずですが、フィクションである「中国の小さなお針子」と同じようなトーンに聞こえました。美術史を学ぶために異国フランスに留学して、そこで映画を志したきっかけ、さらに外国語で小説を書き始めたきっかけ、そして母国での映画撮影に関わる数々の苦難についてもしかりでした。
(つづく)
日仏学院には部屋ごとに同型のドアがあり、ドアの向こうがどのようになっているのか、内部で何が行われているのかは、外からは伺い知ることはできず、私はトイレの場所が分からず、間違って授業中の部屋のドアを開けてしまいました。こういう建物の構造は、昨年初に美術展で訪れた旧フランス大使館とも似ています。そんなところにも文化の香りを感じてしまうのはフランスならでは、です。
作家は時間に少し遅れて案内者に連れられて登壇しました。見るからに東洋人の特徴を備え、日仏学院の雰囲気とは似合わないおじさんで、小柄でどこかおどおどしているようにも見えました。ただ眼鏡の向こうの二つの目が(近眼のせいなのかもしれませんが)輝いていて、この男性の好奇心の分量は一般人に比べて過剰に多いのだろうと思えるのでした。そして彼こそがいかにも、あのような特別な、お互いに似ても似つかない個性的な作品群を産み出した人物に違いないのだと話を聴く前から納得したのでした。
新島氏の上手なリードに応えて、彼が次々と披露する体験談はどれも常人では想像しえない特異なものでした。聴いていると、それら自体が一篇の小説のようなのですが、彼のいくつかの作品と同様にユーモアで包まれているため、本来そこにあるはずの悲愴さは後退してしまっているのでした。例えば文化大革命期に下放政策で再教育を受けた体験は苛酷極まりないはずですが、フィクションである「中国の小さなお針子」と同じようなトーンに聞こえました。美術史を学ぶために異国フランスに留学して、そこで映画を志したきっかけ、さらに外国語で小説を書き始めたきっかけ、そして母国での映画撮影に関わる数々の苦難についてもしかりでした。
(つづく)













 いつの間にかワールドカップが終わっていた。
いつの間にかワールドカップが終わっていた。