此宣言を盾に「死刑廃止論」を言う者の大いなる矛盾を暴く
国際人権規約B規約(1979年8月29日)
第3部
第6条(生命に対する権利及び死刑の制限)
1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
※
「法律によって保護される」とされているが、どのような形で保護されることを期待するものであろうか?
ただ単に、「人を殺してはいけない」といずれかの法律に書くだけでは「殺人」に対する何の抑制も為されない。抑制するには、殺人をさせない為に、法律での「抑止条項」がなければならず単なる「訓示」的条項」を法律に記しても何の抑制力も生まれないのである。詰まり、此の抑制は殺人を犯させないような強い抑制力を伴うものでなくてはならないのであって、それには法律で「厳しい懲罰」を規定しなければならないのだ。
屡、巷間では、「殺人犯に対する死刑などの規定を科しても、『死ぬことを厭わぬ前提で殺人を犯す者』に対しては何の抑止力も為さない」などと言うもの者が、そのことを前提として「死刑廃止論の主張」をするが、このような論理は「部分を全体に拡大する詭弁」である。
更に、冤罪を理由にして、死刑廃止論を言うものがあるが、此れは司法手続きの問題を死刑廃止論にこじつける異論であり、全く真摯に死刑問題に取り組むものとは見られるものではない。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪か行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
3 生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる規定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法の如何を問わず免れることを許すものではないと了解する。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる。
※ 「出来る」のであって、「しなければならない」ものではない。
5 死刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
※殺害は禽獣でも、例えば、人の幼時でも「してはならない」と分かるものであり、殺人と言う最も忌むべき項を為したものは単なる年少から来る「不憫さ」で回避してはならないものである。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国によリ死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。
※ 6項で言っていることは、6条全体を見ると、日本の死刑廃止論者が言っているように「譬え極悪な犯罪である殺人を犯したものであっても国家権力によって命を奪うことは人権に反する」と言うものではなく、「人の命を奪う行為を抑止する為に法律でそのような犯罪を抑止することを認めている」としただけのものであり、然れども、この6条に拠っては、「死刑廃止論を目指す国に対しては、この6条の規定が抑止するものであってはならない」としたものである。
※ しかもだ、国家権力による人殺しは許されるものでは無いと言う輩は、そもそも我が日本は、主権者は国民にあり、法律は主権者である国民の代表が作る者であり、専制独裁国家のように権力者の恣意で死刑を決められるものではなく、更に、こう言う異論を声高に叫ぶ者は、では、「個人が人を殺すことは認めているのか?」と捉えざるを得ない暴論を吐いているのである。「人の命を奪うと言うことが赦されざることだ!」と言っといて、人の命を奪った者の命を保障しようとは、まるで、個人の殺人を奨励するかのようなトンでもない矛盾を曝け出しているのが、死刑廃止論を言う似権主義者なのである。














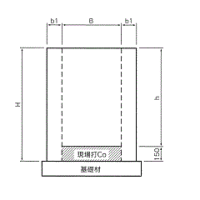





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます