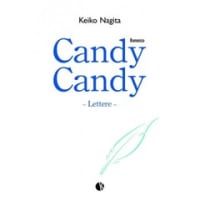キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
第2章
希望の花
希望の花
テリュースは、もの憂げにピアノの蓋を開けて片手ででたらめな音を鳴らした。もう片方の手にはいつものティーカップを持っていた。濃く煎じた紅茶独特の香りが、嗅覚を刺激し気持ちをやわらげた。
(一日の始めはやはりこれだな) 最初の一口を飲みながらテリュースは思った。
その青年は、窓の近くに配置したお気に入りのクイーンアン様式のチェスターフィールド肘掛け椅子にのんびりと座って一人暮らしのその部屋を見渡した。外では夏のにわか雨が街を濡らし、舗道に落ちる雨粒のリズミカルな合唱が子守唄のように音色を上げた。考えごとをするには最高の日曜日だった! テリュースの考えごとは昨夜に始まり、今朝雨に起きてからも続いていた。
テリュースはキャンディからの手紙のことを……キャンディのことを考えずにはいられなかった。
キャンディからの手紙はテリュースが送ったものより多くのことが書いてあったが、その中身は巧妙で、彼が手紙に込めた内容はそっけなく見過ごされていた。自分の心が変わっていないことを伝えるためにテリュースが捻り出したあの簡潔な一文は、事実上無視されてしまったか或いは読み損なわれていた。
「きみはほんとに変わっているよ、キャンディ」 テリュースは声に出して言った。「10年もの間、音沙汰もなく放っておいたあげくに手紙を出したおれの怠慢を責めるどころか、自分が連絡を怠っていたと謝るなんて……。まるで、おれたちが連絡を失ったのは、きみの責任であるかのようにだ。それに、しかるべき時間が過ぎたらきみに連絡しようと心に決めていたことを、おれはあえて伝えたのに、きみからの返事は田舎暮らしについてのたわいもないことばかりだ」
「きみがそのつもりだったとしても、おれはへこたれないぜ、ターザンそばかす」 片方の眉を上げながらテリュースは警告した。「きみには、おれが最も性急に知りたかったある情報を伝えてくれるだけの優しさがあった」
テリュースは椅子から立ち上がり、手に紅茶を持ったまま窓の方へ歩いた。
「独身婦人になるだって?」 キャンディの言葉を引用して言った。「おれに言わせればそんなことはあり得ないね、アードレーのお嬢様」
テリュース・G・グランチェスターは、この10年間で初めて本来の自分に戻ったような気がしていた。

――夏が永遠に続けばいいのに……。アニー・コーンウェルは温室で暖かな午後の風を受けながら思った。足元では、小さなアリステア・コーンウェルが、エンジン音を真似ながらお気に入りの車のおもちゃで遊んでいた。
息子のようすを見ようと明るい目を下げたその若い女性は、母親としての満足感で口元に優しい笑みを浮かべた。庭のテーブルの上にはまだ読まれていないちょっとした分量の手紙と、午後のお供のジャスミンティーが置いてあった。
洗練された女性の外見とは裏腹に心の中は田舎娘のままだったので、アニーは温室のシダやランの中でこのうえない平穏を感じていた。そこはアニーにとって日々の忙しい社交生活からの隠れ場であり、社会的地位の重責から逃れ一息つける秘密の場所であり、一人瞑想にふけることのできるとっておきの避難場所だった。
アニーは黒髪の後れ毛を払いのけ、その髪をボブに短く切る勇気がはたして自分にはあるだろうかと再び思いをめぐらせた。近頃では誰もが最新の流行を熱心に追いかけているようだった――もちろんエルロイ大おばさまのような年配の婦人は除いてなのだが。アニーは、自分の見事なストレートの髪はボブにピッタリだと知っていて、その髪型にしたら自分はどんなに魅惑的に見えるだろうとうっとりした。けれども二つの事柄がその髪を長いままに留めていた。一つは母親が男の子のような短髪に反対していたこと、そしてもう一つは毎晩いつもの結い上げた髪を下ろす時に、豊かな長い髪が夫に及ぼす影響力だった。アニーは、自分自身のうわついた決断力のなさを心の中で笑った。
(キャンディがボブにしたらきっとあか抜けるわ) アニーは考えた。(彼女の自然なカールはメアリー・ピックフォード風のウェービーボブにピッタリだもの)
しかしアニーは、キャンディが実用的だというそれだけの理由から長い髪のままでいることを知っていた。キャンディは、誰かのために見栄えを良くすることにも、ファッションにも関心がなかった。そのようなことを逡巡しているうちに、アニーの思考は最近の一番の悩み事に行き着いた。それはキャンディが独身のままでいるということだった。
アニーは多くの意味で幸運に恵まれていた。大人になり経験を積むにつれて、アニーは、人生の中でまさに物事が悪い方向へ行ってしまいそうな重大な局面では、キャンディがいつも何らかの方法で助けてきてくれたことをはっきりと認識するようになった。キャンディがアニーのために自らを犠牲にしてきた一方で、アニーがその同じ親切を返せるようになるまでには何年もかかった。アニーはその部分では自分を誇りに思うことはできなかったけれど、キャンディがしてくれたことには深く感謝していた。
アーチーとの結婚でさえ、ほんの若い頃からキャンディによって形づくられたようなものだとアニーは思っていた。――もしキャンディがアーチーを断って横に退いていなければ、今では自分を情熱的に愛してくれているこの素晴らしい優しい男性と結婚することはなかっただろう……。ここで一つ作者からつけ付け加えておくと、アニーの忠実な献身は、いつしか彼女が最も願ったアーチーの心を勝ち取っていた。
そのように幸運な身の上にあればこそ、アニーは幼馴染が同じ種類の幸福を勝ち取る手助けをしたかった。しかし残念ながらキャンディは、お見合い話にあまり乗り気ではなかった。年月が過ぎてもキャンディが人里離れた山奥での生活を続ける意志が固いので、アニーは絶望に陥っていた。時々アニーは、その恩人がしてくれたことに見合ったお返しをすることなど決してできないのではないかと思った。
「何を深く考え込んでいるの、ぼくの愛する奥さん?」 突然、耳の近くで男性の声がささやいた。
アニーは目を上げて、好意的な光を浮かべて夫のハシバミ色の瞳を見た。そして短いけれども優しい口づけを交わした。床で遊んでいた小さなアリステアは、両親の開けっぴろげな愛情表現をじっと見てクスクスと笑った。
「パパの小さなステアは元気かい?」 アーチーは愛情のこもった動作で子供を持ち上げながら聞いた。
「あそうぼよ、パパ。あそぼう」 3歳の男の子はクスクス笑いを続けながらねだった。
アーチーにはそれが何かはっきりとは分からなかったが、ちょっとした瞬間に……その子どもの表情の何かが……懐かしいある別の顔を思い出させた。恐らくはその笑顔か無垢な黒い瞳の輝きが、兄の大切な思い出を呼び覚ましたのだ。アーチーは急に胸が苦しくなり、思わず息子を胸に抱きしめた。
「よし相棒、一緒に遊ぼう」 アーチーは、その子のバラのような頬にキスをしながら言った。
床で父と息子が遊ぶ中、その若い家族はしばし心地よい静けさに包まれた。最近では小さなコバルトブルーのフォード・モデルTが遊びの中心だった。アニーはお茶と手紙をお供に、ガーデンテーブルから二人の様子を眺めていた。
「何かいい知らせは?」 しばらくしてアーチーは、ラベンダーの飾りが付いた、ふくらはぎをかすめるローウエストのプリーツスカートをはいた妻に見とれながら聞いた。そのドレスが妻のほっそりした腕を引き立たせる様子がアーチーの気に入っていた。
「キャンディはまだ大工さんや配管工の人たちと忙しいそうよ」 苛立ちを含んだ声でアニーが返答した。
「あんなに手ごわい親方に追い立てられる職人さんたちには同情を禁じ得ないね」 怖れ知らずの彼のいとこが、年齢が彼女の2倍にもなる大勢の男たちを指示するさまを思い浮かべて、アーチーは含み笑いをした。
「女監督でしょ」 アニーが正した。
「違うよ、ぼくは的確な言葉を選んだつもりだよ」 アーチーがからかう。
「あなたったら」 アニーは口をとがらせた。
「君を心配させているのはその事なの?」 アーチーは、妻が考え込んでいた理由を推測して問いかけた。
「ある意味ではそうよ。キャンディったら人付き合いをしようとしないのだもの。キャンディはポニーの家に引きこもるのではなくて、このシカゴでもっとたくさんの人に会うべきなのよ」 アニーは力説した。
「冗談だろ? キャンディはこのところ旅行だってたくさんしているじゃあないか。年内にもまだいくつか回るところがあるはずだよ」 アーチーが言い返した。
「まあアーチー、わたしが言いたいのはそういうことではないの。キャンディはポニーの家の後援者を訪問しているだけよ。あなたやアルバートさんが必要な経費を援助できるというのに、そんな努力をする必要がどこにあるのかしら?」
「ねぇアニー、キャンディにはキャンディのルールがあるんだよ。他の人たちにも協力してもらえるようにって、ぼくたちからの寄付に制限を設けたのはそもそもキャンディの考えだったんだから」 アーチーは答えて言った。「キャンディは自分のことは自分でやるのが好きなんだってこと、そろそろ理解すべきだよ。ぼくたち一族の地位に完全に頼るのは窮屈なのさ。尊重してあげようよ」
「そんなのばかげているわ! 後援者の人たちを訪問する代わりに、キャンディはわたしたちとここで夏を過ごすべきなのよ。後援者の人たちなんて、ほとんどが結婚しているか年を取りすぎているんだもの。全然よくないわ」 アニーは苦々しく訴えた。
「アニー、きみはいつになったらキャンディの仲介役を止めるつもりだい?」 アーチーは胸の上で腕を組みながら問いただした。
「キャンディにふさわしい、キャンディを幸せにしてくれる男性が見つかるまでよ、アーチー」 常ならぬ決意でアニーは答えた。
「キャンディは幸せになるために夫を必要としていないよ、アニー。長い間見てきて、ぼくは、キャンディは結婚に向いていないと信じるようになった。きみはどうしたら理解できるのかな? キャンディの自由な精神は、例えるなら……」 アーチーは適切な表現を探して言葉を止めた。「……風のよう、かな? この地球上に、その風を素手でつかまえられるだけの力を持つ男がいるとは思えないよ」 アーチーは、尽きぬ憧れの思いを声ににじませてそう結論づけた。
「ああ、アーチー、そんな風に言わないで。わたしはキャンディにはしっかり身を固めてほしいの。キャンディのことはあなたより余程わかっているわ。キャンディだって、他の女性と同じように愛される必要があるのよ」 涙が思わずアニーの頬を伝った。
「わかったよ、スウィートハート」 アーチーは妻を元気づけた。「そんなに泣かないでよ。キャンディに会いに行くかい? 予定よりも早くキャンディに会えば、きっときみの気持ちも落ち着くよ。もしかしたら、きみが主催するティーパーティーに出席するようにキャンディを説得できるかもしれないよ。どうかな?」
アーチーが優しく支えるように手を握ると、アニーは涙の中に笑顔を見せた。小さなステアは父親の腕の中で眠ってしまっていた。その小さい手は、人生の避けがたい苦難など知りもしない至福の中で、コバルトブルーのモデルTをしっかりと握りしめていた。

「ではお聴きください、ファニー・ブライス嬢でセカンド・ハンド・ローズ」 ラジオのアナウンサーがそう紹介すると、ポニーの家はまもなく女性の高調子の歌声で満たされた。リズミカルで遊び心のあるその曲は、中古品店を営む父を持つ若い娘の、決して新品を持てない不満について歌っていた。おかしみのあるその歌詞が、職人たちの顔に笑顔をもたらすのに時間はかからなかった。一人の職人が一緒に歌い始めた。
中古の巻き髪
わたしが身につけるのは中古の真珠
新品なんて持ったことがない!
みんなわたしが2番街の中古のローズだと知っているわ
楽しい歌が大好きなキャンディは、踊りたくてうずうずしてきた。
「一緒に踊りませんか、お嬢さん?」 大工のトンプソンが聞いた。
「誰も誘ってくれないのかと思ったわ!」 キャンディが目を輝かせて返事をすると、大工と娘は陽気な音色にあわせて踊った。活気に満ちたステップで、キャンディは新しいスタイルの踊りに精通しているようだった。五十代初めのトンプソンはすぐにへとへとになり、最後まで踊りきるのがやっとだった。曲の終わりで互いにお辞儀をすると、男たちは拍手喝采した。
「キャンディさんは実に見事な踊り手ですなぁ」 トンプソンは帽子で自分を扇ぎながら言った。
「いとこのアーチーがすごい名人なのよ」 キャンディは陽気な目を輝かせながら答えた。「会うたびに最新のステップを教えてくれるの」
「そのレッスンはちゃんと生かされてますよ。わしが請合います」 トンプソンは、自分がもう以前のように若くはないと心の中で思いながら笑った。
「そうね、好きなことは覚えるのが早いものだって友達のパティは言うけど、確かにわたしはこういう歌が大好きだもの」
「それならわしだってファニー・ブライス嬢は大好きですよ」 表情を輝かせてトンプソンが答えた。「とても平凡な女の子だと言われていますけど、ニューヨークでいつか彼女のショーを見てみたいものですなぁ。きっと最高の経験になりますよ!」
「こいつの言うことなんか真に受けちゃあいけませんよ、キャンディさん」 別の建築業者の男が会話に加わった。「このトンプソンはブライス嬢のことなんかに興味はなくて、ジーグフェルド・フォリーズの可愛い女の子たちを見たくて仕方ないんだから」
「きっとそうね」 キャンディがそう言い返すと男たちは大笑いした。
「さっさと仕事に戻らんか!」 冗談が気に入らずにトンプソンは部下を叱りつけ、キャンディの方を向いて穏やかな口調で話しかけた。「仕事に戻らせていただきます、お嬢さん。ダンスをしに来たのではないですからね」
「そうでしたわね、トンプソンさん」 トンプソンが話題を突然変えたことに笑顔をこらえてキャンディは答えた。
「新しい居間の窓について相談したくて来たのですよ。よくよく考えたんですが、この窓が西向きというのはやはりよくないと思いましてね。特にポニー先生がこの部屋で午後を過ごされる時は、太陽の日差しが顔にあたって不快な思いをなさいますよ」
内心キャンディは、会話が改修工事という安全な話題になったことがありがたかった。ニューヨークと聞いただけで、その街に住むある一人の男性のことを思い出して動揺してしまうのだ。過去には、時がテリュース・グレアムに関する苦しみをやわらげてくれて、いつの日か、若かりし頃の甘い思い出としてだけ考えられようになることを期待していた時もあった。その日が来たらテリィとスザナに再会し、澄み渡った笑顔を浮かべてあいさつをして二人を友人として迎え入れるのだと。
キャンディの一部ではテリィをこのように見られるように心から努力した。しかし別の部分では全力でそれに抵抗し、彼の思い出の品をこっそり保管していた。かつて一度だけ、テリィからの昔の手紙を燃やそうと思い立ったことがあったが、そう考えただけで決心が萎え、代わりにアルバートさんに頼んで昔の日記と一緒に預かってもらうことにしたのだ。今でもそれらはアルバートさんの手元にある。それでも理屈抜きで、キャンディはテリィの舞台に関する好意的なレビューの新聞切り抜きを取っておいて、とりわけ何年も前にアニーが最初に送ってくれた切り抜きを大切にしていた。この思い出の品の中にはテリィのシルクの白いタイもあった。それで心が収まるわけではなかったが、それでもそのタイを持ち主に返す機会がなかったことは今となっては幸運だったと感謝していた。しかし今、ポニーの家の改修工事に集中しようと努力してみても心臓の鼓動は激しいままだった。
(あなたのことをどう思えばいいのよ、テリィ) キャンディは静かに自分に問いかけた。(あなたからの手紙は何を意味しているの?)
最初の手紙が届いて以来、この4か月の間に20通以上もの手紙が続けて送られてきた。キャンディは、二人の間のこの新たな長距離の友情の本質をどう捉えたらいいのかわからなかった。手紙の中のテリィは昔と同じように実にくだけた調子で、時には遊び心さえあった。それでも、二人の間の10年間という隔たりがまだ空中に漂っていることは明らかだった。遅かれ早かれ二人はそのことについて話をしなければならないだろうが、今はまだ早かった。現段階では過去に関することには決して触れず、互いに軽い調子で手紙をやりとりすることで暗黙に合意していた。
キャンディは、スザナに関してもどうしたらいいのか分からずにいた。同情を送るにはもう遅すぎたが、かといって彼女の死に関して心からの悼みを何も伝えていないことには罪悪感を抱いていた。しかしこうした感情があったとしても、テリィの手紙の内容が未来に対する前向きな展望で輝いているような時には特に、キャンディは自分が望むことを表現する言葉を見つけることができなかった。
居間の窓に関する新しいアイデアを話し合った後、キャンディは大工さんたちに後を任せて自分は日常の仕事に戻った。まだ午前中だったので、ほとんどの子どもたちはポニー先生とレイン先生の授業を受けていた。何人かの子どもたちは具合が悪く寝室で横になっていたので、キャンディはその子たちの様子を見に行った。薬をちゃんと飲んで具合がよくなってきているのを確かめてから、キャンディはズボンとシャツの仕事着に着替えた。
キャンディは肉体労働を楽しんだので、牛の乳搾りや、小さい子どもたちの洋服の洗濯や、ベジタブルガーデンの手入れなどの下働きの作業を与えられても不満はなかった。こうして一人でいる時には、思考はたいてい大切な友人のいるさまざまな場所へと飛んだ。いつもであればキャンディは、休みなく飛び回るアルバートさんの遠い国々でのビジネスのことや、パティが色とりどりの言葉で説明してくれるオックスフォードでの大学生活のことを考えるのだが、今は先週訪ねてきてくれたアニーとのことを思い出していた。
その幼馴染は今ではとても優雅な女性になり、キャンディが知る中でも最も愛らしい小さな男の子の立派な母親となっていた。アニーとの友情を大切に思っていたし小さなアリステアにも会えるので、キャンディはアニーの訪問をいつも楽しんだ。そしてそれは今回も例外ではなかった。小さなステアは本当にかわいらしくて自分になついていたので、キャンディはその子から目を離すことができなかった。
「キャンディ、アリステアにかまうのを止めてここに来てちょうだい!あなたに着てみてほしい最新のものをたくさん持ってきているのよ」 アニーは滞在の二日目のある時点で言い立てた。
ステアとその同じ年頃の4人の子どもたちと一緒にかくれんぼで遊んでいたキャンディは目隠しを外した。アニーの毅然とした表情から、その言葉に従う以外の他に選択肢がないことを悟った。キャンディはしぶしぶと目隠しのハンカチを最年長の男の子に渡し、あきらめのため息とともにその友人の後に従った。
「子どもたちがお昼寝しているときにすればいいじゃない、アニー」 家に戻る道すがらキャンディはまだ抵抗していた。
「その時になったらなったで、今度はやらなければならないことがたくさんあって忙しいと言い張るもの」 アニーは断固として言った。「だから今なのよ」
時にはこのようにアニーが親分風を吹かせ、キャンディがそれに従順な態度で従うようになっていた。役割が昔と逆転しているこのような状況を、キャンディは心の中で面白がって笑った。
二人の娘が部屋に入ると、キャンディは、女性らしい衣類が寝室全体に広げられ飾れているのに目を見開いた。
「スーツケースの中にこのお洋服を全部入れてきたの、アニー? どうやって入ったの?」 キャンディは不思議がった。
「わたしのやり方があるのよ。それに、できるだけたくさん持ってこようと決めていたの。そうでもしなければ、あなたはお洋服を新しくする暇を全然見つけないんだもの」 アニーは自分の腕前に誇らしげに答えた。
しばしの間二人は秋冬色に彩られた品々に見とれて過ごした。キャンディも美しい洋服や装飾品に心を動かされないわけではなかったので、アニーが自分のために選んでくれたドレスや帽子やコートや靴を身に着けて、とても楽しい時を過ごした。それでも時折、その目は外で遊ぶ子どもたちを見るために窓の方へとさまよった。
「この3着のガウンは夢のようよ、アニー、ありがとう」 繊細なデザインのパーティードレスに見とれながら、キャンディは感謝をこめて言った。「でも、ここでは着る機会があまりなさそうね」
「やめてよ、キャンディ。サンクスギビングのディナーパーティーには来てくれるのでしょう? それに、11月にはボストンとピッツバーグへの旅行もあるじゃない。まさかデニムのズボンで行くつもりではないわよね」 キャンディがその時着ていた作業着を指さしながら、アニーは冗談めかして答えた。
「ビジネス旅行なのよ、アニー。ビジネスミーティングに出席することもあるし、時には後援者の方々とのフォーマルな昼食もあるわ。そういう場所にはアフタヌーンドレスと、クロッシェ帽子と、コートで十分事足りるのよ」
「でも来月はシカゴに来なくてはだめよ。ティーパーティーを開催するから」 アニーは気軽に言い添えた。そして――紹介したい新しいお友達がいるから……と暗示するような、特別な輝きをその瞳に浮かべた。
キャンディは、疑わしげに眉をひそめてアニーを見た。アニーのその声色が、新たなお見合いを企んでいることを露呈していた。
「アニー、ねぇアニー、もうお願いだから堅苦しい金持ちの男の人はやめてちょうだい。わたしには興味がないって何回言ったらわかってもらえるの?」 キャンディはけん制した。
「でも今回の人はきっと好きになるわ」 アニーは招待の真の目的を認めて言った。「とっても寛容で、良心的な人なの。もちろんとてもハンサムよ」
「そんなにもその人が好きなら結婚を許可してあげるわ」 キャンディは皮肉を込めて返した。
「わたしはもう結婚しているわ、おばかさん」 そのブルネット髪の娘が抗議をしながら枕を投げるとそれがキャンディの右頬にあたった。
それが枕投げ競争を始める絶好の合図になり、二人の娘は笑い声を部屋中に響かせながらしばらくの間その遊びを楽しんだ。台所のポニー先生にもその笑い声がはっきりと聞こえてきた。ポニー先生は、いくら時が過ぎても決して変わらないものがあるのだと改めて思った。
「もうやめて、キャンディ!」 いつでも最初に降参するアニーが叫んだ。
「弱虫ね」 枕投げ競争の間にアニーが投げた服から頭を出してキャンディは不平を述べた。瞬間、服の一つがキャンディの注意を引いた。「一体これは何なの、アニー?」 奇妙な形のランジェリーを不思議そうに見つめてキャンディは聞いた。
「コルセットじゃないの、ばかね」
「うそでしょう? そんなのは過去のものだと思っていたわ。新しい流行はもっと自然な感じの形でしょう?」 キャンディは、上部にブラジャーのようなものがついた、この新しい形のコルセットをどう理解していいのか分からず聞いた。
「そうね、でもすべての女性が新しいローウエストのスタイルに似合うような細身でやせた体型に恵まれているわけではないわ。最近では体のくびれやでっぱりを目立たなくするの。今シーズンはヒップや胸が大きすぎるのは流行りでないのよ」 アニーは、キャンディが驚きで奇妙なしかめ面をしているのには気付かずに説明した。
「それって、男の子みたいにぺたんこでなければだめという意味?」 キャンディは信じられないというように聞いた。
「うーん、わたしはそんな風には言わないわ。ただ、昨今の形が以前よりもスタイリッシュなのよ。でもキャンディ、あなたはそんなに心配しなくても大丈夫。ヒップのシルエットは問題なしよ。ただ、胸をちょっと工夫する必要があるわね。コルセットが助けてくれるわ」
「冗談でしょう?」 キャンディは笑った。「15歳の頃は、胸を持ち上げるためにあの窮屈なコルセットを着させられたのよ。しかもそのころには持ち上げるだけのものもなかったわ。今はやっと自然の摂理のおかげで胸も出てきたっていうのに、15歳のように見えるために押さえつけなければならないなんて。あり得ない! 絶対着ないわよ」 アニーの提案をきっぱり却下してキャンディは言った。
「強情にならないでちょうだい。胸が大きいと真珠がおしゃれに見えないのよ。ネックレスが中央に自然に下がらずに両端に分かれてしまうもの」
「構わないわ。わたしはいつものブラとキャミソールでいいわ。とにかく勧めてくれてありがとう。それからティーパーティーにも招待してくれてありがとう。でも残念だけど行けないわ、アニー」 キャンディは厳しく聞こえないように努めながら結論付けた。
「仕様のない人ね」 下着をたたみ、タンスの引き出しにしまいながらアニーはふくれて言った。そして、何か反論を考えつく前に、その目が引き出しの中のハンカチの束の上に置いてある封筒をとらえた。
その動作を見て、キャンディは何がアニーをだまらせてしまったのかをすぐに理解した。
キャンディは心の中で、テリィの手紙を保管しているいつもの箱にしまう代わりに、引き出しの中に手紙を置いておいた自分を責めた。(なぜ油断していたの?) キャンディは思った。
「そうよ、テリィからの手紙よ」 キャンディは、アニーが質問を発する前に一瞬の沈黙の後にそれを認めた。
「テリィがあなたに手紙を書いたのね! 大事件だわ! でも今朝手紙が届いた時にキャンディは驚いていなかったわね」 そう声に出して考えながら言うと、アニーの頭に一つの考えがひらめいた。「テリィから手紙を受け取るのはこれが初めてではないのね?」
「そうね、初めてではないわ」 キャンディはクローゼットに服をかけ、忙しくしようと努めながら認めた。
「それはよかったわ!」 意味をかみしめながらアニーは大声を発した。「テリィはまだ独身よね?」
「まあ、アニー! 妙な考えを起こさないでよ。彼は婚約者を亡くしたばかりなのよ!」 キャンディは出来る限り無関心を装って答えた。
「お願いよ、そんなのもう二年も前のことよ、キャンディ。あなたはわたしを欺いてきたのね。二人が連絡を取り合っていることを何も言ってくれなかったわ。わたしがあなたのために忙しく求婚者を探している間、その求婚者はあなたの鼻先にいて、あなたのドアをノックしていたなんて! 少なくとも今回ばかりはその人を気に入っているわね」
「お願いよ、その空想好きな頭で大げさなストーリーを想像しないでちょうだい、アニー。ロマンスのようなものは何もないのよ」 キャンディはうろたえて激しく否定した。「お互いの近況を知るために手紙をたまに送りあっている古い友達というだけ。それ以上のことはないの」
ステアとその同じ年頃の4人の子どもたちと一緒にかくれんぼで遊んでいたキャンディは目隠しを外した。アニーの毅然とした表情から、その言葉に従う以外の他に選択肢がないことを悟った。キャンディはしぶしぶと目隠しのハンカチを最年長の男の子に渡し、あきらめのため息とともにその友人の後に従った。
「子どもたちがお昼寝しているときにすればいいじゃない、アニー」 家に戻る道すがらキャンディはまだ抵抗していた。
「その時になったらなったで、今度はやらなければならないことがたくさんあって忙しいと言い張るもの」 アニーは断固として言った。「だから今なのよ」
時にはこのようにアニーが親分風を吹かせ、キャンディがそれに従順な態度で従うようになっていた。役割が昔と逆転しているこのような状況を、キャンディは心の中で面白がって笑った。
二人の娘が部屋に入ると、キャンディは、女性らしい衣類が寝室全体に広げられ飾れているのに目を見開いた。
「スーツケースの中にこのお洋服を全部入れてきたの、アニー? どうやって入ったの?」 キャンディは不思議がった。
「わたしのやり方があるのよ。それに、できるだけたくさん持ってこようと決めていたの。そうでもしなければ、あなたはお洋服を新しくする暇を全然見つけないんだもの」 アニーは自分の腕前に誇らしげに答えた。
しばしの間二人は秋冬色に彩られた品々に見とれて過ごした。キャンディも美しい洋服や装飾品に心を動かされないわけではなかったので、アニーが自分のために選んでくれたドレスや帽子やコートや靴を身に着けて、とても楽しい時を過ごした。それでも時折、その目は外で遊ぶ子どもたちを見るために窓の方へとさまよった。
「この3着のガウンは夢のようよ、アニー、ありがとう」 繊細なデザインのパーティードレスに見とれながら、キャンディは感謝をこめて言った。「でも、ここでは着る機会があまりなさそうね」
「やめてよ、キャンディ。サンクスギビングのディナーパーティーには来てくれるのでしょう? それに、11月にはボストンとピッツバーグへの旅行もあるじゃない。まさかデニムのズボンで行くつもりではないわよね」 キャンディがその時着ていた作業着を指さしながら、アニーは冗談めかして答えた。
「ビジネス旅行なのよ、アニー。ビジネスミーティングに出席することもあるし、時には後援者の方々とのフォーマルな昼食もあるわ。そういう場所にはアフタヌーンドレスと、クロッシェ帽子と、コートで十分事足りるのよ」
「でも来月はシカゴに来なくてはだめよ。ティーパーティーを開催するから」 アニーは気軽に言い添えた。そして――紹介したい新しいお友達がいるから……と暗示するような、特別な輝きをその瞳に浮かべた。
キャンディは、疑わしげに眉をひそめてアニーを見た。アニーのその声色が、新たなお見合いを企んでいることを露呈していた。
「アニー、ねぇアニー、もうお願いだから堅苦しい金持ちの男の人はやめてちょうだい。わたしには興味がないって何回言ったらわかってもらえるの?」 キャンディはけん制した。
「でも今回の人はきっと好きになるわ」 アニーは招待の真の目的を認めて言った。「とっても寛容で、良心的な人なの。もちろんとてもハンサムよ」
「そんなにもその人が好きなら結婚を許可してあげるわ」 キャンディは皮肉を込めて返した。
「わたしはもう結婚しているわ、おばかさん」 そのブルネット髪の娘が抗議をしながら枕を投げるとそれがキャンディの右頬にあたった。
それが枕投げ競争を始める絶好の合図になり、二人の娘は笑い声を部屋中に響かせながらしばらくの間その遊びを楽しんだ。台所のポニー先生にもその笑い声がはっきりと聞こえてきた。ポニー先生は、いくら時が過ぎても決して変わらないものがあるのだと改めて思った。
「もうやめて、キャンディ!」 いつでも最初に降参するアニーが叫んだ。
「弱虫ね」 枕投げ競争の間にアニーが投げた服から頭を出してキャンディは不平を述べた。瞬間、服の一つがキャンディの注意を引いた。「一体これは何なの、アニー?」 奇妙な形のランジェリーを不思議そうに見つめてキャンディは聞いた。
「コルセットじゃないの、ばかね」
「うそでしょう? そんなのは過去のものだと思っていたわ。新しい流行はもっと自然な感じの形でしょう?」 キャンディは、上部にブラジャーのようなものがついた、この新しい形のコルセットをどう理解していいのか分からず聞いた。
「そうね、でもすべての女性が新しいローウエストのスタイルに似合うような細身でやせた体型に恵まれているわけではないわ。最近では体のくびれやでっぱりを目立たなくするの。今シーズンはヒップや胸が大きすぎるのは流行りでないのよ」 アニーは、キャンディが驚きで奇妙なしかめ面をしているのには気付かずに説明した。
「それって、男の子みたいにぺたんこでなければだめという意味?」 キャンディは信じられないというように聞いた。
「うーん、わたしはそんな風には言わないわ。ただ、昨今の形が以前よりもスタイリッシュなのよ。でもキャンディ、あなたはそんなに心配しなくても大丈夫。ヒップのシルエットは問題なしよ。ただ、胸をちょっと工夫する必要があるわね。コルセットが助けてくれるわ」
「冗談でしょう?」 キャンディは笑った。「15歳の頃は、胸を持ち上げるためにあの窮屈なコルセットを着させられたのよ。しかもそのころには持ち上げるだけのものもなかったわ。今はやっと自然の摂理のおかげで胸も出てきたっていうのに、15歳のように見えるために押さえつけなければならないなんて。あり得ない! 絶対着ないわよ」 アニーの提案をきっぱり却下してキャンディは言った。
「強情にならないでちょうだい。胸が大きいと真珠がおしゃれに見えないのよ。ネックレスが中央に自然に下がらずに両端に分かれてしまうもの」
「構わないわ。わたしはいつものブラとキャミソールでいいわ。とにかく勧めてくれてありがとう。それからティーパーティーにも招待してくれてありがとう。でも残念だけど行けないわ、アニー」 キャンディは厳しく聞こえないように努めながら結論付けた。
「仕様のない人ね」 下着をたたみ、タンスの引き出しにしまいながらアニーはふくれて言った。そして、何か反論を考えつく前に、その目が引き出しの中のハンカチの束の上に置いてある封筒をとらえた。
その動作を見て、キャンディは何がアニーをだまらせてしまったのかをすぐに理解した。
キャンディは心の中で、テリィの手紙を保管しているいつもの箱にしまう代わりに、引き出しの中に手紙を置いておいた自分を責めた。(なぜ油断していたの?) キャンディは思った。
「そうよ、テリィからの手紙よ」 キャンディは、アニーが質問を発する前に一瞬の沈黙の後にそれを認めた。
「テリィがあなたに手紙を書いたのね! 大事件だわ! でも今朝手紙が届いた時にキャンディは驚いていなかったわね」 そう声に出して考えながら言うと、アニーの頭に一つの考えがひらめいた。「テリィから手紙を受け取るのはこれが初めてではないのね?」
「そうね、初めてではないわ」 キャンディはクローゼットに服をかけ、忙しくしようと努めながら認めた。
「それはよかったわ!」 意味をかみしめながらアニーは大声を発した。「テリィはまだ独身よね?」
「まあ、アニー! 妙な考えを起こさないでよ。彼は婚約者を亡くしたばかりなのよ!」 キャンディは出来る限り無関心を装って答えた。
「お願いよ、そんなのもう二年も前のことよ、キャンディ。あなたはわたしを欺いてきたのね。二人が連絡を取り合っていることを何も言ってくれなかったわ。わたしがあなたのために忙しく求婚者を探している間、その求婚者はあなたの鼻先にいて、あなたのドアをノックしていたなんて! 少なくとも今回ばかりはその人を気に入っているわね」
「お願いよ、その空想好きな頭で大げさなストーリーを想像しないでちょうだい、アニー。ロマンスのようなものは何もないのよ」 キャンディはうろたえて激しく否定した。「お互いの近況を知るために手紙をたまに送りあっている古い友達というだけ。それ以上のことはないの」
キャンディは、テリィとの新しい関係が、ロマンティックな種類のものではないとアニーを説得するのに大変な労力を要したことを思い出していた――少なくとも現時点ではその話題を取り下げてもらうことに全力を尽くした。今こうしてその時のことを思い返してみると、テリィとのことに関しては、アニーにも他の誰にも頼らないでいることに少し後ろめたさを感じた。ミルクを台所に置きながら、キャンディは再びため息をついた。キャンディはただ、テリィに対する自分の気持ちを誰かに打ち明けることができなかったのだ。おそらくそれは、彼に対するどんな感情でさえも自分の心の中に隠してきた習慣に起因していた。キャンディは、テリィと別れてからずっとそうしてきたので、そうする以外できなかったのだ。
陽が高くなっていた。レイン先生のベジタブルガーデンから新鮮なにんじんやほうれん草を収穫する作業に没頭しているように見えていても、キャンディの頭の中はテリィのことでいっぱいだった。今は10月の中旬だったが、ブロードウェイでのテリィの新作舞台はまたもや大きな成功を収めていた。キャンディはテリィのことを誇らしく思わずにはいられなかった。一番最近届いた手紙の中で、テリィは間もなく国内を公演旅行でまわると言っていた。その差し迫った旅のことに思いを馳せていると、キャンディは、テリィが手紙の中でこれまでに語ってくれた数えきれない旅の出来事の中からサンフランシスコの家具職人の話を思い出していた。その家具職人はとても技能が高く、ミス・ベーカーの家具もいくつか製造したとテリィは教えてくれた。この話からキャンディは、クリスマスにポニー先生に新しい居間用のロッキングチェアーをプレゼントすることを思い立ち、テリィに打ち明けたのだった。
キャンディは、テリィが西海岸への公演旅行の間にポニー先生のロッキングチェアーを手に入れて、クリスマスイブの前までには特配便で送ると返事をくれた時の感激を思い出してほほ笑んだ。テリィが購入してくれたと知ったらポニー先生はその贈り物に興奮して、椅子から引き離すためだけに軍隊の一部隊が必要になるだろうことがキャンディにはわかっていた。けれどもそんな無邪気な計画が、その年の終わりまでに予期しなかった一連の出来事に進展することなど、この時には知る由もなかった。

*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします