キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
キャンディとテリィは多くの点で異なっていたが、いくつかの共通する特徴も持っていた。そのような共通する特徴の一つに頑固さがあった。頑固で強情な二人の人間が同じ屋根の下で暮らすとなれば、その二人の間にどれ程の愛情があろうとも、問題が起きるのは明らかだった。それ故に、夫とその父親との関係の修復を促すという最善の意図があったにせよ、キャンディは今や大きなリスクを抱えていると言ってよかった。
その晩テリィが仕事から帰ってくると、キャンディは公爵の話題に焦点を絞って出来る限りの説得をすることに決めた。しかし妻としての経験不足から、キャンディはその話題を持ち出す前に、夫の機嫌を伺うことを怠ってしまったのだった。
『リチャード三世』の稽古がその日に始まり、テリィは演じる役の心理を追及する困難な作業の真っただ中にいた。そのためテリィは、しばらくは誰にも邪魔されることなく長時間一人で役の勉強をせねばならず、今後の数週間は日常生活にも大きな支障が出ることになるだろう――と妻に伝えたのだった。それを聞いたキャンディは、勉強に集中するために夫が早々に書斎へと消えてしまうのを恐れて、夕食が終わると直ぐに公爵の話題に取り組むことにした。
「ねぇテリィ……お父さんのことを考えたりすることはないの?」 ミセス・オマリーはすでに帰宅し、二人で夕食後のお茶を飲みながらキャンディは思い切って聞いた。
「いや、一度もない」 テリィはとげとげしく答えた。初稽古というのはいつでも難儀なもので、テリィの気分はその晩すでに若干苛立っていたのだ。そんな状態の時に、父親のことなどは最も歓迎できない話題だった。
キャンディは、テリィが張り詰めた様子になってきたのを感じたが、この話題は別の機会まで待つべきだという内心の声に逆らって、当初の計画をそのまま押し通して続けた――
「本当に? 最後に会ってから、もう何年も経っていると感じることはないの?」 キャンディは、紅茶に入れる角砂糖をいくつかのらりくらりとした動作でつまみながら、その話題に固執してもう一度聞いた。
「一切ないね。互いのことに関心を持つには、おれたちはもうあまりに長いこと離れて暮らしているし、疎遠になっているからね」
テリィはこのように返事を返すと、紅茶を飲むことに集中した。しかし、その指は無意識にテーブルをコツコツと叩いていた。
「長いことって、どれくらい?」 キャンディはそれでもあきらめずに再度質問した。
「もちろん、おれがセントポール学院を去った時からだ。11年以上になる」 キャンディがこの話題に固執することに、すでに怒りが湧き上がってきているのを感じながら、テリィは答えた。
「それじゃあ、わたしたちが離れ離れでいたのとほぼ同じ期間なのね。それだけの長い時が過ぎてもわたしたちの仲が上手く行ったように、テリィとお父さんだってきっと……」
「比較する意味のないことだ!」 テリィはキャンディの言葉を途中で遮った。その声には明らかに激しい怒りが込められていた。「おれには忘れることも許すこともできないことが、おやじとの間にはあったんだ。あの人は、おれがまだほんの小さな子どもの頃に、ただ見捨てるためだけにおれを引き取った。ちゃんとした父親であれば決してしないようなことだ!」
「テリィだってほとんど何の説明もないまま、わたしをイギリスに置いて去ってしまったことがあるわ。そしてその後はわたしも、このニューヨークにあなたを置き去りにしたことがあるわ。それでも上手く行ったじゃない」 キャンディは、その声にテリィの怒りと同じ激しさを含ませて反論した。
「いい加減にしろ、キャンディ!」 テリィはナプキンをテーブルに投げつけて声を荒げた。「おれたちの関係と、おれとおやじの関係を比べようとするその考え自体が馬鹿げていると言っているんだ! おれたちが……きみとおれが互いの元を去った時には、それはいつだって、そうすることが相手にとって一番良いことだと思ったからだった。その判断がいくら間違っていたとしても、おれたちは寛容な心からそうしたんだ。それに引き替え、おやじには子どもを見捨てる理由などなかった……おれが、あの人の憎んでいる女の産んだ子どもだということ以外にはね」
「それが本当の理由だったと、どうしてわかるの? もしお父さんとちゃんと話をする機会を持てば……」
「止めろ、ターザンそばかす」 テリィは荒々しく言葉を遮ると、キャンディを責めるように問い詰めた――「きみが何をしようとしているのかわかったよ。きみは、おふくろとこの話をしたんだろ?」
「違うわ。お母さんとはこのことについて話してないわ」 キャンディも、怒りが込み上げて冷静でいられなくなっているのを感じながら言い返した。
「それじゃあ、きみは一体何がしたいんだ? おれたちはこれまでおやじの話をしたことがなかったし、それを今ここで始める理由も見当たらない。この話題はこれでお終いだ」 テリィは席から立ち上がってそう言い切ると、一人になるために書斎に向かおうとした。テリィには自分の怒りが爆発寸前だということがわかっていたので、そのような場合には一人になり、怒りが静まるのを待つのが得策だったのだ。しかし、キャンディは別の考えを持っていた。
「ねぇテリィ……もしわたしが、お父さんはこのニューヨークにいて、テリィに会いたがっていると言ったら、あなたは何と言う? それでもこの話題はこれでお終いにしてしまうの?」 キャンディは、テリィの関心をこの話題に引きつけるための、最後の頼みの綱を持ち出して呼び止めた。
「なるほど、それがこの会話の目的だったのか」 テリィの怒りはとうとう爆発した。「おやじがおれの留守の間にここへ来て、自分の弁護をするようにおれの妻を説得したというわけか。きみを使っておれを脅そうとするなんて、いかにもリチャード・グランチェスターがやりそうな陰険なやり方だぜ。あいつはちっとも変わっちゃいない! 今後あいつと話すことは二度と許さないからな、キャンディ」
「どうしてテリィはそうやって何でもひねくれて解釈して、物事を意固地に捻じ曲げて捉えるの?」 キャンディも椅子から立ち上がって言い返した。その顔は怒りで紅潮していた。「お父さんはあなたに会うためだけにはるばる大西洋を越えてきて、プライドを飲み込むと言っているのよ。それなのにあなたときたら、お父さんがあなたを脅そうとしているとしか思えないの? ……それからわたしが何をしようと、あなたにはそれを禁止することなどできないわ!」
「きみは、出会った頃のお節介な女の子のままなんだな。あいつがおふくろとおれに何をしたか知りもせずに……。それに、もしおれがあいつの言うことを聞くようなことがあれば、おれたち二人のことにだって何をしたかわからない。おれの人生にあいつを立ち入らせることなど絶対にあり得ない。知りもしないことに口を出すのはもう止めてくれないか、キャンディ」
「お父さんが不在で、あなたを情緒的に放置して傷つけたことを、わたしが理解できないほど頭の鈍い人間だとテリィは思ってるの? お父さんが、お母さんに対してもとても卑劣なことをしたのを知らないと思ってるの?」
「ほらみろ!」 テリィはキャンディを非難するように指を差しながら大きな声で言った。 「きみはおふくろとこの話をしていたのに、さっきは否定していたな!」
「そうね、お母さんはお父さんとの関係や、あなたが産まれた時のことや、あなたがグランチェスター家の跡取りとしてお父さんに引き取られたいきさつを話してくれたわ。でも、お父さんが手紙を送ってきたことについては何も言わなかったのよ」
「それでも、公爵がちゃんと教えてくれたんだろ? そうなんだろ、そばかすちゃん?」 キャンディにぶつける言葉の衝撃を強めようとするかのように、テリィは体を折り曲げて言い捨てた。
「どうしてそんな風に、まるでわたしがあなたを騙したみたいな言い方をするのよ、テリィ?」 キャンディはテリィを厳しく非難した。「テリィはまるで無茶苦茶よ。お父さんはもう一度あなたの人生を支配しようとしているわけじゃないわ。ほんとにもう! 何をそんなに恐れているの? お父さんは、ただあなたと面会したいだけなのよ。 少なくともお父さんが何を話したがっているのかだけでも、聞いてみようとは思えない?」
「無茶苦茶なのはきみの方だよ、キャンディ。きみはもうこの件に関して十分知っているようだから言うが、おれは去年の11月からずっと考えて、おやじとの関係の修復はしないと決めたんだ。おれには、きみがいつものようにお節介を焼くだろうとわかっていた。でも止めるんだ、キャンディ。おれは許さない。今回は駄目だ。この件に関しては……。ここは立ち入り禁止だ」
「立ち入り禁止?」
「そうだ!」
「それじゃあわたしの寝室も立ち入り禁止よ、あなた」
テリィはこの怒りの脅迫にびくっとした。
「そんなことしていいはずがないだろ、キャンディ。きみはおれの妻だぞ!」 テリィは傷つき激怒して大声で叫んだ。
「でも、だからといって、わたしがあなたに腹を立てている時でさえ、あなたの好きにさせなければならない訳ではないでしょう?」 キャンディは辛辣に言い返した。
「そうか、それがきみの最終的な言い分なんだな?」 テリィはまるで最後通告を出すかのように問い質した。「上等だよ、ミセス・グレアム。そっちがその気なら、こっちも好きなようにさせてもらうさ。今夜は劇場の楽屋で眠ることにする。きっと今夜だけにはならないと思うけどな!」
キャンディはテリィのこの発言に衝撃を受けたが、引き下がるどころか怒りが加速度的に増していった。
「いいわよ、行けばいいわ……でも、そこでわたしがあなたに戻って来てくれと泣きついてくるのを待っても無駄よ」
「そのうちわかるさ、マダム……そのうちね」
この最後の言葉を残してテリィは後ろを向き、コートを掴むとカッカしながらアパートを飛び出して行った。アパートに残された妻の方は、初めての夫婦喧嘩の苦い後味を噛みしめていた。

ひとたび怒りが燃え上がれば、そこには理性の入る余地などなくなるものだ。腹立たしさが判断力を曇らせ、自分が悪者にされたという感情だけが思考を支配してしまう。そしてそのような場合には、自己防衛の苦い思いが、愛が人の心に呼び覚ます無私の精神を蝕んでしまうのだ。口論の後テリィとキャンディは、それぞれが自分の感じる憤りと傷ついたプライドに自分自身を明け渡してしまった。二人はそれぞれ一晩中、口論の中で交わされた言葉を繰り返し思い出しては、悪いのは相手の方だという結論に達した。そして、傷ついた側として、許しを求めてくるのは相手の義務だと結論付けた。
男性にとっては、夫婦の寝室から締め出されること以上に傷つくことはなかったし、それと同じくらい、自分が侮辱されたことが未解決の状態で交わりを求められること以上に、女性を腹立たしくさせることはなかった。ある意味では、二人ともが怒りを感じるのは当たり前な状況ではあったが、若さと経験の浅さから、傷ついた感情を相手に伝え損ねていたことに気付くことができずにいた。
このようにしてその週末は、夫が何をしているのか一切わからないまま、キャンディは家に篭って反抗の中で過ごした。最初キャンディは、こちら側にこそ道理があるのを認めようとしない、テリィの頑固さに腹を立てていたが、その後は自分がどう扱われたかということに憤りを感じた。キャンディは、テリィが自分に彼の人生の一つの側面に関わることを禁じておきながら、寝室を共にすることを求めたことが信じられなかった。そして夫の沈黙と不在にさらに怒りを感じた後で、その数時間後にはテリィのことを心配し始め、最終的には会いたい気持ちが募っていった。この時点になると、キャンディは口論の内容をもう一度吟味して、自分が慎重さを欠いて行動したことを恐怖と共に認めた。この気づきは、怒りの感情よりもさらに心を蝕んだ。
片やテリィも同じような道程を辿り、その週末の間、自分を見失っていた。過去2年の間に、テリィは役の追求に没頭するために、一晩、あるいは週末を通して劇場に泊まったことは度々あった。しかし今回は、穏やかならぬ気持ちが心を占めて、役の勉強に集中することができなかった。テリィは自分自身の憤りと、ニコチンの禁断症状が脳に及ぼす影響に苛まれながら、まるで檻に閉じ込められたライオンのように、自分の楽屋で何時間も過ごした。その憤りの中で、テリィは怒りの真の原因を見極めることができずにいた。思考は同じところをグルグルと回っては、キャンディが自分と寝室を共にするのを拒絶したという一点へといつも戻ってきた。男としてのプライドがあまりにも傷ついていたために、テリィは三日三晩の間、《父親に対する憤り》という、本来の怒りの原因が見えなくなっていたのだ。
1月28日の朝がやってくると、テリィは前年までの誕生日と同様に――この4日間、楽屋の長椅子で寝たことを考慮すると、もしかしたらこれまで以上に――惨めな気持ちを抱えて目を覚ました。その日は水曜日で、テリィは陰鬱で不快な気持ちのまま、カントリークラブに乗馬と稽古前のシャワーを浴びに行った。しかし、体を動かしてみたところで気分はちっとも晴れず、何人かの顔見知りにロッカールームで声をかけられ結婚したことを祝福されると、ことさら気が滅入った。どこへ行こうとも、キャンディのことを頭から追い出すことができなかった。
テリィは目の前の朝食にはほとんど口をつけずに、頭の中で起きたことを再考してみた。すると、キャンディを求める思いが増していることに影響されてか、この数日の内で初めて、テリィは自分の過ちを認識し始めた。しかしその日は稽古の重圧で、そのことをじっくり考える時間がほとんど取れず、夕食を済ませて誰もいない劇場に戻って来た時になってやっと、自分の犯した過ちの重さを両肩にずっしり感じたのだった。するとテリィは、父親の話題はキャンディには立ち入り禁止だと怒鳴りつけた時のことを、突如として思い出した。そして、その時にキャンディが見せた怒りと傷ついた表情を思い出すと、テリィはさながら悪夢を見ているような気持ちになった。キャンディは、まるで殴られでもしたような顔をしていたのだ。その記憶に突き動かされたようにテリィは椅子から立ち上がると、ジャケットとコートを掴んで楽屋を飛び出し、アパートへと向かった。テリィには、自分が間違っていたことを認める心積もりができていた。
テリィがアパートに帰り着くと、折り悪く、そこにはミセス・オマリーしかいなかった。ミセス・オマリーは仕事を終えて帰り支度をしていたが、キャンディは外出していて、劇場で夫と会うから夕食には戻らないという電話がちょうど数分前にあったことをテリィに伝えた。
ミセス・オマリーからの情報は、テリィにとってこの世の全てに匹敵するものだった。テリィはほとんど運転手の首を絞めるようにして、劇場までタクシーを飛ばしたと言っても言い過ぎではないだろう。劇場に着くと、そこには自分の車が停まっていて、車の中ではロベルトが静かに新聞を読んでいた。これからアパートに戻るまでには、キャンディとの長い話が必要となるだろうと予想して、テリィはロベルトを家に帰した。そして直ぐに自分の楽屋へと向かったが、心臓の鼓動が大きく脈打ち、こめかみにまでその鼓動を感じていた。
楽屋のドアを開け、緑色のドレスに身を包んだキャンディの細身の姿を目にすると、テリィの瞳は大きく見開いた。キャンディはコートを腕に掛けたままで部屋の真ん中に立っていて、目の周りのクマが、睡眠を十分とっていないのを物語っていた。それでもテリィが部屋に入ってくると、キャンディの顔は再び輝きを取り戻した。
「わたしを許して!」
「おれを許してくれ!」
――二人が同時にそう言うと、テリィはキャンディを素早く腕に抱きしめて、渇望と後悔の念の入り交じった情熱的な口づけをした。唇を貪るように何度も合わせると、二人の涙が混ざったしょっぱい味がした。その日一日中、テリィに何を言おうかと考えていたキャンディは、テリィの唇が激しい強さで自分の唇を繰り返し撫でる感覚に、頭の中にあった言葉をすべて忘れてしまった。その日の朝にキャンディは、テリィに同じように情熱的な口づけをされる夢を見て目覚めたのだが、それでも夢の中では、二人とも今のように震えてはいなかった。
それはまるで、離れ離れだった長い年月の苦しみが十倍にも増したために、肌と肌を激しくぶつけ合うことでその痛みを和らげようとしているかのようだった。二人はこれまで経験したことのないような欲求に突き動かされ、無言のまま、明らかにある一つの目的に向かって動いていた。キャンディの体は壁と、背の高いテリィの体の間に挟まれ、二人は向き合って立っていた。服を着たままでキャンディが震える足を広げると、二人はにわかに、しかし熱烈に愛し合った。その行為の一つ一つの動きの中に、二人は今一度、苦しかった思いを吐き出して心の悪魔を追い払い、肉体をなだめて魂を癒した。
二人には、その時ある一線を越えようとしているのはわかっていたけれど、そこには肉体に溺れる以上の意味があった。二人はただ一つになるために、自発的に自制心を放棄することを、無言のままに確認し合ったのだ。すべてが終わって欲望の熱が引いていくと、二人の感情は互いを優しく思いやる気持ちへと変わって行った。二人は長椅子に一緒に横たわり、乱れた脈を整えていた。
「おれは、きみに許しを請おうとアパートに戻ったんだ」 心地よい余韻の波に浸りながら、テリィは最初にそう言った。
「わたしも同じことをしに、ここに来たのよ」 キャンディは、テリィの顎の割れ目を人差し指で軽くなぞりながら、笑顔で告白した。
「でも、あれはきみのせいじゃなかった……きみは良かれと思ってしたことだ」
「最善の意図でやったことではあるのよ、テリィ。でも、説得の仕方にかなり問題があったわ」 キャンディは、悲しそうな笑顔を見せながら自分の非を認めた。
「おれがあれほど身構えた反応をしていなければ、きみの言い分に道理を見いだすことができたかもしれない」
キャンディは、今の発言をよく理解しようとして、テリィのことをじっと見つめた。今宵は、ただ夫との仲を修復することだけを求めていたのに、妻である自分の方に正当性があったとテリィが認めていることが、にわかには信じられなかった。しかしながらキャンディは、あの口論の日以来一人で過ごした孤独な夜から、正しい側であるよりも、愛されることの方がもっと大切だということを学んでいた。
「今は、お父さんの問題はそっとしておきたいの。テリィが自分で解決することが一番だもの」
「それじゃあ、もしおれが、この問題に関してきみを蚊帳の外に置いておきたくないと言ったら? もし、おれには何をどうすればいいのかさっぱりわからないから、きみの助けが必要だと言ったら?」
「その時は、喜んであなたの助けになるつもりよ。でも、もしまたわたしの助けは不要だと思ったら、お願いだから、自分で解決したいということを率直に伝えてね」
「そうするよ。でも、きみはそれを受け入れられるの?」
「あなたの人生から、わたしが理由もなしに締め出されてしまったみたいに感じないような言葉で伝えてさえくれたら、受け入れられると思うわよ」 キャンディは遠まわしに言った。
「この問題は立ち入り禁止だとおれが言ったことが、きみを傷つけたんだろ?」 テリィは推測して聞いた。
キャンディは、頭をテリィの肩にもたせかけながら静かに認めた。
「そうね……でも、それについてはあまり悪かったと思わないで、テリィ。わたしだって、最低なやり方で仕返しをしたんだもの。わたしもあなたを傷つけてしまったわよね?」
「おれにはきみが必要なんだ……おれのそばに……おれの眠るベッドに……おれの腕の中に……一晩たりとも欠かさず。この数日は、きみがいなくておれはほんとうに惨めな思いをしていたよ」
テリィの告白にキャンディの心はしぼみ、突如として再び後悔の念に駆られた。
「今日はテリィのお誕生日だったのに……」 キャンディは落ち込んだ声で言った。「二人で一緒に賑やかなお祝いをして、去年までとは違うお誕生日にしたかったのに……。わたしが愚かにもあんなことを……」
「もう済んだことは忘れるんだ、ラヴ(愛しい人)」 テリィはキャンディのおでこにキスをしながら言葉を遮った。「この無意味なケンカから、学んだことだけを覚えておこう」
それでもまだキャンディの心が沈んでいるのを察すると、一瞬ためらった後でテリィは言葉を付け足した――「それに、今日の誕生日は結果的にはそんなに悪くなかったぜ」
「どうしてそんなことが言えるのよ? まるで大晦日の夜みたいに、すべてが台無しだったじゃない!」 キャンディは口をとがらせて言った。
「きみが言うのとは反対に、あの大晦日は、きみをおれのものにした、おれの人生の中の最も輝かしい夜として、おれの記憶の中にいつまでも刻まれるだろう。そして今夜は、このおれの誕生日に、きみはおれの昔からの夢の一つを現実にしてプレゼントしてくれたんだ」
キャンディは説明を求めて顔をしかめた。テリィは、キャンディにはまだ早すぎる話題を始めてしまったかもしれないと考えて、再び一瞬ためらった。それでも、二人がすでに十分に、肉体の欲求の世界を奥深くまで進んできたことを考えて、単刀直入に話すことにした。
「おれにとってのこの神聖な場所できみと愛し合うことは、長年の間おれが大切にしてきた空想だった。前にも楽屋に泊まったことがあると言ったのは嘘じゃない。自分の人生にうんざりすると、おれは一夜を過ごしにここへ来て、この完全な静寂の中で、きみの思い出を呼び覚ましては、まさにその場所で、きみを……きみの体を……きみの魂をおれのものにすることを空想していた。空想は、時には甘くて深く、時には今日のように激しく燃えるようなものもあった」
「あなたは確かに変わった想像力を持っているわね、テリィ」 キャンディは、テリィの赤裸々な告白に、顔が赤らんでくるのを止めることができなかった。
「その辺の奴らと何にも変わらないぜ、ハニー」 キャンディの発言にテリィは笑った。「ほんの少年の頃から、男ってのはたいてい女の人をそんな風に見ているものだからね」
キャンディは、呆気にとられてまばたきをした。
「少年の頃から? じゃあ……学院にいた頃も、わたしのことを……そういう風に見ていたの?」 衝撃を受けてキャンディは聞いた。
「もちろん! ずっとそうだったぜ、そばかすちゃん」 最高にいたずらっぽい笑顔を顔に浮かべてテリィは答えた。「ホントさ、キャンディ。おれのきみへの愛は、一度たりともプラトニックだったことなんてなかったからね」
キャンディは半ばうろたえ、半ばどきどきしながら黙って聞いていた。男性の心理を思いがけず垣間見たことが、キャンディにとって男の人を理解する突破口となった。すると、これまでの肉体的な愛の行為を思い出し、突如としてとんでもない疑問が頭に浮かんだ。自分でも驚いたことに、キャンディは勇気を出してその疑問を口にした。
「他にはどんな空想をしたの?」
テリィには、キャンディがこの話題に興味を示していることがにわかには信じられなかったが、二人の親密さを増すための、新たなる扉を開く機会を歓迎した。
「それについては本が一冊書けるほどだけど……、きみは本当にもっと知りたいの?」 その声に明らかにいかがわしさを含ませて、テリィは聞いた。
「ただちょっと……興味が……ある……から……」 キャンディは唇をかみながら白状した。
「それだよ! そういうことは、不用意にやっちゃだめなんだ」 テリィはキャンディの口元を指さして言った。
「何のこと?」
「そんな風に唇をかむことだよ。その動作が男心をどう刺激するか、きみにはわかっていないんだ」 テリィは指でキャンディの唇を撫でながら、臆面もなく言いのけた――「それじゃあ、おれの頭の中にある、きみに関する空想を全部話すところから始めるけど、その前に、きみはおれに一つ約束をしなけりゃならないな」
「打ち明け話の代償に、あなたが何かを要求しているように感じるのは何故かしら?」 キャンディは、テリィのずうずうしい口調に対して、同じような不遜なもの言いで返した。
「当たり前だろ。この世界では、すべてのものに値段があるんだぜ、奥さん」
「わかったわよ。あなたの空想の世界を垣間見るための金額を言ってみて」 キャンディはトゲのある口調で挑んだ。
「その空想を現実にすること」

それから一週間後、事前の取り決めに従って、遂にリチャード・グランチェスター公爵が息子を訪問しにやって来た。二人は夕食後に、テリィの家で会うことで合意していた。プライバシーを確保するために、雇用人たちはすでに自宅に帰されていたので、キャンディ自らが玄関で義父を出迎えた。そこで慣例通りの挨拶を交わしてから、キャンディはテリィが待つ書斎へと公爵を案内した。
テリィと公爵を書斎に残して部屋を出ると、キャンディは居間に駆け込んで窓を開け、通りを見下ろした。案の定、前回の時と同じように、公爵の運転手と秘書が車に残って待機していた。しかし前回と違うのは、日はすでに地平線の彼方に沈み、気温は低くなっていたことだった。いたわり深い心に従って、キャンディは階段を降りて道を渡ると、その二人の男性をお茶に招待した。
その招待に二人の男性は最初面食らい、しばらく当惑したままで互いに顔を見合わせていた。そして、秘書がようやく返事を返した――
「奥様、それは適当でないと存じます」
「まずはお互いに自己紹介をしましょうよ。そうすれば、気まずさも薄らぐと思うわ。紳士方、どうか車から降りて頂けません?」
当惑した気持ちと、《紳士方》と呼ばれたことへの驚きを感じながら、二人はキャンディの言葉に従った。
「これでいいわ」 三人が向かい合った形になると、キャンディは手を差し出して自己紹介を始めた――「ほとんどの人は、わたしの名前をキャンディス・グレアムだと思っていますけど、お二人には安心して本当の名前で自己紹介できます――キャンディス・ホワイト・グランチェスターです」
「エドワード・パーキンスと申します、貴婦人様」 キャンディの温かみのある握手にまだ驚きを感じながら、秘書が自己紹介した。
「ジョン・サミュエルズでございます、貴婦人様」 運転手も秘書同様に、この状況に当惑しながら言った。
キャンディは二人のうやうやしさに若干の楽しみを見出し、自分に対して使われた敬称のことは気にしないことにした。握手を交わした後でキャンディはそのまま二人をアパートへと案内し、ダイニングルームに招き入れてから約束通りお茶を出した。
雇用人用の部屋以外の場所でグランチェスター家の人間にお茶に招待されることは、この二人の男性にとって普通のことではなかった。しかも、そのグランチェスター家の人間が自分たちと同じテーブルに座ってお茶を楽しんでいる状況は、この世の終わりと言ってよかった。
「パーキンスさんは、もう何年くらい公爵の元で働いているんですか?」 二人の前に座ってから、キャンディは会話のきっかけとして気軽に質問した。
強靭な体つきをした、髪がほとんど禿げあがった50代前半のパーキンスは、信じられない思いでキャンディを見た。グランチェスター家の人間からは、かろうじて苗字で呼ばれることはあっても、「さん」付けで呼ばれたことなど一度もなかったのだ。
「20年でございます、奥様」 おそらくアメリカでは、雇用人がこのような扱いを受けるのは普通なのだろうと考えて、パーキンスは遠慮気味にそう答えながら心の中で思った――(アメリカ人というのは奇妙なものだ)
「それはとても長い年月ね、パーキンスさん。そちらのサミュエルズさんは、何年くらい働いているんですか?」 キャンディは雑談を続けた。
「25年でございます、奥様」 40才代後半の、表情に富んだ目をしたサミュエルズが答えた。
「ということは、お二人とも、わたしの夫の子供の頃を知っているのね。彼はいたずらっ子でしたか?」 キャンディは興味を持って聞いた。
「侯爵様でございますか?」 外で凍えていた体をお茶が温めるにつれ、心地悪さが薄れていくのを感じながらパーキンスが聞いた。「そのご質問ですが、わたくしがグランチェスター公爵閣下の元で働き始めたときには、侯爵様はもうすでに学院にお入りになられていましたので、あまりお目にかかることはございませんでした。しかし何度かお目にかかった時の印象は、とても物静かなお子さまであったと覚えております」
キャンディは、テリィに付けられた敬称に驚いていたが、そのことは後で夫に話すとして、今は脇に置くことにした。
「サミュエルズさんはもう少し覚えているのでしょう?」 キャンディは運転手に問いかけた。
「はい、覚えております。公爵閣下のお父上様がお亡くなりになって、イギリスにお戻りになられた年に雇っていただきましたので……。侯爵様も、まだひょろひょろとした少年だった頃は、他の子たちと同じような普通のお子さまでございました。こう言っては何ですが、後々口数が減ってしまわれたのでございます。ご入学された学院の、厳しい校風の影響だったのではないかと存じます」
「興味深いお話しだわ」 キャンディは感想を述べた。そして公爵とその息子が書斎で話をする間、その後もキャンディのリードで三人の会話は続いた。

*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします















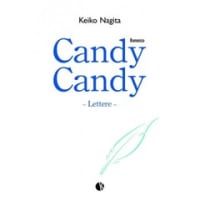









婚約の報告をした時にも、ポニー先生が二人がこうなることは予想していましたね。テリィの妄想……実際は空想でなくて妄想ですよね……そちらの言葉を使って訳そうかとも思いましたが、きれいな方の言葉を選びました
どうなることかと思いましたが、喧嘩したまま続く、じゃなくてよかったです~
「運転手の首を絞めそうに急がせた?」のには笑ってしまいました。
いかにもやりそうで
一人になれる楽屋で、キャンディのことを考える日々があったんでしょうね。
学院でも?
思春期男子ですからね~
その頃のキャンディなら間違いなくひっぱたいてますね。
使用人の方たちとも仲良くなっちゃうのは、キャンディならではですね。
色々なエピソードが、嬉しすぎますね
学院時代の言い争いを彷彿とさせるような、初めての夫婦げんかですね~
キャンディの「あなたは私を学院に、私はあなたをNYに置き去りにした」の言葉が心に沁みました。
それと「侯爵様」、いいですねぇ(^_^) 私には、テリィは“腐っても貴族”“骨の髄から貴族”というイメージが強いので、何気に嬉しかったりします。
そしてテリィの妄想…
次回更新楽しみに待ってます!
テリィは自分が幸せになれると思っていなかったみたいなので、妄想の世界の中だけでもキャンディと一つになっていたんですね~。テリィ……
もも様
今回のテリィの怒りの様子は、学院でキャンディにエレノアの写真を見られてしまった時の荒々しさを感じますね。お父さんのことはまだ未処理だから、同じような反応をしてしまったのでしょう……きっと。
この作者さんも、ももさん同様にテリィの出自にはこだわりがあるようで、着ているものや行動の中に、隠しても隠しきれない、否定しても否定しきれないテリィの貴族趣味がところどころ表現されております。テリィ萌えのツボでしょうか
真剣夫婦喧嘩シーンだというのに、テリィの激昂が学生時代と変わってなくてほのぼのしちゃいました。
あぁテリィだ!と懐かしくて嬉しかったです。
キャンディは大人になりましたね。でも強情なところはやっぱり変わってなくて(^^)
仲直りの方法がバカップル仕様なんですけど、何故この二人だとロマンティックなんでしょう…ひとえに作者さまと主さまの綴りの美しさだと思います。
そしてテリィの若者らしい想像力に吹き出してしまいましたが、彼は肉食だからセクシーなんでしょうね(^w^)言い寄る女性には困らなかったでしょうに、長きに渡って空想の相手にはキャンディしか有り得なかった所がまたテリィで嬉しくなっちゃいます。
お忙しいところ、いつも素敵な時間を頂いて感謝しています。
また更新楽しみにしていますが、時節柄ご自愛下さいませ。
夫婦になった2人が心も体も正に体当たりでぶつかって行く過程で相手の反応に幾度か「にわかに信じられない」という気持ちになっている所が何だか新婚さんらしくて初々しいですね。そんな事を重ねて互いの息を合わせていくんでしょうね~。
テリィの空想話、なんだかリアルで思わず頭の中のアニメ・テリィが実写に替わってしまいました(爆!)因みに私の妄想ではもしテリィが実在したら・・・シャープなキアヌ・リーブスにケビン・コスナーの甘さを加えたような・・・結構イケてる妄想じゃないって思うんだけど、皆さんのより素敵な妄想の、いや空想の、お邪魔をしてたらゴメンナサイ!
ちぇり様の言う通り、テリィは肉食だからセクシーなんですよね~。童話の王子様では肉欲の世界には入って来れませんの、大人の恋愛の相手は、やはりテリィしかいないのです
てぃえんてぃえん様
ブログ主も「to be continued」とタイプせずに、延々と皆さまに翻訳をお届けできればどれほど素晴らしいことかと思います……です。
てぃえんてぃえん様のテリィ像、なんとなくわかる気がします。海外ファンの間では、ベン・バーンズが最近のテリィ実写版のファイナルアンサーになっておりますが……。ブログ主の永遠のアイドルは80年~90年の頃のマット・ディロンなので、テリィの荒々しいと同時にやんちゃでおちゃめな部分はその辺を重ねております……
他の読者様の心の中のテリィも知りたいですね
私は、今はおじさんになってしまったけれど若い頃のレイフファインズですね~(顔はそこまで似てないかも+テリィはもっと敏捷で引き締まってるイメージですが)大人の色香というか…スーツ着た時のセクシー度にテリィを重ねてしまいます。ハムレットで賞を取った時の粋なタキシード姿はかなりテリィとかぶりました(^_^)
皆さんそれぞれのテリィイメージが聞けて楽しいです。
他にどんな名前が出てくるんでしょうか…
ここ数日息子の高校受験でバタバタしていて、1週間ぶりにこちらを覗いたら何と更新されているではありませんか!何かと気忙しく苛々する毎日、こちらの小説に癒されています。ブログ主様ありがとうございます。
キャンディとテリィ、喧嘩できるのも相手がいてこそ、一緒になれたからこそですもんね。二人がまだ少年少女な部分と大人な関係と両方なのでドキドキします。テリィが感情をストレートにぶつけられる相手はキャンディだけだし、今まで辛く寂しい日々に耐えてきた分、少しくらい妄想、我儘言っても許してあげたいという気持ちにさせられます。
ところで私のテリィのイメージは少年時代のエドワードファーロングです。(あくまで少年時代の。です)ターミネーター2でのバイクを飛ばすシーンや母親への屈折した想い、憂いを帯びた美少年ぶりがテリィと重なるのです。でもキアヌリーブスやマットディロンもイメージ候補で同じ方がいて嬉しくなりました!