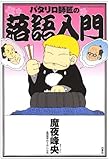映画を見たあとにすぐ買って、一気に読んでしまった。
やはりおもしろかった。
これは自分の娘を殺された女教師が、犯人である少年AとBに、
ある復讐をした、と告白するところからはじまるサイコミステリー。
被害者は加害者に、加害者は被害者にと入り組んでいく、真っ黒な物語なのである。
小説のほうは、ひとりひとりの告白ごとに章が分かれているので、
章が進むごとに違った「真実」が浮かび上がってくるという構造が、
よりくっきりとしている。
もしかしたら有吉佐和子の「悪女について」や、映画「羅生門」のように、
「人の主観の頼りなさ」を裏テーマにしていたのかもしれないが、
でもここには、そこまで事件そのものに対する認識の違いがあるわけではない。
ひとりひとりがどのように追い詰められ、どのようにその「行為」に至ったかを、
それぞれの登場人物なりの手法で「告白」するという流れのなかで、
それぞれの人物のキャラクターや心理状態が、次第にくっきりと見えてくる。
教師の森口と、少年Aである渡辺修哉の告白は、とても論理的で淡々としているのに比べ、
少年Bとその母親の告白は、どんどんくずれていき、支離滅裂になっていく。
まるで狂っていく人間の脳内観察をしているかのようだ。
つまり、そのしつこいほど緻密なモノローグの応酬が、
エンターテイメント(こういう小説にこの言葉を使うのは勇気がいるけど)になっているのだ。
どんな犯罪にも、どんな狂気にも、その人なりの理由がある。
人には人それぞれの真実があって、それはかくも自分勝手で残酷で、
そんな無限の真実がぶつかりあいながら社会は動いている。
いじめをする子供たちには、いじめる側の「真実」が、
殺人者には殺人者なりの「真実」が。
そして、こういう種類の物語には、大抵あるべき「正義」や「救い」が、ここにはない。
教訓めいた結論も、倫理的なテーマの提示もなく、ただ残酷なまでに物語はばっさりと終わる。
(映画にはオリジナルの一言が付け加えられている。これに関しては、また後日書こうと思う)
それによって読者は、ここになんらかの意味付けやテーマ設定を、自分でせざるを得なくなるのだ。
これが、この物語の最大の魅力であり、
そして一部の人にとっては、どうしても受け入れられない理由になっていると思う。
つまりこれは、読む人の気持ちや状況によって、すこしずつ書き換えられる、
読者参加型ストーリーなのである。
映画でもその性質は受け継がれ、むしろ監督の意図によって増幅させられている。
映画の話をしてたとき、私の友人は、
木村佳乃演じるモンスターペアレントのことを
「かわいそうに。一生懸命、子供を愛してるだけなのに」
と言っていた。
私にとっては、あの母親があのなかではいちばん共感しがたく、最低最悪の登場人物だったので、
ものの見方というのは人によってこうも違うものかと愕然とした。
比較的気の合う映画友達でさえ、そうである。
(補足すると、彼は最近、子供が生まれたばかりなのだ。)
さらにひとつ思うことは、あまりこれを深くとらえると迷宮にはまるかもしれない。
作者は、少年犯罪に対して思うことはあるのだろうが、
どこまで強い正義感でこの物語を書いたかどうかは、あやしいものがある。
前述したように、これは、さまざまな人間の脳内を緻密に書き分けたエンターテイメントであり、
答えがどこかにあると思ってはいけない。答えは自分のなかにしかない。
それが、原作を読んでやっとわかった私なりの「告白」のとらえかたである。
そんなわけで、「告白」ハマっています。
映画のことも、そのうちもういちど書こうと思います。