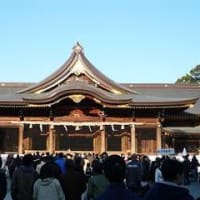チベット問題を理解する際に、「国民国家」の概念を持ち出すとわかりやすい。
近代以前の中国王朝とチベットの関係は、軍事的な保護者と宗教者との関係であった。皇帝がチベット仏教を信じていた元や清の時代は特に、チベットは信仰の「聖地」として尊重された。チベット関係の文献を読むと、中国とチベットが対等だったかのような書き方をしているものが多いが、これははっきり言って不正確である。軍事的には庇護関係にあり、宗教的には師弟関係にあったと理解するほうが正しい。
国民国家では、軍事的には服属しているが宗教的には上位であるという、こういう関係はなかなか通用しない。例えば国民国家に不可欠である普通教育制度を思い起こしてもらえればいい。そこでは、国家に属する「国民」が平等に同じテキストを使って同じ言葉で学ばされ、その内容も実用的である。小学校に通ってしまえば、幼少の頃から仏教の経典を一心不乱に勉強する、ということは当然ながら難しくなり、そうして仏教者の教育的な価値は減ってしまうことになる。
軍隊もそうである。国民国家の軍隊は、徴兵制にせよ志願制にせよ、国家に属する平等な「国民」によって構成される軍隊であることが大前提である。別の国家に守ってもらうなどということは、別の国家の「国民」に同化してしまうことを意味し、国家の独立性も損なわれることになる。
なにより国民国家の国際社会のシステムが、宗教文化的には独立して軍事的には中国の庇護を受けるという、従来のチベットのようなあり方を許さない。19世紀末のイギリスは、中国を飛び越えて直接にチベットの外交交渉が出来たが、中国王朝が「反抗しない限り干渉しない」という原則をとっていたからで、チベットが「独立国」であったからではない。
その後イギリスが干渉の度合いを強めると、軍事的な庇護者としての地位を失うという危機感を強めた中国が反発しはじめ、イギリスに対抗するためには国民国家の国際社会に参画し、チベットを全面的に統合しなければならくなくなった。これが今、「侵略」と非難されている事態だと解釈したほうがよい。本当は19世紀以前の、「反抗しなければ何やっても自由」というあり方が中国にとっても理想なのだが国民国家の国際社会はそれ許さないのである。国際社会から見れば、「反抗しなければ」というのは独立性を許さないと同義であって、そのような国際社会の認識を受け入れたチベット人も「独立していない」という不満を強めていく。「チベット独立」を最も強く掲げたのは、1920年代の親イギリスのダライラマ13世の政権においてであり、国民国家の国際社会に無関心な昔ながらの寺院勢力は独立にほとんど無関心であった。後者の勢力がパンチェンラマに結集し、イギリス=インドに親しいダライラマに対して中国と接近したことが、現在に至るまでのチベット問題に尾をひいている。
チベット問題などを見ると、20世紀末に流行した多文化主義という思想の無力さを痛感する。西側社会は民族文化の自治や多様性を認めろと軽く言ってしまうが、アメリカ社会などにおける文化的な多様性というのは、領土や血のつながりに根ざしたものではなく、あくまでアイデンティティの問題が中心である。多文化主義は、アイデンティティの問題以外は、他の「国民」とそれほど違いのない生活水準や教育水準を送っており、またマイノリティもそう望んでいること、そして政教分離なども大前提である。経済的な後進地域で「政教一致」の社会であるチベットに、多文化主義がおよそ当てはまらないことは言うまでもない。多文化主義というのは、あくまで成熟した国民国家社会の思想である。
「チベット独立」というのも、全面的に反対はしないが、四川省や青海省などの「外チベット」のチベット人を分断し、彼らをさらなるマイノリティへと転落させてしまう。独立した民族国家のなかで少数民族が抑圧されるという問題は、ユーゴスラビアでも経験していることである。また現在の国際社会は(特に日本は!)、もちろん中国への遠慮であろうが、チベット問題への関与にそれほど積極的ではないし、ダライラマ自身も独立を否定している。「独立」は現実的な選択肢として有り得ないと考えたほうがいい。
中国政府の関心は、「とにかく反抗しなければいい」のであり、政治的な安定を確保できればチベットの宗教文化などは別にどうでもいいことなのだ。チベット社会も、半ばそういう「無関心」の扱いを望んでいるところもある。しかし、「とにかく反抗しなければいい」という態度による統治は、国民国家という社会制度では有り得ないのである。伝統社会の「反抗」は単純に「刃を向ける」ということを意味したのだが、国民国家における「反抗」は普通教育制度のカリキュラムや、国家の定めた法律、税制度や経済制度などに対する異論も含まれてしまう。チベット社会の宗教的慣習に合わない教育や法律への意義申し立ては、中国政府から見れば「反抗」そのものである。
特に2000年代の「西部大開発」というプロジェクトが、かえって「反抗」の文脈をますます拡大しているところがある。「国際競争」の中で経済成長を維持するための資源確保が喫緊の課題である中国は、チベットやウィグルの資源に目を付けると同時に、鉄道などの大規模なインフラ整備によって民族問題を一挙に解決しようとした。少数民族が同じ経済活動のインフラに入るようなれば、自ずと「中国人」意識も強まることを政府は期待したのである。ところが結果は期待したものとは逆になった。確かに、これはチベットにも「お金が落ちる」ようになったのだが、当然ながらそれを専ら享受するのは資本力を有する中国人である。増えたとは言え、チベット自治区における中国人の比率は1割以下であり、チベット人は中国人を「少数派のくせに経済を圧倒的に支配している」として、反感をますます強めていくことになった。
その意味でこの問題は、現在の世界を席巻する新自由主義的な経済システムとの関連で考えたほうがいいかもしれない。普通の「中国人」でも生活に困窮している人は膨大であり、それはチベット人の状況と大して変わりないはずだが、「民族」の旗を掲げることができないので強い声を挙げることができないのである。中国政府が最も恐れているのは、少数民族と貧困層が政権および市場経済批判で「共闘」してしまうことであり、私は中国政府があそこまで強硬な態度に出ている理由はむしろここにあると推測している。もっとも、もともと共産党というのはこの「抑圧された民族と労働者の連帯」を目指していたはずのだが・・・・。
近代以前の中国王朝とチベットの関係は、軍事的な保護者と宗教者との関係であった。皇帝がチベット仏教を信じていた元や清の時代は特に、チベットは信仰の「聖地」として尊重された。チベット関係の文献を読むと、中国とチベットが対等だったかのような書き方をしているものが多いが、これははっきり言って不正確である。軍事的には庇護関係にあり、宗教的には師弟関係にあったと理解するほうが正しい。
国民国家では、軍事的には服属しているが宗教的には上位であるという、こういう関係はなかなか通用しない。例えば国民国家に不可欠である普通教育制度を思い起こしてもらえればいい。そこでは、国家に属する「国民」が平等に同じテキストを使って同じ言葉で学ばされ、その内容も実用的である。小学校に通ってしまえば、幼少の頃から仏教の経典を一心不乱に勉強する、ということは当然ながら難しくなり、そうして仏教者の教育的な価値は減ってしまうことになる。
軍隊もそうである。国民国家の軍隊は、徴兵制にせよ志願制にせよ、国家に属する平等な「国民」によって構成される軍隊であることが大前提である。別の国家に守ってもらうなどということは、別の国家の「国民」に同化してしまうことを意味し、国家の独立性も損なわれることになる。
なにより国民国家の国際社会のシステムが、宗教文化的には独立して軍事的には中国の庇護を受けるという、従来のチベットのようなあり方を許さない。19世紀末のイギリスは、中国を飛び越えて直接にチベットの外交交渉が出来たが、中国王朝が「反抗しない限り干渉しない」という原則をとっていたからで、チベットが「独立国」であったからではない。
その後イギリスが干渉の度合いを強めると、軍事的な庇護者としての地位を失うという危機感を強めた中国が反発しはじめ、イギリスに対抗するためには国民国家の国際社会に参画し、チベットを全面的に統合しなければならくなくなった。これが今、「侵略」と非難されている事態だと解釈したほうがよい。本当は19世紀以前の、「反抗しなければ何やっても自由」というあり方が中国にとっても理想なのだが国民国家の国際社会はそれ許さないのである。国際社会から見れば、「反抗しなければ」というのは独立性を許さないと同義であって、そのような国際社会の認識を受け入れたチベット人も「独立していない」という不満を強めていく。「チベット独立」を最も強く掲げたのは、1920年代の親イギリスのダライラマ13世の政権においてであり、国民国家の国際社会に無関心な昔ながらの寺院勢力は独立にほとんど無関心であった。後者の勢力がパンチェンラマに結集し、イギリス=インドに親しいダライラマに対して中国と接近したことが、現在に至るまでのチベット問題に尾をひいている。
チベット問題などを見ると、20世紀末に流行した多文化主義という思想の無力さを痛感する。西側社会は民族文化の自治や多様性を認めろと軽く言ってしまうが、アメリカ社会などにおける文化的な多様性というのは、領土や血のつながりに根ざしたものではなく、あくまでアイデンティティの問題が中心である。多文化主義は、アイデンティティの問題以外は、他の「国民」とそれほど違いのない生活水準や教育水準を送っており、またマイノリティもそう望んでいること、そして政教分離なども大前提である。経済的な後進地域で「政教一致」の社会であるチベットに、多文化主義がおよそ当てはまらないことは言うまでもない。多文化主義というのは、あくまで成熟した国民国家社会の思想である。
「チベット独立」というのも、全面的に反対はしないが、四川省や青海省などの「外チベット」のチベット人を分断し、彼らをさらなるマイノリティへと転落させてしまう。独立した民族国家のなかで少数民族が抑圧されるという問題は、ユーゴスラビアでも経験していることである。また現在の国際社会は(特に日本は!)、もちろん中国への遠慮であろうが、チベット問題への関与にそれほど積極的ではないし、ダライラマ自身も独立を否定している。「独立」は現実的な選択肢として有り得ないと考えたほうがいい。
中国政府の関心は、「とにかく反抗しなければいい」のであり、政治的な安定を確保できればチベットの宗教文化などは別にどうでもいいことなのだ。チベット社会も、半ばそういう「無関心」の扱いを望んでいるところもある。しかし、「とにかく反抗しなければいい」という態度による統治は、国民国家という社会制度では有り得ないのである。伝統社会の「反抗」は単純に「刃を向ける」ということを意味したのだが、国民国家における「反抗」は普通教育制度のカリキュラムや、国家の定めた法律、税制度や経済制度などに対する異論も含まれてしまう。チベット社会の宗教的慣習に合わない教育や法律への意義申し立ては、中国政府から見れば「反抗」そのものである。
特に2000年代の「西部大開発」というプロジェクトが、かえって「反抗」の文脈をますます拡大しているところがある。「国際競争」の中で経済成長を維持するための資源確保が喫緊の課題である中国は、チベットやウィグルの資源に目を付けると同時に、鉄道などの大規模なインフラ整備によって民族問題を一挙に解決しようとした。少数民族が同じ経済活動のインフラに入るようなれば、自ずと「中国人」意識も強まることを政府は期待したのである。ところが結果は期待したものとは逆になった。確かに、これはチベットにも「お金が落ちる」ようになったのだが、当然ながらそれを専ら享受するのは資本力を有する中国人である。増えたとは言え、チベット自治区における中国人の比率は1割以下であり、チベット人は中国人を「少数派のくせに経済を圧倒的に支配している」として、反感をますます強めていくことになった。
その意味でこの問題は、現在の世界を席巻する新自由主義的な経済システムとの関連で考えたほうがいいかもしれない。普通の「中国人」でも生活に困窮している人は膨大であり、それはチベット人の状況と大して変わりないはずだが、「民族」の旗を掲げることができないので強い声を挙げることができないのである。中国政府が最も恐れているのは、少数民族と貧困層が政権および市場経済批判で「共闘」してしまうことであり、私は中国政府があそこまで強硬な態度に出ている理由はむしろここにあると推測している。もっとも、もともと共産党というのはこの「抑圧された民族と労働者の連帯」を目指していたはずのだが・・・・。