「法楽寺」
桃太郎生誕地、卑弥呼説の有る倭迹々日百襲媛生誕地だとして、最近とみに人気の有るお寺が記紀に記された「黒田廬戸宮」の伝承地とされる古寺「法楽寺」です。

ただ、廬戸宮は現黒田池近辺に中心地が有ったと思われ、地形や位置関係から黒田尋常小学校跡地ではないかと考えられ、法楽寺は廬戸宮の北西端に位置したと推察されます。

この地域は、式下郡(しきのしもごおり)黒田(久留多)郷(くろだごう)として、倭名称にもいち早く記されるほど歴史のある地域です。

現在、黒田にある法楽寺は往時の面影は殆んど無く、
僅かに地蔵堂壱宇を残すのみと成っていますが、その歴史的価値は高く、600年代初期、聖徳太子が飛鳥より法隆寺(607年建立)へ行脚の際、屏風(三宅町屏風)の地にて休息の折、南に紫雲のたなびくのを訝り、調べられ、
七代考霊天皇一族の祭祀を見つけられてここに祭壇を守るべく寺を建立、「法」の一字を用い法楽寺と命名したと伝えられています。

往時は7堂伽藍12坊とかなりの規模だったとされ
1489年、室町幕府8代将軍足利義正の時の別当が書いた板絵が、唯一当時の様子を伝えています。

この板絵には考霊神社と共に黒田大塚古墳も含まれており、考霊天皇一族の祭祀を守る迹に建てられた寺である事が良く解ります。

また、このお寺は二人の女帝からも称号を受けています。
33代推古天皇より「黒田山磯掛け本寺」の勅号を戴き、「法隆寺,法輪寺」等と共に大和五法寺の内に数えられたとのこと。
慶雲四年(767)には元明天皇より「法性護国王院」の勅号を賜っています。
2人の天皇(共に女帝)から勅号を受けることも他に例が無いかと、
さらに弘仁九年(819)、弘法大師が在住し法楽往生院と名付けています。


この法楽寺もまた、幾度かの戦火に見舞われ、今はその面影も有りませんが、縁起書等によれば、
鎌倉時代の真応元年(1222)に再建されたが、元正元年(1573)、松永久秀と筒井順慶の合戦のおり焼失。天正六年(1578)、筒井順慶が再建。二十五坊があり、徳川幕府によって厚く保護されてきましたが維新の際に寺領は廃せられ、堂宇その他諸建物は大破させられ、僅かに子安地蔵堂と鐘楼、庫裡を残す現況で、田畑地も農地解放により全く無財産寺院になった記されています。

大和志料は「本堂の本尊は勝軍地蔵秘仏なり」と記しています。
[因みに、710年奈良に遷都(このころ法隆寺が再建される)、712年古事記完成、720年日本書記完成。]
明治維新の神仏希釈が決めてとなり、収入の道を閉ざされたこの寺が売り食いで食い繋ぎ、全てを無くし、一時無住寺に為ったのも止むを得ない事かもしれません。
孝霊神社(廬戸神社)
当時、廃寺が相次ぐ中、村人の請願で考霊神社を黒田池北に移し(現在の考霊神社)双方ともに、何らかの形を残せたのは不幸中の幸いと言えるかも知れません。
今残る明治二年黒田村から法楽寺宛申請状に
「今般御一 新ニ付神仏混淆之義格別之御趣意厳旨之御布令も御座候ニ付、村方江御遣シ被下」と有ります。

建立以来1400年、法隆寺と殆ど変わらない歴史を有しながら、忘れ去られようとしているこの寺ですが、
視点を変えてみると、この寺の持つ歴史的意義は非常に大きく、
今、歴史書にはあまり名前の出てこない七代考霊、八代孝元から更に、吉備津彦命を始とする4道将軍を派遣したとされる十,十一代嵩神、垂仁天皇あたりが、日本の国造りの中心的人物である可能性はかなり高いのではないかと考えられます。
殆ど証拠の無い中、室町時代の別当の書いた板絵の持つ意味は大きく、古い小さな天皇の祭祀を守るには寺の規模はあまりにも大掛かりで、板絵には法楽寺境内に考霊神社と共に大塚山古墳まで含まれています。
このことだけでも、通常のお寺ではないことが伺われます。
また、法楽寺と共に、黒田郷に属していた石見の石見鏡作り神社等を含め、この地域に関する公的な記録が不思議なほど殆どないのも事実です。
現代ではその地名や伝承、社伝等と、状況証拠というべきものによって推測する以外に方法が有りません。
欠史八代、消された歴史に大いに関係している可能性が高いのではないかと考えます。

昔を知る人の話によれば、戦前はまだ多少、昔の面影を少し残し、碑や絵巻物、書籍など多少残っていたと言います。
大和鉄道(現、近鉄田原本線)の施設工事の折、法楽寺の北の部分で無数の勾玉や土器が出土したと言い、高齢者の中には猫茶碗にしたとか、飾りつけにしたり子供の玩具に成ったり、果ては蔵にしまってそのまま建て替えの際邪魔になるので捨てたりと、誰が、何処へ持ち去ったのか、今は知る由も無い状態です。

更にこの神さん、人目に触れるのを極端に嫌うとか。
遷宮の際も、ごく僅かな人数で、真夜中に人目を避けて行われました。
現在の孝霊神社は黒田池の北端の堤防に位置し、そんなに広くもない境内に東を向いて鎮座します。

御神体は、孝霊天皇を中に、大和迹々日百襲媛(卑弥呼説が有力)五十狭芹彦尊(吉備津彦尊.桃太郎のモデル)若武彦尊、孝元天皇当5体とも7体とも言われます。

境内社に稲荷神社(祭神 保食神)と荒神神社(火産霊命)を祀る。
孝霊天皇という奈良時代の諡号は、「桓、霊の間、倭国大乱」と表された後漢書の孝霊帝に合わされていて、この人物が倭国大乱の主人公であることを示唆しているとの見解も。
















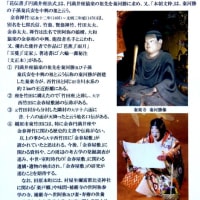




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます