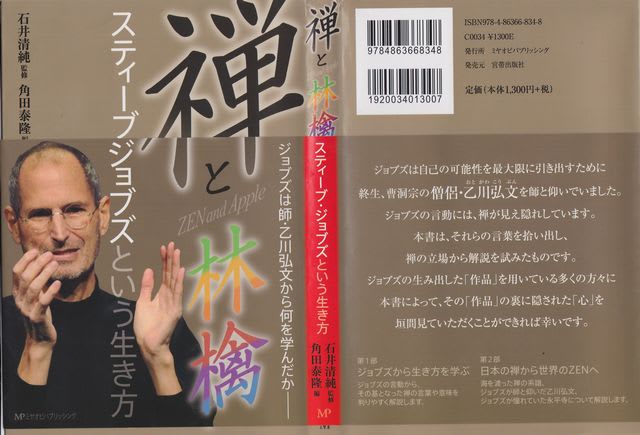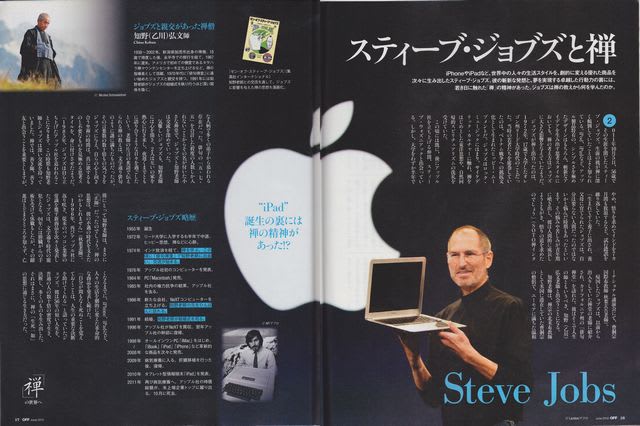竹本 祐介
「自覚」という言葉があります。よく「社会人としての. 自覚を持とう」などと使われます。
yahoo辞書によると「1.自分の置かれている位置・状態、また、自分の価値・能力などをはっきり知ること。2.仏教用語で、自ら覚りをえること。」と書いてあります。
このことが、はっきりと分かっていれば何も困らないと思いますが、えてして人間というものは自分を知らないが為に間違いを犯します。結果「こんなはずじゃ・・・」とか「わかっちゃいるけど・・・」とか「またやってしまった・・・」とか思うこととなります。
潜在意識が原因とも言えますが、潜在意識は隠れた意識なので、気づく事ができません。また顕在意識でわかっているつもりでも、他人にしか見えない自分もいます。さらに忘れてしまった自分もいると思います。先ずは、わかる範囲で自分の事を「はっきり知る」ことにより自分軸と言うものが出来てくるのだと思います。
サンフランシスコ州立大学の心理学者ジョセフ・ルルトとハリーインガムが提唱したマトリックス表を用いた「ジョハリの窓」と言う自己分析のツールがあります。近年では大手企業の新入社員研修などでも活用されているようです。
この「ジョハリの窓」とは
「他人は気付いていて自分にはわからない」→盲点の窓
「自分では良く知っているが他人には見せていない」→秘密の窓
「自分も他人も良く知っている」→開放の窓
「他人にも自分にもわからない」→未知の窓
という4つの窓にわかれて自己分析をしていくと言うものです。
改めて自分を見つめ直し、他人に見えている自分を教えてもらい、さらに自己開示とフィードバックによって「開放の窓」を広げることが成長に繋がるとされています。
さてこの「ジョハリの窓」に近いことを「禅」でも唱えております。いやジョハリの窓よりも踏み込んでいると思います。
仏言、それ授記に多般あれども、しばらく要略するに八種あり。
(道元禅師『正法眼蔵』「授記の巻」)
一者 自己のみ知りて、他は知らず。
二者 衆人ことごとく知りて、自己は知らず。
三者 自己衆人、ともに知る。
四者 自己衆人、ともに知らず。
五者 近くのものは気づき、遠くのものは気づかず。
六者 遠くのものは気づき、近くのものは気づかず。
七者 近くのもの、遠くのもの、ともに気がつく。
八者 近くのもの、遠くのもの、ともに気づかず。
一者~四者まではまったく「ジョハリの窓」と同じで、五者以降は他者に対しての事だと思われます。ここで言う遠近は物理的な距離だけでなく、精神的な距離もさしていると思います。ジョハリの窓では自己を焦点に考えていた事が、道元は他者との関わりにも関連付けて考えています。

また『正法眼蔵随聞記』では「四つの句」を用いて因果についても説明しています。
一 冥機冥応 見えない所で行われたことに、見えない報いが起きること。
二 冥機顕応 見えない所で行われたことが、見える報いを生むこと。
三 顕機冥応 見える所で行われたことに、見えない報いが起きること。
四 顕機顕応 見える所で行われたことが、見える報いを生むこと。

ここで言う「報い」とは正しいことや悪いことではなく、単なる現象としての結果と理解した方がよいでしょう。行動をおこせば必ず何処かに「果」が現われると言う事です。偶然に思える出来事にも必ず「因」があるとも言えます。潜在意識下での願いを把握するために、過去に起こった事を検証するのに役立つと思います。
このように「禅」では単なる自己を知ることに留まらず、自分以外のものとの関係や、因果を用いてそれを駆使し、「自己をならうということ」を探求しています。
一番最初にご案内した「自覚 : 自分の置かれている位置・状態、また、自分の価値・能力などをはっきり知ること。」これは仏教用語で言う「自覚」即ち自ら覚りを得る事に繋がって行く事になるのだと思います。
まずは自分の現状を知り、改善すべき所は直し、さらに五感を研ぎ澄ませて、もの・ことにあたり、未知の自分(潜在能力など)を見出し、他者との関わりの中で自分を役立てる事に繋げていきましょう。
参考書籍 花岡光男『道元明明百草の夢』(リフレ出版) 雑誌『日経おとなのOFF』(日経BP社)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
☆☆ THE ZEN ~ZEN mind,Beginner’s mind~ ☆☆
●Vol.1 【自己をならうということ】 東京開催 8月31日(土)
●Vol.2 【万法に証せらるということ】 東京開催 9月29日(日)
●一泊研修会inおごと温泉 【「空」じる力~心のデトックス~】
琵琶湖畔 おごと温泉 旅館「木もれび」一泊3食付
(1室4名相部屋となります。勿論男女別部屋です)
澤谷先生は30年間カウンセリングを続ける中でこの「禅」の教えに
注目してきました。
しあわせな人生を実現する為に「禅」の教えが大いに役にたちます。
通常のセミナーでは広義にわたってしあわせな人生の秘訣をお伝え
しておりますが、今回に限り「禅」「仏教」に特化した講義を行います。
このセミナーは、東京近郊の方でない方もインターネットにて全国どこ
でも受講できます。
又、予習復習ができるように特設サイトを作成する予定です。
この企画は、後にも先にも今回だけです。逃すと二度とありません。
この機会に是非ともご参加下さい。
↓ お申し込み受付開始です!↓
http://www.kou-sawatani.com/sem-thezen.html
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄