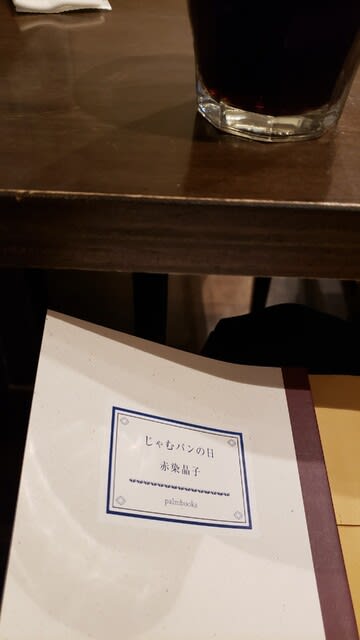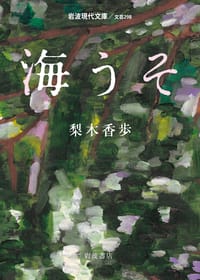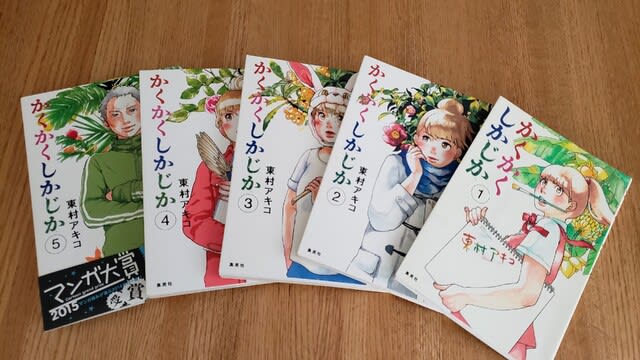4月の読書会課題本「三千円の使いかた 著・原田ひ香」
原田マハではなく原田ひ香。
文庫本になってからなのか、すごく売れているみたいです。帯には35万部突破とありました。
連作短編集で、登場人物はある家族。
●姑であり祖母琴子(73才)
銀座のデパート勤務の時、商社マンの夫に見初められ結婚。5年前に肺ガンで夫は他界。息子夫婦と同じ十条で、孫たちから素敵と言われる一軒家に、良い家具や食器に囲まれてひとり暮らす。夫が残したものは1000万と数百万の普通預金。年金は月8万。普段から常にアンテナを張り、高金利の銀行をみつけては資産を動かしていたものの、最近はそれも面倒になってきた。大金だと思っていた数百万が今は数十万、心の拠り所だった1000万に手をつける日も近いのではと不安に思う日々。そんな時は母の教えで結婚してからずっと欠かさない家計簿をつけることで心を落ち着かせている。
●嫁であり母智子(55才)
23年前に30年ローンで建てた十条駅から徒歩10分の一軒家に、家事が全くできないそして家庭に無関心な夫(精密機械メーカー勤務、智子に言わせればさっぱり意味が分からない課長ではなく次長職)と暮らす。仏文科卒、バブル世代。結婚してからもずっと英語とフランス語を学び続けている。更年期に悩まされ、以前はあそこで買ったら女も終わりと敬遠していた商店街にある激安衣料店「むらさき屋」の大ファンとなり、保温下着をこよなく愛す。スマホではなく携帯を使用。夫には弟がいるが関西在住で妻の実家の家業を継いでいる婿養子状態。長男の嫁として義母の今後を考えると頭が痛く、見て見ぬふりをしている。800万あった貯金も、娘たちの大学進学や娘の結婚に関わる費用、親たちの葬儀代、自分の入院費用などで一気に目減り、現在100万。
●長女真帆(29才)
専業主婦。短大卒、元証券会社勤務。結婚6年目。十条の2Kのアパート(家賃88,000円)に、高校時代の友人で消防士(月収23万年収300万)の夫と3歳の娘の3人暮らし。現在預金600万(うち100万は真帆独身時代に貯めたもの、夫独身時代貯金ゼロ)。証券会社勤めの経験から日々株価をチェックし、手堅く資産運用、お小遣いは自分で稼ぐと決めている投資の知識豊富、節約はするが知恵を絞り貧乏くさい生活はしない賢い主婦。目標は娘大学入学までに1千万!
●次女美帆(24才)
大学卒業後、西新宿にあるIT関連会社勤務し1年半。オシャレな街中目黒に近い祐天寺の築浅10畳の1Kマンション(管理費込98,000円)に半年前から念願の一人暮らし。節約のため弁当を作ろうと8,000円のまげわっぱを買ったものの1日で挫折、コンビニでの買い物、カフェでのお茶が日常化、まとまった休みは旅行と使いたいものには惜しまない金銭感覚。貯金は30万。彼氏はいるが最近微妙な雰囲気。
この4人と彼女たちに関わるひとたちでまとめられた6話の短編になっています。
「三千円の使い方」という題なので、年代によっての三千円の使い方が描かれていると紹介されていることもありますが、実際は第1話のタイトルが「三千円の使い方」というだけで、ほかの5話はお金にまつわる内容ではあるけど、三千円は関係ないと思っていいです。
わたしが特に共感したのが義母琴子の話「七十三歳のハローワーク」と嫁智子の話「熟年離婚の経済学」
年代的にでしょうかね。
「七十三歳のハローワーク」
今後の生活費が不安になった73歳の琴子が、働こうと思い立つ話なんですが、そう思うきっかけが、嫁智子から頼まれたおせち教室の手伝いで、お礼にもらった5000円が想像以上に嬉しかったんですね。あまりの大きな喜びに、自分自身、戸惑ったとありましたが、この気持ちとってもわかるんです、わたし。
娘を出産後も落ち着いたら働くつもりでいたのですが、10年間は夫の希望を尊重すると決め、50才になって即効パートにでました。
その会社は大量採用するけど早いと1日、1週間、1ヶ月とどんどん人が辞めていくようなブラックな職場で、今ならパワハラって訴えていいくらい恫喝あり、いびりありの鬼のような女性管理職がいて、何人もやられ、わたしもそのひとりだったのですが、それでも辞めるよりお金をもらえる方が嬉しくてたまらなかったんです。自分名義の通帳を記帳しに行き、印字された数字を見てわたしも涙が出るくらい嬉しかった。
夫はケチな人じゃなく、結婚当初から給料も全部わたしに渡してくれて、なにを買ったかも全く頓着しないのですが、わたしはずっと「ひと」のお金を「使わせてもらっている」という意識が抜けなかったんです。夫が自分の稼ぎを全部わたしに渡すことも信じられなかった。わたしにはできませんもん。今もパートのお金で家族のものも買いますが、意識は「わたし」のお金で買ってるです。
わたしはお金が大好きなんです。だから働きたい。お金に働いてもらうより、頭悪いから身体動かして働く方が性にあってます。まぁ今は元気だからそう言えることなんですが。もし3億宝くじが当たったとしても働く気がする。お金あるからいつ辞めてもいいと、いびられても内心鼻で笑って働けそうです。当たらないかな宝くじ。
といっても週3パートなんで、フルタイム勤務のかたからするとお気楽でいいわねってところでしょうか。
「熟年離婚の経済学」
こちらは身につまされる内容でした。
開腹手術して退院の日、夫や娘は都合が悪く一人で帰宅。多分一度も掃除機をかけていないのだろう埃っぽい部屋で疲れてソファでウトウトしていると夫からメール。「今夜は、外食でもいいし、出前でもいいよ」
夫は自分が退院した日でも「出前でいいよ」っていうのだろうかと考え込む智子。
わかるわー、この想像力のなさ。
わたしも寝込んだ時に夫が「なに食べたらいいかな」と言ってきたのには、唖然としたわ。3歳児じゃあるまいし、頭あるだろ、自分で考えろよって情けなかったわ。
なんにもしないしできない夫に嘆く智子に、娘たちは手厳しい。
「お母さんも悪いんだよ。お父さんにご飯の作り方とか教えればよかったじゃない。おばあちゃんに育てられた時間よりお母さんと一緒にいる時間の方がもう長いじゃない」
我が家の娘はもっと言うのよね。
「お父さんはさ、お母さんがいない時の方がちゃんとしているよ。なんでもやれるんだよ」だってさ。
話を本に戻して、智子の親友千さとが熟年離婚を考えていることを告白する。
元客室乗務員千さとと大手航空会社勤務の夫は似合いのカップルだった。その夫に女がいることが、とあるきっかけで判明。夫を問い詰めたところ、待ってましたとばかりに夫から離婚を突き付けてきたのだと。
そこからの離婚に関するお金の話が興味深い。
千さとは30歳で結婚。55歳の今、大学生の一人娘がいる。
離婚するとなると結婚生活25年間で貯めたお金を折半するのだとか。専業主婦でも夫の稼ぎは妻のお陰でもあるという考え方でそうなるらしい。ただ結婚以前の貯金はそれぞれのもの。
現在のままでいたら国民年金13万、厚生年金が10万、合計月々23万。熟年無職夫婦の1ヶ月の平均収支は25万足らずだから貯金を取り崩したとしてもそう困らない。
千里と夫は同い年。夫は大学卒業後すぐ就職、33年働いて結婚して25年。だから33対25で分ける。ザックリいうと4対3。年金も貯金も退職金もその割合で分ける。国民年金は折半、厚生年金は4対3。
千さとの話によると、彼女夫婦はこうなる。
国民年金が65,000円、厚生年金は夫が57,000円、私は43,000円。でも支給されるのは私たちが65になってから。さらにこれから5年、夫が60才になるまでには新しい女が夫を支えることになるからそこから引かれる。
夫が前の会社を退職して新しい会社に入った時の退職金が2000万。それも4対3。夫が1,143万、私が857万。独身家庭では女性のほうがお金を遣うらしく、月平均が15万。わたしのように離婚して最初の10年間は年金が出ない計算だと、パートで月7万くらい稼いで足りない分は貯金で取り崩していると、8年後には貯金は残ってない計算になり、年金受け取る前に貯金ゼロになる。それが63才。住んでいるマンションのことだってある。
その話を聞いて言葉も出ない智子は、翌日預金通帳を開いて愕然とする、ほとんど底をついていたのだ。
って、そこツッコミどころよね。
専業主婦で、夫がお金全部握っているわけじゃなく通帳も自由にみれる環境だったら、家にどれくらいお金があるか、ちゃんと把握してないと怖くて生活できないと思うんだけど。娘二人大学に出して、ローン組んで持ち家もあるわけだから、ある日自分ちの通帳が底をついていることに気づいて愕然!なんてことにはなるはずがない。
専業主婦を作者はなめてないか。
さて、智子。
千さとから聞いた離婚後のシビアな試算に、ショックを受ける。夫の不満も我慢して結婚生活を続けるしかないのかという現実をつきつけられ、退職後の夫との生活を想像し、溜息をもらす。
数日後、千さとが離婚試算でお世話になったファイナンシャルプランナーへ智子も相談に行く。
FPに、夫への不満は自分が我慢すればいいのだと思わず、本当のところ自分はどうしたいのかをよく考えてみてとアドバイスされる。そして具体的なことも。
・買い物の後は財布の中身を確認し、レシートを整理する
・最後の週は買い物に行かず、冷蔵庫の中のものを一掃するつもりで使い切ってしまうレシピを考える。
・週に何日か夫と別々に夕食をとる日を決める。(智子は習い事の日、皆は帰りに食事をするのに夫の食事作りがあり参加できないでいたので)
夫の夕食の準備だけして、今日は私は外で教室の皆と食事の日だからってなんで言えなかったのかな、智子は。夫が望んでいるのではなく、智子自身がやって「あげたい」という思いもあったんじゃないのかな。
FPのアドバイスは、わざわざお金払ってまで聞きに行くほどの内容ではないけど、行くというその行動が大事な気がする。行動することで頭の中が整理されるからね。ここに来たことは無駄だったなと思うことも含めて。
この本に出てくる話はどれもハッピーエンドで、そんなにうまくいくか?って思ったりするけど、軽く読むにはいい本だと思った。
知らないうちに奨学金を親から背負わされた美帆の新しい恋人の話は、いくらなんでもまわり甘すぎないかと思う。借金返してから結婚しても遅くない年齢だと思うけどな。
日本で最も歴史ある旧家のお嬢様とその夫君を思い起させる内容だったわ。