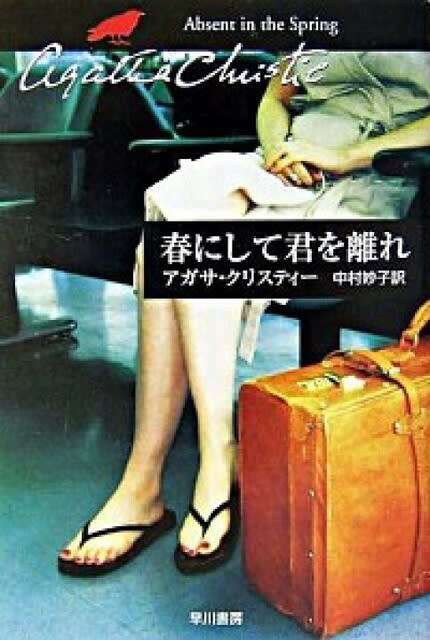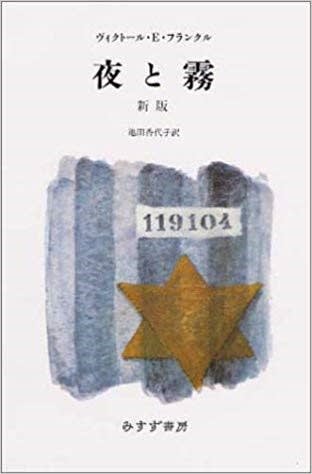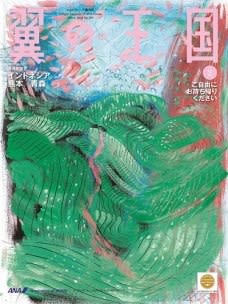11月の読書会の課題本「WONDER」
インパクトのあるブルーの表紙、きっと多くの方が本屋さんで見かけていると思います。
わたしもそうでした。何度も目にしました。
でも一度も手に取ることがありませんでした。
ジュリア・ロバーツが母親役で映画化もされ、
それをいろんな雑誌が取り上げ紹介している記事も読んで知ってはいましたが、
頭の中を素通りでした。
メールで今度の課題本は「WONDER」ですと送られてきましたが、
ピンときませんでした。
ネットで検索し、あーあの映画の原作なのかとわかり、
横浜ビブレのブックオフへ。
いつもはエスカレーターで上がるのですが、その日は急いでいたのでエレベーターで。
扉が開いた目の前が児童書の棚で、まるでわたしを待ち構えていたかのように、
棚の真ん中のブルーの背表紙が、目に飛び込んできたのです。
児童書だってことは知らず、海外文学コーナーを探すつもりでいました。
エレベーターをでてわずか1分もかからずに、お目当ての本を手に入れることができました。
「WONDER」
顔に大きな障害を持って生まれてきた男の子の話です。
以前朝日新聞で記者の方のお子さんが顔に障害を持って生まれてきたことで、
顔に障害を持つ方たち数人を取材し取り上げていた記事がありましたが、
読んでいてちょっときつかった記憶があります。
~オーガスト・プルマンはふつうの男の子。
ただし、顔以外は。生まれつき顔に障害があるオーガストは、はじめて学校に通うことになった。
だが生徒たちはオーガストの顔を見て悲鳴をあげ、じろじろながめ、やがて「病気がうつる」と避けるようになる。
一方で、オーガストの話をおもしろいと感じる同級生は少しずつ増えていた。
そんなとき、夏のキャンプで事件が起こる……。全ての人に読んで欲しい、心ふるえる感動作。~(Amazonより)
この小説は、主人公の男の子、友達、姉、姉の彼氏、姉の友達の独白でそれぞれの章が構成されています。
特に姉の章は、障害を持った弟がいる姉の気持ちがとてもよく描かれています。
弟のことで自分の友達が離れていく寂しさだったり、
自分を知らない人が多い高校生活では弟のことを知られたくないと思う気持ちと、
そんな気持ちになる自分を責めてしまったり。
自分に悲しいことがあっても、弟がもっとつらい思いをしているんだからと自分に言い聞かせたり。
本人もそうだけど、障害のことで、その家族もまたいろんな気持ちを抱えて生きているわけですよね。
主人公オーガスト10歳。
ずっと家でお母さんに勉強教えてもらっていたけど、とうとう学校に行くことに。
その顔にみんな驚き、避けられます。いじめだって受けます。裏切りにだってあいます。
でもやっぱりいるんですよね、彼に興味を持つ子が。
いろんな考えのひとがいるってことは大事だってこういう時改めて思いますね。
いっぱい書きたいけど、ネタバレになるからやめときますね。
オーガストを執拗にいじめるジュリアンって男の子がでてきます。
「WONDER」ではジュリアンの章はないんです。
いじめっ子側の気持ちも知りたいですよね。
残念だなと思っていたら
出たんですね「もうひとつのWONDER」

こちらではオーガストは主人公ではありません。
「WONDER」を読んだら絶対にこちらも読んだほうがいい。いや読むべき!
オーガストをいじめていたジュリアンの章ももちろんあります。
そして終盤に記された驚くべき事実に、あなたは気づくか!(なーんてね)
それにしても、悩みは万国共通なんだな~としみじみ思います。
思春期独特の友達関係の悩みなんて、外国の子は日本の子よりさっぱりしているのかと思っていたけど、
この本を読んだ限り、あんまり変わらない。
スクールカーストってどこにも存在するんですね。
たぶん読書会の課題じゃなかったら、手に取ってなかったと思います。
あのブルーの表紙のなかにはこんな素晴らしい話が書かれていたとは。
この本はおおむねハッピーエンドです。
ただちょっと出来すぎかなって思わないでもない。
わたしは遠い昔、養護施設に併設された養護学校で働いていたことがあり、
そこに行って初めて、世の中にはこんなにも様々な障害があるんだとショックを受けました。
知的な面と身体的に重複しての重たい障害を持った子どもたちが生活する施設の方に出向いて
授業をやる訪問学級や学校の小学部で仕事をしました。。
小学部は、知的にはほとんど問題がなく身体的に障害がある子たちが学んでいました。
障害があることで親から捨てられた子たちもいました。
小説のように優しいパパやママ、お姉ちゃんがいる中で生活できる境遇にはない子たちのほうが多かったかな。
学校や施設にいる間はまだ守ってもらえますが、
外で働けるような子たちは、高等部を卒業したら施設を出て就職して自立しないといけない現実がありました。
だから先生方は勉強を教えるだけでなく、本当の親のように親身になって優しく時に厳しく接しておられました。
ある女性の先生は、担任している小学生の男の子(オーガストと少し似ている)のことを、
いづれ思春期を迎えたあたりから自分の境遇に絶望する日が来ると思う。
それでも強く生き抜いていってほしいから、そのことをいつも頭に置いて接しているとおっしゃってたのを覚えています。
(そのJ君ももう30代、どんな人生を歩んでいるのかな~)
小説にも素晴らしい先生たちが登場します。
その先生方の印象的な言葉を紹介します。
「いつも、必要だと思うより、少しだけ余分に人に親切にしてみよう」(トゥシュマン校長先生)
「正しいことをするか、親切なことをするか、どちらか選ぶときには、親切を選べ」(ブラウン先生の9月の格言)