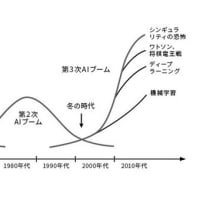建国後の合衆国ー13 南部奴隷社会 黒人奴隷の家族https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/f641aafdfca84d2c422a977033cccfa8
からの続き
イギリスの家族制度が植民地時代の百数十年間、そのままの形で存続することは新大陸では不可能でした。
植民地時代末期には分割相続制度が一般化し,長子相続制は南北問わずに事実上消滅していました。
spの理由の一つとして、植民地での土地の広さに比べ、労働力の不足が挙げられます。 父親は、多くの子供たちの労働力を確保し、荒野を開拓して農業経営を拡大するためには、何らかの形で分割相続を分割相続を約束する必要があったのです。
とはいっても、家父長の権威は依然として存在しました。 たとえば、植民地時代のニューイングランド農村社会は自給自足的性格が強く、若者たちにとって農業と村のわずかな手工業以外にほとんど雇用機会はありませんでした。
しかも、家父長たちは子供が成人に達しても財産分与を渋り、相続を期待する息子たちの労働力を支配し続けました。
当然、彼らの結婚年齢は引き延ばされ、親の祝福を得て結婚して生計は別にしても、土地所有権の譲渡は先のことでした。
父親がまとまった財産を子供たちに譲り始めるのは、四季に近づく晩年になってのことだったのです。
しかし、植民地時代の急激な人口増加と、19世紀に入ってからの内陸開発と工業化の進展により、伝統的家父長支配の経済的基盤が崩壊しました。
入植後、二代、三代、四代と続く間に、個々の農民の土地所有は細分化し、分割相続されるべき親たちの土地は足りなくなりました。
息子たちはもはや、親の小さな土地を分割相続して生計を立てることは期待できずに、西部に移住して農業に職を求めるか、都市の労働者その他の職を求めることになります。
その時、父子の間に何が起こったのか。 二通りの点検があったようです。 一つは労働運動指導者トマス・スキドモア載せ因縁時代の例です。 彼は1790年コネチカット州フェアフィールド群ニュータウンで十人兄弟の総領として生まれ、十三歳になる前に地域の学校の教師になりました。
父親は当然のこととして給料を全部取り上げました。 しかし、十八歳になったスキドモアは金を父親に渡すことを拒否し、親と喧嘩して家を騙した。
後に彼の社会批判の中核には、家父長支配に対する厳しい批判と、遺産相続制度そのものの全面的否定の観念がありました。
変えの兄弟が十人であったことは、18世紀には普通でした。 人口急増の一因は多産にあったのです。
ベンジャミン・フランクリンの父は、後妻として入った彼の母に十人の子供を産ませ、さらに先妻の子共が7人いました。 スキドモアの家出もそれほど例外的ではありませんでした。
伝統的な考え方によれば、息子たちは21歳になるまで「父親のために働くことを義務付けられた一種の財産のように見なされていました」(ジョーゼフ・F・ケット)。
したがって、新たな雇用機会を外部に求める若者は、17歳から21歳ころの間に、父親の強い反対を押し切って独立しました。
もちろん、実際には一定のお金を支払うなど、父親との間に様々な形での妥協が図られることも多くありました。
植民地時代の徒弟制度は、未成年者の雇用形態であると同に、技術教育と親に代わる後見監督機能をも果たしていました。
建国初期には、多くの職種で徒弟制規制が著しく弱まり、少年たちが徒弟期間を務めあげずに逃げ出し、よそで職人として働くことも多くなりました。
すでに紹介したロードアイランド型工場では、少年たちは最初から徒弟としてではなく、賃金労働者として働きました。 このことも、彼らの親たちからの自立を早めることになりました。
他方、もっと恵まれた人々の例もあります。 聖職者や弁護士のような高等教育を必要とする専門職で成功した人々の場合、彼らは子供を働かせるより高等教育の機会を与え、若い頃から独立心を強めるように育てた記録も残されています。
しかし、このような子供たちは全体の数からいって消して多くはありませんでした。 ただ、彼らは指導的なっ役割を果たす人々であり、19世紀に支配的な文化を形成し、『世論』を左右したという点で、この子育ての型はアメリカ発展の推進力になりました。
若者たちの親からの経済的自立は、決して豊かな未来を保証するものではありませんでしたが、彼らの職業や住居や移住地に関する自己決定は、広く人間関係一般に根本的な変化を惹起しました。
ウィービは19世紀前半の人々の空間的・社会的流動化を『選択革命』と名付け、これを基軸概念に、19世紀前半の政治・社会史全体を説明しています。
この人口の流動化は、19世紀前半の米国史を理解するには大事な視点です。
(関連情報)
1. 建国後の合衆国-1 ジャクソン大統領による土地強奪
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/e3133076c791bcb68fb784f0fda0aada
2. 建国後の合衆国ー2 メキシコ領土獲得戦争
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/b98362c56ee34ea0232ce7abf35a2b18
3. 建国後の合衆国ー3 有料道路建設https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/f7732681a17552137e8e825d693d70bc
4. 建国後の合衆国-4 大運河建設ブームhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/5a8e291c0bbcae626aa9c16566cf0b1b
5. 建国後の合衆国-5 蒸気ボートhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/36926fea375feebeec7b870a643154c2
6. 建国後の合衆国-6 鉄道時代の開幕https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/e41b415af0cde7ab639ced37ea333168
7. 建国後の合衆国ー7 工場制度の出現
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/406176fab1ec1dcdaf117cefbabd0024
8. 建国後の合衆国ー8 世界最初の紡績一貫工場https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/31c7061b6eed00409710025e11d2456e
9. 建国後の合衆国ー9 労働者階級の出現https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/8bdbf78f3133393e6b6bce7fd5f600f7
10. 建国後の合衆国-10 アメリカ労働運動の出現https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/e5101f09aaf0bd4a9f80e26db3ad96ad
11. 建国後の合衆国ー11 南部奴隷制社会 綿花王国の形成
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/d6b63441e361c8a771e9185c019a9534
12. 建国後の合衆国ー12 南部奴隷社会 黒人奴隷の文化https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/a7fd8a1c3adb08f6e6bec419395a4192
13. 建国後の合衆国ー13 南部奴隷社会 黒人奴隷の家族https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/f641aafdfca84d2c422a977033cccfa8
14. 建国後の合衆国ー14 家父長的権威の衰退と近代家族https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/50d8dea63fd8e50975de0d2578a6355b
PS.
・アメリカを正しく認識する 建国までの歴史概略シリーズのまとめhttps://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/c92a98cc78bf8a2cff02eab33b4b245b