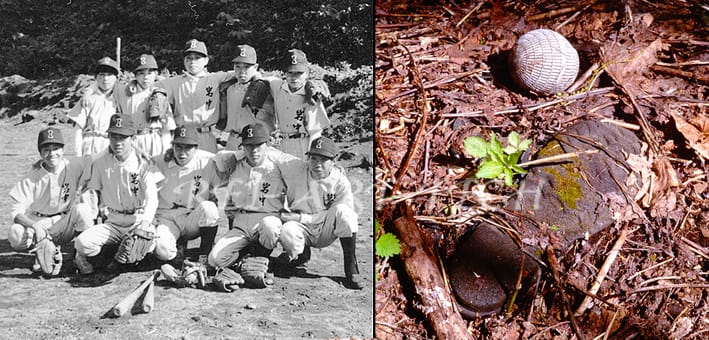そろそろ雪虫の季節が過ぎ、本物の雪の季節になってきました。
熊野の取材・病院当直と子育ての毎日で、以前のようには知床にも行けなくなってしまいましたが、久々に知床から連絡が! 産經新聞の人が話を聞きたいと言うので、連絡をとってみて、とのご連絡です。知床開拓について取り上げてくれるのかな、ありがたいな、と思いながら、「産經新聞の芸術特集」をつくっている広報堂という会社に電話をしてみると、
「国会図書館で御本を見まして」(ありがとうございます。国会図書館????)
「大変良い本で感動しました」(ありがとうございます)
「11月●日(おお、もう来週ではないか)の産經新聞朝刊に誌面1面を使って芸術特集をし、22名を取り上げるのですが、その一人として栂嶺さんを取り上げたい」(ありがとうございます)
「東日本全体に配布されるので●名の読者の方の目に触れます」(細かい数字は忘れた)
「大きさは8センチ×9.5センチ枠になります」
「つきましては広告扱いになりますので、24万円お支払いいただきます」
目ん玉飛び出ましたよ(笑) …………無理!!(即答)
そういう商売だったか!(笑)
子育て中でほとんど働いてない人間に、いや働いていたとしても、24万円は目ん玉飛び出ますよ。今までたくさんの雑誌や新聞が「知床開拓スピリット」を取り上げて下さって、記事中で宣伝もして下さって(いずれも広告料なんてナシですよ)、今からわざわざ24万円払って8センチ×9.5センチに載せたいとは思いませんですよ。
それに、現在第1刷が完売で、出版元にも在庫がない状態。「広告」を目にしてもらっても購入していただけない状態なのです。(ウェブ書籍化の話もあったが、その後何の連絡もないので、何も進んでいない状態ではないかと)
というのを説明して、お断りしたのですが、本当にお断りになったのかどうか不安だな~~(^^;
「断ったよ!!」と、来週になっちゃう前に、一応ブログにも書いておくよ~~~
それで、「広報堂」「産經新聞」で検索すると、たくさんたくさんヒットしますね(^^;;;
どれを読んでも、電話のやりとりの台詞は一緒なのですね。(それで「国会図書館」だったのか………)
働いてないと言ったら、「知床財団はもう辞められたのですか?」と言われて、変だなあと思ったんだけど。(私は知床財団で働いたことないヨ)
それにしても、自費出版の人をターゲットにしているらしいと読んで、そっちの方が嫌かも(笑) 「知床開拓スピリット」が、自費出版でないと出せないような本だと(出版社が認めてくれないような本だという意味で)思われてるとしたら嫌だなあ。(ああ、それで、"個人"が"24万円も"かけて広告しなければ売れない本だと思われたのかな)
出版のために頑張って下さった柏艫舎が怒っちゃうよ。