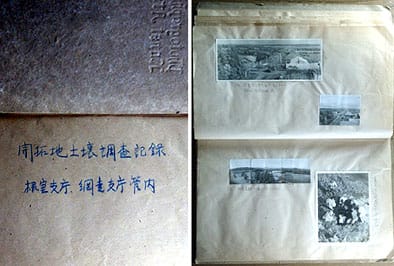平尾水分神社(奈良県宇陀市)のオンダ祭りのことを毎日小学生新聞(1/22)に書いたので、それについてもうちょっと。
このお祭りは、オンダ=御田祭りということで、苗代をつくって"幸福の種(稲籾)"を播き、鳥を追い、育った苗を田んぼに植えるまでを神様の前で演じる予兆行事です。
が、私が先日からちょこちょこ書いている修正会の性格も持っているのですね。先日取材した野迫川村のオコナイも、北今西集落のオコナイは別名「おんだ」と言われ、弓手原集落のオコナイは「修正会」と言われているように、私は時々、おんだと修正会の線引きがどこにあるのかわからなくなります。
平尾のおんだ祭りの修正会らしい所は、最後にやっぱり"鬼"が出て来ることです。
いえいえ、いわゆる鬼ではなくて、ここでは「若宮さん」という不思議な力を持った人形なのですが。
私は若宮さんは怖~~かったです。喜んで取り囲んでいた子供たちは怖くなかったのかな。
まっくろな翁の面に、こよりでぐるぐる巻きになった布だけの身体がくっついています。自分の身体の病気の部分とか、痛いところと同じ部位のこよりを若宮さんからほどいて、自分の身体の同じ部位に結び付けると病が治る、というのです。若宮さんは祭りの最後に、村人たちの病を癒すためだけに登場します。私も重いカメラの持ちすぎで悪くした右ヒジに、もらったこよりを結びました。
が、実は同じような所作は、今まで度々目にしてきました。
秋田県のナマハゲやヤマハゲでは、彼らが落としていったケデ(簑)の藁を、皆が競って拾い、身体の痛いところに巻き付けたり、頭に貼付けたりします(頭が良くなるんだそうな) 彼らが身につけていたケデ自体に神聖な力があるとされ、年が明けると、ケデは神社の柱やご神木に巻き付けられて、その後1年間村を守る鎮守の神になるのです。
石垣島の白保の獅子舞や、川平のマユンガナシィが落としていったクバのかけらもそう。
そして、奈良県五條市のだだ堂の鬼走りなど、修正会に登場する鬼の身体に巻き付けられている「こより」がそうなのです。
修正会の鬼は、ほぼ例外なくミシュランのタイヤマンか、ボンレスハムのように、ぎゅうぎゅうに縛られています。これは一体なあに?
私がよく思い出すのは、大分県で見た修正鬼会の鬼たちです。寺での修正会が終わった後も、鬼たちは魔や厄を追い払う神となって、一晩中かけて集落全戸を1軒1軒まわり、明け方頃やっと寺に戻ってきます。でも、寺に戻ってきた鬼はまだ、魔を封じる力をビンビンに撒き散らす荒ぶる神なんですね。それを皆で一斉に飛びかかって押さえつけ、「鎮め餅」という鬼を鎮めるためのお餅を無理矢理口の中に突っ込み(!)、そして、鬼の身体を縛り付けていた白い紐(こより)を刃物で切る。紐が切られて、初めて、鬼役の人は"人間"に戻るのです。
私は、紐やこよりは、鬼(神)の力を発揮させる、もしくは、その内に封じ込める力を持っている、と理解しました。若宮さんが身体中にぐるぐる巻きにつけているこよりも、鬼神の力を内在し、魔=病を封じ込める不思議な力を持ったこよりなのです。
このお祭りは、オンダ=御田祭りということで、苗代をつくって"幸福の種(稲籾)"を播き、鳥を追い、育った苗を田んぼに植えるまでを神様の前で演じる予兆行事です。
が、私が先日からちょこちょこ書いている修正会の性格も持っているのですね。先日取材した野迫川村のオコナイも、北今西集落のオコナイは別名「おんだ」と言われ、弓手原集落のオコナイは「修正会」と言われているように、私は時々、おんだと修正会の線引きがどこにあるのかわからなくなります。
平尾のおんだ祭りの修正会らしい所は、最後にやっぱり"鬼"が出て来ることです。
いえいえ、いわゆる鬼ではなくて、ここでは「若宮さん」という不思議な力を持った人形なのですが。
私は若宮さんは怖~~かったです。喜んで取り囲んでいた子供たちは怖くなかったのかな。
まっくろな翁の面に、こよりでぐるぐる巻きになった布だけの身体がくっついています。自分の身体の病気の部分とか、痛いところと同じ部位のこよりを若宮さんからほどいて、自分の身体の同じ部位に結び付けると病が治る、というのです。若宮さんは祭りの最後に、村人たちの病を癒すためだけに登場します。私も重いカメラの持ちすぎで悪くした右ヒジに、もらったこよりを結びました。
が、実は同じような所作は、今まで度々目にしてきました。
秋田県のナマハゲやヤマハゲでは、彼らが落としていったケデ(簑)の藁を、皆が競って拾い、身体の痛いところに巻き付けたり、頭に貼付けたりします(頭が良くなるんだそうな) 彼らが身につけていたケデ自体に神聖な力があるとされ、年が明けると、ケデは神社の柱やご神木に巻き付けられて、その後1年間村を守る鎮守の神になるのです。
石垣島の白保の獅子舞や、川平のマユンガナシィが落としていったクバのかけらもそう。
そして、奈良県五條市のだだ堂の鬼走りなど、修正会に登場する鬼の身体に巻き付けられている「こより」がそうなのです。
修正会の鬼は、ほぼ例外なくミシュランのタイヤマンか、ボンレスハムのように、ぎゅうぎゅうに縛られています。これは一体なあに?
私がよく思い出すのは、大分県で見た修正鬼会の鬼たちです。寺での修正会が終わった後も、鬼たちは魔や厄を追い払う神となって、一晩中かけて集落全戸を1軒1軒まわり、明け方頃やっと寺に戻ってきます。でも、寺に戻ってきた鬼はまだ、魔を封じる力をビンビンに撒き散らす荒ぶる神なんですね。それを皆で一斉に飛びかかって押さえつけ、「鎮め餅」という鬼を鎮めるためのお餅を無理矢理口の中に突っ込み(!)、そして、鬼の身体を縛り付けていた白い紐(こより)を刃物で切る。紐が切られて、初めて、鬼役の人は"人間"に戻るのです。
私は、紐やこよりは、鬼(神)の力を発揮させる、もしくは、その内に封じ込める力を持っている、と理解しました。若宮さんが身体中にぐるぐる巻きにつけているこよりも、鬼神の力を内在し、魔=病を封じ込める不思議な力を持ったこよりなのです。